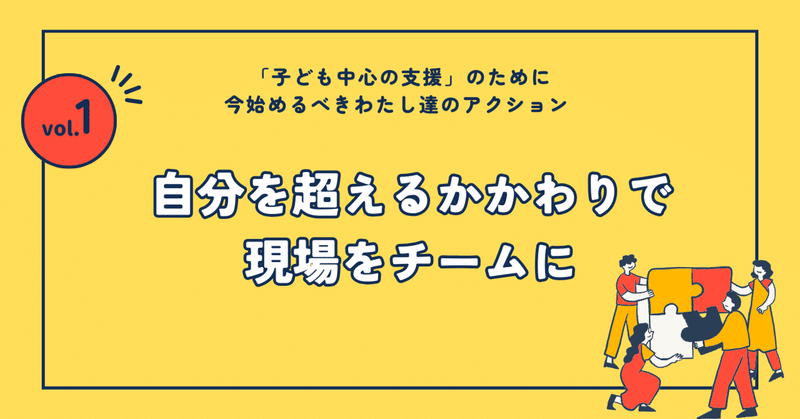
【短期シリーズ】「子ども中心の支援」のために、今始めるべきわたし達のアクション vol.1 ー自分を超えるかかわりで、現場をチームにー
発達障害をはじめ、通常の教育支援だけではカバーしきれない子どもたちをどうケアしていくべきか、議論されることが増えています。
現在、児童発達支援を担う施設・事業所は1万1000以上、放課後等デイサービスは1万9000以上あります(いずれも令和5年(2023年)2月現在)。政府も障害児支援を重視し推し進めていますので、こうした支援施設は今後、さらなる増加が見込まれることでしょう。
私たちデジリハは、デジタルアートとセンサーを活用したリハビリツール「デジリハ」の開発・提供を進めています。放課後等デイサービスをはじめ、複数のリハビリや療育の現場でこの「デジリハ」を導入していただく中、デジタルならではの特長を生かして、「すべての子どもたちのアソビが拡がる支援」を、皆さんと一緒に見いだすことができました。

その一方、私たちがたくさんの障害児者支援の現場と接点を持たせていただく中で、皆さんからのお悩みを伺うことも少なくありません。そのポイントはいくつかありますが、あえてまとめて表現するなら「子ども中心の支援の提供がしにくい構造がある」というものです(しばしばビジネスの世界では「顧客中心」という言葉が使われますがここではそれになぞらえて、「子ども中心」と表現してみました)。
なぜ「子ども中心の支援の提供」がしにくいのか。これをさらに掘り下げてみますと、「人にまつわる問題」がありそうです。
療育の現場では、指導員、保育士、理学療法士、作業療法士など様々なスタッフが関わります。こうした様々な役割・専門性を持ったスタッフが、それぞれの能力を生かして相互に補完し合ったその時に、「子ども中心の支援の提供」が可能になります。その時、施設に関わるスタッフは、単に人が集まった状態である「グループ」から、目標に向けて互いに補完し合う「チーム」へと変化したことを意味します。
立ち戻って、悩みのある療育現場のお話を探っていきますと、「グループからチームへの変化がうまくいっていない」という現状もうかがえます。
組織がチームとして機能している場合は、目標の達成に向けて構成メンバー同士の協力がうまくいっており、メンバーそれぞれが感じる労働満足度は高まる傾向にあります。しかし、組織がグループの状態にとどまっている場合、そこでの人間関係は希薄になりがちで、職場内で孤立するおそれも否めません。これでは、スタッフの労働満足度は上がりませんし、何よりも子どもとご家族の満足度の低下にもつながります。施設の経営を揺るがしかねない問題です。
どうしたら、スタッフ、そしてサービスを受ける当事者と家族、その両方がうれしくなれる療育現場がつくれるのか。私たちデジリハは、療育に関わっている皆さんと一緒に、「子ども中心の支援の提供を可能にする、療育現場に必要なチームビルディング」というテーマについて考えていきます。チームビルディングとは、「一人ひとりの能力や個性を生かしながら、効果的な成果を出せるチームをつくり上げること」を指します。
まだ私たちデジリハも、このテーマについて着手し始めたばかりで、仮説を設定するにとどまっている段階です。しかし、療育現場をより良いものにしていきたいという思いは、皆さんと同じです。「子ども中心の支援の提供を可能にする、療育現場に必要なチームビルディング」を実現するために、様々な仮説を設定しながら、デジリハのメンバー、そして外部のご協力者の方々を交えつつ、皆さまが働く療育現場でお役に立てるヒントを見いだしていこうと思っています。
今回はこの記事シリーズの第1回をお届けします。株式会社デジリハのゼネラルマネージャー、また理学療法士として国内外の現場経験が豊富なセラピストのひとり、仲村佳奈子が、このテーマ「リハビリ現場のチームビルディング」に対する思いを語ります。
グアテマラで学んだ「何でもやること」の価値
――仲村さんは大学病院勤務の理学療法士からキャリアをスタートされたそうですね。その点では、デジリハの導入を検討される立場にある、放課後等デイサービスにお勤めの方々と同じ目線を持っておられると思います。理学療法士として、現場でどんな経験を積んでこられたのか、お聞かせください。
仲村:元々子どもが好きで、進路を考える時に、子どもに関わる仕事をしたいと考えました。でも保育士などはピアノとか弾けないし私には無理だなあと。一方で、理学療法士や作業療法士などのリハビリ関係の仕事があるんだと知りまして、直感で理学療法士になろうと決めました。
そんな経緯から、学生の時から「理学療法士になるのなら、小児を担当したい」という明確な意思を持っていました。最初の就職先である大学病院も、子どもに関われる職場ということで選びました。
大学病院には4年ほど勤務しまして、いろいろな経験をしました。大学病院が別法人として設立した医療型障害児入所施設に出向し、施設におけるリハビリテーション部門の立ち上げ作業にも関わりました。ゼロから活動を組み立てるのはとても楽しかったですね。
――その後、大学病院を退職して、JICA海外協力隊の理学療法士ボランティアとしてグアテマラに行くことになったわけですね。外国語は、得意だったのですか。
仲村:いえ、頑張りましたよ。グアテマラの公用語はスペイン語で、ほんとうにまったく分からないところから勉強しました。
――JICAの海外協力隊としての派遣先は、現地の特別支援学校で、そこで子どもたちを支援する理学療法士(physical therapist)として勤務されました。ここの経験からどんなことを得ましたか。
仲村:一つ大きいのは、組織での立ち回り方ですね。派遣先であるグアテマラの特別支援学校には、理学療法士の資格を持っている現地出身の同僚が数人いました。しかし学校の現場の都合、人員が足りず、理学療法士なんだけど普通の教科を教えるとか、そういった姿がままありました。「私は理学療法士だから理学療法士の仕事しかしない」と主張しているような人は、役に立たない雰囲気です。

私は海外協力隊の派遣期間である2年間しかそこにはいられません。子どもたちへの直接的な支援・介入はもちろんやりますが、それ以上に残せるものがあるとしたら何だろうかと考えてみたところ、私が日本に帰った後もそこに居続ける同僚に受け入れられるやり方でないとだめだろうな、と思いました。言葉もたどたどしい外国人が「あなたは間違っている、私が教えます」みたいなスタンスは、絶対受け入れられないはずなので。
そこで、学校では本当に何でもやりました。学校のお掃除も一緒にやったし、仮装パーティーもやりました。そうやっていく中で、相手に役に立ちそうなことをそっと言う。すると「すごく役に立ったよ、ありがとう」と喜んでもらえることもありました。喜ばれました。これを重ねていく中で、うまくいくやり方がだんだんと分かってきました。

ただ私としては、基本的には「気づいてもらえたら超ラッキー」くらいのつもりで取り組んでいました。提供した何かを使ってくれなかったとしても、それは彼らのせいではありませんし。求められることは何でもやったうえで、とにかく種をまくという姿勢で取り組んでいました。
こうした経験を重ねるなかで、「バックグラウンドが違う人たちの中で自分が伝えたいことをちゃんと聞いてもらえるように立ち回る」というノウハウはすごく養われました。
今はもうその学校がありませんし、そもそも私が2年間の任期を終える直前に、一緒に仕事をしてきた同僚がごそっと辞めたんです。これはめちゃくちゃショックでした。ただ、私個人としては得られたものがありましたし、私が伝えたことが同僚たちのその後の人生に何らかの形で役に立っていてくれたらという小さな希望を持って、日本に帰ってきました。
今から思うと、現地の状況はなかなかひどいものがありました。事故に遭って脊髄損傷になったのに「足をマッサージしてればそのうち治る」って言われて病院から帰された人とか、「うちの子は5歳になっても首が据わらず、喋りもしないので困っている」という親とか。

――それはかなりひどい状況ですね。
仲村:後者のケースは、おそらく脳性麻痺であるはずなのに、何のケアもされていないわけです。国が違えば医療事情が異なるのは仕方がないことですが、絶望を感じましたね。
リハビリという仕事はとても好きだったのですが、社会の大枠に関わることは、どんなに個人として技術を上げようと頑張っても何も変わらない。私が残りの人生でどんなに腕を磨いても、この人たちにその努力は届かないということに気づいてしまったんです。
――医療事情がまるで異なる国に足を運んだことが、一度立ち止まって次なる展開を考えるきっかけになったわけですね。
仲村:日本に帰ってからは、これまでとは違うアプローチがしたいなと考えました。「臨床に戻ってリハビリをするだけでは変わらないものがある」と分かったためです。
――その後仲村さんは、「デジリハ」の元々の開発組織であるNPO法人Ubdobeにジョインします。その経緯を教えてください。
仲村:JICAの海外派遣から帰ってきた後、先にも話しました「やりたいことの大枠は見えてきたが、どういうアプローチを取ればいいのかわからない」と模索している時期がしばらく続いていました。
仕事もしつつ、いろいろな人に会ったりしたのですが、何かのイベントで出会った人に私の体験や考えを話したら「僕の知り合いがデジリハを作っているのだけど」と教えてくれました。早速ホームページを調べ、これは面白そうだなって思っていたら、代表の岡(勇樹)とツイッター(現X)でやりとりすることになりまして。「面白いじゃん」みたいな反応をもらい、今度説明会やるから来なよと誘われました。2018年秋頃のことです。
私は早速、Ubdobeの三軒茶屋の事務所で開催された説明会に行きまして、そこでUbdobeのメンバーと意気投合しました。最初のうちは業務委託で週に1回程度ミーティングに参加するという程度の関わり方だったのですが、ちょっとずつ範囲が広がってきて、今やズブズブですね。途中に約1年間の英国留学が挟まっていますが、それが終わるタイミングでUbdobeでの仕事にフルコミットしようと決め、結果として今は株式会社デジリハのゼネラルマネージャーをしています。

「答えはいつも子どもたちが知っている」
――『デジリハ』はデジタルアートやゲーミフィケーションの要素を盛り込んでおり、楽しくリハビリをしてもらいながら効果を上げていくことを狙って開発されています。「お話を聞いて面白そうだと感じた」とのことですが、具体的にはどんな点に惹かれましたか?
仲村:私はこれまでの業務経験も含めて、子どもたちには楽しくリハビリしてほしいという思いを強く持っています。子どもたちへのリハビリを成功させるためには、その子を観察しながら、自ら動きたくなるような“種”を気付かれないよう、周囲に撒いていきます。わざとらしいと動いてくれません。子どもはその点、すごく賢いんです。やらされることをすごく嫌います。
以前、臨床にいたとき、子どもを泣かせてしまったり、あるいは飽きて寝られてしまったりということも経験してきました。リハビリが必要な子は、それまでの人生でいっぱいやらされてきています。こちらの強制感が強いと、次第に全く言うことをきいてくれなくなってしまいます。
一方、デジリハのようなツールを使うことで、リハビリに楽しく取り組んでもらえるんじゃないだろうかと感じました。またデジリハはリハビリが必要な子どもたちと社会の垣根を越えられるようなツールとしても使えて、その点でも私のやりたいことに沿っていると感じました。グアテマラでの経験もあって、社会の側からアプローチする必要があると強く感じていましたので。
――この記事を含む本シリーズでは、「子ども中心の療育現場」というテーマについて、読者と一緒に考えていきます。仲村さんが今まで経験してきた療育現場や、デジリハを通じていろいろな療育現場を見聞きする中で、現場における課題の共通点は、何かありますか。
仲村:立ち戻った話になるのですが、私は以前、先輩の理学療法士の方に、「答えはいつも子どもたちが知っている」という言葉を教えていただきました。「子どもたちにたくさん接して、感じて、いろんなことを教えてもらいなさい」という趣旨なのですが、それは今でも大切なモットーにしています。
――今の「答えはいつも子どもたちが知っている」という言葉は、「子ども中心」という概念をまた別の形で表現したフレーズと言えそうですね。
仲村:私がある施設で働いていた時、ショートステイなどでよく利用しておられたお子さんがいました。私だけでなく施設のスタッフ全体で適切に関わった結果だと思うのですが、そのお子さんが、数週間、数カ月をかけて、すごい変化を見せてくれました。最初は表情がほとんどなかったのですが、次第に笑っているような表情を見せたり、人工呼吸器を利用していて話すことはできないのですが、なんとか声を出して反応しようとする様子がうかがえたりと、たくさんの変化を見せてくれました。
つまり、施設のスタッフが目的を持って子どもにきちんと関われば、どんどん反応してくれる。この経験を通じて、子どもたちがどう成長するかは、環境次第なんだなと感じました。これが私の根源的な原動力となっています。今でも、お子さんに関わる時に一番大切にしていることです。
療育現場の特性にまつわる構造的な問題
仲村:一方で、スタッフの皆さんそれぞれに「子どもたちを信じたい」という思いがあったとしても、「何をどうすれば子どもたちのためになるのかわからない」という意見も、いろいろなところで見聞きしてきました。
その理由は、もしかしたら自分の領域から出ていくのがつらいことだからというのもあるかもしれません。私はたまたまグアテマラで極端な体験をしたので、自分の専門外のことも率先してやる、ということを身につけてきました。けれども、一般的にはつらいことです。
どの療育現場も、おしなべて人手が足りません。そんな中、専門性の高い資格を持った人がスタッフとして入ってきた場合でも、時に専門外の仕事を求められることもあります。つまり、「私はこれだけやります」という姿勢だと、きつい言い方ですが役に立たないとも見なされかねません。
しかしながら、国家資格や医療機関での業務経験があるなどの専門性を備えた人ほど、日常的・包括的なケアや支援を提供する放課後等デイサービスなどの現場では「私はこういうことをやりたかったんじゃない」と辞めちゃうというケースもあるとよく聞きます。
――それは療育現場の特性にまつわる「構造的な問題」と考えられそうです。しっかり専門的な勉強をして、かつ経験を積んだ人ほど、理想と現場のギャップに苦しむかもしれないということですよね。
仲村:そうですね、例えばリハビリの専門職が知識と経験に基づいて他のスタッフにアドバイスしたとしても、「リハの人はわかってない」と受け取られてしまうこともあると思います。
ただ、自分の専門性が、ほかの専門性を持ったスタッフの仕事にどう生かせるかという関わり方をすると、何かいいものが生まれる気もします。
私は以前、施設で働いていた時にある保育士さんに言われた内容が今でも印象に残っています。それは「私は保育士だから遊びを考えるのが仕事だし、楽しいのだけれども、今ここにいる子どもたちは自分が考えた通りの遊び方が難しいことがある。でも仲村さんがいると、その子の状態に沿ってアレンジしてくれる」というお話です。私はそれを受けて自分のアプローチは間違っていないなという確信を得ることができました。
――実りあるチームビルディングのために、自分の専門性をほかのスタッフが生かせるようにシェアしていくという意識付けができると、それが突破口になるのかもしれませんね。
少しずつ自分を超えるかかわり合いが、療育現場をチームにする
――仲村さんのお話を伺いますと、「子ども中心の療育現場の創造につながるチームビルディング」というテーマを考えた場合、ひとつ重要なポイントがありそうです。それは「スタッフがそれぞれの専門性を生かしながら、少しずつ超えたかかわり合いを作り出す」ことです。言い換えると、「自分を生かしつつ、通常の役割分担を超えた協力ができる雰囲気作り」が大切だということでしょうか。
仲村:施設で働いていた時、預かった子どもをお風呂に入れようというタイミングがありました。しかし、その時、お子さんの腕の筋緊張が強く、グっと握り込んでしまっていました。私はその時、同僚のスタッフさんと2名体制で入浴介助をしていたのですが、「腕の構造上、こうやって、こうやって動かすと開くんですよ」と実演しました。するとへえー本当だ、と感心されました。解剖生理学的には、扱う関節を一度に何個も動かすのではなく、1個ずつ関節を操作していくのがセオリーだと知られています。
ここから転じて、ストレッチの講習などもやりました。よく施設では子どもを抱っこしますが、まずは自分の体のケアが大切だからです。あとは、ベッドの高さの調整など介助がしやすい環境整備の提案もしました。その結果、直接私がお伝えしたわけではないのですが「仲村さんのだっこの仕方をまねしたら疲れにくい」というコメントを受けたこともありました。
――仲村さんが培ってきた身体に関する知識や技術を、ほかのスタッフが享受できるように、うまくアレンジして伝えたわけですね。
仲村:総じて皆さん、「子どものためになやりたい」という純粋な思いがあります。しかし、現場にいるとどうしても、その純粋な思いが貫きにくくなるという状況がありそうです。何かしらのきっかけを通じて、役割分担を少し超えていく関わり合いができる雰囲気をつくることがポイントかもしれません。
――今回の記事で議論してきた話題は、経営学の世界では組織論や人材マネジメントに類するものです。学術論文や書籍を探すと、「病院経営の組織マネジメント」に類するものは比較的充実していますが、「療育現場の組織マネジメント」や「療育現場の人材マネジメント」は少ない印象です。
仲村:その理由としてひとつ考えられるのは、特に放課後等デイサービスについてはその制度自体が平成24年(2012年)からと、業界全体の観点で見ればまだまだ若い制度で、経験に基づく確かな指導ができる人がほとんどいないことです。
放課後等デイサービスの制度が生まれてから、施設のオープンが各所で相次ぎました。「自分の子どもが障害児なので問題意識を持って経営者として施設を立ち上げました、指導員になりました」という人も多くいて、想いをもって頑張っている人たちが現場にはたくさんいます。しかし、どうしても歴史が浅い制度とそれに基づく組織形態ならではの課題があるのだと思います。
厚生労働省が公開した「放課後等デイサービスの実態把握及びに関する調査研究報告書※」によれば、放課後等デイサービスに勤務している人のうち、5年目という人さえも少ない現状があります。現場では経験者が少ない中で、どうやってマネジメントや指導をするのかという難しい状況に直面しているケースが多いのではないかと思います。
――だからこそ、療育現場をグループからチームに変えていくために、何か共通的な課題なのか、何が突破口になりうるのか、調べていく必要があるかもしれませんね。
(次回に続く)
(聞き手・構成は高下義弘=編集者・ライター)
※この報告書は令和2年(2020年)3月に公表されたもの。URLはhttps://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000654183.pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
