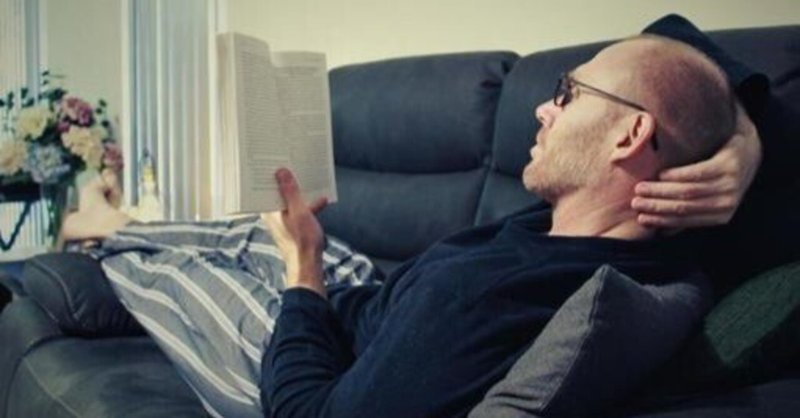
【読書】2023年1月に読んだ本
当月に読んだ本を紹介します。
・伊藤和夫著『英語構文詳解<新装版>』駿台文庫
私はまったく英語を話せない。なのに秋ごろに欧州で短期間仕事をする可能性がありアタフタしている。しばらくしたらビジネス英会話を始めるが、その前に「キックを入れる」必要があるので、受験英語の参考書を繰り返し読むことにした。著者のことをあまり存じ上げなかったが受験英語の巨人らしい。あと10回くらい読みたい。
・小原照記・藤村祐爾著『Fusion 360 マスターズガイド ベーシック編 改訂第2版』ソーテック社
正十二面体スピーカーの作製のため。
・戸田山和久著『思考の教室 ─じょうずに考えるレッスン』NHK出版
酒井・吉川両講師による「非哲学者による非哲学者のための哲学入門読書会(https://socio-logic.jp/nonPhilo/bookclub.php)」の第二期テクストとして指定されているため。私は第一期第二期の6回通し券を購入している。第一期開催期間中は運悪く体調不良が続き1回しか出席できなかった。第二期はまじめに全回出席したい。
戸田山本は約20年前に『知識の哲学』(産業図書)を読んで以来。口語体は、見かけ上は読みやすく理解しやすいように感じるが、著者自ら設定した課題、その解答のために著者が用意した素材(読者にとって既知のものと未知のものがある)、そしてその素材の組み合わせによる課題への解答、などが見分けにくくなっており、英語の学術論文などに比べて読み進めるのに時間と根気を要する。
日常的に口頭で交わしている言葉遣いは本書の口語体より情報密度が薄く非論理的なわけで、すると、日ごろの発話内容から主張内容を明確に理解するのは、論文や本を読むよりはるかに難しいことになる。
・國井良昌著『ついてきなぁ!設計トラブル潰しに「匠の道具」を使え! FMEAとFTAとデザインレビューの賢い使い方』(日刊工業新聞社)
会社で管理規定の更新をなりゆき上担当することになり、意見収集するために通読。
本書には「品質」というビッグワードは冒頭の2,3ページにしか登場せず、代わりに「設計トラブル」または「トラブル」という単語を用いて説明が続く。著者によれば、トラブル発生の原因は「ディスカッションの欠如」である。
本書には「設計」と「トラブル」という単語が何度も登場するが、この単語の意味を明確に書き表した箇所はない。ただし通読すると、これらは以下の因果関係にあるものとして描かれていることが分かる。
①ディスカッション【増】
→②設計(現実と机上計算の一致)【改善】
→③組織のDNA【改善】
→④トラブル【減】
③について触れる箇所はほとんどない。本書は上記の因果関係を所与のものとして宣言したあと、②に絞って、職場で流通させるべき新しいイディオムを取り扱う。
この新しいイディオムは簡単だ。「故障事例」と「故障の回避方法」だけしか含まれていない。故障事例は会社の過去にしか存在しないから、クレーム記録を紐解けば設計者も管理者もアクセスできる。故障の回避方法は単に論理的なものだから、設計者も管理者もその適否を意見できる。
こうして新しいイディオムは設計者と管理者の共通言語となる。両者はそうして初めてディスカッションを始めることができる。さすれば若手設計者の誇りも勤労意欲も高まり、製品の信頼性が高まり、再びわが国の製品品質が世を席捲するであろう・・・
この方法では、新規技術を用いた設計を取り扱うことはできない(過去事例しか参照できないから)。ご丁寧にも以下のようにクギを刺す場面がある。
ある技術者は、安易なパイオニア精神からQCDに関わる新規技術を、いきなり開発商品に導入してしまう場合があります。技術の神様はそれを許してはくれません。98%中の約33%の割合でトラブルを引き起こすのです。
技術の神様!
野球の神様や将棋の神様は聞いたことがあるが、技術の神様は初耳だった。冒頭の因果関係の、有無を言わせない導入の仕方もふくめ、著者はどうも運命論や決定論に近い考え方を持っているようだ。達人というものは、事の帰結を、自分の意思から離れた懲罰や恩寵のように捉えたくなってしまうのだろうか。インシャラー。
本書は、設計を担う職場のイディオムや対話ルールを扱っている。本書はここまでは言っていないが、これを制度設計と呼んでも差し支えないだろう。
製品設計は制度設計を前提とするのだ。
カール・ワイク著『組織の社会心理学』(遠田雄志訳、文眞堂)で指摘されたとおり、職場の人々というものは、過ぎ去った出来事でも経過中の出来事でも、自分たちが何をしているのか解釈しその都度理解しながら振舞っている。
本書には、組織自身が、設計という出来事の解釈・理解・振る舞いを観察し、組織自身でその適否を判定する仕組み ─組織の意思決定─ の一様式が示されている、と理解したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
