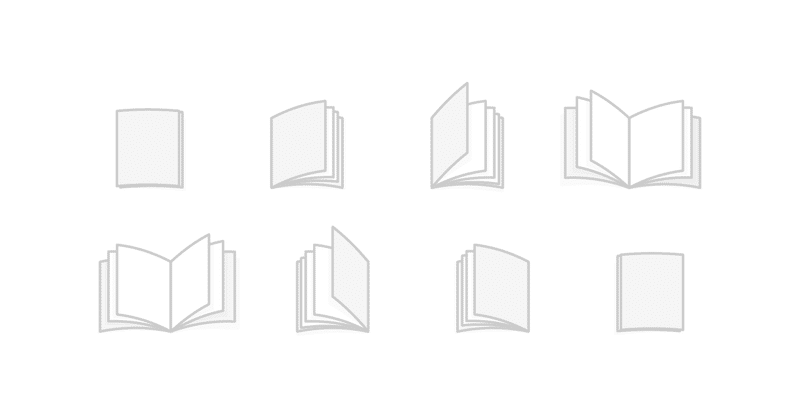
「嫌われる勇気」
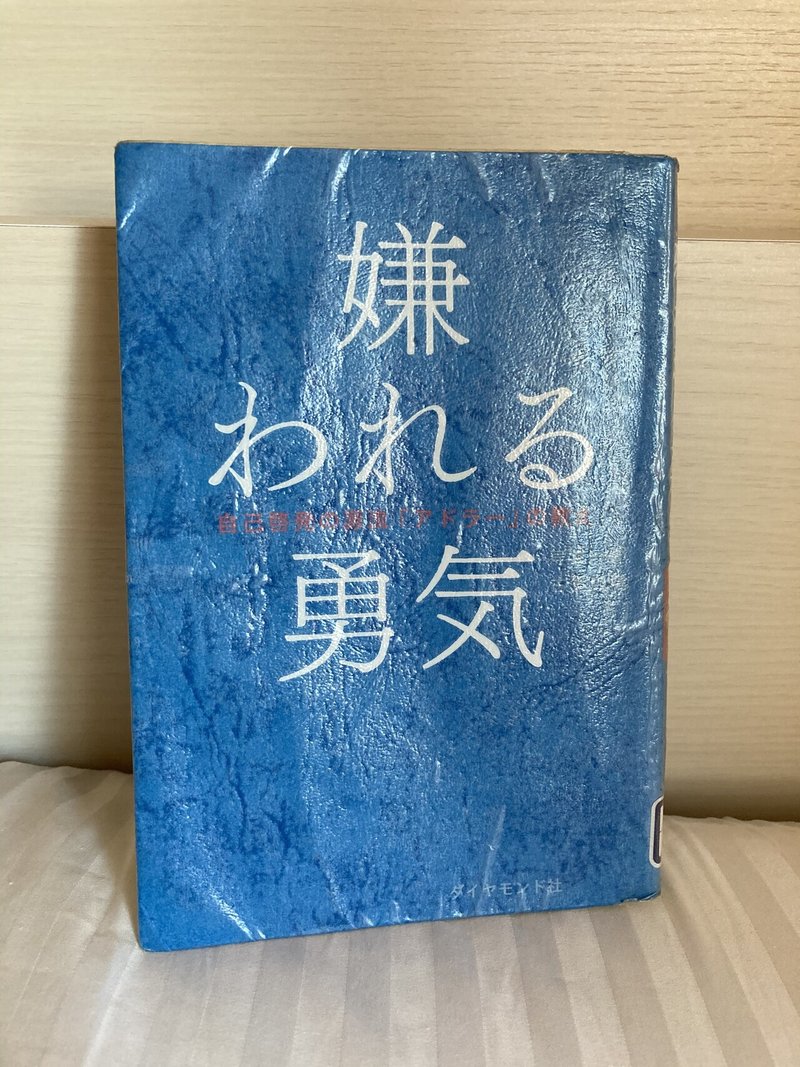
[きっかけ]
ずっと話題になっていた本だったので一度は読んでみたいと考えていた。
[感想]
本書は青年と哲人の二人の登場人物が会話することによって話が進むが、こういった形式に触れるのは初めてだったのではじめは抵抗感があった。しかし、読み進めると違和感なくページをめくることができた。漫画のようにスラスラ話が進んでいったような印象。
嫌われる勇気と一言で「アドラー心理学」のことだった。
アドラー心理学とはアルフレッド・アドラーが提唱した個人心理学のこと。哲人が青年の悩みやコンプレックスに対する答えとしてのアドラー心理学は私の中で革命が起きたほどの衝撃だった。
大学で個人的な趣味嗜好として心理学を履修したり、心理学の本を購入して読んでいたが初めて自分の思考・両親からの教育に準ずるのものに出会ったからだ。アドラー心理学に基づいた子供教育の本が数多く出版されているが、両親はアドラー心理学を知っていて教育に取り入れていたわけではなかった。私がある程度自己を理解しているうえでアドラー心理学に出会うには十分すぎるタイミングだと感じた。
この本を読んで一番心に残ったのは、
自分の経験によって何かが決定されるわけではなく、過去の経験に「どのような意味を与えるか」によって自分の生を決定している。
同じ国、同じ性別、同じような境遇であったとしてもそれぞれに異なる意味を与えていた場合にそれぞれの生き方やその後の人生は全く異なったものになるということだと認識した。
自分の人生は自分で決めるもの、よく言われる言葉だが実際に自分で決めている部分は個人によって大きく異なるのではないかとこの本を読んで思った。「親が大企業に行ってほしいというから大手に就職する」「コロナで経済が不安定だから安泰を取って公務員になる」「世間体悪くなりたくないからとりあえず就職する」などよく聞かれる言葉だが、それは本当に自分の人生を自分で決めているといえるのだろうか。本書では、人は他者の期待を満たすために生きているのではない。他者の期待など満たす必要がない、と述べる。自分以外に誰が自分の人生を生きてくれるのか、と。
本書では他人との付き合い方についても述べている。自分と他者の課題を分けること、それだけで人間トラブルが減る。例えば、子どもに勉強しろという親がいるがこれは子どもの課題に親が土足で踏み込んでいることと同じ。まったく子供のためにはならない。また、自分が相手を信じるか、相手が自分を信じるかもそれぞれの課題となるのでたとえ、自分が相手を信じるという選択をして相手が自分を裏切ったとしても、信じると決めたのは自分で裏切るという選択をしたのは相手の課題ということになる。相手の課題に対して土足で踏み込むことは対人トラブルのもとになりかねないし、そもそも分別しなければならないものだ。それをわきまえて生きてきたつもりだが、もっと意識して生きていこうと思った。
学ぶことが多かったアドラー心理学。「嫌われる勇気」の続編と位置付けられている「幸せになる勇気」も読みたい。
あとがきに著者とともにこの作品を作った古賀史健氏が著者の岸見一郎先生を通したアドラー心理学に触れた時に考えたように、岸見先生を通したアドラー心理学とそうではない他の著者のアドラー心理学、またアルフレッド・アドラー氏の著書を読み、比較してみたいとも思っている。
#女子大学生のしがない読書 #嫌われる勇気 #岸見一郎 #古賀史健 #アドラー心理学
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
