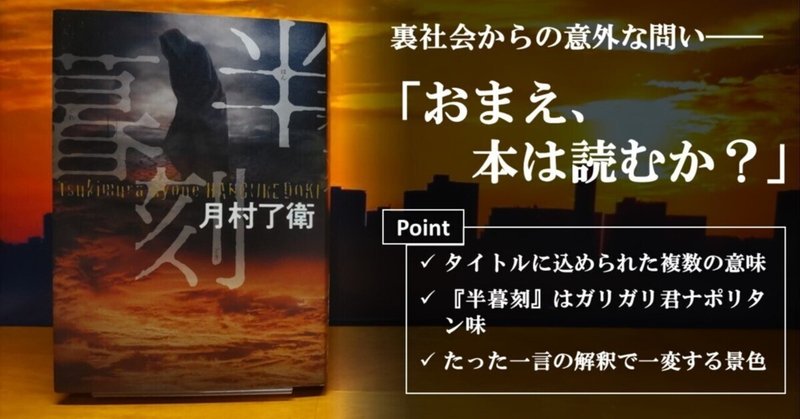
クライムサスペンスの皮を被った読書論 『半暮刻』書評
読後感という言葉がある。
これはいわば本の〝後味〟とも呼べるようなもので、これが良いものほど後の記憶には残りやすい。
基本的に世の人は刺激の強いものを好む。しかし大抵の場合、それは〝味〟に関する刺激であって、〝後味〟に関するものではない。そして〝味〟が刺激的なものというのは、およそ感想を聞いても「美味かった」「甘かった」「辛かった」と通り一遍の返答に堕しがちだ。
例えば(少し古い話題で恐縮だが)、「倍返しだ!」でおなじみの『半沢直樹』というドラマが一時おもしろいということで話題になった時期があったと思う。これは主人公の半沢直樹が逆境に立たされながらも信念を貫き、最後には不正を働く人間を大逆転で完膚なきまでに打ちのめすという痛快さが人気を博した。
この『半沢直樹』という作品についての感想を求めると、私を含めた大半の人は「すかっとした」というような感想を口にすることだろう。
一見これは〝後味〟のようにも見えるが、実のところこれは〝味〟に関する感想だ。〝後味〟というのはもっと思考の奥深くに根付き、折に触れては思い出すような――そんなもののことを指す。
無論これは、大和田の「お、し、ま、い、デスッッッ!」が脳裏にこびり付いて離れないというような低次元の話ではない。
今回紹介する『半暮刻』は『半沢直樹』からそういった刺激的な〝味〟を差し引き、代わりに深い〝後味〟を獲得したと形容できる作品だ。ジャンクフードがお好きな方はここらで退店願おう。刺激的な味を好む人を高級料理店に連れて行っても甲斐はない。
1.読み進めるたび深くなるタイトルの意味
物語は社会に出る直前の独特な青さを持った翔太と海斗がヤクザでもカタギでもない「半グレ」が運営するカタラグループのもとで女の子を風俗に落とすバイトをするところから始まる。
二人はコンビを組むことでみるみると成績を上げ、トップテンの仲間入りを果たし、羽振りのいい生活を手に入れ、その成功体験を<学び>と捉えて自己肯定感と全能感を形成していった。
しかしそんな生活が長く続くはずがなかった。
カタラは摘発され、主犯を含む八名とともに翔太は警察に捕まってしまう。一方で、海斗は運よくワッパをかけられずに難を逃れたのだった。
こうして当初裏社会のクライムサスペンスが滔々と展開されるものとばかり思っていた読者は突然に裏切られる。なにせ、ここまでが全体の五分の一なのだから驚きだ。
その後読者は、ヤクザの下っ端になる翔太と大手企業のホープになる海斗という鮮烈なまでに対照的な二人を目の当たりにする。
肩書だけを見ればあたかも海斗の方が更生して社会復帰を果たしているように見えるわけだが、そう話が単純であれば面白みは随分と減じてしまっていたことだろう。
さて、本書は前半が「翔太の罪」、後半が「海斗の罰」というドストエフスキーを彷彿とさせる二編からなっており、この対照的な構造こそが本書の駆動力になっている。換言するならば、翔太と海斗という二人の人物がその後どう生きていくのかに紙幅を割いた作品が本書なのである。
そしてすでにお分かりのこととは思うが、『半暮刻』というタイトルは「半グレ」という言葉に引っ掛けたものになっている。半グレ時代を経験した二人の物語と考えれば確かにピッタリな命名だ。
しかし、私にはどうもこのタイトルにはそれ以外の含意もあるように思えてならない。
陣能はヤクザで黒だ。城有は半グレで灰だ。黒と白を混ぜ合わせたら、どうしたって灰なんだ。決して白ではありえない。つまるところ黒なんだ。でも俺は考え違いをしていた
何が黒で何が白なのか、その境界線を見極めながら本書を読むことによって――つまりグレーという色を読者が白と黒に腑分けすることによって、この小説はコントラストを増し、初めて輝いて見えてくるのではないだろうか。
2.二人の人生が浮き彫りにするもの
本書では折に触れて山括弧付きの<学び>という言葉がたびたび登場する。これは<気づき>や<向上心>という言葉も同様だ。
ときに、翔太と海斗はカタラでバイトをする際、女の子を<F>に落とすテクニックを<マニュアル>から習得していた。そしてその内容を忠実に実行し、それによってトップテンにまでのし上がった経験が彼らにとっての<学び>となっていくのである。
この<学び>をその後の人生でも実践し続けたのが海斗だ。実際彼はカタラの件で逮捕されなかったのを良いことに、大手企業への就職を成功させ、ホープとしての地位を確立し、傍目には順風満帆と見えるようなキャリアを形成する。海斗はこの輝かしい自分の姿こそはカタラ時代の<学び>のおかげであると固く信じていた。
一方で翔太はというと、懲役三年の刑期満了後、ヤクザに身を窶し、一種の虚無主義に陥って今にも無気力・無感情の中に消え入りそうな様相を呈するようになる。かつて自身の生活をうなぎのぼりに向上させ、自己肯定感を徹底的に裏打ちしてくれたはずの<学び>は、ときこの場合に至って何らその役割を果たそうとはしなかった。
そんな時、彼を救ったのが『脂肪の塊』だった――なんて言ったら笑われてしまうだろうか。
これは名作と言われる古典、モーパッサン著『脂肪の塊』という短編のことを指しており――などと書けば随分ものを知っているように見えるのだが、私が当初肥満体質の男性を想起していたことは言うまでもない。
とはいっても、『脂肪の塊』が直接翔太に心機一転するような強い衝撃を与えたわけではない。そもそも、娼婦が戦火に追われて馬車で逃げ出した折、敵軍占領地を通過するために同乗者たちに敵軍仕官と寝ろと迫られ、結局その通りとなった挙句、同乗者からはのけ者にされる――というような救いの欠片もない話で生きる活力を取り戻せるものなら取り戻してみろといいたい。
要は、『脂肪の塊』はきっかけに過ぎなかったのだ。『脂肪の塊』を読んでから翔太は『オリヴァー・ツイスト』、『赤と黒』など次々と小説を読むようになっていく。
そしてふと思った――<マニュアル>とは大違いだ。
この<気づき>を機に彼の人生は徐々に変わっていく。彼と本を繋いでくれた一人の女性と交流を深め、彼自身それと知らずに背を向けていた過去と向き合い始めるのである。
3.ガリガリ君ナポリタン味
さて、原点回帰して『半沢直樹』の話に戻ろう――と言ってしまうとこの文章が『半暮刻』についてのものではなくってしまうのでいけないな。とりあえず、冒頭の話題に話を戻そう。
最初に私はこの小説を『半沢直樹』から刺激的な〝味〟を差し引いた代わりに、深い〝後味〟を獲得した作品だと評した。その理由というのをここで詳らかにしていきたい。
若干ネタバレになってしまって恐縮なのだが、物語の終盤、海斗は最終的にとかげのしっぽ切りにあって凋落の一途をたどる。海斗の就職した大手企業というのはその実、中に腐った肉塊を詰め込んだ宝石箱のような企業で、組織悪が是とされる社風を持ったとんでもない企業だったのだ。
しかし〝とかげのしっぽ切り〟と表現したように、本書は『半沢直樹』のように組織悪が一網打尽にされるような話にはなっていない。また海斗についても、法の下で裁きを受け、完膚なきまでに打ちのめされる――というような展開にはならない。尾羽打ち枯らし、膝をつくような惨めな姿が描かれるわけではないのだ。
つまり何が言いたいのかというと、本書には読者がスカッとするような〝ざまぁ展開〟が用意されていないのである。これが万人にオススメが難しい所以の一つだ。
仮に『半沢直樹』をオススメするのがガリガリ君のソーダ味を誰かにオススメするようなものだとしよう。では『半暮刻』はどうかというと、これはガリガリ君のナポリタン味を誰かにオススメするようなものなのだ。なかなか万人に受け入れられるものかどうかわからない。
尚、そもそもガリガリ君が苦手な人がいるんじゃないのかという指摘はこの際黙殺するものとする。
一方で、〝ざまぁ展開〟という万人受け要素を控えた代わりにこの小説が獲得したものは非常に大きかったのではないかと私は考える。逆に言えば、もしこの小説が〝ざまぁ展開〟を積極的に取り入れていたとすれば、この小説の意義は大いに損なわれてしまっていたことだろう。
要するに本書は一瞬で過ぎ去ってしまう刺激的な〝味〟ではなく、後に残る〝後味〟をとったのである。では、その〝後味〟とは一体何なのかという話になるが、次からはそれを論じていこう。
尚、ナポリタン味のガリガリ君に〝後味〟があるかどうかという議論は捨て置くものとする。
4.たった一言の解釈で一変する景色
さて、先にも言及したように海斗は大手企業から解雇されても絶望の前に膝を屈するどころか、「次はもっとうまくやる」と考えるようになる。つまり、全く反省というものをしていない。
そんな中、カタラ摘発以降一度も顔を合わさなかった海斗と翔太が各々の<学び>を胸に再会を果たす。
「海斗、おまえ、本は読むか?」
物語の最終盤、翔太は海斗にこう問いかける。
さて、これに対する海斗の返答について言及する前に、ここで一度海斗の過去の言動――すなわち腐肉の詰まった宝石箱での1シーンを取り上げておきたい。
「なにこれ?」
手に取って書名を見る。『掃除婦のための手引書』とあった。
「せっかくアドルーラーには入れたってのに、君はウチを辞めて清掃業にでも転職する気?」
「違います。それはルシア・ベルリンの短編集で……小説なんです……深夜は待ち時間も多いから、せめてもの息抜きにと趣味の読書を……」
「なんだ、息抜きの時間があるんじゃないか」
(中略)
彼女は自分のように<学び>をしてこなかったのだ。<努力>してこなかったのだ。だから<向上心>に欠けているのだ。
「小説なんか読んでいる暇があったら仕事をしろ」と海斗は(あくまで彼の基準で)無能な社員を非難するのである。
では、これを踏まえたうえで海斗の翔太の問いに対する返答を見てみよう。
「あのね、僕はG大卒なんだ。少なくとも君の百倍は読んでるよ」
本書の最後のページに登場する海斗のこの言葉をどうとらえるかが本書を読むにあたって最も重要な部分ではないかと私は考えている。
無論、この文章は額面通りに受け取ることも可能である。〝本を読むような人間ではない〟という昔の評価のまま翔太と接している海斗にとって、それが実際に真実であるように思われたであろうことは想像に難くない。
しかし、私はこの解釈の他に少なくとも二通りの解釈を導きたい。
その一つ目の解釈が〝海斗の虚栄心の表出〟だ。
この問いが海斗へ投げかけられる前、翔太は家庭を持って子供を授かったという話を海斗にしていた。一方で、海斗はその凋落の中で大手企業のホープの座だけでなく家族すらも失っている。曲がりなりにも楽しみにしていた我が子との対面を果たすことすらなく――である。
翔太よりも<学び>を得ているはずの自分が彼なぞに劣るはずがない。そんな心境が海斗の中に生まれていたのではないか。そう考えると、海斗の返答は単純な見栄、つまり嘘として解することができるように思う。
そしてもう一つの解釈が〝読書対象の差異〟だ。
これは海斗の返答事態は額面通りの意味ではあるが、翔太とは読んでいるものがまるで違うという解釈である。
既に述べたように翔太は小説を読むようになっていた。一方、海斗が本を読んでいるというのが事実であるとした場合、果たして彼は一体何を読んでいたのだろうか?
ここで鍵となるのが山括弧で囲われた語句の数々だ。
<向上心>、<気づき>、<努力>、<学び>……エトセトラエトセトラ。
なんとも都合のいいことに、今日書店に行けばこれらを<マニュアル>化したものが魑魅魍魎の如く跋扈しているのが目に入る。
おそらく海斗が「読んでいる」と言ったのは、まさにそういう類のものを指しているのではないだろうか。そう考えると、クライムサスペンス小説が途端にぐっと身近に感じられてくるから奇妙なものである。
5.〝後味〟とは〝グレー〟である
何が正しい解釈とか、そういう議論をするつもりは私には寸毫もない。そもそも、私の胸中では前述した二つの解釈が黒と白の比率を分けるが如く〝グレー〟として混じり合っているような塩梅である。
きっとこの先、他の文章に触れた時、あるいは実生活のふとした時に私の中でこの黒と白の比率がはっきりわかったような気がする瞬間がくるのだろう。
これこそがまさに〝後味〟である。「あぁ、あれはこういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間――そのカタルシスを後に残してくれるのだ。
たしかに太極図が如く最初から黒と白がはっきり分かれているのは分かりやすくてよろしい。「おもしろい」「おもしろくない」で語るのも簡単だ。しかし私が思うに、読書においては先に取り上げた海斗の言葉のような〝グレー〟こそを楽しみとしなければならないのではないだろうか。
『半暮刻』はこのように、読書について考えさせてくれる物語なのである。
しかし、こんな玄人を気取ったいけすかない筆者のような読み方を万人にしてほしいというわけでもない。
ここまで書いてきておいて元も子もないようなことを言うようだが、本書は多少外連味に欠けるとはいえ純粋な物語としても十分に楽しめるものとなっている。なので、本記事を読んで少しでも興味が湧いた方は是非手に取ってもらうことをオススメしたい。
――とは言って見たものの、どうやらすでにジャンクフード好きのお客様はどこかへいってしまったようである。はてさて、どうしたことだろう。
……。
わからない。だが、多分私のせいではないだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
