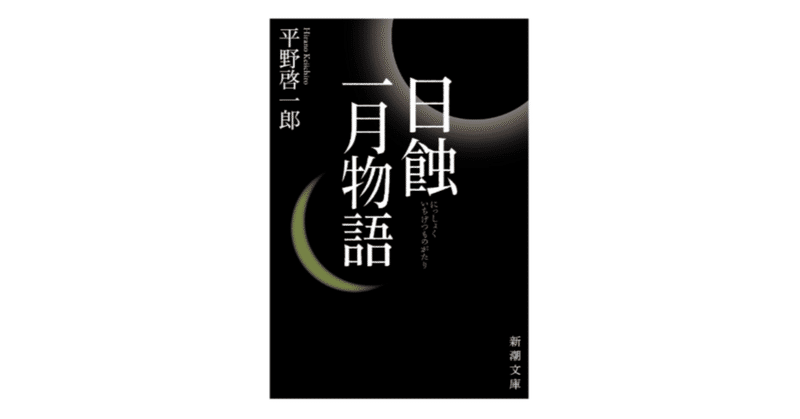
なりすましと変身2 (平野啓一郎試論)
【警告】
小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。
このテキストは『平野啓一郎論』の第五章です。
最初から読みたいという方はクリエイターページのマガジンをご覧下さい。
錬金術(一体の体験)
平野の初期三部作「日蝕」、「一月物語」、『葬送』の表立ったテーマは「二元論の統一」である。特に「日蝕」は、全編「統一」の暗示に満ちている。
「フェカンにて」の小説家大野の処女作は『太陽と月の結婚』というタイトルなのだが、これが平野の「日蝕」を指すのは自明だろう。「太陽と月の結婚」とは「反対の一致」を表す錬金術の用語だが、現象としては「日蝕」なのだから。
具体的には、「反対の一致(二元論の一致)」は、太陽と月、男性と女性、生と死、熱と冷といった一見真逆のものが統合されることを意味する。
錬金術の理想において、神が創造したこの世界は完璧である。完全な神が創造した世界が完全でない筈がない。それが完全でないとしたら、本来のバランスを失っているからだ。
たとえば、全ての金属において「金」が、その本来の姿なのである。錬金術とは、金を作り出すものというより、金属本来の完全形を取り戻すための作業に他ならない。
「日蝕」の錬金術師ピエェル・デュファイも「金属は、窮極に至っては必(かならず)黄金たるべき」であると言っている。
ピエェルは、錬金術を結婚に譬える。
「結婚は、本質が熔け合う。以前の本質を矛盾した儘保ち得る。有らゆる対立は一なる物質の裡に解消せられる。その物質には、完き存在そのものが、ありありと現れる」
「太陽と月の結婚」とは男性原理と女性原理の結婚であり、完全体を取り戻す儀式である。
巴黎(パリ)大学で神学を学んでいた「私」は異教徒の哲学書を探し求め旅に出る。
「私」は異教哲学を放置するのではなく、神学と統合しなければならないという固い信念を抱いていた。ここでの「異教哲学」とは『決壊』の〈悪魔〉がバラ撒いた犯行声明のようなものだ。思想(言葉)は人の身体に侵入し、その者を操る。悪は徒らに排除するのではなく、体系の中に従属せしめなければならない。「有らゆる対立は一なる物質の裡に解消」せしめねばならない。
ある村に辿り着いた「私」は、夕食後に村を歩く。
村の中央には直線状に川が流れている。南西側は川を直径とする半円状の土地である。また、北東側は川を直角の対辺とする直角(二等辺)三角形を形作っている。直角の頂点には石造の家がある。ピエェル・デュファイが住む家である。つまり、この村は南西側が半円、北東側が正方形を対角線で切断したような形になっている。村は、円と正方形の合成である。
「私」はピエェルの家を訪れる。ピエェルは無口な男であり、「私」を無表情のまま迎え入れると、何の説明もしないまま黙々と錬金炉に向かって作業に勤しむ。
ピエェルの面には焰の赫(かがや)きが踊り、焰は肉に食込む。奇妙なことに、ピエェルと錬金炉は一体化したように見える。
また、物語の終盤、捕らえられた両性具有者(アンドロギュノス)は異端審問にかけられ、焚刑に処せられる。火がアンドロギュノスの足下に迫ると、轟音が鳴り響き、空には日食が起こり(太陽と月の合一)、巨人が現れ性交する(男女の合体)。アンドロギュノスは男性器から精液を発射し、その精液は自らの陰門へと流れ込む。
その時、「私」は自分自身が焚刑に処せられているように感じた。アンドロギュノスは「私」だった。「私」は世界に包まれる。
「日蝕」は、全編を通して「統合(合一)」のイメージを描く。
さて、「一月物語」も表向きは二元論の合一をテーマとしている。
井原真拆は自我の分裂に悩む青年である。彼は、西洋の自由主義思想に触れ「個人」としての自立した生き方に憧れた。
自我がそこにあるとして、その自我を発見した己とは一体何であろうか。その場合、自我は二つ存在するのか。
真拆は、二元論の相剋に苦しみつつ、いつしか超越的な存在との一体化を願うようになっていた。
また、ショパンの死を中心に描く『葬送』は、一見、統合のドラマには見えないが、これもまた二元論の合一に関する物語である。
何故なら、ポーランド出身のショパンは全スラヴ民族統合の象徴だからである。ロシアは、ポーランド独立の旗印にされることを恐れてショパンを警戒している。
そして、もう一方の主役であるドラクロワは古典主義とロマン主義の統合の象徴である。彼は、安易に古典主義の克服を唱えるロマン派の画家達にも与しないし、ロマン派を単に古典主義の洗練と考える古典派にも同調しない。彼が願うのは、古典派とロマン派の統合である。
「火色の琥珀」は焰に見入られた男の話だ。
同性愛者ではないが女性にも興味の持てない「私」は、焰を見つめている間だけ勃起し、性交が可能である。
彼が、ランプの炎に囲まれて休んでいる時、地震が起き、セーターに燃え移った炎で全身火だるまになる。一命は取り留めるが、全身の火傷で皮膚が壊死し、ケロイド状になり、おぞましい姿となる。しかし、やがて鮮やかなピンクの皮膚が再生し、彼は「変身」を経験する。その肌を見ていると、自分でも「一度死に、再生した」と感じるのだった。
『決壊』で、溶鉱炉の技術者だった治夫は錬金術師にも似ている。
治夫は、溶鉱炉の中で孫を焼く夢を見る。
鉱炉は生きものだと、治夫は息子たちによく語っていた。
治夫は、屹立する巨魁な鉄の子宮を眩しげに見上げ、崇は母親である和子とキスをしている。
溶鉱炉とは子宮であり、孫の「たっくん」は死ぬと同時に生まれている。実際、孫は家族の中で一番若いのである。
息子の嫁であり、孫の母親である佳枝は数珠を持っている。
これら夢の全てが、死と生の合一、死と再生を象徴している。
溶鉱炉とは錬金術の炉であり、火葬場であり、かつ子宮である。
また、治夫が苦労して集めた枕木がコークスに入れ替えられていると良介が語るのも面白い。ここでは、コークスは治夫の大切な枕木の成りすましである。
「初七日」では、父を亡くした康蔵は霊柩車に乗り火葬場に向かうのだが、そこは幼い頃に見学に行った製鉄所の溶鉱炉を思い出させる。ここでも火葬場は溶鉱炉であり、錬金炉である。
幻想的な短篇「清水」では、清水が滴るとともに「私」は足下の時間へと浸透していく。
「私」はまさに死につつある。
清水の滴った先が死だ。自分の死は、きっと、水銀のような溶解しやすい金属に似たものなのだろうと「私」は思う。
ちなみに「日蝕」では、錬金術で不可欠の賢者の石を得るために硫黄水銀理論というものが説かれていた。水銀は、錬金術において最も重要な金属である硫黄と水銀の一方である。
従って「清水」にも錬金術(死と再生)のイメージが煌めいているのである。
そして、「日蝕」に登場するアンドロギュノスは、死と生の象徴であると同時に、結婚(性交による両性の合体)の象徴でもある。
女性器と肛門にバイブレーターを突き立てられた姿を曝された『顔のない裸体たち』の〈吉田希美子〉は、村人の前で焚刑に処せられたアンドロギュノスを思わせる。
〈吉田希美子〉は、ネットで知り合った〈片原盈〉の強引な説得で、行為の最中を撮影されるようになる。写真と動画はCDーROMに収めて渡された。〈吉田希美子〉自身も、徐々に撮られることの快感を知っていった。
〈片原盈〉は、〈希美子〉の裸体をハンドル・ネームの〈ミッキー〉として、ネットの掲示板にも投稿する。彼女は、それを知ってもさほど怒らない。
〈吉田希美子〉は、カメラによる他者からの視点を通じて、〈ミッキー〉という異質な存在との、全的な、即自的な統一を初めて真に実感したのだと、平野は書く。
ネットでの〈ミッキー〉としての自分と、現実世界の〈吉田希美子〉という存在。
その「全的な、即自的な統一」とは不可解だが、この時、平野は、もしかしたら三島由紀夫の『金閣寺』を思い浮かべていたのかも知れない。
「『金閣寺』論」(『三島由紀夫論』)で平野は、『金閣寺』において、〈心象の金閣〉と〈現実の金閣〉が同じ「金閣」という固有名で呼ばれていることが、この作品の混乱の原因だと論じている。溝口の内界と外界にはそれぞれの〈金閣〉があり、それらは乖離している。作者も、それらを区別するべきだったと言うのだ。
〈心象の金閣〉とは、幼い頃から父によって語られた幻想の金閣である。初めて目にする〈現実の金閣〉は、それと釣り合わない。〈現実の金閣〉は〈心象の金閣〉の物象化であり、美しくあらねばならない筈なのに。
現実の〈金閣〉は黄金の〈美〉に取り囲まれている。その壁が消滅すれば、その一郭は周囲の世界と連続し、欠けるところのない全体を形成するのであると平野は論じる。
現実の〈吉田希美子〉と、映像の中の〈ミッキー〉。
彼女は、パソコンのモニターに映し出された自分の裸体を見て、淫らな想像を掻き立てている男たちを想像する。
「彼女の顔は、彼女の性器と肉体的に連続した。その輪郭は、一本の線として、彼女という一個の個体の周囲を途切れなく一周して結んでいた」
彼女は、自分の身体を舐めるように眺める男たちの視点を手に入れることによって、やっと自分という輪郭線を取り結ぶことが出来たのである。彼女は自信を得る。
あらゆる属性を取り払われた〈吉田希美子〉の身体は〈ミッキー〉の裸体と重なり、合致する。
『決壊』では、治夫の妻和子が生と死の合一を経験する。
息子である良介が殺され、兄の崇が殺人容疑で逮捕された和子は精神に異常を来す。
和子は良介の骨壺を肌身離さず抱いたまま一日を過ごすようになる。遺体をバラバラに捨てられてしまった良介の骨が揃わないため、納骨はまだ叶わない。彼女は、五体揃うまで良介を手放す気はないのである。
和子は骨壺に微笑みかける。彼女は再び懐妊した。死を受胎したのである。
崇の時は、赤ん坊を義母がすぐに取り上げてしまった。その経験がある和子は、良介の時には、お腹の中の子とよく会話していたのだった。骨壺を優しく撫でさすり、小声でささやきかけ、満ち足りた気分になった。
和子は良介と一つになる。
それは、佳枝がお腹にいる良太に向かって話しかけていたのと同じ光景である。異なるのは、佳枝が生者を抱き、和子が死者を抱いていることだが、生と死の合一が可能なら、両者は変わりない。
和子は狂うことが出来た。和子は平野作品において最も幸福な人間の一人である。
2024.2.9 文章を読みやすく修正しました。内容に変更はありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
