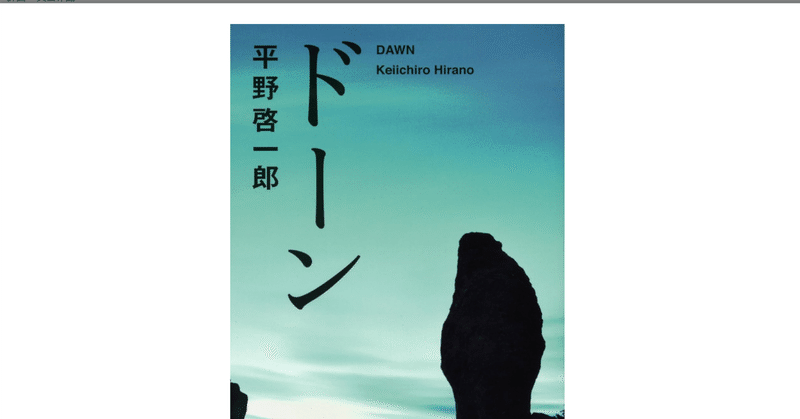
身体、場所と言葉 3(平野啓一郎試論)
【警告】
小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。
このテキストは『平野啓一郎論』の第三章です。
場所の言葉
第一章で述べたように、分人主義の核心は「個人は分割可能だが、他者との関係は分割できない」という点にある。
『決壊』の佳枝は、お腹の中の我が子に話しかける。約束を守って予定日にきちんと生まれてきてくれた我が子を自分の分身のように感じる。それは他者でありながら自分自身でもある。
繰り返すが「個人は分割可能だが、他者との関係は分割できない」。
この時、佳枝に生まれた分人関係は、母子という最も濃密な分人関係である。
佳枝は出産によって自分が分割され分身が生まれる経験をした。それは佳枝のファンタジーに過ぎないが、とはいえ、ここでは母子の関係は切断不可能である。それは分身なのだから。
平野は「「多生懸命」もたらす世界へ」(『モノローグ』)で次のように書いている。
「一生懸命」という言葉は、鎌倉時代の御家人が領地を命懸けで守る「一所懸命」が転じたものである。その変化は、人間が場所から解放され、アイデンティティの根拠が生の軌跡へと移行したことを示す。個人の主体(人格)が対応するのは「一所」であり「一生」であった。人格の住処(すみか)である「身体」が分割不可能だからである。しかし、その事情はインターネットとサイバー・スペースの拡充により変化しつつある。私たちは、仮想現実に於いて自由な人格を持つようになるだろう。
場所に縛られ「一所懸命」で生きるしかなかった人間は、サイバー・スペースという「多所」を得る。分割不可能な「身体」から解き放たれ、様々な自由な人格を持つことが可能になったのだ。
佳枝は「一人の人間の命が、何もない外界の空間に、突如として兆した孤独な一点として、剥き出しのまま開始されるのではなく、必ず母親が現に所有している肉体の内側に、いわば場所を許される形で始まるという事実について、妊娠の期間中、折々思いを巡らせていた」。
人が自由にサイバー・スペースを持つとしても「場所という概念から解放」された訳ではない。人はどこかの場所に存在する以外にない。胎児にとって「存在を許された場所」とは母親の中である。
母子関係が、分人主義でいうステップ3の、特定の相手に向けた濃厚な分人関係であるとすると、「場所」との関係はステップ1の地域性にあたる。
「鎌倉時代の御家人」のような人たちにとって、どこで生活し、誰と分人関係を築くか、どこに存在を許され、誰と交流するかは、出自によってほぼ決まっていただろう。
現代人にとっては「人格の住処」も多様なものとなる。
「最後の変身」の「俺」は、そもそも場所によって自分を変化(変身)させていくのに長けている人間だった。父親が「転勤族」だったために子供の頃から何度も引っ越しを繰り返したせいである。
「俺」は他人に快く迎え入れられるための技術を身に着ける。クラスの一番凡庸な生徒を手本にしながら、そいつのすることなすことを真似するという方法だ。
どうせ数年いるだけの場所である。そつなくやり過ごすために「俺」は平凡な生徒を真似する。両親も「愛想のいい家族」という見かけだけを守ろうとする。「俺」は他人を全く信用していないが、彼にとって、誰に対しても感じの良い、決して嫌われない人間でいるのはたやすい。
しかし、そのような生活に嫌気がさした「俺」はついに引きこもりとなり自室を最後の「人格の住処」とする。彼はありとあらゆる役割(分人関係)を降りた。
また、「俺」は、自分という存在の稀薄さは、度重なる転校で人間関係が希薄なだけではなく場所にも関係していたという。
父親が勤務する百貨店が地方都市を中心として店舗を展開していたため、彼の家族は、パッとしない町ばかりを転々としていた。それらは、かつて製造業で栄えたものの現在は用済みとなり、歴史的な使命を終えた都市ばかりであった。「俺」の厭世観は、荒廃しつつある地方都市の姿と関係している。
世の中への不信感が頂点に達したのは、父親がマイホームを購入し、東京の郊外へ引っ越したせいであると「俺」はいう。地方ばかりを渡り歩き、虚構の役割を脱ぎ替えることでやり過ごしてきた「俺」にとって、東京はあまりに巨大だったのだ。彼は、大きな本屋で一生かかっても読み切れない量の書物を目にして圧倒された時のような感覚を味わう。
平野は「モノが魅了する街」(『文明の憂鬱 』)で、パリという洗練された都市について語っている。そこは、東京やニューヨークのように、「最後の変身」の「俺」が圧倒されるほどにモノに溢れ返っている場所ではないが、美術館や歴史的な建造物は飽きるほど存在するし、買い物をするにしても何ら不満のない街である。
彼は、小説というジャンルは、産業革命以降の「モノ」が恐ろしい勢いで充実していった時代の変化に対応して発展していったのだという。十八世紀文学において「場所」は本質的な問題ではなかった。しかし、スタンダールを経てバルザックに至る過程で、パリという「場所」が重大な意義を持ち始める。バルザックの執拗で過剰なモノの描写。それは、当時に人々にとって新しい現実であった。
『葬送』でも、パリと田舎の対比がしばしば描かれる。
パリのサロンに集うような階級の者たちにとって、郊外に保養に出かけるのは日常である。また、当時のパリは、度重なる革命と反革命によって政情は極めて不安定であり、実際に上流階級をターゲットとした暴動があちこちで起こっていた。田舎の別荘に引っ越すのは避難という意味もある。
また、病身のショパンにとって馬車や汽車の移動はそれだけで負担が大きいのだが、それ以上に、繊細なショパンにとって場所によって変化する対人関係(分人関係)が精神的にストレスになる。
パリでは毎日のように誰かが訪ねて来るので、気の休まる暇がない。天才の名を欲しいままにしているショパンといえども、サロンでの人間関係は活動に大きく影響するのだ。また、ちょっとした言動が噂となってパリ中を駆け巡り、それがいちいち神経に障る。
しかし、田舎では訪ねて来る者は少ない。分人関係が制限されショパンは安らぎを得る。ただし、金策のため強行したスコットランド旅行では、見知らぬ者たちに連日引き合わされたちまち病気は悪化してしまう。
田舎での生活で分人関係が制限されるということは、ショパンの愛人であるサンド夫人のように家族関係がうまく行っていない場合は、その問題が先鋭化するということを意味する。サンド夫人は、ノアンの別荘で、娘夫婦と決別する決定的な事件を起してしまう。
限られた分人関係というシチュエーションは『ドーン』でも描かれている。
火星探査に向かう宇宙船内でノノ・ワシントンが精神に変調を来す。ノノ・ワシントンは、明日人に、メルクビーンプ星人による脳へのウィルス攻撃により自分の記憶は汚染され書き換えが進んでいると必死で語る。火星探査のプロジェクト自体がメルクビーンプ星人の計画の一部であり、このままではクルーの一人であるリリアン・レインの身が危ないという。
妄言が止まず、メンバーに対して暴力を振るうようになったノノ・ワシントンは地球に帰還する日まで拘束されてしまう。
そもそも、有人探査で最も懸念材料とされたのが、二年半もの間、閉鎖環境において同じメンバーで共同生活するクルーの精神状態であった。
ノノ・ワシントンは訓練生時代にリリアン・レインと恋人同志になりかかったほど親密だった。彼が、その妄想の中で彼女に固執しているのはそのためである。リリアン・レインは、共和党副大統領候補の娘であり、かつて生物兵器の開発に携わっていたのではないかという疑いが持たれる危険な人間である。
ノノ・ワシントンの変調は、限られた変化のない分人関係によって、かつてのリリアン・レインとの分人が再び現れたせいだとされる。
これは『葬送』でサンド夫人の一家が別荘に越したせいで分人関係が固定され、くすぶっていた問題が表に現れてしまった状況と似ている。
「一区切りついた、という実感」(『考える葦』)でも、平野は「『ドーン』で〈分人 dividual〉という概念に至って以来、私はもう後戻り出来なくなってしまった。自己の把握の仕方も、他者の理解も、文学作品の見え方も変わった。例えば、漱石の『三四郎』や『坊っちゃん』などは、郷里と東京、郷里と松山といった二つの場所での分人化の視点抜きには読めない」と語っている。
平野自身が、北九州という田舎から京都という洗練された都会へ出て来た身であった。
郷里と東京、郷里と松山、田舎と都会、地方と東京、北九州と京都、火星と地球、ノアンとパリ。
既に紹介したように『私とは何か——「個人」から「分人」へ 』でも、彼は、京大に在学していた時に、高校時代の友人を大学の友人に引き合わせ、居心地の悪い思いをした経験を語っていた。
平野は、そこまでは書いていないので推測に過ぎないが、高校時代の友人との会話を大学の友人に聞かれる気まずさとは、北九州弁を聞かれる恥ずかしさもあったのではないか。
『葬送』で病身のショパンはチャルトリスカ大公妃の見舞いを喜んだ。それは、彼女が美しく聡明な女性であるだけでなく、祖国の言葉であるポーランド語を喋るせいである。彼は母国語で会話できることに心からの安らぎを感じる。ポーランド語を耳にし、傷が癒されるのを感じる。ショパンは母国語というものの神秘をこれまでよりもずっと強く感ずるようになっていた。彼の心の最も深い秘密を発見するにはポーランド語(彼自身の言葉)が必要なのである。
土地と言葉、そして土地の言葉によって育てられる人間は、それぞれが深く結び付いている。恐らく、分人関係と場所、言葉との連関は切っても切り離せない。
「北九州と、屋根の上の記憶——木村伊兵衛『川開き』」(『考える葦』)では、平野は、子供の頃、親に頼まれて、北九州の実家の屋根に上り、竹竿で柿の実を取った思い出を語っている。「落ちなさんなよ(落ちないようにね)」と下からかけられた北九州弁が、今も妙に鮮明に耳に残っているのだという。
それは、平野の身を案じて、気遣ってかけられた優しい言葉である。その懐かしい北九州弁を思い出す時、恐らく平野はショパンのように癒やされているのであろう。
さて「初七日」では、父を亡くした兄の康蔵は土地の言葉を話し続ける。
葬儀で故郷に帰った弟の研次は、自分より優秀だった兄が、長男であるが故に地元の市役所に就職したことを負い目に感じている。故郷に戻った研次も、すぐに土地の言葉を話すようになるが、度々転勤を繰り返した研次にとって、既に話す言葉とは「賃貸契約」のようなものになっていた。
地域が異なれば言語が違う。兄は、実家を守ると同時に、ネイティブとして土地の言葉をも守ってきたのである。
従って、康蔵と研次は、もう「心の最も深い秘密」を共有する仲ではない。
『決壊』で、法要のために家族を連れ北九州に帰省した沢野良介は、駅に迎えに来ていた母の車に乗り込む。しかし、車内のオーディオから流れる韓国語の音声のCDに違和感を覚える。母は、最近韓国語を習い始めたのだという。韓国に興味を持ち始めたなど聞いたことがない。その気まぐれも不可解だが、何より気持ちが悪いのは、慣れ親しんだ母の声が、まったく知らない言葉を発しているという違和感である。良介はそっとCDを止める。
更に平野は「「気持ち悪い」文学の最高峰——小島信夫『城壁』」(『考える葦』)で、小説『城壁』に関して、自作の「初七日」にからめながら「精神的に追い詰められた隊員が方言で会話をし始める辺りに強い印象を持った」と書く。
平野はビルマ(現ミャンマー)に戦争に行った祖父のことを思い出しているのだ。彼は、この祖父のことを何度も何度も繰り返し書いている。彼は「祖父は、果たしてジャングルの中で、郷里の北九州弁を喋ったのだろうかということを考えた」という。「方言という、生れ育った場所と不可分に根差した言葉ほど、侵略戦争の矛盾を先鋭的に際立たせるものはない」。
確かに、ミャンマーのジャングルで発せられる北九州弁は違和感を生むだろう。京都の焼き肉屋での北九州弁の会話が、その場の空気をぎこちなくさせたように。
場所と言葉、そして、その言葉を話す人間は不可分である。
『空白を満たしなさい』で、鳩を蹴り殺すのを目撃して注意したのを逆恨みしているらしい警備員の佐伯を追って、徹生は佐伯の地元を訪れる。
「駅をあとにした時から、徹生は自分が、佐伯という人間の内部へと、無断で足を踏み入れているような奇妙な感覚に見舞われていた。現実の町でありながら、どこかで、あの男の記憶の中の町と地続きになっている感じがする」
そこは佐伯が生まれ、土地の言葉を受け取り、佐伯自身となった場所だ。
人は外界を解釈し分節化する。場所の記憶はその解釈によって取り込まれ身体の一部となる。このインプットとアウトプットは渾然一体となっている。佐伯という人間があのような人格として生まれたのは、それが全てではないにしても、この場所と関係している。佐伯の言動の一つ一つは場所の記憶と結びついている。徹生が佐伯の内部に入り込んだような気がするのはそのためである。
また「一月物語」では、山中で毒蛇に嚙まれ介抱されていた真拆は毎晩同じ夢を見る。真拆は夢に現れる女に取り憑かれてしまった。傷の癒えた真拆は山を降り、下界に戻らなければならない。
しかし、下山すれば、二度と女を眼にすることは出来まいと真拆は思う。女の夢はこの山と深く結びついている。
真拆は山から夢(言葉)を受け取る。言葉は真拆の夢(身体)の中に侵入する。
ところで、谷崎潤一郎は、場所の移動と作風の変化が大きく連関している作家である。谷崎は関東大震災後、関西への移住を余儀なくされたが、以降の作品が文体も含めて関西という「場所」と大きく関係しているのはあまりに明らかである。
『陰翳礼讃』も関西に移り住んでいなければ生まれなかった評論であろう。
「電機器具等のデザインが、伝統的な日本家屋に馴染まないという議論は、「日本語」と「外来語」との不調和として理解される。谷崎のような洗練された文章家は、「日本語」の「陰翳」の中に、現実の生活に次々と持ち込まれてくる「シエード」や「ストーヴ」といった新語のための場所を空け、それらを落ち着かせることに非常に腐心したはずである」「「陰翳」は、いたるところに 『陰翳礼讃』と「インターナショナル・スタイル」」(『モノローグ』)
人々の生活の痕跡や、モノと人との親しげな「関係」の蓄積が「陰翳」となる。
谷崎は小説家なのだから文体について敏感なのは当然だが、その点を差し置いても、家具の配置(空間)が文章の語感(一種の身体感覚)に置き換えられている点は注目に値する。
一部の語句が、身体に存在しない単語に置き替えられてしまったインタビュー記事が極めて不快であるように、そもそも日本語によって分節化されている生活に持ち込まれた「シエード」や「ストーヴ」などの外来語は、なかなかその場に調和しない。実際日本人の生活が変化したのだから仕方がないとはいえ。
それらは、日本人の生活という身体感覚に侵入してきた他者なのである。それは「陰翳」を齎(もたら)す、モノと人との関係の意味をも変質させる。
しかし、それは小説家にとっては拒否でない現実である。谷崎は「それらを落ち着かせることに非常に腐心」するし、平野だって同じ立場ならそのようにするだろう。バルザックが溢れ返るモノたちを積極的に作品に取り入れていったように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
