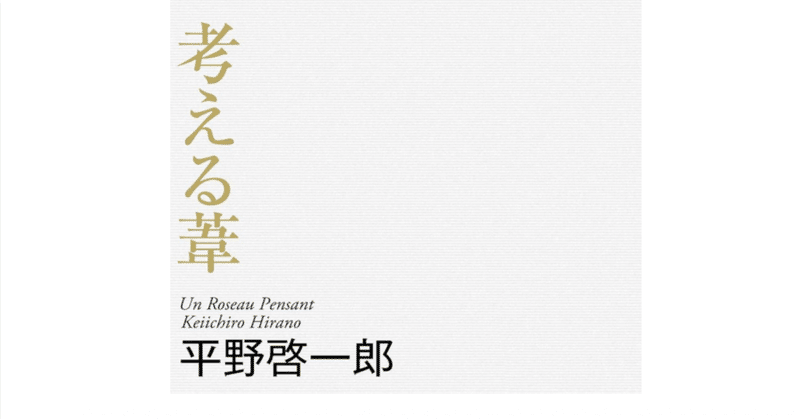
身体、場所と言葉 2(平野啓一郎試論)
【警告】
小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。
このテキストは『平野啓一郎論』の第三章です。
意味を埋め込まれた身体
不如意の感覚は身体に埋め込まれた他者から生じる。
その埋め込まれた他者とは言葉である。「あなた方は愛し合わなければならない」という当為命令のような。
平野は「私は折々、新聞や雑誌のインタヴューを受けるが、記者の中には、私の発言をまとめる際に、つい自分の語彙を混ぜ込んでしまう人がいる。そうすると、ほとんど身体的な、非常な違和感を覚える」と語っている。
「自分の中に絶対に存在しない語彙というのはあるもので、ありきたりであるにも拘わらず、自分の言葉としては、生まれてこの方、一度も使ったことがない単語というのは、案外、少なくない。誰かの言葉が、どうしようもなく浮薄に感じられる時には、やはりそれが、その人の実存とは何ら必然的な関係を有さない場合だろう」(「“我が事”としての西洋政治思想史——小野紀明『西洋政治思想史講義——精神史的考察』」(『考える葦』))
平野の言う「身体的な違和感」が、ものの喩えでないことは明らかだ。それは、意に沿わないまま身体(インタビュー記事という肉声)に埋め込まれた他者なのだ。彼が感じる違和感は実感であろう。
『顔のない裸体たち』では、テレクラや出会い系で知り合った女性を次々とナンパしていた〈片原盈〉は〈吉田希美子〉に出会い夢中になる。といっても、その肉感的な身体と、反応の良さに対してである。
彼は二度目の性交で早速二個のバイブレーターを持参する。彼は女性器や肛門にバイブを挿入した姿に殊の外欲情するのである。「舌や男性器でさえ、愛の意味を帯びることが出来る。しかし、バイブレーターは、ただ性欲のためにだけ製造された道具だ。女の肉体にそれが埋め込まれることは、いわばその意味が埋め込まれることである」と平野は書いている。それが、愛し合った恋人同志であったなら、挿入されるものは「愛の意味」を生む。しかし女性を物としてしか扱わない〈盈〉にとって、バイブレーターは単なる性欲の象徴である。
恋人であったなら、むしろ〈希美子〉は羞恥心から拒否したかも知れない。しかし、彼女は、出会い系で知り合った、他人というべき資格すらない男の要求(単なる性欲)は難なく受け容れる。「愛」ではないのが明らかだからである。
さて、平野は、金原ひとみの『蛇にピアス』を論じて、次のように述べている。
「軽率な一般化は慎まなければならないが、女性作家には、身体感覚として受け止めたことがらを、論理展開に頼ることなく、ダイレクトに読者に響かせるような言葉に変えるのが巧みな人が多い。この作品は(中略)随所にそうした体感的表現がちりばめられている。その中心をなすのは「痛み」である」
これもまた、サルトル評と同じく、やや問題含みの発言である。「女性にロジックはない。彼女らはただ感情的なだけだ」という偏見をただなぞっているだけにも見えるからだ。
しかし、平野がここで自分自身について語っているのは明らかである。身体感覚を言葉に変えるのは女性作家に限らないし、平野作品にも体感的表現はちりばめられているのだから。
そして、平野はそのような表現の中核には「痛み」があるという。
視線によって生じたサルトルの内面の傷から実存主義が萌芽したように「痛み」から意味は生じる。
挿入されたバイブレーターの感覚にも意味は宿る。
また、インタビュー記事に埋め込まれた不愉快で異質な他人の言葉は、別の意味を発生させ、彼の語ろうとした論旨自体を揺るがしかねない。
クリストファー・ノーラン監督の映画『インセプション』評も面白い。(「「インセプション」としてのフィクション——クリストファー・ノーラン『インセプション』」(『考える葦』))
平野は、夢の描写がクリアすぎること、破綻なくシーンが繫がりすぎていること、『ダークナイト』ほどの寓意性が見られないことなどの欠点を指摘するが、彼がこの映画にすかさず反応している様子自体が興味深いのである。何故なら『インセプション』は、ターゲットを眠らせ、他人の夢(いわば身体)の中に侵入してアイデア(=言葉)を植えつけるというストーリーだからである。
これは「日蝕」で、異教に興味を持つが異端審問官になるのは拒絶している主人公が「異端者を捕らえ焚刑に処したところで、思想そのものが放置せられるのであれば、解決されたことにはならぬ」と語るのにも似ている。
放置されたアイデアは、必ずや、次に潜り込む身体を見つけ、侵入し、伝染していく。異端の思想は次の異端者を作る。
また、平野は「刹那は去らず、幾たびもナルシスを幻惑する 篠山紀信『AESTHETICS』」(『モノローグ』)というエッセイでは次のように語っている。
人間は、誕生してすぐに、母親を始め多くの他者の目に触れ記憶される。それは単なる映像ではなく言葉によって分節化された輪郭である。その輪郭としての言葉は、親族などによって本人にフィードバックされ、彼の者は、それを自己像とする。人が自分の生の最初の数年について知り得るのは証人たちの言葉によってであり、それが自分という人間を形作るのだ。
人は、出産の瞬間から他者の視線に曝され続け、言葉をかけられ続ける。身体の輪郭(=自己像)とは言葉である。
平野が「“我が事”としての西洋政治思想史——小野紀明『西洋政治思想史講義——精神史的考察』」で「浮薄な言葉」を使いたくないと言うのは、それが自分の言葉でないからだ。自分の言葉とは、自分の身体を構成する言葉のことだ。
『決壊』で、妊娠した佳枝は胎内の子供に『まだだめよ』と言い聞かせる。「まだだめよ」とは、まだ予定日ではないから生まれてくるには早いという意味である。
佳枝は、その言葉が体内の命に届いたのだと確信する。何故なら、子供は予定日きっかりに産まれたからである。佳枝は、その子を自分の分身だと感じる。
このエピソードは、『空白を満たしなさい』の徹生が、父親が死んだ年齢きっかりに自分も死ぬのではないかと考えているのに対応しているといえるだろう。
佳枝の「この日に産まれよ」という当為命令に従って生まれた我が子。
父と同じ年齢で死ななければならないという命令に怯えていた徹生。
同一視のメカニズムが二人に働いていることは明らかである。
徹生が父親との同一視によって死を予感していたのと同様に、自分の言葉が届いたと信じることによって佳枝と子供の同一視は完成し、彼女は我が子を自分の分身だと確信したのだ。
彼女が語りかけていたのは、自分の中の他人であり、同時に自分自身でもある。
「彼女は、一人の人間の命が、何もない外界の空間に、突如として兆した孤独な一点として、剥き出しのまま開始されるのではなく、必ず母親が現に所有している肉体の内側に、いわば場所を許される形で始まるという事実について、妊娠の期間中、折々思いを巡らせていた」
こうした考えを彼女に語ったのは義兄の崇だった。
彼女は悪阻により「痛み」を感じる。その痛みは、彼女の言葉を注入された何かである。
そして、産まれてきた子供を見て、彼女は不思議さに打たれる。ただ感じるだけだった存在が、実際に目の前にある。「痛み」は意味として産み出された。
そして赤ん坊には良太という名前がつけられ、皺だらけだったその輪郭線が、最後の言葉によってきれいに閉じられた。
名前のない物体は、輪郭も定かではない何かであるに過ぎないが、名前(固有名)により、そのものの輪郭線がきっちりと定まる。その何かは「良太」と呼ばれ、人々の意識の中、あるいは社会の中に存在を許されるのである。
言葉が人を作る。そして人は言葉である。
『決壊』で、弟殺害の容疑者となった崇は、警察が情報を収集して、それを警察が想定した犯人像を手本に、プラモデルのように組み立て、自分を真犯人に仕立てようとしていると語る。崇が何を証言しても、そのための材料を提供している、ということにしかならない。
崇は、DNA鑑定や、防犯カメラの映像を集めることで無罪を証明しようと考える。
警察は証言(言葉)によって犯人を構築する。崇が警察に対抗しようとして集めるのは物的な証拠である。
『フェカンにて』の大野は、父を早く亡くし、『空白を満たしなさい』の徹生同様、自分も父と同じ年齢で死ぬのではないかと考えている。
大野は、伯父達に、死んだ父の話をよくせがんだという。父の法要では皆が泣いていた。父親は平凡な男だったが、その死は人に惜しまれた。
父の死は一個の空隙(くうげき)であったと大野は言う。七十キログラムほどの細胞のかたまり。それが些細な機能不全で全てが失われる。その存在の消失。それを埋めるものはない。
「大野が知った最初の言葉とは、その空隙を満たそうとして、満たしきれないあらゆる言葉ではなかったか。」
「空隙」は比喩ではない。死とは身体の喪失である。そして、身体が言葉であるなら、警察が言葉によって犯人を作りあげようとしたように、死んだ人間も言葉によって再構成することが可能なのではないか。大野は空隙をあらゆる言葉で埋めようとする。それは大野にとっての「最初の言葉」である。
『高瀬川』は、語り手が「大野」であることからしても、「フェカンにて」同様、一種のメタ私小説的な作品であろう。
『高瀬川』の大野は、冒頭、やや不可解な思索を巡らせている。
「例えばここに、ビスケットが一枚ある。私は確かに今、このビスケットを掌の上に眺めている。そして、食べてしまう。すると、記憶の中には、掌の上の一枚をビスケットの像が残る。
今度は掌の上に何も置かずに、ただビスケットの像だけを思い浮かべてみる。
(私は注意深く、一旦掌を握り、開いた後にそこにビスケットの像を思い浮かべ、また、掌を握った。)」
ビスケットは失われたが、ビスケットの像は残る。
目を閉じてしまえば、食べられたビスケットも、現にそこにあるビスケットも、同じビスケットの像に過ぎない。掌の上のビスケットだけが実在するとは言えない。最初からビスケットなどなかったのかも知れないではないか。
では、記憶を手繰(たぐ)っていけばどうだろうか。ビスケットを箱から取り出し、紙包みを破って、掌の上に置いた記憶。しかし、そのようなものが本当に当てになるのだろうか。現に、二枚目のビスケットは最初のビスケットを模倣して、無限に記憶を延長しはじめている。残っているのは、ビスケットを掌の上に載せたときの現実感だけである。
恐らく、彼が言いたいのはこうだ。
ビスケットとは死者(父)である。
あるのは死者の記憶だけである。それは大野にとっては、親族の語った思い出話だ。
記憶は父が確かに存在したことを証明しようとして無限に延長される。「空隙を満たそうとして、満たしきれないあらゆる言葉」が増殖する。
大野は、本当は、それらの言葉の虚しさを知っている。
残るのは、ビスケットに触った時の現実感だけであり、父の身体の、七十キロの細胞のかたまりの重みの感じだけである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
