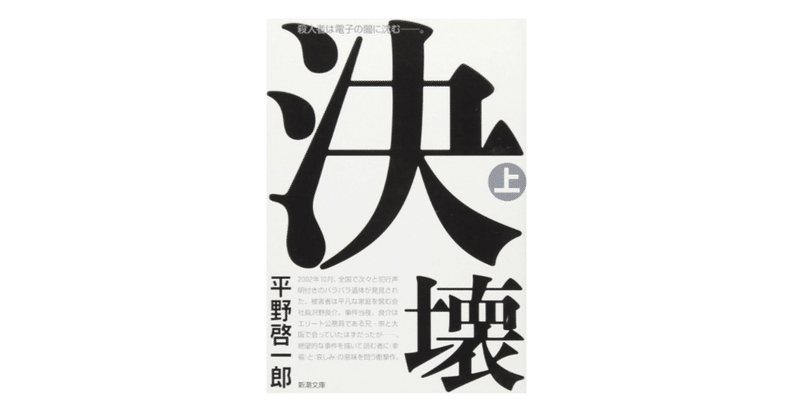
固有名と属性 4(平野啓一郎試論)
【警告】
小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。
このテキストは『平野啓一郎論』の第四章です。
最初から読みたいという方はクリエイターページのマガジンをご覧下さい。
遺伝子
『私とは何か』には、不可解なところがもう一つある。
平野は、このエッセイの最終章で「あえて触れてこなかった問題が一つある」として、遺伝要因の影響について語っている。
彼は、遺伝の影響に触れなかったために「フラストレーションを感じていた読者もいるかもしれない」というのだが、そうだろうか。
最終章まで読み進めた読者の中で「遺伝について語らないのは片手落ちじゃないか」と感じていた者がどれくらいいるのだろう。
むしろ「遺伝」という、自分の意思ではどうにもならない、いわば不可抗力なものを論じても仕方ないのではないかと感じた人間の方が多いのではないか。ことに自己啓発的な読み方をしていた場合は特にそうだ。乗り越えられない壁を設定されてしまったら自己啓発の意義は薄れる。
著者は、自分の中の分人を足したものが個人、分人の構成比率がその人の個性だと語ってきた。では、遺伝は、その比率のうちのどこに入っているのだろう。
平野は実際に、遺伝の問題は「本書が扱える範囲を超えている」として、やや匙を投げている。
それにも拘わらず、平野が遺伝要因について言及せずにはいられないのには理由がある。
彼は、自分のちょっとした仕草や性質が死んだ父と似ていると周囲からしばしば指摘されることから、遺伝に興味を持った。対人関係を最重要視する分人主義において、話したこともない人間、直接影響を受けた筈もない人間と似ているという事実は逆に見過ごせない。
その興味は小説にも反映されている。
『本心』の石川朔也は、母が事実婚をし、朔也をもうけた後にすぐに別れてしまったために、父親の記憶はない。(それは母親から聞かされていた事情であり、本当はもう少し複雑であったが)
朔也は、自分の、凡そ母には似ていない、まったく非現実的で内省的な性格は、父親譲りなのだろうと思っている。
『顔のない裸体たち』でも、父親からDVを受けて育った〈片原盈〉について、その容姿は、人が見たら吹き出すほどに父親とそっくりだったと少々意地悪に書いている。
喘息で苦しむ孫を見て『決壊』の和子は「やっぱり、遺伝もあるんかね、喘息は。」と言う。
病弱な体質。それは『葬送』のショパンやドラクロワも、あるいはそうなのかも知れないが、本人にはいかんともし難いものである。
良くも悪くも、親子は似るのだ。
『かたちだけの愛』で、愛する人の義足を設計することになるプロダクト・デザイナーの相良の父親は歯科技工士だった。父は義歯を作っていたのである。偶然とはいえ、親子が人体の欠損した部位を作る仕事に就いているのは因縁を感じる。
更に遺伝が重要な要因となるのは『ある男』である。
弁護士の城戸は、里枝の亡夫であるXの身許を調査していた。
城戸は、Xが原誠という男であることを突き止める。原誠は、殺人犯の息子という出自を隠すために戸籍交換を繰り返していた。
城戸が、原誠の父親が小林謙吉死刑囚であると確信したのは、二人の顔があまりに似ているためだった。
また、それ以上に重要なのは、Xである原誠が谷口大祐と偽って里枝の許を訪ねた時のことである。
里枝は、離婚して郷里に帰り実家の文房具店を手伝っていた。里枝は、たまにスケッチブックや画材を買いに来る原誠(大祐)に惹かれて、その写生を見せてもらう。彼女は、その素朴な絵に大きく心を動かされて思わず涙をこぼす。二人は交際を始める。
話はそれで終わらない。
城戸が、Xの素性に気づいたのは、たまたま確定死刑囚の公募美術展を見たためだった。死刑囚小林謙吉の絵は、谷口大祐を名乗っていた男、Xの写生にそっくりだった。
親子は、顔だけではない。描く絵までも似ているのである。
しかも、原誠(谷口大祐)が、最初に里枝と会話した時、既にスケッチブックを持参していたのは意味深長である。彼は最初から、本人が自覚していたかどうかには一切無関係に、父親そっくりの絵、つまり自分は本当は谷口大祐ではないという証明を持参していたのだ。城戸が、里枝から、その絵を見せてもらっていなかったら、Xが誰だったのかは永遠に分からなかったのである。
そして「氷塊」の少年もそうだった。
少年が、喫茶店の女が本当の母だと信じたのは、母の遺影と、その女が似ていたからだった。それは母が死んでいるという事実より強力だった。母と自分は似ており、母とあの女は似ている。
「フェカン」の大野が、自分が父親の年齢で死ぬだろうという時、そこには父親との同一視が働いている。父親と自分は似ている。
「自分が死ぬだろう」という予感は「父親が死ぬだろう」という予感と等価である。「父親と同じ年齢で死ぬだろう」は「自分と同じ年齢で父親は死ぬだろう」と同じ意味だ。それは父親が既に死んでいるという事実より強力なのである。
『ある男』の原誠も、自分がいつか父親同様の暴力性を剥き出しにして人を殺すのではないかという予感に脅やかされ続けた。
そして、実は「氷塊」の喫茶店の女は、毎週木曜日に不倫相手の歯科医師と待ち合わせをしているのだが、女は女で、いつもこちらを見つめている少年のことを気に留めていた。
女は、あの少年は、不倫相手の子供なのだと想像した。あの華奢な体つきとほっそりとした顔立ちは母親似なのだろうと彼女は信じた。その眼差しは、まるで、母親が息子に忍び込ませたものであるかのようだった。女は良心の疼きを感じる。しかし、男に打ち明ければ、この恋愛は、その瞬間に終わるだろう。女は逡巡する。
さて『私とは何か』で、平野は、人の個性は遺伝要因と環境要因によって生まれるが、分人の話は主に環境要因に限定しての話であることを認めている。
彼が遺伝要因の話題を後回しにしていたのはそのためである。
そして、平野は『決壊』において、「犯罪」を巡る遺伝要因と環境要因について考察したという。
『決壊』のバラバラ殺人事件の真犯人である〈悪魔〉、篠原勇治は、高校生である友哉を呼び出して、殺人の意思を吹き込もうとする。その際の台詞はこうである。
「世界は実際、そのクズ(友哉が憎んでいたクラスメート)が死ぬことを願っている。事実を見るべきだ。あなたは、殺す人間として、この世界に選ばれている。遺伝と環境を未然の殺人からプロファイリングした結果、最適の人物としてリストアップされた。どんな固有名詞を与えられた人間であったとしても、あなたとまったく同一の条件下に置かれれば、必ず殺人を犯すようになっている。
あなたと同じ両親、あなたと同じ土地、同じ容貌、同じ性格。すべて同じならば、当然にその人間が殺人を犯さなければならない。人間とは、単なるデータの束だ。その束のあり様が、たまたまあなたの場合、殺人者であるために最適だった! 世界は、微細な作用を、多年に亘って及ぼし続けて、今、活性化することに成功しつつある。あなたの固有名詞をラベルとして貼ってね。」
確かに、犯人を「単なるデータの束」として考え、証言の積み重ねによって崇を容疑者としたのは警察である。
そして、警察に疑われて苛酷な取り調べを受け、真犯人に対しては相当な恨みを持っていてもおかしくない筈の崇も、犯人と同意見なのである。
崇は、親友の室田との会話で、全ては遺伝と環境だと言う。犯人を赦すも赦さないもない。罪というもの自体が、この世界には存在しないからである。犯罪者に責任はないし、そもそも犯罪者なんて存在しないと崇は語る。
全ては遺伝と環境である。
崇と良介という兄弟からしてそうだった。
良介は、何をやっても優秀な兄に劣等感を抱いていた。しかも、崇は不登校になった子の面倒をよく見て、暴力を振るう教師から庇ってやったりもする優しい子供だった。そして、良介は、地方のつまらない会社に就職し、兄は東京にいる。生まれつきの差も、環境の差も明らかだった。
良介は、全てに恵まれている兄が、それを生かすだけの努力をしようとしないのが不可解であり、もどかしいのである。
さて、環境とは場であると同時に、その場(地域・組織)での対人関係である。遺伝も、身体に埋め込まれた他者であり、一種の対人関係だともいえる。異なるのは、周囲の人間とは対話出来るが、遺伝の発現は一方的であることだ。
当為命令が身体の不調をもたらしたように、良太の生まれ持った器質は喘息をもたらす。
『ドーン』の火星探査船でクルーの一人であるノノ・ワシントンは精神に変調を来すが、それは遺伝子的なストレス耐性に問題があったせいだと地球上で噂された。劣悪な遺伝子が、特殊な環境に耐えられなかったのだと。しかし、それは人種の問題を孕み、マスコミは報道に二の足を踏む。
遺伝子がある種の分人だとしても、その影響力は一方的であり、そこに相互のコミュニケーションはない。それは分人主義の枠には収まりきらない。
しかし、平野がその影響を無視できないのは、知らない他人と自分が何時の間にか似てしまっているという、その不思議さ故である。
崇は、室田に、精神科の操作的診断基準を見たことがあるかと尋ねる。そこでは「悪」は〈健康の欠如〉に過ぎない。精神疾患などというものはない。
ここで、作品のテーマは長編デビュー作である「日蝕」に帰ったのである。
巴黎(パリ)大学で神学を学ぶ「私」は、異教徒の哲学書を求め旅に出る。「私」は導かれるようにして、不思議な村に滞在することになる。
錬金術の考え方では、本来、神が創造したこの世界は完全である。悪など存在しない。悪とは善の欠如に過ぎない。
原初の世界の完全性を取り戻す方法論が錬金術であり、完璧なバランスを回復した卑金属は、その本来の姿である金となる。
あるいは『空白を満たしなさい』のラデックが語るグノーシス主義は、その世界観を反転したものといえよう。
グノーシス主義では悪の存在を認める。
この世界に悪が存在し、その要因が神であるなら、その神は悪の神であるに違いない。また、その神が創造したこの世界は邪悪であり、むしろ悪しか存在しない。
すると、この世界の「善」とは悪の欠如に過ぎないということになるだろう。
悪を認めない現代の「操作的診断基準」は錬金術的であり、全ての人間を病気(ヒステリーや分裂病、倒錯)と見るフロイト・ラカン的な世界観はグノーシス主義的だと言えるかも知れない。
責任概念は、そもそも分人主義では曖昧になる。分人主義は、独立した主体としての個人を否定していた。
分人主義に絶対悪はない。崇が言うように「犯罪」があったとしても、根っからの「犯罪者」は存在しないのである。
何故なら「個人は分割できるが、他者との関係性は分割できない」というのが分人主義だから。
あなたが善を為したとしても、それはあなた一人の手柄ではないし、悪を為したとしても、あなた一人の責任ではない。
全ては遺伝や環境との相互作用である。
完璧な善人もいないし、犯罪者もいない。
そして、遺伝とは、そもそも身体に埋め込まれた他者である。当為命令である。そして他者でありながら自分(親)である。親と子は似ている。
「氷塊」の女は、自分をじっと見つめている少年を見て、その少年が不倫相手の妻の子供だと直感する。そして、その妻に見つめられているかのように感じる。少年はきっと母親似であろう。女は少年の中にその母親を認め、その母親が自分を監視しているかのように思うのである。
ここで女が、自分の罪悪感を少年に投影しているのは明らかである。女は、一切何の事情も知らないのだから。
少年の中に宿る母親の視線とは自分である。女はずるずると不倫関係を続ける自分自身を責めているのである。
また、遺伝要因を考える際に触れておかなければならないことがもう一つある。
「『豊饒の海』論」(『三島由紀夫論』)で、平野は、『豊饒の海』で三島が展開した、阿頼耶識を介した因果の仕組み、輪廻転生という現象について考察している。しかし、遺伝子主体で考えれば、輪廻転生は特に不思議な現象ではない。
生物を遺伝子の乗り物とするリチャード・ドーキンス流の考えでいけば、遺伝子こそが永続的であり、人間とはかりそめの姿に過ぎない。
すると『空白を満たしなさい』での〈復生〉という現象も珍しいものではなくなる。我々は全て、代々因果を継承した復生者(=複製者)であり、生れ変わりである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
