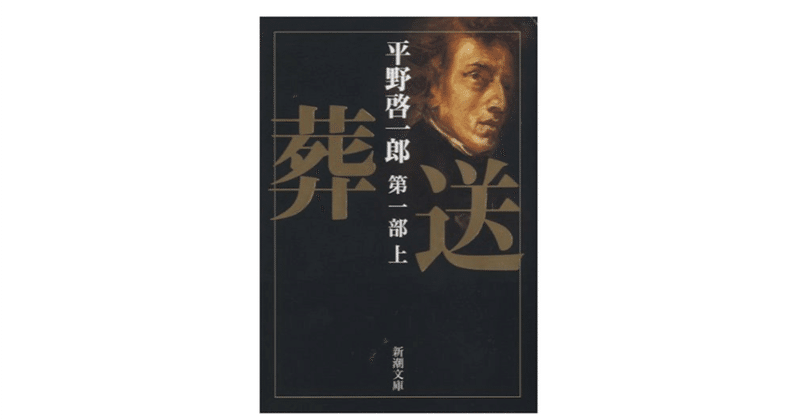
不気味なもの(平野啓一郎試論)
【警告】
小説作品における物語の重要な部分に触れています。未読の方は十分に御注意下さい。
このテキストは「死と役割」の続きになります。
不気味なもの
「日蝕」に登場する両性具有者(アンドロギュノス)の描写は、引用するのが躊躇われるほどにグロテスクである。
平野作品には、同様の、グロテスクで不気味なものが頻出する。
「フェカンにて」で、文化庁の文化交流事業に参加しパリに滞在している大野は、父親が死んだ年齢と同じ歳で自分も死ぬのではないか、それも自殺するのではないかという考えに囚われていた。
彼は、十代の頃に度々描いた自己処罰の幻影を短篇集として著したのだが、それらの作品の残酷な描写は、普段の穏和な彼を知る者達にとって意外なものであった。しかし彼らは、戸惑いつつも、それらは知的な構築であると理解して納得したという。
既に述べたように「日蝕」のアンドロギュノスも、ある種の戸惑いを読者に呼び起すものである。しばし呆然とした読者は、それを、実際には理解できていないままに、何かの「知的な構築」であろうとして納得する。
大野は「自己処罰の幻影」を通じて、中世の磔刑図に見られるような血塗れの残忍さを理解したというのだが、「磔刑」とは、他者によって為されるものであるから、自己処罰(自殺)とは異なる。だが、勿論、単なる他殺とも言えない。キリストの磔刑とは、自らの苦痛を通じて人々を贖(あがな)い、癒す行いである。
アンドロギュノスが二元論の合一、男と女、生と死の統合を象徴しているように、罪の償いとは「他者に於いて自らを処罰する」(「フェカンにて」)ものなのである。
大野は続いて、画家のドラクロワに思いを馳せる。(彼がフェカンを訪れたのは、そこがドラクロワゆかりの地だからだ)
実際の大虐殺を画題としたドラクロワの絵は「絵画の虐殺」と呼ばれた。それは、新古典主義の画家たちにとって唾棄すべきものであった。ドラクロワを代表とするロマン主義以前の絵画とは、美しいものか、あるいは宗教的な逸話を描くものだった。平野の『葬送』では、ドラクロワとアングル一派の対立が描かれる。
ドラクロワは、サロンに集う夫人たちから「あれほど親切でお優しい方が、どうして薄気味の悪い絵ばかりをお描きになるのかしら?」と噂されている。「フェカンにて」の大野と同じく、あるいは『決壊』の沢野崇同様、ドラクロワは他人に親切で優し過ぎる人間だ。
家族を次々と亡くし、親も兄弟もなく、甥のシャルルも失ったドラクロワは孤独である。彼は画家仲間のバリーと動物園へ素描(デッサン)をしに出掛ける。バリーは娘を亡くし、ドラクロワはその葬儀に参列したばかりである。ドラクロワは、以前見たライオンの屍体の解剖を思い出す。幻影の中で、黒ずんだ腐臭を放つ屍肉がバリーの娘の屍体と寄り添い合う。『どうして想像力は、こんな思いもよらぬ場面をちらつかせるのだろう? それこそが、自分の真の心の動きであると言わんばかりに!』
ドラクロワは「不気味なもの」に取り憑かれている。
『葬送』の、もう一人の主人公ショパンもまたそうである。
ショパンは、妹のエミリアが苦しみながら死んでいった様子が忘れられない。エミリアは瀉血(しゃけつ)され、からだ中を発泡膏や芥子泥(からしでい)塗(まみ)れにし、呻き声を上げ続けながら悲慘な最期を遂げた。
ショパン自身がまたそうなのだ。
この小説はショパンの葬儀から始まる。そして、ショパンが愛人であり庇護者でもあったサンド夫人に見限られ、病状が悪化し、苦しみながら死んでいく様子を延々と描き続ける。
ショパンは、今まで一度も経験したことのないような大量の血を吐く。
「彼は発作の最中に目の当たりにしたぞっとするような量の血を金輪際忘れることが出来なかった。その異様さには、何か生とは根本に於いて相容れぬものが無理矢理に這い出して来たかのような不気味な印象があった。自分の中には既にその得体の知れぬものが棲みついている。獰猛に胸や喉を喰い荒らしながらそうしてますます太ってゆきつつあるのだ」(『葬送 第二部(下)』)
「不気味なもの」は、「初七日」において、自宅の庭で倒れた児島康蔵の父、康作においても現れる。
妻の叫び声を聴き庭に降りた康蔵は、横たわる康作に人工呼吸と心臓マッサージを始める。口から泥と吐瀉物を掻き出し、無我夢中で人工呼吸する。あの冷たい唇の感触。康蔵は、後に、あれは別れの接吻だったのだと思い返す。
それだけではない。
復員してきた父の、痩せ衰え、絶望と憤怒の殺伐とした風体。康作は、マラリアを発症し、しばしば癲癇の発作を起こす。熱帯の戦死者たちの幻影が彼を襲う。(『ドーン』では、マラリアを感染させる生物兵器が登場する)
そして火葬場で焼かれて暴れる康作の遺体。
平野にとって「死」とは、そのような残酷な苦しみの果てにあるものだ。
「火色の琥珀」で、全身に火傷を負い、九死に一生を得た「私」は、転院した病院で、湿潤療法という治療法を施される。皮膚が壊死し、ドロドロと溶け出してゆく光景は、おぞましくグロテスクである。
「私は、自分が何にともつかないまま、変身しつつあるということを強く感じました。壊死した皮膚が取り除かれると、まるで少年の亀頭のように鮮やかなピンク色の肉芽が露わになりました。私は後に、死の淵から生還したと、人から随分と言われましたが、その肌を見ていると、やはり一度死に、再生した、という方が近い気がします」
彼は、死と生の合一を体験し変身した、一種のアンドロギュノスである。
「初七日」で康作が火葬場の炉の中で暴れたのも、死んでいた彼が炎に包まれ生まれ返ったのかも知れない。だとすると、火葬場は錬金術の炉だともいえる。
『決壊』で、崇と良介の父である治夫は、引退した溶鉱炉の技術者である。治夫は溶鉱炉で孫の遺体を焼く夢を見る。彼は「屹立する巨魁(きょかい)な鉄の子宮を眩しげに」見上げる。
「屹立する巨魁な鉄の子宮」。ここでは溶鉱炉は、火葬場であり、かつ、やはり錬金炉である。妻と崇は抱きついてキスをしている。孫は焼かれ、恐らくは再び生まれてくるのであろう。つまり、ここでも生と死の合一が為されているのだ。
私の考えでは、ファンタジー的な題材を扱い、SF的なモチーフにも挑戦する平野が、「変身願望」というテーマを扱いつつ、(言葉に語弊があって申し訳ないが)安易な転生ものに陥らないのは、そこに「不気味なもの」が立ちはだかっているためだと思う。
三島由紀夫の『豊饒の海』でも、『春の雪』の清顕は最愛の人に拒まれ咳の発作に苦しみつつ死んでいったし、『奔馬』の勲は腹に小刀を突き立て自決した。
「不気味なもの」は、平野作品の様々な場所に出現する。
たとえば、明らかに死につつある男の幻影を描いた「清水」では、しだれ桜の前にある鳩の屍体としてそれは現れる。毟りとられたかのように逆立った羽は、肉が腐爛して、羽が一本々々勝手な方向をむいて身を捩っている。
同様に、『family affair』では、熱湯で殺され腹を上にして固くなったムカデ。
あるいは、「瀕死の午後と波打つ磯の幼い兄弟」でワンボックス・カーと激突したひったくり犯。もう動かなくなった男の耳からは、磯の岩から這い出てきた蟹のように、赤黒い血が溢れ、流れおちる。
また、自転車で海に行った兄弟たちが見た、花火の突き刺さった巨大なクラゲの屍体。
「最後の変身」で、引きこもりになりネットにはまった「俺」は、遺書として、自殺予告をあらゆるネットの掲示板に書き込み、バラ撒こうとする。殺虫剤を一缶飲み干して、のたうち回りながら、最後の瞬間まで、血とゲロにまみれたキーボードを叩き続けるのだ。その遺書は、虫の大群のように、ネット空間に散らばってゆくだろうと「俺」は夢想する。
その不気味な「虫の大群」は『決壊』ではバラバラ殺人として現れる。
崇の弟である良介は、殺害された後、頭部や腕、足などがバラバラにされ、日本各地にバラ撒かれる。また、発見された遺体は、すかさず携帯で写真に撮られアップされて、ネット上に拡散する。「虫の大群」、あるいはコピーされた大量の「遺書」のように。
そして、私は、平野作品に安易な転生はないと言ったが、ただし、特に理由は示されずに死んだ人間が生き返る『空白を満たしなさい』だけはやや特異である。
とはいえ、徹生が実家に帰り墓参りをするシーンはヒヤッとする。徹生は、墓前で合掌すると「見てみようかな、俺の骨。」と呟く。ここは彼が「不気味なもの」に触れようとした瞬間である。
彼は、母に「馬鹿じゃん。気持ちが悪いだら。」と諭され、墓の扉を開けるのは止める。徹生は、父が傍らにいるような気がしてはっとする。ここで父親との同一視が再び働いているのは明らかである。
繰り返すが、平野作品の主題の一つである「存在」は「身体」と置き換えるべきだ。彼の作品に「存在」の問題はなく、あるとすれば、身体が存在するかどうかという点に於いてだけである。
「存在、時間、死、記憶」を「身体、時間、死、記憶」と置き換えることが許されるなら、彼の作品のテーマ性は一層明確になる。この四つは緊密に連関しているのだから。
たとえば、身体は記憶という形で時間を蓄えたものだし、身体が朽ちれば死が訪れ、時間は停止する。あるいは、身体に蓄えられた時間は、世界という無限の時間に投げ出され、同化するといってもいい。
いずれにしても、平野の興味は身体性を軸としている。
2024.2.10 文章を読みやすく修正しました。内容に変更はありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
