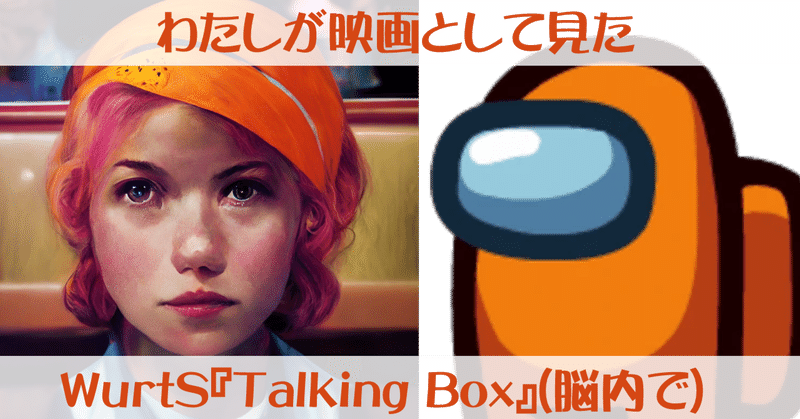
わたしが映画として見たWurtS『Talking Box』(脳内で)
※本投稿をお読みいただく前に※
本投稿は、文学サークル「お茶代」の2022年9月期課題として作成されたものであり、本投稿内に記載のあらゆる内容は事実ではありません。
2008年公開の『アイアンマン』を皮切りに次々と製作された作品群によって構成され、商業的に大成功を収めているMCU(Marvel Cinematic Universe)。その成功に続けと言わんばかりに、ハリー・ポッターやロード・オブ・ザ・リング、果てはアメリカ版ゴジラまでもがそのユニバース化を図っているが、今またここに、映画界に新たなユニバースが生まれようとしている。
まずはここで、今回の記事のテーマとなった『Talking Box』の映像をご覧いただきたいと思う。
今回ご紹介する『Talking Box』は、人狼ゲーム『Among Us』を原作とする作品である。2018年のリリース当初には鳴かず飛ばずであったものの、海外の有名ストリーマーによる配信を契機として世界中で爆発的な人気を集めることとなったこのゲーム。コロナ禍によるエンタメ分野における巣ごもり需要の高まりもあってか、“アマアス”の愛称で、わが国でも大変な好評を博すこととなったことは皆さんの記憶にも新しいだろう。2021年時点でダウンロード数が2億を越えたというのだから、文字通り、モンスター級の大ヒット作品である。このゲームをまだ知らないという方は、以下の記事で詳細を確認していただきたい。
さて、かような大ヒット作品ともなると、実写映画化への道を避けられないのが世の常である。今回、Among Usの映像化権を取得したのはソニー・ピクチャーズ。製作総指揮は三池崇史。この人選については、かつて米『TIME』誌にてジョン・ウーと並び称されたこともある日本の鬼才が、いよいよ世界市場へと向けてどのような作品を送り出すのかと、日本だけではなく世界中の映画界から注目を集めた。また、製作発表記者会見では、本作を第一作目とするAUU(Among Us Universe)と銘打たれたこの新たなユニバースが、今後10年に渡って、最初の三部作から成るサーガを第一フェーズとして、第三フェーズにまで及ぶ壮大なユニバース展開されることが宣言された。その発表を耳にした私は、Among Usほどストーリー性のないゲーム作品の一体どこに、彼らがそのような可能性を見出したのかが甚だ疑問であった。しかし、本作の試写を鑑賞した後にその疑いが全くの見当外れだったことを思い知らされることとなる。
『Talking Box』は、『Among Us』の前日譚にあたる物語である。主人公は、とある理由のためにオレンジ色の目出し帽を被ったまま日常生活を送る無口な詐欺師(=インポスター)、ダーティ。インポスターとは、特に他人に成り済ますことを手段として詐欺行為を行う詐欺師を指す言葉であるが、これはご存じの通り『Among Us』を象徴する用語でもある。そう、つまり本作は、ゲーム内に登場するインポスターの誕生秘話となっているのである。
舞台は、アメリカによる文化的支配の浸食を完全に許してしまった近未来の日本。物語は、ダーティがお気に入りのアメリカン・ダイナーでブルーベリーパイを注文するところから始まる。詐欺グループの元締めから次の仕事の指示を電話で受けている彼の目が、ランチタイムの最繁時を乗り切り、人目を憚ることなく客席でだらしなく伏せ込むウェイトレスの姿を捉える。彼女の名前はエマ。ここでは敢えてウェイトレスということばを用いたが、ピンクブラウンに髪を染め、アメリカンスタイルのメイド服に身を包んだ彼女の容姿の前には、俗にいう“政治的正しさ”などはどこかへ吹き飛んでしまい、誰しもが異口同音に彼女のことをそう称することだろう。
ふと顔を上げたエマの視線とダーティの視線とが交錯する。電話をしながら彼女を見つめるダーティを見つめ返すエマ。次の瞬間、何の前触れもなく店内から店外へとシーンが切り替わると、車に乗った二人を主役とするロードムービーが突如として開演する。音楽に合わせて陽気に笑うエマ。運転するダーティの隣で嬉しそうにハンバーガーを頬張るエマ。ハンディカメラを向けて、ダーティに笑顔を要求するエマ。どこからどう見ても仲睦まじいカップルにしか見えない二人の様子なのだが、どうしてこのような展開を二人が迎えているのかがこの時点では鑑賞者にはわからない。ところが、彼女のこんなセリフによって、店内で起こったことを鑑賞者は知ることとなる。—「どうして私のこと、誘拐してくれたの?」
説明過多とも批判される作品が溢れかえっている昨今の映画状況に照らした場合、とにかくこの作品では鑑賞者に与えられる情報が少ない。二人の表情、一挙手一投足、あるいは画面に散りばめられた多彩な情報など、様々なデータを拾い集めて、スクリーン外で起こったであろう物語を紡ぎあげることが、鑑賞者にはただひたすらに求められることとなる。状況や登場人物の言動から、何が起こったのかを推理する人狼ゲームの醍醐味を、これほど見事に作品に落とし込んだ三池監督の手腕は見事としかいいようがない。「龍が如く」の映像化はいったい何だったのか、「やればちゃんとできるじゃないか、監督」、というツッコミがそこかしこから漏れ聞こえてきそうなほどの出来栄えである。
特に難解だと思われるのが、作品の冒頭からスクリーン左上に表示されている時計表示らしきものの存在である。これについては、試写の終了後における同業者との考察談義の中でもその解釈が分かれるところとなった。ここで少しだけ私の拙い考察を披露させていただきたい。まず、あの一見するとなんの変哲もない“時計表示のようなもの”は、よくよく見てみると私たちが普段見慣れている時計ではない。なぜなら、表示欄の一番右の数字。私たちには“分”が表示されているように見えているものが、24進数表示となっているからである。また、真ん中の数字が“時”を表していると考えられるが、こちらも60進数表示となっている。そして、一番左側の数字が“日”を表していることは明らかであろう。思うに、あの“時計表示のようなもの”がカウントダウンをしていることと、物語の最後にエマが迎える結末を考え併せてみると、あの表示は、地球外生命体にアブダクト(宇宙人といえば、やはり"誘拐"ではなく"アブダクト"である)された際に彼女に刻まれた余命宣告だったのではないだろうか。また、後にも同内容について触れるが、彼女は死へ至る道程をリアルタイムに把握することが可能だったのではないだろうか。
回想シーンだと思われる場面で、エマは友人とともに地球外生命体と遭遇し、何らかの手術を施されている。人類の歴史を振り返ってみればわかるとおり、権力者は“時間”を我が物とすることにより世界を支配しようとしてきた。古くは、古代ローマ初の暦となったロムルス帝によるロムルス歴。それに続く、ユリウス・カエサルが制定したユリウス暦。さらには、ローマ教皇グレゴリウス13世がユリウス暦を改定してつくらせ、現在の暦として用いられているグレゴリオ暦などがその典型である。
暦についての話はさておき、本作で大きな意味をもっていると思われる“時計時間”について考えてみた場合、現代社会はこの時計時間によって支配されていると言ってもよい。眠りから覚めたから起きるのではなく、一定の時間になったら起きる。空腹を感じるから食べるのではなく、特定の時間になったら食事をとる。また余暇の時間でさえ、私たちは与えられた時間の中でしか自由を享受することができない。つまり、グリニッジ標準時間が策定されて以降、私たちは時計時間によって完全に支配されているのである。地球の支配を目論む地球外生命体に”支配者の時間”を植え付けられ、彼らの時計時間に囚われたエマの姿が、等しくも絶対的な時間による支配を甘受する私たちの姿の投影であると理解できるところが実に興味深い。
物語の最終局面、すでに地球の各所に巣食う地球外生命体に対処するために組織されたメン・イン・ホワイト(Men In White)たちが、エマを無慈悲に“処分”するシーンについては、アメリカの都市伝説であるメン・イン・ブラックに着想を得ていることは明らかであり、エマの遺体の首筋に刻まれていた「R・T・T・M」なる文字列(最初の文字はRとは似て非なる文字である可能性は大いにある)は、おそらくは地球外生命体、つまり、メン・イン・ホワイトが呼ぶところの“奴ら(They)”によって行われたマーキングであると推測される。カウントダウンがゼロに到達した途端、メン・イン・ホワイトたちがダーティとエマが滞在するモーテルに踏み込んできたこと。その直前に、エマが惜別の涙を流して自らの死の訪れを確信していた様子からも、“奴ら”による手術を受けた結果、彼女が己の具体的な死期を知っていたことは間違いないであろう。
エマの遺体が回収されるシーンの最後では、メン・イン・ホワイトの一人がダーティの目出し帽の首元から覗く「R・T・T・M」の文字に気づくことになるが、もちろんあれは次作へと伸びている大いなる導線だろう。エマと同様に、“奴ら”によって植え付けられた命数を背負いながらも静かに復讐を決意するダーティ。“これは、殺戮へ至る純愛”は本作のキャッチコピーであるが、このコピーの全てがあのダーティの表情に集約されていると言っても過言ではない。まさに、真のインポスター誕生の瞬間である。同時に、ただの人狼ゲームに過ぎなかった『Among Us』に大きなドラマが生まれた瞬間と見做すこともできるのではないだろうか。またこの時に、人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ11号の姿が、ダーティの脳裏にフラッシュバック映像として映し出される様子が、エマの死の背後に蠢く大いなる陰謀の存在を鑑賞者に感じさせ、次作に向けた期待感を煽っているのも、とてもよい演出だったように思う。
まさか、実売価格520円のインディーズゲームが、これほどのスペクタクルSF巨編へと発展しようとは、開発チームの誰もが想像しえなかったのではないだろうか。次作以降の見せ場となる人狼ゲームこそ、三池監督の真骨頂ともいえるバイオレンス表現が炸裂することになることは間違いないが、今はまだ、狂気の物語のはじまりの余韻に浸っていようと思う。
おしまい
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
