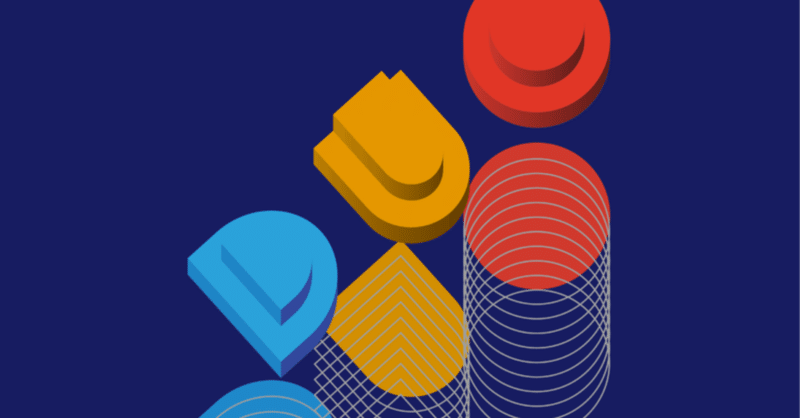
BLOCH DUO PROJECT vol.2「ゆうがらす」あとがき
↑画像クリックでYouTube動画ページが開きます(2021年1月31日まで視聴可)
「ゆうがらす」本編は3:03~32:40
はじめに
先月7月26日(日)、演劇専用小劇場BLOCHからYouTube Liveで配信されたさっぽろアートライブDUOPROJECT vol.2
こちらに、竹原が主宰する劇団「秘密結社デスボルトハリケーン(劇団)」として参加し、『ゆうがらす』という作品を上演しました。
この記事では、本作品の脚本について、自身の思考の整理も兼ねてあとがきを書いていこうと思います。
演出についてはほとんど書きません。なぜなら、(脚本以上に)よくわかっていないから。当劇団では、脚本家竹原と一緒に演劇を作ってくれる演出家をいつでもお待ちしております。
基本はシーンや台詞の意図、構造について、シーンごとに振り返っていくつもりですが、割と脱線するかもしれません。
難しく考えずに、というか本当のところ僕も難しいことはあんまわかってないし、割とノリで脚本を書いている部分も多々あるので、さっくり読んでいただけると嬉しいです。形式上言い切りの形で書いてあるところも「なんか、こうらしいよ」ぐらいの温度感で読んで下さい(マジで!)。
あと、けなしません。
作者が自分の作品をボロカスにけなしてるのとか、気分悪いし……反省は僕が勝手にすればいいことなので。
褒め寄りのニュートラルな立場で書いていきます。
また、最後にこの作品について非公式(ここ重要)アンケートを掲載します。
googleフォームから匿名で送れるので、作品を見て感じるところがあったら、自由に書いて送って下さい(マジで!!)。
※公式にはYouTubeのコメント欄や、Twitterハッシュタグ#DUOPROJECT2にて感想をお待ちしております。そちらもぜひ!
全体として
本作の内容を3行で表すと
・市内勤務のOL硝子(しょうこ)と、写真家の夕奈(ゆうな)はルームシェア(間借りと言った方が正しい)をしている
・夕奈が硝子に自身の結婚を告げる
・本当はお互いがお互いを(恋愛的に)好きだったが、結局別れる(夕奈が家を出る)ことに
となる。
そもそも、この作品を作るにあたって、一つの軸として
「ストーリーは3行でまとめられるぐらいシンプルに」
を置いた。
演劇という表現形態は、人を描くという点において強みがあると思う。それは、「基本的に台詞によって物語が進む」というのがあるし、「実際に生身の人間がリアルタイムで演じている」というのもある。
ここで、複雑なストーリーを軸に置くと、どうしてもそのストーリーに沿って人物を(半ば無理やりに)動かす必要性が生じる。すると、自然体でリアルな人を描くことが損なわれることにつながる。
もちろん、これらが絶対に両立しないわけではないが、「人物を描き、結果的にストーリーが浮かび上がってくる」という流れの方が、より自然な作品になるのではないか、と個人的には思う。
というような演劇論を語っていると、いつまでたっても本編の振り返りにたどり着かない……ので、この話はここで一旦切り上げるとして(いつかそういう話をするマガジンを作るかも)。
戯曲に必要な最小単位は「場所」と「人物」らしい。その場所で人物同士(一人芝居の場合もあろうが)の「会話」「対話」が起こることによって、物語が産まれ、戯曲になるのだという。
本作品は
場所 → マンションの一部屋
人物 → 二人の女性(硝子と夕奈)
をまず設定し、
・ここは硝子の部屋で、夕奈は間借りしている
・二人は高校の頃からの友人
・事実上の恋人同士のような関係だった
など、更に詳細な設定を足していった。
そしてそこに
夕奈 → 硝子に結婚を報告し、別れなければならない
硝子 → 本心では別れ難いが、送り出さなければならない
と、行動の指針を設定することで、物語を立てていった。
また、説明台詞を極力排した文体で、ストーリーの都合を感じさせないよう留意した。
「優しくてやるせない」をコンセプトに、全体を通してノスタルジックな雰囲気を出せるよう作っていった。
個人的参考書
『演劇入門』平田オリザ(講談社現代新書)
『高校生のための実践劇作入門―劇作家からの十二の手紙』北村 想(白水社)
『表現の技術』髙崎 卓馬 (中央公論新社)
シーン1(3:03~7:30)
※時間は動画の再生時間(多少のズレあり)
導入部。
ここで意識したのは「作品に慣れ、ルールを理解して貰う」こと。
軽口の漫才的なやり取りを見せることでこの作品の全体的な「台詞回し」(→ 作品に慣れる)及び、この戯曲が「会話劇」であることを示す(→ ルールの提示)。
また、「硝子のキス」から「夕奈の結婚宣言」をシーンの最後に出すことで、ストーリーの軸を明らかにするとともに、後のシーンへの引きにする。
なるべく、ノイズとなるような「わからない」を生じさせず、かつ「引き」を持たせることに留意し、導入部とした。
ちなみに動画内で流れているオープニング(最後のエンディングも)は竹原の自作曲なので、マジで聴いてくれ。(脱線)
シーン2(7:30~13:30)
溶暗、溶明を挟んで、シーン2。
早くも脱線すると、一般に舞台が完全に暗くなることは「暗転」、照明が上がり次のシーンが始まることは「明転」と呼ばれているが、これらは正しくは「溶暗」「溶明」。
「暗転」「明転」は「暗い/明るい中で転換(= 舞台セットが変わること)する」ことを指す。
「確信犯」なんかと同じで、もはや誤用の方が一般的に浸透しているので、「暗転」「明転」と書いたとしてことさらツッコまれないだろうが、戯曲賞に送る時に「溶暗」「溶明」と書いておくと審査員が「おっ、コイツ分かってんじゃん」となって好印象かもしれない。
ただ、現場で「ここ溶暗で!」なんて言うと、おそらく「え?」って聞き返されるので、そこは素直に「暗転」と言った方がいいと思う。
さておき。
このシーンで、夕奈は家から出るために部屋の片づけをしているが、すぐサボるので全く進まない。大掃除なんかでよくある「思い出の品が発掘されて片づけがそっちのけになる」やつだ。
硝子も硝子で、口では「片づけなよ」と言っておきながら、夕奈と一緒になって思い出話に花を咲かせている。
シーン1のキスもそうだが、案外、硝子は久しぶりに夕奈が帰ってきてテンションが上がっているのかもしれない(夕奈の結婚のこととは、また別に)。
ここで、二人の関係性がまた一つ提示される。
二人は高校の頃からの友人で、文化祭についてなにがしか思い出があるらしい。
これが、後の回想のシーン(シーン3、シーン5)へと繋がる。
また、全体としてコミカルなシーンにして、シーン1の最後の静かで情緒的なやり取りから雰囲気を変えている。
あとがきらしい話をすると。
夕奈がギターの練習に使っていた童謡『夕焼け小焼け』
夕奈は、歌詞を
からすが鳴いたら かえりましょう
と間違えて覚えているが(正しくは「からすと一緒に かえりましょう」)、これは竹原が実際に間違えて覚えていたことから。
ノスタルジックな雰囲気にしたいな
↓
夕暮れのイメージ……夕焼け小焼け、弾き語るか
↓
歌詞……間違って覚えてた……
弾き語りがブリッジ的に挟まり、シーン3へと繋がっていく。
シーン3(13:30~18:00)
回想のシーン。
転校してきた硝子が、演劇部室で初めて夕奈と出逢う。
ここで、前のシーンから時間と場所が変わる(高校時代の演劇部室)が、「ギター」という小道具が、この変化の橋渡しをしてくれている。
映像と違って、演劇では場面の変化にかなり気をつかわなければならない。
映像ではカットを一つ挟めば基本的にどんなシーンにもつなげられるが(それでもルールや定石はあるだろうが)、演劇はどうしても現実的な舞台の制約がつきまとう。部屋のシーンがいきなり屋外にはならないし、2020年のシーンがいきなり1970年にはならない。そこには、場面変化を納得させるに足る何かが必要になる。
一応「一方○○年の××では」と台詞で示してしまえばどうとでもなるが、それはあまりに陳腐(逆に、そういう力業が許される雰囲気を作っておき、それ自体を「ネタ」として組み込む、ということも出来るかもしれないが)。
いずれにせよ、この作品では場面変化に効果的な理屈・理由をつける必要がある。
これを解消する手段の一つが「小道具」を使うこと。このシーンでいうところの、ギター。
ちなみに、シーン4からシーン5の間も、同様に時間と場所が変わるが、これについてはほぼ無策。照明に頼りきり。(ごめん☆)
また、直前のシーンで発掘された高校時代の制服を着させようとする夕奈に硝子が言った「絶対着ないからね」は、このシーンで制服を着て出てくることへのフリになっている。
シーン4(18:00~24:53)
シーン3始まりと同じようにギター弾き語りジングルを挟み(これは天丼と呼ばれる技法だよ。いいね?)、シーン4。
片付けも終わり、旦那から電話もきて、いよいよ夕奈は家を出ていく。
夕奈にとっても、自身の結婚は予想外のことだった。
"彼"と二人で写真を撮り、「にへぇ」と笑う顔を見せられた時、どうしようもなく「この人と一緒になるんだ」と思わされてしまった。
そのことを、硝子に伝えるが、それは浮気の言い訳ではない。夕奈は言い訳をする立場ではないし、そもそもこれは浮気でもない。
二人は恋人ではないからだ。
ここでついに、今までずっと保留にしてきた二人の関係について決着をつけなければならなくなる。
この関係に対する硝子の答えを
夕奈と友達になれてよかった
という台詞で表した。
硝子はこの関係性を友達と定義した。これは「本当はずっと好きだった」とはもう言えない硝子の、せめてもの抵抗の言葉でもある。
裏設定ではあるが、作者的には「この二人は、まあセックスぐらいしてるでしょ」と思っている。役者にも、そのつもりで役作りしてくれ、と注文を付けた。
シーン5(24:53~32:40)
夕奈が出ていって広くなった部屋で、一人たそがれている硝子が、高校時代のことを回想するシーン。
演出的な話も絡んでくるが。
夕奈が制服で入ってくるのに対し、硝子がそのままの服装なのは、このシーンが硝子の回想であることを示すため(シーン3では逆)。
もちろん、二人ともハケさせられないという現実的な都合もある。というよりは、その都合を解決するために設定を作ったと言った方が正しい。
文化祭終わりの、なんとなく浮ついた落ち着かない雰囲気。そこで交わされる、とりとめもないけれど、どこか深い話。
高村さんの話についての二人のスタンスの違いは、二人の別れにおける重要な要素を担っている。
このシーンの最後、夕奈が振り返って硝子に言う
私も初めてだったから!
という台詞は、夕奈にとって硝子は初恋の相手だった、ということを暗に示している(センター国語の設問になりそうな話)。
また、「最後のキスで物語を始めて、最初のキスで物語を締める」は、この作品でやりたかったことの一つ。
ちなみに、この作品は去年の11月に当劇団の旗揚げ公演『どうせ誰もみていないのに』でも上演したが
夕奈 うん。あのー、アレ作ってた、アレ。
硝子 どれ?
夕奈 サグラダファミリア!
硝子 サグラダファミリア。
夕奈 完成させてた。
硝子 完成させてた!?
は、全てのステージでウケた。
脱線というか、単なる自慢である。
アンケート
※アンケートで「このシーン/台詞ってどういう意味があるの?」的質問が来たら、当記事に追加するかもしれません。
「おー、面白いじゃねーか。一杯奢ってやるよ」 くらいのテンションでサポート頂ければ飛び上がって喜びます。 いつか何かの形で皆様にお返しします。 願わくは、文章で。
