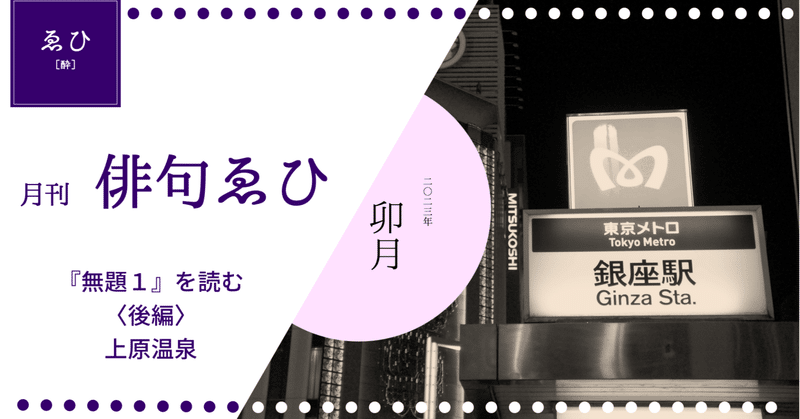
【note7月公開!】切れ字「や」と「の」を考える【月刊 俳句ゑひ 卯月(4月)号 『無題1』を読む〈後編〉】
こちらの記事は、月刊 俳句ゑひ 卯月(4月)号の『無題1』(作:若洲至)を、上原温泉が鑑賞したものの中編です。まずは作品の掲載されている本編、及び〈前編〉〈中編〉をご覧ください!
切れ字「や」と「の」を考える
春の夜や浅き階下を銀座線
最近、切れ字について悩んでいる。筆者の俳句生活は師によって、切れ字の代表選手である「や」の使い方の練習から始まった。「や」は、季語に接続させて用いることが多く、切る効果が句にメリハリを生んだり、季語の本意を全体へ響かせる効果が大きい。筆者にとっての「や」は、気の置けない幼なじみのようなもので、これまでの自作において「や」の使用率は高い。
それが最近、「やを使わないようにしている」と言う俳人に出会った。私はその人の俳句に対する考え方をかなり信用している。「や」を使わないとはどういうことだろう。「安易だ」と、その人が考えているような気はする。確かに、形を作りやすくはある。「や」で切りさえすれば、出来はともかく成立はするので。逆の見方をすると、型の力が圧倒的なだけに、自立心を阻むという意味で、作家性に関わる怖い切れ字なのかもしない。その俳人は、安易には頻用すまじという意味で、自らを律しているのかもしれない。
さてそんな「や」がドーン、の一句。まずは鑑賞してみよう。季語における春の夜は「春の夕」→「春の宵」→「春の夜」の順番で深まっていくが、この使い分けは繊細に行いたい。掲句はいちばん深い時間帯。場面は都市部の地下鉄駅。自宅へ直帰するなら残業の疲れに頭がぼんやりとし、飲み会の帰りなら足元がふらついていたりして、構内も車内も弛緩した空気に満ち満ちている。春の夜の茫漠としてどこか艶めいた趣きを、作者はまずそんな光景に仮託した。
銀座線は、東洋で初めての地下鉄として1927年(昭和2年)の東京に誕生した。初めは浅草・上野間、徐々に伸ばして1939年(昭和14年)に現在とほぼ同じ路線になった。筆者は鉄道に詳しいわけではないが、掲句の「浅き階下」には利用者としての体感がある。それは、紆余曲折を経て2000年(平成12年)に全線開通した都営地下鉄大江戸線との違いを感じるようになったことが大きい。東京の地下鉄でいちばん深い駅、地下7階分の深さとも聞く大江戸線の六本木駅で下車すると、地上に出るだけでもけっこうな時間がかかる。六本木の地上で待ち合わせる時は、地下での移動時間を計算に入れないと遅刻してしまう。それで相対的に銀座線の「浅さ」がわかるようになった。

作者の頭の中は、地上と地下の区別のみならず、その地下が更にミルフィーユ様の階層を成しているらしい。最深の大江戸線が走る地層から見て最も上層にある銀座線。たとえば銀座駅には地上へ上がる出口がいくつもあって、階段をトントントンと上がればすぐに外気に触れることができる。地下にいながら夜の気配を感じ取るためには、ここはどうしても、春の夜に最も近く隣り合う「浅き階下」でなくてはならず、地下鉄線の中でいちばん浅い地層を走る銀座線でなくてはならなかった。この句の面白さは、地下鉄の景を見たまんま、あっさりと描いているようでその実、選ばれた言葉のひとつひとつがしっかりとした根拠を持ち、そして、横に広がる地下空間と、縦に広がる地下空間を構造的に捉えてみせたところにある。
さて。「や」の話に戻る。
春の夜や浅き階下を銀座線
春の夜の浅き階下を銀座線
ここまで書いてきたことを理由に、筆者は、掲句においては「や」のほうが良いと思う。「の」が生む軽い切れは、作者が展開させた空間の重層性や、地上と地下、地層と地層を隔てる「壁」のようなものに対抗するためには弱く感じたから。季語の本意が句の中にある壁に遮られてしまって行き渡らない感じ、と言えばよいだろうか。「や」ならば、分厚い床を破って地下深く染み込んでいきまっせ、というような根性がある。切れ字の選択には、本来このように句の内容の多角的な点検が必要なのであって、それはおまけのようにくっついているわけではないのである。
ただし筆者はこれまで、その安定感から「春の夜や」を、以降のフレーズとの馴染みやすさから「春の夜の」を、軽いノリで使い分けたし、連作にした時は隣の句とのバランスを取るためだけに「や」⇄「の」を入れ替えるなどしてきた。その都度切れ字の比較を真剣にやったのかといえばして……ない。
基礎を大事にする姿勢と、基礎に依存する態度は、全く違うのに似て見える。そこを自覚的に区別しておかないと、先々が怖いことになりそうだと、気がつき始めている。だから今は、切れ字について悩んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/97043851/profile_afddf4bbfaa9813d96fb1ab304d2b64f.png?width=60)