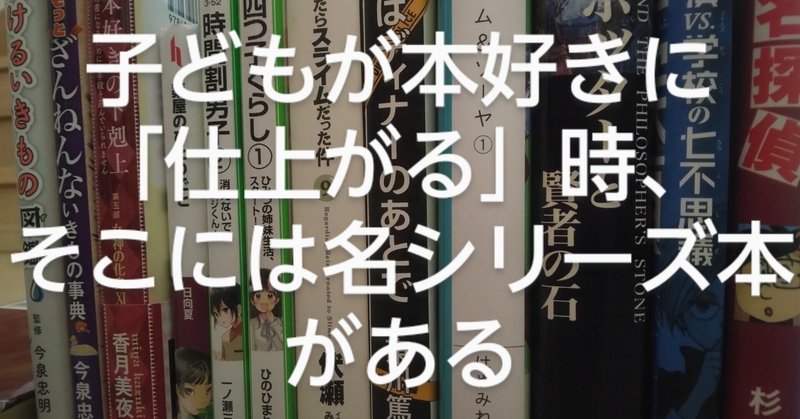
(20)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~
お手紙、つづきです。
「家にある本で、デジタル漬けになる前に『読む』習慣を」
・・・というお話をしています。
低学年までは動画やゲームがなくても家で楽しく過ごせます。
「みんな見てる」「そういう時代」は少し横においといて・・・
読む楽しみとすんなり出会える時期を大切にしたいなと思います。
・お手紙(19)はこちらからどうぞ。
(19)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
今日は
「子どもが本好きに仕上がる時、そこには名シリーズ本がある」
・・・というお話です。
さて、シオリさん。
「読むのが楽しい」と子ども自身が感じ、家にいる暇な時間に自分から本を手に取るようになったら・・・それは本好きとしてかなり「仕上がっている状態」かな、と私は思います。
お手紙(19)でお話した、自転車にスイスイ乗れている状態、自転車に乗ってきれいな景色を見に行けるようになった状態・・・でしょうか。
こうなるには、やっぱり一定期間子どもが「夢中で読める本」が必要なのですが、この強~い味方が「シリーズ本」だと思うんです。
シリーズ本の魅力は、なんと言っても1巻を読んで「おもしろかった」ら、2巻、3巻・・・を読むハードルがかなり低くなるということ。
基本的に同じ主人公、同じ世界観なので、2巻以降は1ページ目からスッと世界に入っていくことができますし、親としても「この本はどうかな・・・好きかな・・・?」と毎回お試しのドキドキを味わわずに済みますから、本を勧める親として、ものすごくラクです(本音)。
次女の言葉を借りると、「この主人公の子が、幸せになるかどうか、知りたくて、次の巻が待ちきれない・・・」――まさにそういうことですよね。
ハマってくれると、本当に助かります!
なので私は、5歳の図書館通いから一緒に「本好き大作戦」を始めた長女には特に、
「好きそうな一冊」よりも「好きそうなシリーズ本の第1巻」
・・・を意識して勧めてきました。
これはもちろん、好みによるし、タイミングによるし、家庭によるので、「絶対にこのシリーズはいい!」と断言はできないのですが・・・。
――それでも参考までに、我が家ではどういう順番で子どもが夢中でページをめくるようになっていったのか、読んでいったシリーズ本のラインナップを書き留めておきたいと思います。
1.「もしかしたら名探偵」「いつのまにか名探偵」などの
「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ
(作・杉山亮/絵・中川大輔/偕成社)
・・・お手紙(9)でお話した、絵本から児童書へ移行するための架け橋になってくれたシリーズ。この詳しいエピソードはお手紙(9)にゆずりますが、長女が「文章を読んでおもしろさを感じる」キッカケを作ってくれた名シリーズです。
2.「科学探偵 謎野真実」シリーズ
第1巻は「科学探偵vs.学校の七不思議」(作・佐東みどり、石川北二、木滝りま、田中智章/絵・木々/朝日出版社)。
・・・このエピソードもお手紙(10)にゆずりますが、長女が「謎解き」好きという方向性をより強く意識した本選びでした。
「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズよりも文章量がアップしています。 これを小学2~3年生のころに読んでいました。
3.「ハリー・ポッター」シリーズ
(作・J.K.ローリング/訳・松岡佑子/静山社)
・・・この詳しいエピソードもお手紙(10)にゆずりますが、小学4年生の時に3カ月かけて全11巻を読破。長女は初めて「続きが知りたくてたまらない!」という感覚を得たようです。
すべての巻を映画未鑑賞の状態で読んだので、「1巻を読んだ時はハリーの顔も声も知らなかったけど・・・それが逆に良かったかも」と本人談。先がわからないからこそ、夢中でページをめくったようです。
ちなみに、文章だけの全11巻を読破したことが、後々も本人の「読む自信」につながっているようで、今でも時々、読書中の長女に私が「すっごい分厚いもの読んでるね・・・」と声をかけると、
「ハリポタのほうが長いから、これくらい平気」と返してきます。
やっぱり、「あれを読めたんだから、これも読める。読んでみれば、おもしろさがわかる」という体験がベースになっているようです。
4.「都会(まち)のトム&ソーヤ」シリーズ
(作・はやみねかおる/画・にしけいこ/講談社)
ハリポタの後で夢中になったシリーズがこれです。
2年ほど前、映画化で話題になっていたので、まずは1巻を読んでみたところ・・・どハマり。その時既に16巻くらい刊行されていたので、その後も読むものに苦労せず、今もかなり楽しませていただいています。
挿絵も何枚かあるのですが、文章のボリューム的には一般的な小説と変わりません。
はやみねかおる氏・・・という作者の名前に聞き覚えがあり、調べると「そして五人がいなくなる」などの「名探偵 夢水清志郎」シリーズと同じ作者だったと知り、びっくり。とても長い間活躍されている作家さんでした。ジュブナイルミステリの名手で、多作な方なので、「ほかにも読むものがたくさんあるぞ」と嬉しい発見!
最近では思春期の入り口となった長女に、女子高生が主人公の「モナミは世界を終わらせる?」(作・はやみねかおる/角川書店)をお勧めしたら、夢中で読んでいました。
5.「謎解きはディナーのあとで」シリーズ
(作・東川篤哉/小学館)
これは5年生の時に読んだものです。ドラマの再放送をたまたまテレビで一緒に見て、「これ原作の小説もおもしろいんだけど、読んでみる?」と聞いたところ「読む!」と言ったので購入。先に少しだけドラマを見ていたのですが、役者さんのイメージと小説の世界観がぴたりと一致したようで、楽しく読んでいました。
じつはこれ、長女が初めて読んだ「いわゆる児童書ではない」ミステリーなのですが、本人にそれを言ったところ「ふ~ん」という薄い反応。
「文章しかない」のも、「長い」のも、「ハリー・ポッター」や「都会のトム&ソーヤ」ですっかり慣れていたので、当たり前ですが「おもしろければ子ども向けかおとな向けかは関係ない」ことがこれでわかりました。
6.「転生したらスライムだった件」シリーズ
(作・伏瀬/イラスト・みっつばー/マイクロマガジン社)
長女はこのアニメの大ファンなのですが、アニメ2期を見終わったところ、「続きが知りたい! 3期はいつ?」と聞かれ、「そんなことは知らないけど・・・続きが知りたいなら小説を読んでみたら?」と提案したところ「読む!」となったので、物語上アニメ2期の続きである小説版7巻から読み始め、現在も読破中。
小説版は2023年9月現在20巻まで刊行されているようで、長女は21巻を心待ちにしています・・・。
この「転スラ」はライトノベルというジャンルですが、本好きでなければおとなでもひるんでしまうほど「どっしり」「びっしり」とした本格的な小説です。
長女の場合、すでにアニメの世界観が頭の中にできあがっていて、そこから7巻のページをめくったことですんなり文章の世界に入ることができたようです。
まるで、自分の想像力を頼りにアニメ3期を頭の中で創りあげているようなおもしろさなのでしょう。
通常は、すでに映像作品(映画やアニメ)を見ているものの小説版をいちから読むのは子どものにとって難しいこともあるのですが、この場合は「知ってる世界の、まだ知らない話」なのが読みやすさを助けたようです。
自分で勧めておきながら、こういう読み方もあるんだな・・・と妙に感心してしまいました。
7.「時間割男子」シリーズ
(作・一ノ瀬三葉/絵・榎のと/角川つばさ文庫)
「転スラ」を読んでいる同時期(5年生)に、長女が友人から借りて読み始めたのがこの「時間割男子」。
私は知らなったのですが、子ども達に大人気ということで、この時点で8巻くらいまで刊行されていました。
これまで読んでいたものと比べると、少し幼いのかな・・・とも思ったのですが、主人公の女の子が同じ小学5年生ということもあって、長女はいろいろ共感しながら読んでいました。
この頃、あらためて本の好みを長女に尋ねると、「おもしろければ、ジャンルはなんでもいい!」との答え。
もともと、わりと緻密な構成のミステリーやファンタジーが好きそうだな・・・と思っていましたが(時間割男子はファンタジーと言えばファンタジー)、「読む」ことに慣れた結果、「おもしろいのかな・・・失敗したくないな」と深く考えなくても、「とりあえず読んでみよう」とサクサク手が動くようになってきたようでした。
「読む」のがひとつの技術だとすれば、技術が高まってきた状態です。
このころから長女は「スピード感あふれる乱読派」になり、私が「ちょっとこの本、子どもに人気あるみたいだから読んで感想聞かせてくれない?」とお願いすると、「え~いいよ~」と言って(仕事のように)読んで感想を伝えてくれるようになりました。
そしてこの頃、小学1年生だった次女が、長女が読んでいる「時間割男子」をパラパラとめくるようになったのです。
放っておくと、1巻をぜんぶ読んでしまい、「おもしろかった!」と言ったのでした。
「ほとんど文章だけど、読めたの?」と聞くと、「絵が可愛いから、読めた~」とのこと。
そして、「ぜんぶの漢字に読み仮名ついてるよ!」と教えてくれたので、私もあらためて目を通してみると、1年生で習うどんな簡単な漢字にも読み仮名がついていること、現代の子どもの感性に合ったイラストがたくさんあり、会話中心で楽しく読める内容であること・・・に気づいたのでした。
今さらながら、大手出版社の児童文庫ってすごいな・・・と思い、こういう本なら次女も読めるかもしれない、と思ったのです。
そこで、「時間割男子」にはさまっていたリーフレットを見て、大人気だという
8.「四つ子ぐらし」シリーズ
(作・ひのひまり/絵・佐倉おりこ/角川つばさ文庫)
・・・の1巻を購入してみた私は、さりげなく本棚に並べておくことに。 すると次女は、これも手に取り、だまって読んでいたので、「おもしろい?」と聞くと「うん、おもしろい」と答えたので、結局これも全巻揃えることにしたのでした。
このころから次女の「自分と同じ目線の女の子たち」が主人公の話を好む傾向が強まりました。
そしてまた、学校の図書室から自分で児童書を借りてくるようにもなり、そのたびに「こんなの借りてきた・・・」と見せてくるので、私も「おもしろそうだね。本選ぶの、じょうずだね」と褒めてあげるようにしていました。
ちなみに私は、本が好きな子に「本を読んで偉いね」という褒め方をする必要はないと思っています(サッカーが好きなんて偉いね・・・アイドルが好きなんて偉いね・・・と褒める人がいないのと同じです。好きなんだから、偉くはないですよね)。
けれど、「またおもしろそうな本読んでるね! 本選びがじょうずだね」とはよく言ってあげるようにしていました。
すると子どもは、「自分は、自分で好きな本を選ぶことができる」という自信をつけることができます。
これは、末永く本好きでいるためには、自分で本選びができるようになることが大切だからなんですね。
ーーさて、話を戻し、長女がこの後読むようになったのは、これも大人気の
9.「本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~」シリーズ
(作・香月美夜/イラスト/椎名優/TOブックス)
これもまた「転生したらスライムだった件」と同じ流れで小説を読むことになりました。
そう、アニメを見ていたのですが、第3期が終わり、「続きが知りたい!4期はいつ?」と聞かれて、「そんなことは知らないけど・・・続きが知らいたいなら小説を読んでみたら?」と提案したところ「読む!」となったのです(まったく同じ展開・・・)。
物語上アニメ3期の続きである小説版8巻から読むことになり、現在も読んでいるのですが、原作の小説は30巻以上あり、いずれ1巻から読み直したとしても・・・かなり長い時間楽しめそうです。
本一冊でも、おもしろいものを書くのは凡人には難しいのに、
これだけ長い文章で、子どもの心をワクワクさせ続けてくれる、そんな物語を書ける作家さんは素晴らしいーー感謝しかありません。
さて、続いては・・・。
10.「薬屋のひとりごと」シリーズ
(作・日向夏/イラスト・しのとうこ/ヒーロー文庫)
長女が「本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~」と同時進行で読んでいるのがこれです。
一緒に書店へ行った時に見つけて、1巻をお試し購入。
読んでみると長女が、「・・・ハリポタ以来の衝撃かも!」と言って、すぐ夢中になりました。聞くと「主人公のキャラクターがおもしろい」とのこと。
今は私も読んでいるのですが、謎解きのおもしろさもさることながら、登場人物の造形、人物相関図のなかなかの複雑さ、それぞれの生い立ちや立場による思惑、数巻にわたる伏線の張り方、会話のユーモアとシニカルさのバランス・・・などが見事で、これはとてもとても読書初心者向けではないなぁ・・・と感じました。
現在のところ13巻まで出ているようで、これもジャンルとしてはライトノベルなのですが、読みごたえは決してライトではありません。
文体は淡々としていますが、文脈に含みがあり、なかなかの読解力が必要ーーそして、なんだか最高にクセになります。
この、文脈のおもしろさを体で感じるようになると、読書というのものは、なかなかやめられない脳の娯楽になっていきます。
ハリー・ポッターでいちど「本はおもしろい」と確実に実感したであろう長女ですが、その後いろいろ読むことでもう一周し、「なんとも言えない文脈のおもしろさ、豊かさを感じる」という二週目に入ってきているな・・・と感じました。
「転生したらスライムだった件」「本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~」と読書の入りが違うところは、先に映像化作品を見ていないところ(あえてコミックにも手を出していません)。
やっぱり、いちから自分のイメージだけで紡いだ物語は、格別なようです・・・。
この秋アニメ化もされるということで、親子で楽しみにしています。
ちなみに、子ども達へ私が日常的にお勧めしていたのは、
11.星新一のショートショート
いろいろな出版社からいろいろな仕様で刊行されているので、どれ、とは言えませんが、蔵書から何冊か取り出して渡していました。
これは、サクっと読めて、クスっと笑える(けれど、完成度が高い)ので、長女も次女もお気に入りです。
シリーズものというわけではありませんが、生涯で千話以上書いたとされる方で、著作が多いので、「読んでも読んでもなくならない」という意味でも読書の強い味方です。
ーーさて、最後になりますが、長女は最近、学校の図書室から住野よる氏の作品をよく借りてくるようになりました。
最初は、ベストセラーとなった「君の膵臓をたべたい」。
続いて 『か「」く「」し「」ご「」と「』、「この気持ちもいつか忘れる」、「腹を割ったら血が出るだけさ」、「また、同じ夢を見ていた」など、立て続けに借りて読むようになり、読了後は「よかった・・・」と泣いていることもあります。
ーー成長を感じました。
住野よる氏は、長女が初めて好きになった「作家」です。
作家を基準に本を選んだのが、初めてのことなのです。
そして、自分の感覚で本棚から手に取り、読んでみたら感動した・・・という体験を、親(私)の介入なしにしていることが、よかったと思いました。
子どもが本好きに「仕上がる」まで、「本読みスイッチ」が途切れないためにシリーズ本がおすすめ・・・というお話をしてきましたが、それと同じように、「多作の作家」さんを味方につけるのも、とても効果的なことだと思います。
住野よる氏は多作というほどではまだないかもしれませんが、10冊以上は刊行されているので、今長女はそれを頑張って追いかけている状態です。
「このシリーズなら読める」から、「この作家なら読める」「この作家をもっと読みたい」・・・と興味が移っていくと、どんどん本の沼にハマっていくのかもしれませんね。
ちなみに私が小学生の時、ハマりにハマって本好きに「仕上がった」きっかけの作家は・・・赤川次郎氏です。超・多作ですね!
――長くなりました。
読んでくださってありがとうございます。
少しでも、参考になれば幸いです。
次は、読書傾向で子どもの個性や性格が理解できた話・・・をしたいと思っています。
お手紙、続きます。
〈全部読みすごいと言われ「本の中、ハリーと一緒に生きてただけよ」〉
・お手紙(21)はこちらからどうぞ。
(21)5歳頃から〝積読本〟と暮らすことが「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
・お手紙(1)はこちらからどうぞ。
(1)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
