
【Vol.1/5】温故知新的な「Free Soul 90s」のフィロソフィー~「Suburbia Suite」が音楽の聴き方を変えた ー 橋本徹×柳樂光隆×山本勇樹『Ultimate Free Soul 90s』座談会@HMV & BOOKS
◆温故知新的な「Free Soul 90s」のフィロソフィー
山本:発売されたばかりの『Ultimate Free Soul 90s』、こちらはユニバーサルからの3枚組なんですが、まずは制作に至る経緯を橋本さんから簡単にご説明いただいていいですか。
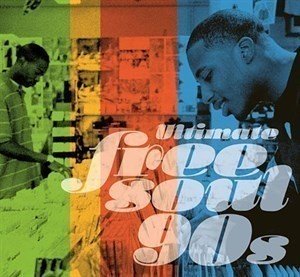
橋本:2014年がフリー・ソウル20周年ということで、レコード会社の方からいくつか企画をいただいてコンピレイションを作ったんですね。その中で『Ultimate Free Soul Collection』という、

僕たちがいいなと思ってプレイしてきたものの中で、特に人気が高かった曲を3枚組でスペシャル・プライスのコンピレイションにするというのがあって。これはもともとユニバーサルの営業さんの企画だったんですけど、そのときの僕はどちらかというと「2010s Urban」シリーズのような、現在進行形の選曲をやりたいなと思っていたので、「じゃあファンの人気投票で収録曲を決めてもいいんじゃないか」というような話もしていたんですけれども(笑)、同時に「2010s Urban」の選曲もしてくださいとのことだったので、

『Ultimate Free Soul Collection』というのを作ったんですね。やはり営業の方の話は聞いておくべきなんでしょうか(笑)、これが大きなヒットになりまして。で、レコード会社の常として「Ultimate」シリーズでいろいろできるんじゃないかということで、モータウン編とブルーノート編と、

その後ワーナーさんからもうちの会社の音源でどうですかということで、『Forever Free Soul Collection』というスピンオフ企画が誕生したんですけど。

で、去年の夏前くらいに「新しいコンピレイションの企画どうですか?」という話をいただいた時期に、ちょうど「2010s Urban-Jazz」の対談がHMVであって、そのときにちょうどここにいる柳樂くんが「Free Soul 90s」シリーズをたくさん持ってきて話してくれたんです。それがどこかに引っかかっていて、じゃあ「Ultimate」で90sやりますか、という気持ちになったのが企画の発端というか、実はあの対談がモティヴェイションになって今日に至っていると。

柳樂:「Free Soul 90s」を持っていった理由は、橋本さんが最近の新譜を中心に「2010s Urban」のコンピレイションを作ってるじゃないですか。それに僕の「Jazz The New Chapter」(以下「JTNC」)っていう本で紹介しているようなアーティストが登場していて。

橋本:すごくシンクロしているんだよね。
柳樂:それを聴いたときに感じたフリー・ソウルっぽさが、70年代の音源を中心としたシリーズというよりは、90年代の「Free Soul 90s」の雰囲気ととても近いと感じて。
橋本:今日、2時間かけて3人で話したいと思ってるのはまさにそこで。『Ultimate Free Soul Collection』のコンセプトというのは、いわゆる“ベスト・オブ・ベスト”で、みんなが好きな曲やDJパーティーでのキラー・チューンがひたすら入っているというようなものだったんです。一方で「Free Soul 90s」は、山本くんや柳樂くんがよく理解してくれているように、それだけではなくていろんな時代やジャンル、過去と今を紐づけて音楽を楽しんでいくというコンセプトが大きくて、1995年にこちらのレジュメにもあるように6枚の「Free Soul 90s」のCDを出したんですけど、僕らの好きな70年代の曲のサンプリングやカヴァーなど、直接的な影響が大きい曲を収録していったんですね。『Ultimate』がすごく人気があるのは、「いい曲ばっかりだ」「懐かしいな」という部分が大きいと思うんですけど、今日はその部分ではなくて、「Free Soul 90s」のコンセプトの部分を皆さんにお伝えしたいなと。それはフリー・ソウルのやってきたことの重要な部分であり、なおかつ「JTNC」とも激しくシンクロする部分だと思うので。それを曲をかけながら説明していけたらいいなと。
山本:今、『Ultimate Free Soul 90s』のCDの説明を橋本さんからしていただいたんですけど、過去と現在をつなげるというフリー・ソウルの役割、それを柳樂さんも強く感じていると思うんですが。
柳樂:そうですね。橋本さんって、70年代のソウルやジャズ、ロックやフォークとかからフリー・ソウルっぽい曲を選んでコンパイルしている、というイメージなんだけど、それはただ古い曲を選んでいるというより、その時その時に合った、基本的に新しいものとして選んでいるんですよね。
橋本:そうですね。20年ちょっと前、最初にフリー・ソウルのコンピレイションを出したときは、古い音楽の埋もれていた名曲を取り上げているという印象も強かったせいか、上の世代の方からは重箱の隅をつついているといったお叱りも受けたりしたんですが(笑)、実際にはそんなことはなく、現在進行形で光り輝いているものを選んだつもりでした。でも、よく聴いていない人からするとそのように映ったみたいで、「違うんですよ」っていう気持ちで作ったのがこの「Free Soul 90s」の6枚のシリーズだったんですね。僕は歳をとってあまりいろいろ言われなくなったんだけど、柳樂くんが現在同様の問題に直面してるんだよね(笑)。古いジャズの評論家やお堅いジャズ・マニアの方には「なぜ『JTNC』はジャンルとの接点や国や地域との接点ばかりアプローチするんだ」って思われたりしてると思うんだけど、20年前に僕も同じような経験をしてるんだよね。

柳樂:なるほど(笑)。「Free Soul 90s」を僕が好きだったのは、言い方は大きくなるかもしれないけど、わりと教育的な感じがしたんですよね。山本さん、なんとなくわかりません? リアルタイムのネオ・ソウルとかヒップホップとかアシッド・ジャズとか、基本的に過去の何らかの音楽との接点があるものが選ばれてたり。それが当時出ていた「Suburbia Suite」で表現されていたと思うんですが。このときのライナーは誰が書いてるんでしたっけ?
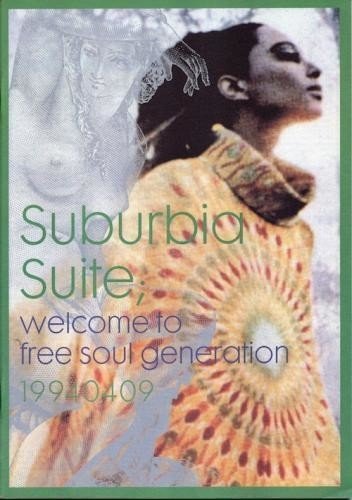
橋本:佐々木士郎、今ではライムスターの宇多丸として有名ですけれど。それから渡辺亨さん、あとは一緒にDJしていた二見裕志さん、僕の4人です。当時はCDを出すたびにフライヤーを作っていたんですが、ライナー同様になぜこの曲が「Free Soul 90s」に選ばれているかがわかるように説明をしていました。
柳樂:クエストラヴか誰かが言っていた名言みたいなのがあって、「Jazz is a teacher, Hiphop is a preacher」っていうんですけど(ジェイムズ・ブラッド・ウルマーの「Jazz Is The Teacher (Funk Is The Preacher)」という曲に由来するフレーズ)、「ジャズが先生でヒップホップは宣教師で、ヒップホップは布教してるんだ」ってことなんですけど。「Free Soul 90s」はそういうのをすごくわかりやすい形でやってた。普通にヒップホップ聴いてても、じゃあソウル聴こうってなかなかならないじゃないですか。
橋本:そこを紐づけてくってことだよね。
柳樂:そこが新しかったし、解説してったってのはすごく意味があったと思います。
橋本:ありがとうございます(笑)。特に、単なるベスト・オブ・ベストではなく、そういう意味合いを込めて選んでるんですよってことを、今日ここにいる皆さんに伝えられたらな、ということでこのレジュメを用意しました。当時のフライヤーであったり、最もわかりやすいのはその次に出てくる「bounce」(タワーレコードの月刊音楽情報誌。橋本は96年4月から99年3月まで編集長を務めた)の「Free Soul 90s」が出たときの特集記事なんですけども。これは僕が編集長になる直前の時期なので、フリーランスとして取材を受ける立場でした。「Free Soul 90s」で僕が意図したことであったり、「JTNC」を通じて柳樂くんがやろうとしてたりすることがすごく理解しやすくなるミーティングの対談原稿なので、これを読んでいただいたら、温故知新的な「Free Soul 90s」のフィロソフィーみたいなものが伝わるかと思っています。その記事の中では『Clear Edit』という、架空のコンピレイションを「bounce」のために選曲しました。1995年の「Free Soul 90s」は、BMG、東芝EMI、ソニーという3社から2枚ずつリリースされたんですけど、ポリドール、マーキュリーといった、現在のユニバーサル音源は使われていないんですね。なのでこの架空盤には、ユニバーサル音源がいろいろ入っています。『Clear Edit』は、今回の『Ultimate Free Soul 90s』のプロトタイプになっているな、とこの記事を読み返してさっき思ったんですけど。これを実際に実現したいな、っていう気持ちがどこかにあって、今回90年代のコンピレイションを作ろうと思ったのかな、と感じましたね。
トークショウは、橋本徹さんによる『Ultimate Free Soul 90s』の制作の背景、そしてそのコンセプトの解説から始まった。橋本さんが強調していたのは、一見ベスト・ヒット集にも見える『Ultimate Free Soul 90s』だが、その裏側には90年代音楽と70年代を中心としたフリー・ソウルで脚光を浴びた音楽との結びつきがある、ということだった。僕は高校時代からオリジナル・ラヴやフリッパーズ・ギター(コーネリアスと小沢健二)といった、いわゆる“渋谷系”の音楽が好きだったので、彼らがインタヴューなどで語っていた洋楽を聴き、その音楽的ルーツを探っていくことにワクワクするものを感じていた。さらに94年にフリー・ソウルに出会い、フライヤーに書かれていた「山下達郎ファン必聴」「オリジナル・ラヴに影響を与えた」といったフレーズに惹かれ、「Suburbia Suite」掲載のレコードを探しては聴いていた状況だったから、イヴェントで配布されたレジュメの「Free Soul 90s」の三つ折りフライヤーに掲載されていた「Good Recycler」を、当時とても刺激的に感じたことを思い出した。現在進行形の同時代音楽を起点として、現在から照射した過去の魅力的な音源を紹介する。それが橋本さんの昔から変わらない姿勢だというのは、ここに挙げた話でわかるだろう。(waltzanova)
◆「Suburbia Suite」が音楽の聴き方を変えた
橋本:じゃあ最初にこのレジュメの説明をしておきますと、僕が1996年2月に出した「Suburbia Suite」の「Suburban Classics: For Mid-90s Modern D.J.」という号の記事です(当日の参加者には、「Suburbia Suite」や「bounce」のコピーなど、分厚いレジュメがサブテキストとして配布された)。「Suburbia Suite」は、今の方はあんまりご存じないかもしれないんですが、僕が90年代前半に作り始めたコラムやレコード紹介文を載せたフリー・ペーパーなんですね。それを再編集した形で、1992年に最初のディスク・ガイドが出ます。それはどちらかというと映画音楽であったり、ソフト・ロック~ジャズ・ヴォーカル~ボサノヴァ~フレンチといったタイプの音楽をフィーチャーしていて。当時、レコード会社からも掲載盤をリイシューしませんかという話が来て、いわゆる渋谷系的な感性がとても盛り上がってきた頃だったので、そこともシンクロして、大きなブームになったんです。ただ、そのタイプの音楽は、その後僕が紹介してきたような音楽を聴いていただければわかると思うんですけど、あくまで僕の中の一部でしかなかったので、そういう白いスマートな方だけではなくて、ソウル・ミュージックやクラブ・ミュージック、よりわかりやすく言うと黒っぽいグルーヴ感のあるものを紹介したいなと思って始めたのがフリー・ソウルで、DJイヴェントとディスク・ガイド、コンピレイションという形でスタートしたのが1994年春だったんですね。実際にはDJイヴェント以前にディスク・ガイドやコンピレイションは作っているんですけど、1996年に出た「For Mid-90s Modern D.J.」は、実際にクラブ・パーティーを始めた後のもので、そのドキュメント的な色彩がすごく強くなっています。当然パーティーの現場では70年代ソウルだけがかかるわけではないので、そこと相性のいいヒップホップやR&B、グラウンド・ビートのUKソウルやアシッド・ジャズであったりっていうものが混ざってくるんですけど、そういう12インチをディスク・ガイド化したのがこの号で、その紹介部分だけを今回は抜粋しています。これは「Free Soul 90s」のコンセプトと直結するもので、本当に短い文章しかつけてないんですけど、何をカヴァーしたかとか何をサンプリングしたか、といったことを押さえてガイドしたものです。70年代音楽と当時現在進行形の90年代の音楽の結びつきを示すために作ったものですね。
柳樂:こういうものが出る前って、ロックならロック、ソウルならソウルという、ジャンル別のディスク・ガイドが一般的でしたよね。ロックの評論家の人がロックの歴史を書いて、その後に名盤ガイドがついてるという感じ。例えば「レコード・コレクターズ」みたいにもう少し焦点を絞ってAORだけとか、そういうのはあったと思うんですけど。今でこそ当たり前ですけど、こうやって見てみると白人と黒人、あまり馴染みのない国の人も全部出てるじゃないですか。コラム「frank talk, free style」も何らかのイメージでまとめているっていうのがすごく新鮮だったし。音楽性やその構造でまとめているわけではないんですよね。
橋本:聴いたときに感じるフィーリングを伝えることを目的に作ってましたね。
柳樂:例えば、ソウル的な構造があるわけじゃないけど、スティーヴン・スティルスのファンキーなフィーリングの曲は入る、みたいな。
橋本:ソウルを感じるものであればどんどん紹介していったし、DJパーティーでかけていましたね。
柳樂:アフリカのアーティストとかでも、洗練されたものだったら入っている。
橋本:ブラジル音楽も然りだよね。
柳樂:だから、ジャンルで切らずにフィーリングで点で集めていったらすごく大きくなったっていうのは、とても新しいことだったんじゃないですかね。さすがにこれが出たときはリアルタイムではなく、僕は東京に出てから古本屋で買いましたけど。
橋本:僕は80年代後半に大学生だったんだけれど、当時は各ジャンルのオーソリティーの方がいらして、“ひとつの正しい価値基準”みたいなものが音楽ファンの間で共有されていて。そういう中ではディープなサザン・ソウル的なブラック・ミュージックであればあるほど評価が高かったという印象があるんですけど、自分の耳で聴いたり感じたりしたときに、そういうディスク・ガイドや音楽書では軽視されていたり、もっと言ったら掲載されていないようなアーティスト――わかりやすい例を出すとリロイ・ハトソンやテリー・キャリアーだったり、あとはチャカ・カーンやスティーヴィー・ワンダーがジャズっぽい、とかいってすごく評価が低かったりってことに、大学生の自分なりにすごく違和感を感じてたんですよ。でも、実際にアメリカの黒人たちに聞くと、アーバンなものが好きで、「チャカ・カーンやスティーヴィ・ワンダー最高!」って言ってたりするわけでね。プリンスもそうですが、なんかちょっと日本の黒人音楽ジャーナリズムだけ、今の言葉でいうガラパゴス化している印象があって、それはジャズでも全く同じことがあったんだけどね。
柳樂:まあそうですよね。ディー・ディー・ブリッジウォーターがディスコっぽいものをやっている頃のって、いわゆるジャズの世界ではすごく評価が低かったわけですけど、ラリー・レヴァンとかはガンガンかけてたわけですよね(笑)。
橋本:だから、そのクロスオーヴァーする部分だったり、ジャンルとジャンルの接点だったり、時代と時代の接点だったりってものが拾われなかったんですよね、昔は。歴史観っていうのも全部古い音楽の方から新しい音楽の方に向けたものだから、新しい音楽になればなるほど評価が低い、みたいになってしまって。それを僕は逆にしたかったというか、現在から見た過去とか、歴史を横に見る、みたいなことなんですけど。ちょうどCDが出てまもなくの頃で、古い音楽も再発とかで新譜と同じように接することができるようになった時代だったんで、理解してもらえる同世代の人も何人かいたので、形にしてみたというところですね。
柳樂:やっぱり再発のCDが新譜のように魅力的なものとして出てきて、それが新譜と一緒に売り場に並んでたっていうのは刺激的でしたよね。
山本:僕は高校1年生のときにフリー・ソウルが始まって、その前の中学3年生のときにジャミロクワイがデビュー、あとはブラン・ニュー・ヘヴィーズ、ワークシャイ、スウィング・アウト・シスター、みたいな。
橋本:J-WAVEとかでパワー・プレイされてたしね。
山本:そういう世代なんですけど、当時フリー・ソウルで60~70年代のソウルやロックやブラジルやジャズやAOR、そういうものを初めて知ったから、自分にとっては新譜というか新しい音楽として接して、同時にジャミロクワイやブラン・ニュー・ヘヴィーズとかを、自分の中で解釈しながらというか楽しみながら聴いていた、って感じですね。
柳樂:しかもそれに呼応するアーティストが、海外だけでなく日本でも反応して新譜を出したりみたいな状況があって。
橋本:それは本当に当時の特徴だと思いますね。
柳樂:いろんなものが同時進行で進んでいて、そういう動きをうまく捉えていたのが、当時のHMVだったりメディアだったら橋本さんだったり「bounce」だったり、ってことなんですかね。
橋本:ロンドンのアーティストはもちろんなんだけど、東京のアーティストも現在進行形の動きにリンクしていて、それゆえに古い音楽への関心もあってという時代だったので、いろんなものがつながっていった時代だなと思いますね。
90年代から20年以上が経過した現在、改めて語るべき「Suburbia Suite」の功績というのは、トークショウでも繰り返し語られたことだが“価値観の刷新”という点だろう。それまでの音楽ジャーナリズムでは、ロックならボブ・ディランやビートルズ、ソウルならオーティス・レディングやアレサ・フランクリン、ジャズならマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンというふうに、それぞれのジャンルにおける巨人が存在し、彼らを中心に歴史も構成されてきた。そのもとに名盤も選定され、一種の階層化・序列化がなされていた。それがレア・グルーヴなどDJカルチャーの影響を受け、それまでは多くの人々が知らなかったようなアーティストや曲に注目が集まるようになっていった。それをある種のセンスと視座から体系化したのが「Suburbia Suite」であったわけだが、そのスタイリッシュな編集もあって、東京を中心として大きな影響力を持つようになっていく。さらにCDというメディアの普及によって掲載盤が再発され、“渋谷系”の隆盛とともに、のちに“ニュー・スタンダード”となる多くのアーティストが“発見”された。テリー・キャリアー、ニック・ドレイクやリンダ・ルイス、マイゼル・ブラザーズ、シュギー・オーティス、マルコス・ヴァーリといったアーティストがそれだ。こういった“横から切って(すべてを並列に)歴史を見る”状況は90年代以前には考えられなかったことだ。現在、柳樂光隆さんがやっている「Jazz The New Chapter」もまた、ジャズを現在進行形の音楽という視点から再定義する試みであり、トークショウの最後で橋本さんが言っていた通り、「フリー・ソウルのフィロソフィーを最も本質的に受け継いでいる」のだと思う。(waltzanova)
ここから先は
¥ 250
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
