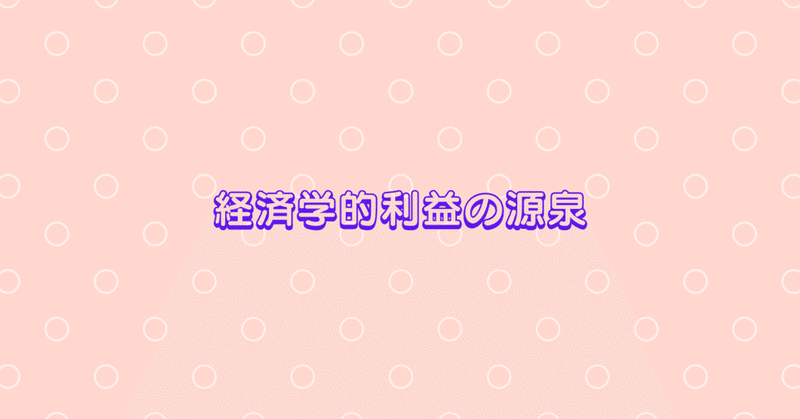
経済学的利益の源泉
限界効用逓減の法則が、メンガーが労働価値説を批判して主観的価値理論を打ち立てたことから展開し始めたところまで見た。すでに見た通り、メンガーは主観的価値理論を数学的に処理することには否定的な見解であったが、にもかかわらず限界効用というものが数学的にモデル化され、それが近代経済学の基礎となってきた。その矛盾こそが、現代経済学の直面している問題として、昨今のさまざまな経済的諸問題として顕在化しているのではないか。
そもそも利益を数学的に処理し、それを客観的評価の指標とすること自体意味があることなのか、という問題提起はあるのだが、直近の現実的問題として、それについて考察する必要があるのならば、とりあえず取り組んでみる必要がありそう。
価値と利益
まず、価値と利益は同じものなのか、という問題がある。(経済的)価値というのは、個々人の(経済的)判断基準に基づいた評価であり、それは会計的には全体としての価格として表現される。一方利益はより会計的な概念であり、売上から原価を引いたもの、ということになる。つまり、利益を上げるには、売上を上げるか原価を下げるか、ということになる。ここで、労働価値説に基けば、働いた物が価値となるので、売上即ち価値となってしまう。そして産業社会においては、労働は賃労働であり、それは生産側にとっては原価に含まれることになる。だから、売上が上がらなければ賃金を切り下げるといった原価低減を行うことが利益の源泉となる。価値と利益の相反というのが労働価値説が産業社会において直面した大きな問題であった。
主観的価値理論
そんな状況に対してメンガーが提示したのが主観的価値理論となる。これに基いて、価値は、それぞれの主観的判断によって定まるので、それによって、供給側の労働価値と需要側の主観的価値の差額が利益になる、というプラスサムの価値理論が、市場経済に基づいて作用する、という理屈が成立した。スミスからの直接的な後継という意味では非常に意義深い考えであると言えるが、一つには現実社会はより産業化していたということ、そしてもう一つにはメンガー自身が認めている通り数学的な処理は難しいという二つの問題によって、経済学にとって現実的な解決策にはならなかった。
そこで限界効用逓減の法則に進む、というのは、ワルラス的な処理を有効にするためのものであり、それはますます現実からの乖離を進めることになった。金本位制を正当化するためのその理論的な混乱が、第一次世界大戦に至るまでの世界の経済的混迷をもたらしたのだと言えそう。
経済的利益の理論形成
第一次世界大戦後に、ケインズが総需要と総供給による財市場の均衡と貨幣市場の均衡から所得と利子率の関係性を導き出し、それによってようやく近似理論的に利益が数学的に導き出される基礎ができたが、それはあくまでも貨幣的な定義による利益であり、価値理論や会計理論との整合性があるか、と言えば、必ずしもそれは自明ではなかった。それは、ヒックスの無差別曲線によって価値理論との統合がなされた後も、やはり現実のデータに繋がる会計理論との齟齬は埋まっておらず、問題解決には至らず、それは今に至っても続いている。
経済的利益の論理的扱いの難しさ
さて、ではいかにしてその問題を解決するか、即ち、いかに価値理論と会計理論との整合性をとり、それを経済学的、貨幣的に裏付けるか。この点で、まず絶望的なのは、労働価値説に基づいた生産者余剰はともかく、主観的価値理論によって数学的に計量されるべき消費者余剰は単なる概念上の道具に留まっており、マクロ経済のモデルには全く反映されないということがある。つまり、いかに主観的価値理論を精緻化して整えたところで、経済学上の利益には一切反映されないのだ。そして、会計理論についても、複式簿記で計算される以上、ミクロ的にはともかく、マクロ的には誤差と会計テクニックでしか説明のしようがない。たとえ経済学的に生産者余剰が計上可能だといっても、それは結局会計的には労働分配率を下げることによって実現されるのに過ぎず、そして労働分配率が下がれば需要は減退し、成長を頭打ちにする。
誤差頼りの経済的利益
そうなると、誤差に頼らざるを得なくなるが、誤差の大きなものは、給与支払いが実際の労働よりも後から発生する、ということであり、それにしても期末には未払給与で調整されるので、他の後払いの支払いとともに、その分の金利分くらいしかマクロ的な利益は発生しない。これは、時価会計主義が強まれば強まるほど、会計的にはマクロの利益は出しにくくなることを意味し、その点で高度経済成長期と現在の成長率の違いに会計方式が大きく影響していることは否めないだろう。特に日本で1998年に公表された退職給付に関する会計処理の成長率に与えたインパクトは非常に大きく、それによって年功序列で資金を企業がプールし、それによって利益を上げるという手法が取れなくなっ多ことを意味する。それは、事実上産業資本主義によってマクロ的に利益を出すことがほとんど不可能になった瞬間であったといっても良いのだろう。会計理論に基づいた利益をベースにした経済学では、成長を望むことは、原理的にほぼ不可能なのだ。
金融技術による経済的利益抽出
それを受けて現在では、貨幣的に裏付けされた価値理論が、金融技術によって会計理論に翻訳され、それが利益の源泉になる、という金融資本主義が主流となっている。つまり、SDGsのような価値に対して証券が発行され、その取引によって利益を出す、というものだ。しかしながら、これにしても結局は会計であり、マクロ的には利益の出ない、単なるゼロサムゲームに過ぎない。
論理的不整合からの利益
より細かく見ると、それは価値理論と会計理論の論理的不整合を金融によって昇華し、それを利益に変える、という手法であり、それは労働価値説でも主観的価値理論でもない。それは如何なる仕組かと言えば、ある価値体系が提示されると、それを会計的に翻訳し、現実に適用するまでの論理的不整合を金融がリスクヘッジという形で証券化することで、利益を金融が吸い上げる、というものであると言える。産業労働者は論理的不整合を顕在化させないように必死に働き、それでも論理的不整合が支持不能なほどに拡大するとその価値体系は崩壊し、解体処理されることになる。
つまり、労働価値説と主観的価値理論に基づいて整合的な価値体系を作り出し、それを論理的に会計的に翻訳しても、それが現実に動き出すまでの間、そして動いている間に論理的不整合が発生すれば、それによって成立しないことになってしまう。本来ならば、整合的な価値体系を作り、それが会計的にも論理的に運営されることで、利益は数学的にも確保されうるのにも関わらず、それを現実に適用する際に論理的不整合が露出することによって、少しずつその利益が金融資本によって削り取られ、最終的にはその仕組は崩壊しうるのだ。
論理的飛躍からの利益
ここで生まれる価値の源泉は、論理的飛躍であると言え、その飛躍を労働者がさまざまな形で埋め、一方で金融資本はその飛躍からリスクを導き、利益を絞りだす。典型的な例では、原子力発電は持続可能なのだ、という論理飛躍を、核廃棄物の存在を無視したり、安全性リスクを軽く見たりすることで利益を出す、ということがある。それは、短期的には国の全面的サポートがあるなど、利益を出しやすいのだろうが、その論理飛躍は必ずどこかで行き詰まる。そのような仕組を価値の源泉にしなければ成り立たないほどに、マクロの利益理論は展開しているのだと言える。そしてそれが、流動性が高く、誤差による利益を顕在化させやすいように見える金融資本主義をさらに正当化させているのだと言えそう。実際には、金融資本主義によって回る金は相対で流れているだけなので、複数の経路を回って利益を分配する産業資本のようには利益は出せず、単なるゼロサムゲームに止まることが多い。
理論的な経済的利益の上げ方
さて、会計理論に基づいてマクロ的に利益を出すのが難しいとした時に、利益はいったいどのようにあげうるのか。一つには、会計理論からのマクロ的利益が誤差であることを考えると、できる限り貨幣の流通速度を上げて、その誤差の幅を広げる、ということがある。ついで、一単位の乗数効果の大きい実体経済になるべく資金を回すことが挙げられる。さらには労働以外の形で購買力をサポートすることで、労働分配率を下げて利益を出しても需要が落ちないようにする、といったことが考えられる。具体的政策としては、一つ目に、貨幣にマイナス金利あるいはそれに準ずるものを適用して、貨幣を保有すること自体がコストであるようにすること、二つ目に、金融資産課税を行い、金融投資の期待収益率を実体経済投資の期待収益率よりも低くすること、そして最後にベーシックインカム等で基本的な所得を保証して基本購買力の底上げを行うことが考えられる。
問題を解決するためには、制度・仕組をきちんと精査した上で、どこに問題があり、それにどのように対応すれば解決に至るのか、ということを冷静に見極める必要があるのだろう。
誰かが読んで、評価をしてくれた、ということはとても大きな励みになります。サポート、本当にありがとうございます。
