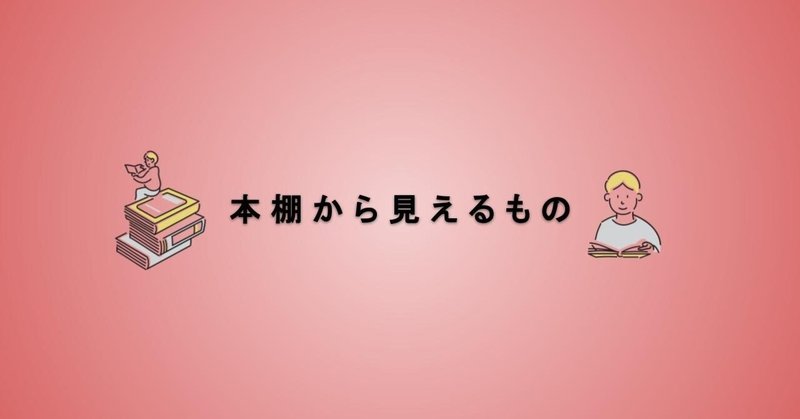
オススメ本#3~田中 泰延 著『読みたいことを、書けばいい。』
そもそも「何を書けばいい」を明解に。誰のためにものを”書く”のか。
”書く”ことだけではなく思考法の参考に。
正直、最近読んだ本でかなり好きです。是非色々な人に読んでもらいたい。
”書く”ということを仕事にしている人以外は、関係のない本かと思われる題名ですが、しっかりと内容を読めば、書くことから派生した”考え”・”想い”に触れることができます。
それでは早速、こちらについて私のおすすめポイントも含め、ご紹介します!
5W1Hを起点とした構成
全体の章立ては、
「なにを(What)」書くのか
「だれに(Who)」書くのか
「どう(How)」書くのか
「なぜ(Why)」書くのか
について、述べられており、「いつ(When)」「どこで(Where)」についても触れてくれています。詳しくは本の中で!(笑)
章の内容一つ一つが非常に明解であり、自身の振り返りにストレートな言葉で入ってきます。そしていまこうして私が書いていることに対しても、ストレートなメッセージを伝えてくれています。
自分がおもしろくもない文章を、他人が読んでおもしろいわけがない。
だから、自分が読みたいものを書く。
核心ですよね。
これはこうしたnoteでの発信や、自身が今まで書いてきたものを改めて読み直し、こう問い直したい。
「この文章、本当に自分で、もう一回読みたい?」
苦しい結論になろうとも、これが事実。
…つまらなくないか?
…もっと端的に言い表せないか?
…なんか説明っぽくないか?
この時点で「読みたい」と思えていないのでしょう。
なぜ「読みたいと思えない」に至るのかについても、重めのパンチで殴ってくれます。
この本は、「発信をする」全ての人に響く内容が盛りだくさんです。
『書きたい人がいて、読みたい人がいる』
そもそも私も一企業、組織の中で働く人間です。日常の仕事の延長線上で物を書くときに陥ってしまうことを端的に伝えてくれています。
文書と文章は違うことを知っておく
私が普段、書いているのは「文書」。
そうか「文章」ではなかった。
日頃から、いや昔から、多くの生徒・保護者、そして部下、同僚などの職場内(外も)に話してきた言葉が完全なブーメランとして直撃する。
定義をはっきりさせよう
その単語に自分がはっきりと感じる重みや実体があるか。
わけもわからないまま誰かが使った単語を流用していないか。
言うは易し、行うは難し。
まだまだ実践できてないぞ、これは。
これを踏まえて、「言葉を大切にする」ことを再確認しました。
※私でいうと…
”教育”の定義を考え抜くことが必要です。
そして”新しい教育の場”の実体を理解することですね。
”サードプレイス”ってなんだろう?を繰り返すことも…。
また田中さんは、本書の中で
ネットで読まれている文章の9割は「随筆」
と仰っています。私の書いている文章も、もれなく「随筆」です。
では「随筆」の定義は?これも定義が大事。
ぜひ、本書の中に田中さんの考える定義があるので、是非ご覧ください。
※正直、この定義は”考え方”として、プレゼンや講義、講演。もっというと熱量の高い授業でも当てはまる”考え方”だと思います。
この定義があるからこそ、
”書きたい人がいて、読みたい人がいる”
のでしょう。是非、参考になると思いますので本書をご覧くださいね。
大事にしたい「調べる」重要性
ここに実は私が感じていた「日本の教育現場」のダメな方法と全く同じ内容が記載されていて、感動した部分。本当にその通り!と思わず、メモ書きに3回も書いてしまいました。
あえてここは本書を読んでいただくことにしますが、
もっとも重要なファクト=文脈
をどれだけ調べられるかが、何かを伝える、書くうえで最重要なのです。
これも面白い表現なので、引用させてもらいます。
調べたことを並べれば、読む人が主役になれる。
調べたことの中には、資料だけでなく、「原体験」も含まれると私は思います。ただしそこには主観が入り込むので、どう客観性を持たせるかは必要です。上述の言葉を自身の中で、どう解釈し、どう定義するかが大事ですね。
『文章を書く意味』
このテーマについては、田中さんが端的に表している言葉をお伝えするだけにとどめておきます。なぜならば、それこそこの”定義”をどう考えるかが、大事なことで、是非本書を読むことから考え始めてほしいと思うからです。
愛と敬意。
これが文章の中心にあれば、あなたが書くものには意味がある。
その「思考の過程に相手が共感してくれるかどうか」が長い文章を書く意味である。
「書くこと」とは
書くことはたった一人のベンチャー企業だ
きっとこうして書いていることが、「誰かの役に立つ」。
そう信じて、書き続けよう。
そういう文章になっているか、もう一度見直そう。
考え抜くことが大事。
そうした先に田中さんは、こうも伝えてくれています。
文字がそこへ連れてゆく
こうして発信していること、そして行動していることが、自分をどこに連れていってくれるのだろう。
この本に、何度も頭を殴られ、自身の振り返りを行いましたが、
書くことの面白み、希望も与えてくれました。
こうしたnoteを書いている方々にこそ、この本はオススメします。
ただ「書く」ことに特化せず、「発表」「表現」への解釈を広げれば、ビジネスや教育、さらには日常の場面でも活用できるものであると確信しています。
まずは自分の文章が、本当に「自分が読みたいことなのか」
改めてここから考えて動いてみたいと思います。
ぜひ、皆さんもご一読を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
