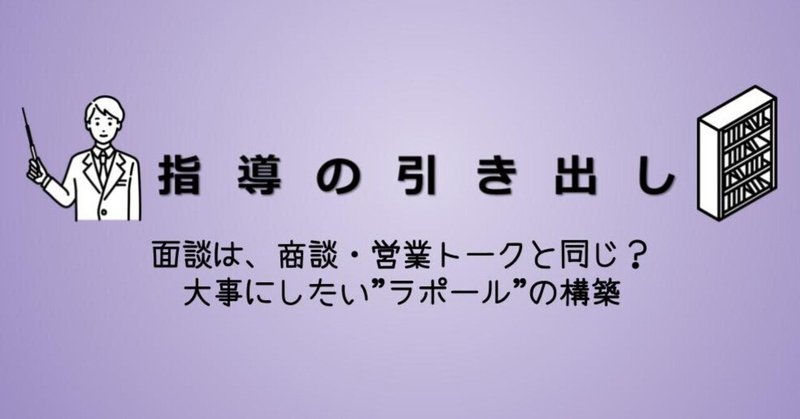
#8〜教育相談のキホン③-先生に向けて-
多くの場面で行われる”教育相談”と呼ばれるもの。
年間300件近くやってきたノウハウをまとめる。
ご覧いただき、ありがとうございます。
久々の「指導の引き出し」ですが、今回の”教育相談の基本”は色々な場面に応用することが出来ると思います。
年間300件近く、保護者・生徒の”相談”に立ちあったノウハウの一部にはなりますが、ご紹介します。
前回までの内容はこちら↓
何よりも大切にしたい「フロントトーク」
会話を始める時に、何もなく”本題”に入ることを始めていませんか?
これは既に”目的”が明確になっている場合は有効ですが、
”相談”の場合は『目的が明確になっているパターンはほぼありません』
もっと言うと
『目的の解像度を上げるために、クラッチング・フロントトークを大事にする』というのが基本のスタンスです。
正直、ここが上手くいくかどうかで、面談の成否が決まるといっても過言ではありません。
当初、私はこのフロントトークがあまり得意ではありませんでした。
早い段階で、本題に入り、そうすると話題が完全に自分の土俵になるので、泰然自若として話を出来る自信があったためです。
しかし、一時期「この話し方で大丈夫か?」という疑問に駆られることが多くなりました。
本来の目的と少しずれたトークを、展開して、
相手の目的と微妙にずれた会話を展開し、「ま、そういうものだよね」という100%ではなく70%程度の納得度で相談を終了していたのだと気づいたからです。
それは面談終了後の相手の表情からもわかるようになってきました。
やはり”笑顔”なのです。
大前提は「信頼関係構築」=ラポールの状態に近づけること
この反省から、相手の話を”聞く”ことにかなりの力を注ぐようにしました。
キーフレーズは、
①なぜ?
②例えば?
③ということは?
そして、ここに併せ持つのが
「受容・共感」と「指導」のバランス感覚です。
ただ、この上述に挙げたものは、
いわゆる状況把握の際に活用するもの。
やはり大前提は「信頼関係の構築」です。
そこでいわゆる緊張関係を壊すための「アイスブレイク」は当然必要になります。
アイスブレイクには、様々な方法があると思いますが、相手に応じた手法をたくさん持っておくことが重要です。
気候・天候の話題
居住地域の話
訪れてもらったきっかけ
時間帯に応じては、食事・飲み物の話
興味・関心・趣味など
色々あるとは思いますが、私の場合は初めて訪れる生徒・保護者の行動を推測して、相談に来るまでの”ストーリー”を作り、その際に起こりそうなことなどを聞いたりします。
「電車混んでなかった?」
「今日は、朝起きることが出来た?」
「(バッグに着けてるキーホルダーを見て)、○○好きなの?」
アンケート蘭の趣味を見て、「◯◯好きなの?実は私も・・・・!」
などなど。そして私自身の失敗エピソードなどもたくさん交えます。
何故なら、「教師・教員は、”完璧な存在”と勘違いする」傾向が多いからです。だからこそ、ただの一人の大人として、真摯に向き合う姿勢が大事になるのです。
ただ誤解しないでほしいのは
”真摯に向き合う”とは、”子どもに媚びる大人”になることではありません。
ここの勘違いをしている教員が、悲しい結果を生むことが非常に多いですので、毅然とした態度であることは絶対です。
※かなり年齢が上の保護者の方と話をしている際でも、
「申し訳ございませんが、今は本人からお話しいただいてもいいですか?」
とか
「そうしたお考えはわかりますが、当校は”託児所”ではありませんので…」
という態度。
「お子さんのお話には道理がありますが、こうしたお話に耳を傾けられたことはありますか?」
など、若干綱渡りなことを話した記憶も何度もあります。
何でもかんでも褒めたり、返事良く話を聞いているだけでは”信頼”は生まれません。大事なのは”ぶれない姿勢”ですね。
”状況把握”は、最難関。
初対面の方の”ニーズ・ウォンツ”を理解することは本当に難しいことです。
何故ならば、
①本人がそのニーズ・ウォンツに気づいていない場合があるから
②本人がそのニーズ・ウォンツを言語化できないから
③本人がそのニーズ・ウォンツを言うことに抵抗があるから
つまり、表層化していても「表現しない・できない・したくない」
そして、内在化しているから「わからない・言葉に出来ない・ごまかす」
などが往々にして起こり得るのです。
だからこそ面談者側に求められるのは、
●複合的に整理をする力
●全体像から現状を推測する力
●内容の解像度を上げていく力
などが求められるのです。特に私が一番取り扱った「転校を検討している」場合の面談は、本人にもう一度嫌なことを話してもらう必要が往々にして出てきます。
そのために環境設定なども非常に大事になりますし、こちらの”見え方”なども非常に大事になるというわけです。
結論は”わかりやすく”
面談をしていると、話は色々それたり、盛り上がったり…。
そして楽しい面談であれば、あっという間に時が過ぎることもありますし、逆に悩みや課題が沢山あれば、それを一つ一つこうすればいいというようにアドバイスをすることで時間がかかる場合もあるでしょう。
そうすると陥りやすいのは…
『面談終わり!いやー、有意義な時間でしたね。お疲れ様でした!』
で終わるパターン。双方ともに満足。だって楽しかったから。
じゃあ、いいじゃないか!
これ中堅どころや、面談・商談に慣れが出始めた人に起こりやすい事象です。ポイントは「結局、結論はなんでしたか?」なのです。
「楽しく笑顔で、帰ってもらうこと」は目標です。
「相手の幸せを願って、面談する」ことが目的です。
楽しい面談を出来て、満足してもらえたからよかった。で
本当に”相手の幸せを願えた面談”と言えるでしょうか?
私は、違うと思います。
大事なのは、この面談を経て、
”次にどんなアクションをするかを見定め、明日からできることを実践できるようにすること”が大事だと思います。
だからこそ、最後に”日程を区切る”・”締め切りを設定する”というように
「いつまでに」
を大事にするのです。大きいステップでもスモールステップでも、この締切という考え方で、実際のアクションに移すことがしやすくなるからです。
だからこそ、結論はわかりやすく
「いつまでに、○○をやってみよう」
「いつまでに、また連絡をして、相談して下さい」
「いつまでに、◯◯を達成できるように、明日から挑戦してみよう」
これが、相手の幸せを願った面談ではないでしょうか。
ここの結論に、納得度をもたせるために、途中のプロセスが大事になるのです。だからこそプロセスを大事にして、結論は”単純にする”ことを意識的にしてみるといいでしょう。
前回も伝えましたが、大事なのは、面談者自身から出てくる言葉です。
「はい、やってみます!」「わかりました!」
これを出せたら、その面談は”価値ある面談”と言えますね。
改めて…教育相談のキホンは、”相手の幸せ”を願えるか。
今回は第3弾。
まだまだ教育相談のキホン編は続きますが、最終的な目的はやはり
"相手の幸せを願って、面談が出来るか"
です。
次回は、面談に入る前段階の環境づくりにフォーカスしてみましょう!
ご覧いただきありがとうございます。
読まれる楽しさを噛み締めながら、継続していきますね。
気軽にスキ・コメント・フォローしてみて下さい。
その一つ一つが本当に"有り難い"です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
