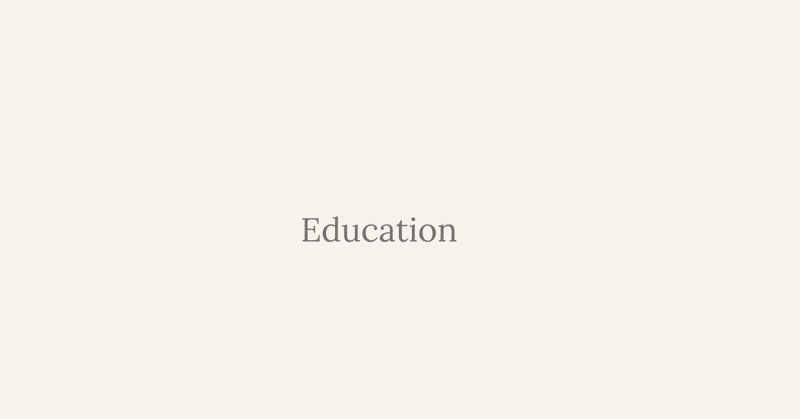
コミュニケーションツールとしてのサッカー
スペイン戦の後、元留学生の海外出身の友人たちから一気にDMが届いて、サッカー(を始めスポーツ)は言葉を超えることを改めて。
先日見かけた「健全な愛国心」という言葉を思い出し、改めていい言葉だなと。
場所の確保とボール一個でできるサッカーで集う、は初期の留学生・移民界隈ではよくあって(南米と日本が圧倒的に多かったけれどなんだかんだ誰でもできるからなんとなく人が集まりやすい)、
国も分野も違う人たちが集まる場所になって、私はそういう場に行って自分と全く異なる生き方をしてきた人たちと出会ったことは人生感を大きく変えたし、
アメリカの場合は英語力で歯が立たないことが多い初期の留学生・移民たちでも「アメリカ人」に「勝つ」ことができる分野だったりもして自信がつきます。(こういうのが結構重要だったりもする)ただし2010年くらい?に日本同様ヨーロッパチームの子供向けイベントなんかがアメリカでも賑わい始めている場所もあったため、以前よりはサッカーできるアメリカ人も増えているかも。
そして、
本田選手の日本代表時代には意見を言っただけでホンダ浮いてる、感じ悪いなんて言われていたけれど、海外に出る選手が増えれば「あいつ空気読めない」なんていうその空気自体が変わるんだと。
一人では変えられなくても、後世に受け継がれて繋がって行けば変わるというのは、様々なことにつながる考え方。
日本の課題は、職業的に本来それをすべき人たちでさえ問題提起ができる人が少ない(割合でみればほぼいない)こと。
みんなやってるからいいじゃん、現状そうなので、という「慣習」を根拠に問題を放置し(放置してるつもりはなくても空気を読むという裏側にはそれが潜んでいる)、綺麗な側面しか存在してはいけないと思い込んでいるのは「思考停止」なんて言われるけれど、
そんな揶揄の言葉ではなくて根源を考えれば、やっぱり「空気を読む」とか「儒教的考え」からきていると思いますが(歴史があるからこそという部分もあると思うけれど)、
日本ではトップクラスの選手でも言葉も通じない異国の地では無名で、孤独やマイノリティの視点から見える世界を知ることで得る本当の意味の「強さ」、メインストリームではない世界を生きることで変化するメンタリティ、日本の「常識」を外から見る視点、個の強さの中で自分がどう立ち回り戦うのか考え抜いて、でも「実力」があれば何人であろうと言葉がどうであろうと評価される世界を知ること、そして結局国は違えど同じ人間であること、、、
サッカーに限らず、海外にチャレンジする人が増えることと国内で頑張る人が両方いて、それがどこかの地点で「たくさん交わる」場所が発生して、日本と世界をより「いいカタチ」で繋げるようになれば日本は変われるのではと思っています。
そのためにはとにかく外に出てみて、日本以外の「空気を知る人」の絶対数が必要だと感じます。中から客観視するのは難しいし、ネットで世界は近くなったけど、やっぱり五感から得る情報は頭で考えただけの情報とは異なるから。(そして「中」のことなんて「中」に入らない限りわからない/出てこない情報ばっかり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
