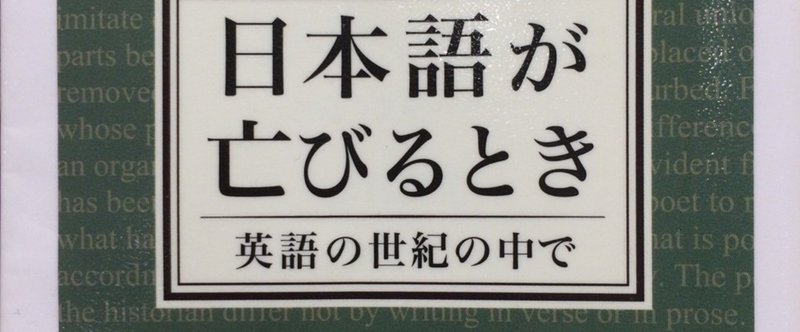
英語または外国語ができるとは(最終回)
ということで、予想外に長引いてしまった「英語ができる」とはどういうことだろう、そしてみんなが英語ができないといけないんだろうか、という話しですが、今回こそ最終回です。
前回、私は、英語はみんなができる必要はない、おそらく高々2割の人ができればいいし、その中のごく一部がすっごくできるので十分、残りの8割の人はやりたければやればいいし、無縁に生きたからといって何の問題もないのではないか、という話しをしました。
最終回である今回は、そんな無責任に2割程度の人がやればよくって、他の人は英語に無縁でいいの?という疑問に対する答えとして、日本の翻訳文化がどこまでそのような状況をサポートできるか、という話しをしたいと思います。
前回紹介した水村美苗氏の「日本語が亡びるとき」の増補で触れられているのですが、ASEANの過半の国はすでに、その国の言語で高等教育レベルをカバーしきれてないそうです。たとえば、シンガポール。経済的に急成長を遂げ、みんな英語をバリバリ話すイメージがあるますが、ではマレー語で高等教育をカバーできているか、というとできていない。つまり英語ができないとエリートにはなれない状態だともいえるわけです。
その点、日本は本当にすごい国なんじゃないでしょうか?英語がこんなにできなくっても、大学に行けるし、講義は受けられるし、専門書だってあるし、社会に出ても出世できるし、、、すごい!
これは江戸末期(19世紀前半)あたりから蘭学のみならず洋学が日本に入ってきて以降、様々な先人がそれを日本語化した努力によるものです。一般的には明治期の福沢諭吉や西周らによる様々な西洋語の日本語化が知られていますが、化学など実際は1820年代あたりから相当の翻訳が始められています。最終的にはその総合的な結実が西周の「百学連環」といってもよいかもしれません(もちろん、西周の作った訳語で使われていないものもいっぱいありますけど)。
もう一冊、前回紹介した松尾義之氏の「日本語の科学が世界を変える」でも、日本人の科学者がユニークな発想で世界を驚かせる理由の一つは日本語で考えられること、それは日本語でこなれた訳語と思想がセットとして働くからだと指摘します。私たちは「塩酸」とか平気でいいますけど、これだって訳語な訳で、この部分だけ外来語(カタカナ語)にしません。そしてどんな用語も日本語化されたときに、日本語の感覚や思想がその日本語化された単語のイメージによって生まれて付加されるわけですね。その文化的ずれが新しい発想、違う発想へつながるというわけです。
その意味で、この本の著者は、たしかに現在も日本語で科学はできているけれど、専門用語はそのままカタカナ語でいう傾向にあるのは望ましくないのではないか、とも言っています。私はその点は微妙だと思いますけどね。
このようなレベルの翻訳は、もちろん科学だけではありません。特に哲学、思想書の翻訳においてもいえそうです。日本では難解な有名な哲学書、思想書が多く翻訳されていることにおいても世界では有数の翻訳大国といえるでしょう。その中に出てくる専門用語も専門家たちが考え用語を当て、それが吟味され一般化していくわけです。
正直、「存在と時間」や「純粋理性批判」が繰り返し、時にはほぼ同時期に2種類の翻訳が出たりする国が他にあるとは思えません。そんなに読者がいるのか、という疑問も含めて、不思議な現象であると同時に、このような現象が起きること自体、または起こせることが日本人が外国語がなくてもやっていけてる証明でもあります。
小説においても同様です。プルーストの「失われた時を求めて」がこんなに繰り返して翻訳される国もないでしょう。みんな第1巻は手にとるけど、それ以降はなかなかたどり着かないと言われるのにw
このような翻訳文化こそが、私が主張するような一部の人が英語ができればよく、それ以外の人はなくても大丈夫でしょうの根拠であり、この翻訳文化を維持することが大事だと考えます。翻訳文化というのは知恵の架け橋としての一つのツールです。英語、または外国語ができないとたどり着けない場所へ、翻訳が連れて行ってくれるわけです。それを英語または外国語ができないとたどり着けないような状況にしたとするなら、それは篩であり、階級差を生むだけではないでしょうか。まさに母国語で高等教育をカバーできない国たちというのはそれを露呈してるのではないでしょうか。英語ができないとね、という人々にとってはそれはクリアしなければならない課題で、クリアできない人は振り落とすでいいという立場なのでしょうか?
私は自分がコンピュータ系の翻訳を社内、社外両方で経験したので思うのですが、単に元の言語のままだと実は日本人の感覚には伝わりにくいものはけっこうあります。そこを日本人にはわかるように訳し変えることはよくあります。実は翻訳管理としては嫌われるのですけどね。しかし、クレームを減らすためには絶対に必要なことなのです。
英語ができないとね、という人々はこのレベルをクリアできる人たちを想定してるのでしょうか。だとしたら、それは相当ハードルが高いことを認識してほしいところです。もちろん理想を言えば、そのようなちぐはぐな時期さえ乗り越えて、日本語感覚にも合うような日本人の英語が形成されることなのかもしれませんが、それをするにはまさに英語公用語以外にはないわけで、それは無謀といえます。
つまり、現状でのベストプラクティスであり、結論は、繰り返しになりますが次のようになります。
●政治やビジネスで世界の一線に出る人は英語ができないといけない(これはまさにハイレベルで)
●それ以外にも英語が外国人とのコミュニケーションや仕事、学問のコンテンツとしてアクセスする必要がある人は、それに応じた英語が必要(でもそれほどすごくハイレベルではない)
●それ以外の人はなくても困らないように翻訳文化が下支えする
●翻訳文化の下支えのためにはそれだけの翻訳者が必要で、それの人々が活動できるだけの経済的余裕を出版などが持たないといけない
●英語が必要な人になるかどうかはわからないので英語教育はやはり必要。でもそれはバランス良いものでないといけない
実は、この最後の教育システムが一番難しいとは思うのです。バランスと取りつつ、でもどこかでは必要な人はハイレベルに引き上げられるような区別が必要になるから。平等を是としてきた日本のシステムではけっこう難しいことかもしれません。
そんなわけで、みなさんは英語はできますか、できた方がよいと思いますか?そして、英語ができなかったとしても困らないシステムがあった方がよいとは思いませんか?
英語だっていつまで普遍語なのかわからないですしね(って、それはさすがに相当先にならないと変化しないか、、、
でも少し未来では機械翻訳で相当部分カバーできるようになるかもしれませんものね。このような「英語ができる」って何よ、なんて言うことが無効になる日(それが教育や社会としてでも、機械翻訳という技術としてでも)が近いとよいなと、私は思います。
長らくご静聴ありがとうございました。
(了)
本文はここまでです。
もし奇特な方がおられましたら、投げ銭してくださるとうれしいです。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
