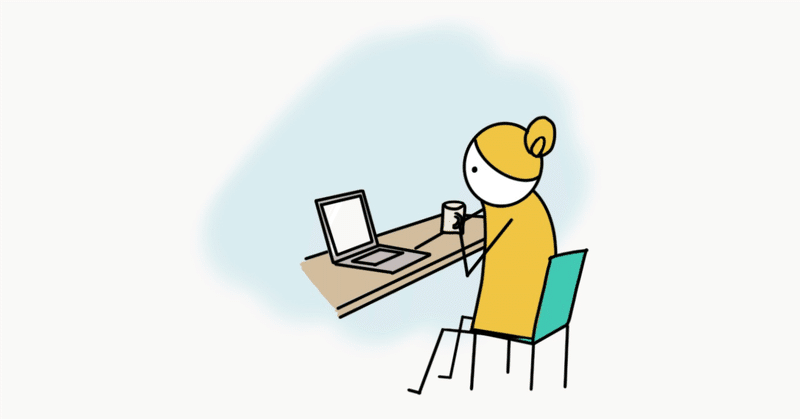
#119 仕事も家庭も「両立」なんてしなくていい、というお話。
どうも、えとろぐです。
働くパパさん、ママさん。いや社会に出て働く人々全ての悩み、それが「プライベートと仕事の両立」ですよね。
私も現在進行形でワークライフバランスについての悩みを抱いています。特に家庭と仕事の両立に頭を抱える日々。
今日の記事ではこの「公私の両立」についての悩みを考えていきます。
・
・
・
そもそも決まった時間に仕事をして、お給料をもらう、仕事の時間とプライベートの時間の明確な区別が始まったのはいつ頃なのでしょう?
nomad journalさんの『【新しい働き方はどのように生まれた?】第20回:俸給生活者の変遷と今後』によるとその起源は「江戸時代の武士」なのだそうです。
”現在、大抵の人は毎日会社に通い給料をもらって生活しています。俸給生活者はサラリーマン、ビジネスマン、OLなどの言葉でも表現され、なんだか近代になって始まった雇用形態のように思われがちですが、起源を辿ると、江戸時代の武士に行きつきます。”
江戸時代といえば1603年〜1868年の200年以上も続いたご長寿時代。令和の2023年から数えても軽く150年以上も昔からこのサラリーマンスタイルは続いているようです。
しかし、私よりも下の世代であるZ世代やα世代の子たちからすると「お金のために自分の時間を使って働き、その対価を得る」ことは前時代的なのかもしれません。
*Z世代:1996年〜2010年の間に生まれた世代
*α世代:2011年ごろに生まれた世代
一時期、仕事と私生活の両立を意味する「ワークライフバランス」という言葉が流行しましたが、この考えもすでに古くなっているみたいです。
「マルチタスクもワークライフの両立もしない」
AmazonのCEOであるジェフ・ベゾス氏が2017年ロサンジェルスのサミットで語った言葉が「マルチタスクもワークライフの両立もしない」だそう。
この言葉についてもう少しネット上で調べてみました。
DIAMOND online『ジェフ・ベゾスの哲学「ワークライフハーモニー」とは何か?』という記事で同氏の言葉による初めての著書『Invent & Wander』が紹介されています。
記事内で同書の抜粋文章が引用されているのですが、
・ジェフ・ベゾス氏は「ワークライフバランス」という言葉が好きではない
・仕事をすることで活力が湧いてくるかどうか、これが私生活の充実にも影響し、反対に私生活の充実が仕事にも現れる
・仕事と私生活は両天秤にかけるものではなく、ぐるぐると循環するもの
・両立(=バランス)ではなく調和(=ハーモニー)を目指す方がいい
これらが同氏の伝えたいメッセージだと受け取りました。
先日、次女が生後半年を迎え、その間の家事、育児を妻に任せっきりにしてしまっている、そのことについての反省を記事にしました。
幼い子どもを持つ親世代からすると、公私の両立は死活問題だと思います。ですが、理想論かもしれないジェフ・ベゾス氏の「ワークライフハーモニー」という言葉は「家庭も育児も両立しなくてはならない」、そんな強迫観念から私を救ってくれる気がしています。
仕事も私生活も楽しんでいいんだ、と思えるとほんの少しだけ気が楽になりませんか?
あまり肩肘張りすぎず、楠木 建さんよろしく『絶対悲観主義』で物事に向き合ってみようかなと思います。
それではおわりにとして自己紹介をしてこの記事を締めます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
おわりに
私は製造業を生業としている会社に勤めながら、noteでの発信活動をしている【えとろぐ】と申します。
幼い頃に両親が離婚し、十代の多感な時期を祖父母のもとで過ごした体験から「片親で育つ子どもをなくす」ことを人生の目的としています。
仕事に家事、育児をしていると心がすり減ってしまうときがありますよね。
楽しいこと、嬉しいことがある一方で、思うように進まないことが山ほどあると思います。
私一人でできることは限られていますが、
「この人はこんな風に家事や育児に臨んでいるんだ」
と私の発信を通して知ってもらうことで
「自分の方が上手くできてる」
「ちょっとこの考え方、参考になるな」
と感じ、あなたの心が少しでも楽になれば嬉しいです。
毎日22時ごろに記事を更新しているので、寝る前のちょっとした暇つぶしにでも読んでみてください。
家事に育児、一緒に頑張っていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございます! 記事は読みやすかったですか?あなたのためになったでしょうか? 私が体験したこと、学んだことが少しでもあなたの心に残るととても嬉しいです。
