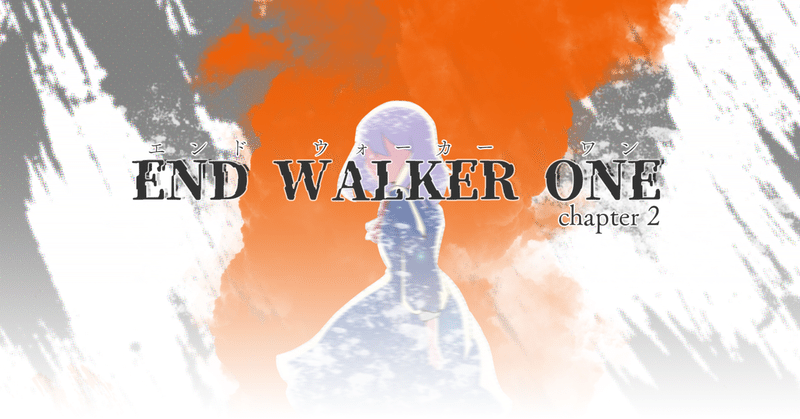
『エンドウォーカー・ワン』第29話
「あー、訓練クソだりぃ……」
「文句言わないの。お給料貰いながら色々勉強させてくれるんだから」
アルター7標準時12時。
対照的な若い男女が廊下を歩いていた。
男性は充血した眠たげな瞳で「にしてもハラ減ったな」と薄い腹を擦る。
「そんなことよりその目は何よ。昨日、何時まで起きてたの?」
「あー、3時くらいだな。いやぁ、オンラインセッションが止まらなくてなぁ」
「仕事に支障きたしてなぁにが『止まらなくてなぁ』よ!」
ブロンドのショートヘアがふわりと揺れたかと思うと、彼女は重心を下にして正拳突きを線の細い青年に見舞う。
「いってぇ! フォリシア、オレになんか恨みでもあるんかよ!?」
「レックス……はあ、自分の胸に聞いてみれば?」
「……ああ、お前が憎くて仕方がないとさ。女だからって何しても許されると思うなよ」
痛む胸を押さえながらレックスは凄んでみせるが、フォリシアは格闘術評価Eの者に対して心底見下す表情で「しょせん、この世は弱肉強食なんだよ。少年」とクスクスと笑って見せる。
二人の体格差はさほどでもないが、普段の運動量が違うせいかレックスは戦闘シミュレーションや格闘術、魔法基礎学など全ての分野でフォリシアに引けをとっていた。
「……クソッ!」
レックスは余裕たっぷりで見つめてくる同僚の顔が気に食わないといった様子で、廊下を早足で歩き出した。
フォリシアとほぼ同時期に入社したというのに、何一つとして敵わない。
――何を意識してるんだよ、オレは。
彼は自らの黒髪を掻きむしると、乱暴に食堂の扉を開閉する。
「……なんでわたし、あんな意地悪なこと言っちゃうんだろう」
苛立つ彼の後ろ姿を見送っていたフォリシアは誰にも聞かれないよう、硝子窓から転がる光たちに向けて囁いた。
「――ってことがあったんですよ! 隊長、頭にきますよねぇ!?」
「いや、消灯時間を守らないお前が悪い」
レックスの愚痴をノインが一刀両断する。
炭酸飲料をヤケ飲みする彼がノインの部屋に転がり込んできたのはその日の夜のことだった。
民間企業の社員寮にしては豪勢な間取りだが、最低限の調度品しかない質素な部屋。
備え付けられているパイプベッドにローテーブル。ワークデスク、簡素なメッシュチェア。対して本棚は後から買い足したと思われるものが二台、彼らは書籍ではち切れそうになりながら広い部屋の片隅に身を寄せていた。
ノインは読みかけの本にしおりを挟むと「先程から同じことを何回も繰り返し言ってるぞ。大丈夫か」と呆れ顔で返す。
「いや、こんなことでおさまりませんよ! あー、クソっ」
レックスはアルター7の民に長年愛飲されてきたモカコーラを呷った。
本家と比べてまったりとしたコクのある味わいと、喉を通り抜けるような爽快さが同居するという何とも不思議な飲料だ。
発売当初は何社もその味を再現しようと試みたが、試行錯誤を何度も繰り返しても辿り着けなかった秘伝の味。
未承認のフレーバーが使用されていると噂されているも、当社はこれを否定。
創立100年を迎えるモカコーラ社の数多いオカルト話の一つとされている。
「大体他人と合同演奏して何が楽しいんだ? 俺には芸術は分からん」
ノインは椅子から立ち上がり、本棚から黄色い帯が生えた本を乱雑に引き抜いた。
その弾みでバラバラと雪崩が起き、新古様々な本が床に流れ込んだ。
「ああ、何してるんですか」
レックスはテーブルに飲みかけのボトルを置くと、本に埋もれて呆然と立ち尽くすノインの傍に屈んで一冊一冊床に積み上げていく」
「ジャンルは――無茶苦茶だから適当でいいですよね」
「ああ、そもそも読み終わったものが殆どだからな。適当でいいから積んでおいてくれると助かる」
ノインは本の山を抱え、大胆かつ慎重に元あった位置へ手早く戻していく。
「すげぇな。本の並び覚えてんのかよ」
機械のようなスピードで整頓する青年に思わず驚嘆し、素に戻るレックス。
返事のかわりに青褪めた視線が返ってきて、彼は反射的に「あ、すんません」と謝罪した。
「いや、自分でも不思議なくらいだよ。そんなに拘りはない筈なのに捨てられないし、何故か忘れることができないんだ」
一つに「999」としての記憶。
ハンドラーの忠実なる猟犬として「銃火を交える」以外の静かな時間。
一つに「ベルハルト・トロイヤード」としての記憶。
幼少期、決して強くなかった彼が見出した知識を武器にするという生き方。
そして両親と書店に通っていた特別で唯一の安らぎの時間。
「何故、だろうな」
「なぜって……そりゃアンタ、決まってんでしょう」
憂いの国の住人を見、レックスは笑いながら一蹴する。
それはまるで先日、谷底へ突き落された仕返しのように悪戯心を孕んでいて。
「大切な人からの贈り物だから。そう、顔に書いてんぜ」
ノインは行く先も見えぬ不安の中で柔らかく微笑んでいた。
執筆・投稿 雨月サト
©DIGITAL butter/EUREKA project
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
