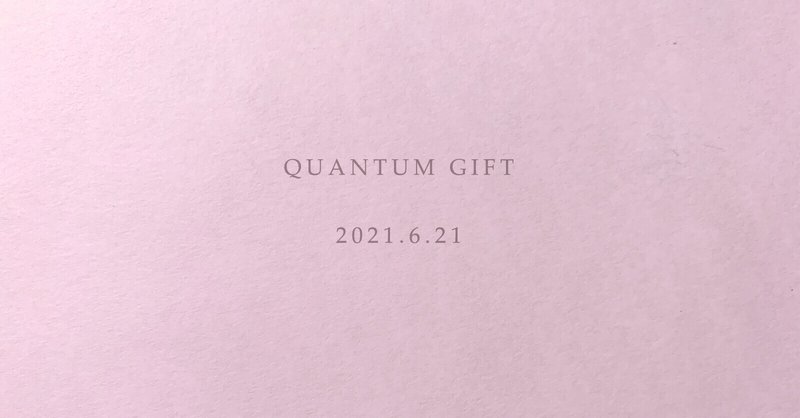
気の流れをデザインする
QUANTUM GIFT
Therapist OCOさんと、月曜日の朝、8時15分くらいから対話をします。大きなテーマは「感覚をひらく」ということ。
アーカイブは残しません。その時、その場の空気感を尊重します。アーカイブは自分の記録であると同時に、未来で誰かに出会うためのツールです。ですから、アーカイブの代わりに僕のテキストによる記録をつけることにしました。
6.21.2021
気の流れが良い(悪い)という表現があります。人や土地を指して言うことが多いように感じます。「風水」というのはまさに気の流れを読む技術と言えるのかもしれません。
建築物は顕著です。間取りや採光窓のレイアウト次第で風通し、日当たりの良い心地よい部屋になるか、そうではないものになるか、わかりやすく「流れ」が表れます。気の流れというのは目に見えませんが、気の流れが良い部屋とはジメジメと重たいものではないことは確かなように思います。
僕はデザインをします。ロゴマーク、ウェブサイト、書籍、あるいは名刺のような小さなものも。(空間もあるけどここでは割愛)。
以前から考えていることですが、名刺のような小さなものの中にも「気の流れ」は存在しているのではないかと考えています。それならばデザインによって良し悪しを左右することも可能だろうとも思うんです。
そもそも「気の流れが良い」とはどういう状態なのだろう?OCOさんの問いかけに対する僕の咄嗟の答えは「元気な状態」というもの。稚拙な答えかもしれませんが、「元気な状態」というのは自分が感じ、判断するということです。誰かに「こうした方が気がいい」と言われてやることではないという点はポイントかもしれません。
呼吸によって「元気な状態」に自分を整えることも可能だそうです。OCOさんは「妊脈(※あっているか確認しておきます)」という東洋医学の教えに基づいた、気の流れを整える呼吸法を今日は教えてくれています。
ちょうど恥骨の前側のあたりから、頭頂にかけた正中を手でなぞりながら呼吸をし、下から上に上がる時に息を吸い込み、上から下になぞりながら息を吐く。やってみると自分の正中が整うようで、軸がしっかりするような感覚があります。
OCOさんの解釈では気の流れが良い人とは、自律している状態でもあるそうです。前述の呼吸は仰向けになった状態でもできますし、ゆっくりと体を起こしていくことも有効です。
体重を支えるために必要な床面積の事を「支持基底面」と言うそうですが、自律とはつまり支持基底面が少ないとも言い換えることが可能です。元気な人は朝起きた瞬間からシャキーン!と立ち上がって行動ができるものかもしれません。逆に言えば、目が覚めてから立ち上がるまでの時間をゆったりと取り、仰向け→座位→立ち上がると順序立てて行動することで、気の流れに逆らわずに元気に活動できるようになるかもしれません。車に置き換えるといきなりアクセル全開は車体にもエンジンにも負荷がかかります。何ごともスムースに。
ここまで書くと「気の流れ=元気」というミスリードを招きそうですが、そうではありません。「元気」を気の出力だとすれば、プラスマイナスゼロの状態が良い状態だと思います。過剰な出力も、出力が足りない状態も異常です。
川の流れに例えるならば濁流のような激しさでもなく、淀みなく流れ続ける川でありたいですね。
ところで、土地にもストレスはあるそうで、ジオパシックストレスと呼ぶそうです。星読みのyujiさんもおっしゃっていたと記憶していますが、神社はもとより聖地に建立される場合と、元は負を背負ってしまった土地を浄化する意味合い等で建立される場合とがあったと聞いたことがあります。
同様に何らかのストレス等により自分の気の流れに滞りを感じたら、神社を建てるようにクリアな洋服を纏うことで元気になることもできるということかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
