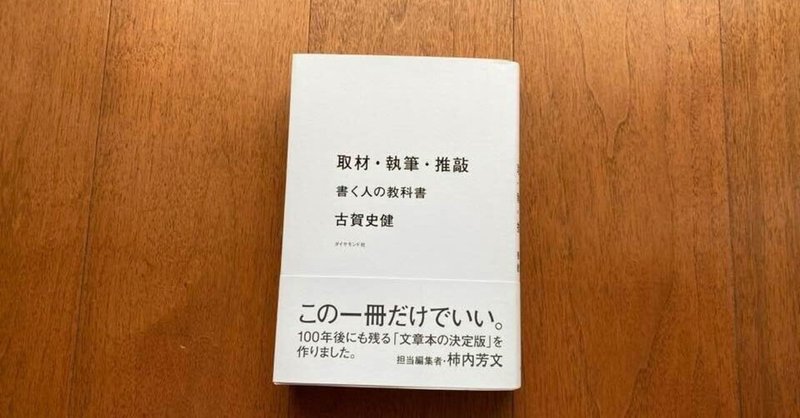
書く醍醐味、読む醍醐味、そして言葉にする醍醐味のすべてが詰まっている。――書評『取材・執筆・推敲』
「思いやりが大事」などと言っている人が、店員さんを呼びつけるのを見るとゲンナリする。主張するのは簡単だが、実践して見せつけないと説得力に欠ける。
「読ませる文章の書き方」という本でも、その文章そのものがあまり面白くないことがある。その本自体がとにかく面白く、それが最高の読書体験になれば、「読ませる文章」を実例として見せつけることができる。この本『取材・執筆・推敲』はまさにそんな本だった。
著者はライターの古賀史健さんである。古賀さんと言えば、一般的には『嫌われる勇気』の共著者として知られているが、出版業界では比類なきライターとして、一度は仕事をしてみたいと思う編集者が数多である。
その面白さは、思考の言語化とそれを伝える術だろう。自分の考えてきたことをここまで言葉にできる、その凄さがある。副題に「書く人の教科書」とある。僕が編集者上がりだからこのテーマに興味があったのは間違いないが、読み終えた感想は、文章をどう書くかを軽く超え、考えたことを言葉にすること、表現すること、そして人に伝えること、そういう力の奥行きをここまで見せてもらったという感動である。ただただ圧巻なのだ。
古賀さんは「書く」とは「つくる」行為であると言い、何をつくるかというと、それはコンテンツである。そして、コンテンツの定義を「エンターテイン(お客さんをたのしませること)を目的につくられたもの」すべてだとする。つまり、ここで言う「書く」は読んだ人が楽しくなる文章のことなのである。冒頭10頁までに、このようなことが書かれている。
ここから続く全470頁の本書は、著者が「書く」ことの定義をした通り、とにかく読ませる。これほどの頁数の本でこれほど飽きさせない本は珍しいのではないだろうか。
そもそも、「読んだ人が楽しくなる文章の書き方」という本を書く、それは途方もない冒険であり、プレッシャーなのではないだろうか。読んだ人が「面白い」と思わなかったら、そこに書かれている内容が全て否定されかねないのだから。こんな難題に挑戦できる人はそもそもいない。それに挑み、見事に読者を引きつけた古賀さんはすごい。その面白さは、どの一頁をとっても、どの一行からも滲み出ている。
この本の醍醐味は何か。それは、「書く」ための作法や心得を超えて、自分との向き合い方を示しているからだ。例えば、文章を書く力を磨くには、まず「読者としての自分」を鍛えるべきだという。ここで言う「読む」とは、本や文章を読むことだけでなく、書くべき対象を見る観察であり、そこから表面的な理解に止まらず、奥にあるものを読み取ることを指している。そして、情報をキャッチするのではなく、ジャッジせよと言う。それは、自分なりの仮説を立てることだ。
こうやって書かれた文章が「わかりやすく」なる。このわかりやすい文章とは、単に、誰もが理解できる言葉は言い回しで書かれた文章を意味するのではない。古賀さんは次のように言う。
「わかりやすい文章」とは、「レベルを落として書かれた文章」を指すのではない。
書き手自身が、わかっている。対象をわかったうえで、書いている。対象をとらえるレンズに、いっさいの曇りがない。「わかりやすい文章」とは、そうした「曇りのない文章」のことである。(p.123)
その上で、
自分のあたまで考えるとは、「自分のことば」で考えることだ。(126)
と続く。この言葉を出版に関わる人に伝えるだけではもったいない。僭越ながらこの本を読みながら共感することが多く、それを言葉にしてくれる嬉しさや賛同を感じていた。ただ、なんとなく思っていることと、それを言葉で表現できることとには、雲泥の違いがある。
共感だけでなく、いくつもの驚きもあった。とりわけ印象に残ったのは、「書く」という行為は「翻訳する」ことであるという言葉だ。少し長いが引用させてもらう。
怒りや悲しみ、喜びなど、ことばを伴わない感情を、ことばにして考える。美術館でゴッホやセザンヌの絵画を観て、こころが震える。それ自体、すばらしい体験だ。でも、せっかくこころが震えたのなら、その震えを「翻訳」したほうがいい。書かなくてもかまわない。誰かに伝えなくてもかまわない。感情の揺れ、震えをことばにする(翻訳する)ことを、習慣化したほうがいい。それは自分という人間を知ることでもあり、ことばの有限性を知ることでもあり、翻訳機としての能力を高めていく格闘でもある。(p.167)
言葉で表現できることの儚さや、表現できないもどかしさを知っているから、これだけ突き詰めて文章を書いてこられたんだろう。この一文から広がる想像力は計り知れない。
本書から得た気づきをあげたらキリがないが、最後の「推敲」はあげておきたい。僕の最も苦手とする作業だが、古賀さんも「気が重い」という。そうかと一安心するも、次の文章を読んだ時には、思わず本を机の上において、読むのを止めてしまった。
徹底した取材者であれ、とぼくは言う。
自分のあたまで理解できたことだけを書け、とぼくは言う。
自分のことばで考えろ、とぼくは言う。
それはひとえに「すべての人に読まれたい原稿」をつくるためだ。(p.430)
研ぎ澄まされた言葉はかっこいい。ここの「ぼくは言う」は、ここまで書いてきたことの繰り返しであり、「前述した通り」と言う意味でもあるが、「私はそう書きましたよね」という読者への復習のための文章だと思えない。むしろ、ここまで書いてきた自分に言い聞かせているように思えた。文章を書くとは、自分を裸になって曝け出すことなのだ。その覚悟の裏には、これだけのことを自分に言い聞かせているのか。
ここまで書いていて、どう終えていいのか分からなくなってきた。僕の言葉を読むより、この本を読んでもらいたい。本を読むのが好きな人は、この本自体が面白いと感じると思う。小さな社内文章でも、もっとうまく書けないかなと思っている人も、この本に目を開かせてもらえるだろう。noteを書いている人なら、線を引きながら読みたいだろうが、線を引くのも忘れて頁をめくってしまうかもしれない。コンテンツをつくるすべての人にも読むのをお勧めしたい。編集者は読むべきだ。
本を書きたいと思っている人は、この本を読んで、自分は無理だと思うかもしれない。なおいっそう本を書きたくなったら、きっとその人は本を書く人なのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
