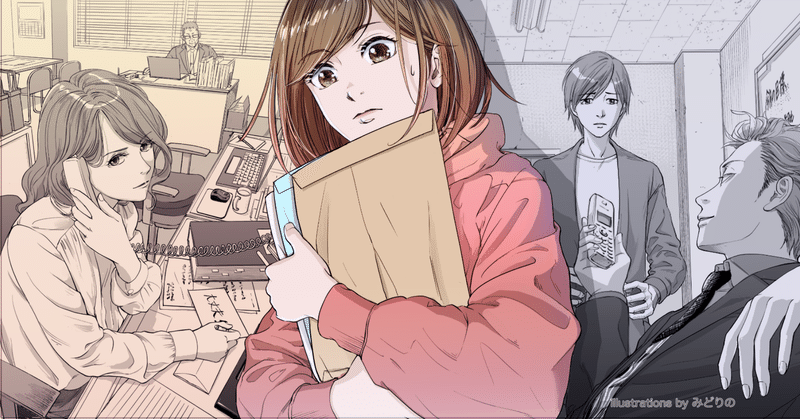
第1話[10]~[13]まとめ/小説「やくみん! お役所民族誌」
第1話「香守茂乃は詐欺に遭い、香守みなもは卒論の題材を決める」
【前回】
[10]罠を仕掛ける
*
澄舞県の東端、八杉市。香守茂乃(かがみ・しげの)宅の電話が鳴ったのは、同じ火曜日の午前10時になる少し前だった。
茂乃は居間でテレビを見ていたので、電話のある玄関まで移動しなければならない。若い頃のような機敏な動作はできなくなった。それでも片付いていれば短い距離のことだが、積み上げた段ボール箱のせいで廊下が狭く、横歩きでなければ通れない。呼び出し音が切れるのではないか、と心配になったところで、ようやく受話器を手に取った。
「はい、香守でございます」
「あ、香守様のお宅で間違いなかったでしょうか」
若い、気の弱そうな男の声だ。聞き覚えはない。頭の中でアラームが鳴る。高齢者を狙うオレオレ詐欺には気をつけなければ、私はまだ若いけどね、と80歳の茂乃は気を引き締めた。
「はい、そげですが」声に自然と警戒の色が籠もる。
「わたくし、五百島市にある五百島シリツ福祉不動産仲介センターのホシノ、と申します」
「はあ、不動産屋さん?」
「いえ、五百島シリツ福祉不動産仲介センターです」
五百島市立の。へえ、そんなところが……いや、あぶないあぶない。市役所を名乗って払い過ぎの保険料を返してくれるという詐欺があるというじゃないか。大体どうして県外の五百島市役所から電話が掛かってくる道理があるのか。怪しいぞ。私は用心深いんだ。
「どげなご用件ですかいねえ、うちには不動産はあーしませんが」
実際は茂乃の家も土地も祖父の代から受け継いだものだったが、本当のことを言う義理はない。不動産はないといえば相手は諦めて電話を切るだろうと思っての嘘だ。
しかし相手からは予想外の反応が返ってきた。
「いえ、違うんです。こちらはコウテキキカンでして、セールスではありません。先日お電話差し上げましたが……」
「はあ?」
茂乃が声を上げると、相手は慌てて言葉を繋いだ。
「いえ、大丈夫ですよ。実は、今度松映市で開設される老人ホームの入居案内パンフレットが届いている方を探していて、香守様のお宅に届いていないかと思って、お電話を差し上げたものです」
老人ホーム。何の話だろう。まったく心当たりがなかった。
「さてなあ、うちには届いちょらんがねえ」
「え」1秒余りの絶句。「松映シニアレジデンスという老人ホームなんですが。青い大きな封筒で」
「届いちょりません。私ねえ、今年で80になあますが、お陰様で元気でピンピンしちょって。信心のお陰だわと思っちょおます。だけん、老人ホームには用がああませんわ」
「そうでしたか、お元気でなによりですねえ」
相手は優しい声でそういった。胸がほっこり暖かくなる。青年の声を聞くと少し孫の充(みちる)を思い出す。線の細い子だ。それだけに可愛かった。
「だんだん(ありがとう)ねえ、お仕事ご苦労様」
「いえ。実はですね、どうしてもその老人ホームに入りたいという高齢者の方がいらっしゃるんですよ。ハシモト・サダコ様、偶然ですが、香守様と同じ80歳だそうです」
「あら、そげですか」
「ここだけの話にしていただきたいんですが、東日本大震災に被災されて福島から五百島に避難された方なんです」
「まあ」あれは大変な災害だった。西日本の澄舞には直接的な影響はなかったけれど、毎日テレビに釘付けになって津波や原発事故の様子を観ていた。
「ハシモト様がですね、幼い頃に澄舞の松映で暮らしておられたらしいんですよ。震災でご家族を全員亡くされ、今は天涯孤独の身の上。せめて人生の終わりに松映に戻りたいと、涙ながらに訴えておられるんです。でも、今回の老人ホームの案内は、香守様がお住まいの地域の中でもごく限られた方にだけ送られていて、届いた人しか入居申し込みができません。なんとかしてハシモト様の願いを叶えたいと、私共がパンフレットの届いた方を探して電話を掛けているわけです」
いつの間にか茂乃の目から涙がこぼれていた。「そおは、願いが叶あといいですねえ」声も掠れて震え、嗚咽に変わった。
「泣いてくださっているのですか。香守様がお優しい心の方で、本当に良かった」
「いや、そぎゃんことないですわね。うちに届いちょったら良かったあもん、お役に立てんで申し訳ないことです」
「本当に届いてないんですね? 青い大型封筒なんですが」
相手の念押しに、茂乃は「はい」と即答した。そんなものが届いた記憶は全くない。
「もしかするとこれから届くかも知れません。その時は、もし差し支えなければ、私までご連絡をいただけるとありがたいのですが」
「それくらいお安い御用ですわね」
茂乃は電話番号をメモに書き取った。相手は丁寧にお礼を述べて、電話が切れた。
世の中にはなんとも可哀想な人がいるものだ。橋本貞子さん、定子かも知れない。名前しか知らないけれど、同い年なら私と同じ時代を生きてきたわけだ。年老いてから震災で家族全員を亡くすだなんて、本当に可哀想。
自分は恵まれている。夫には早くに先立たれたが、一人暮らしでなんの不自由もない。少し離れた比嘉今(ひがいま)には一粒種の長男一家がいる。一緒に暮らすのはいろいろ気詰まりだ、この距離が丁度いい。自分は恵まれている。老人ホームになんて用はない。可哀想な橋本さんの助けになるのなら、老人ホームのパンフレットが届いたら入居権を譲ってあげよう。
──パンフレット?
茂乃はふと何かを思い出した気がしたけれど、何を思い出したのかをすぐに忘れる。なんだろう。なんだっけ。「なんだったかいなあ」と自然と声が漏れる。床を睨んで、うーん、と考える目の端で、電話台の横の古紙ストッカーに青色が見えた。A4判封筒。青。
もしかして。
封筒を手に取り、中身を引き出す。数枚の書類とパンフレットが一冊、その表紙にはマンションのように立派な施設のイメージ図と「松映シニアレジデンス」の文字があった。
「あだん、こおだないか」
茂乃は5秒間パンフレットを見つめた。そして不意に思い出した。これは昨日(もしかすると一昨日かその前)届いたものだ。息子の朗(あきら)が自分を老人ホームに押し込めようとしているのではないかと疑い、朗の家に電話をしたら、違うということだった。歩ちゃんやみなもちゃんとも話をしたっけ。
どうして自分はそれを忘れていたのだろう、という疑問は思い浮かばなかった。それよりも遥かに強い感情──これで可哀想な橋本さんを助けることができる、優しい声の五百島市の担当さんも喜んでくれる、そんな「善意が満たされる喜び」が茂乃の脳を支配していた。
メモを確認して、先ほど聞いた電話番号をプッシュした。2回のコールの後、相手が出た。
「はい、五百島シリツ福祉不動産仲介センターでございます」
先ほどの青年とは違う、中年女性の声だ。
「あの、あの、さっきお電話いただいた香守ですが、さっきの人はおられませんかいね?」
「名前がわかりますでしょうか」
「名前ねえ、どげだったかいなあ」といいながら、電話番号を書いたメモの横に「星野」の文字を見つけた。先ほど電話番号と一緒にあらためて名前を言われ、茂乃が書き取ったものだ。そのこと自体を彼女はもう覚えていない。
「星野さん、ておなあかね? 若い男の人」
「ホシノでございますね。あいにく少し席を外しておりまして、折り返しお電話させていただければと思います」
清潔感のある丁寧な受け答えだ。さすが五百島市役所だけのことはある。茂乃は問われるままに名前と電話番号を告げて、受話器を置いた。
再度電話が掛かってきたのはわずか2分後だった。電話の前で待機していた茂乃は、ワンコールで電話に出た。
「ホシノでございます。香守様、お電話を頂戴したそうで、席を外しており失礼しました」
ああ、さっきの青年の声だ。
「なんと、さっき言っちょられたパンフレット、届いちょおましたわ」
「え、ほんとですか!?」青年の声が華やいだ。茂乃は嬉しくなる。
「最近物忘れすうやになってねえ、年寄りだけん、許してね」
「そんな。こうしてわざわざ電話を掛けてくださるなんて……うぐっ……ありがとうございます、感動して泣きそうです」
言葉に続いて鼻を啜る音が聞こえてきた。ああ、こんなに喜んでくれている。電話をして良かった。私は人の役に立てた。
「そおで、パンフレットはどげすうの? 郵便で送ればいいかいね」
「いえ、その必要はありません。送られた封筒の中に、パンフレットと一緒にピンク色の紙が入っていると思いますので、確認していただけますか」
封筒を覗くと、確かにピンク色の紙が一枚目立っていた。取りだして目を凝らす。標題に「松映シニアレジデンス入居申込書」とある。
「その紙の一番右下にですね、入居権番号として6桁の数字が印刷してあると思います。その番号を読み上げてください」
「はいはい、ちょっと待っちょってよ」茂乃は焦点の合いにくいメガネを外し、申込書に目を近づけた。
「えーと……3、8、3、4、9、6」
「383496ですね」
「そげです」
「この入居権番号をタカハシ様にお譲りいただくことはできますか?」
茂乃の脳内で微かにアラームが鳴った。
「……譲るって、お金のやり取りがああますか?」
「いえ、当センターはコウテキキカンですので、お金のやり取りは禁じられているんですよ。全て無料で、ということになります」
お金が絡まないのであれば、詐欺の心配はない。アラームはすぐ鳴り止んだ。
「タカハシ様は本当にお困りになっていて、香守様の善意にお縋(すが)りするしかありません。どうか購入権番号を無料でお譲りいただけないでしょうか」
「いいですよ。お役に立てえなら、どうぞ番号を使ってごしないね」
「有難うございます、本当に有難うございます! これでタカハシ様も救われます。香守様が思いやりのある方で、本当に良かった」
五百島シリツ福祉不動産仲介センターのホシノ。そう名乗る青年は、茂乃への感謝と賛辞を繰り返して、丁寧に電話を終えた。茂乃の胸に大きな満足感を残して。
*
受話器を置いた青年は、「おし、アタリ来たーっ!」と拳を握って小さく独りごちた。周囲では他の社員が電話中だから、嬉しくても叫ぶわけにはいかない。
背後で様子を窺っていた小太りの男が、上体を屈めて青年の肩に手を置いた。この現場を統括する支社長だ。社内では「ブッさん」と呼ばれている。
「ノリノリだったじゃないか。コマも演技が細かくなってきたよな」
コマと呼ばれた青年──仕事先には「ホシノ」と名乗ることにしている──はにやりと笑って
「あざます。まあ、こういうのは場数ですね」
「なーにを偉そうに。まだ始めて半月だろが。でもまあ、筋はいいやね」
「うす、光栄す」
東京都品川区。大崎広小路駅にほど近い丘陵部にあるマンションの3階に、先ほどの電話の発信元があった。住居用物件ではなく、30畳ほどのオフィス仕様ワンスペース。奥の8畳ほどがパーティションで仕切られ、支社長室兼応接室となっている。
主室中央には事務机が6台。今そこに、支社長を除く5人の男と1人の女が腰掛け、3人が電話中だ。男は支社長を含めて全員がスーツ姿、女も事務服で、見た目は普通の商社の様子と何も変わらない。出入り口からすぐの位置に受付カウンタが設けられており、女が一番近くに座る形だ。
香守茂乃に伝えたホシノの電話番号は、ここには繋がらない。あれは別に契約しているレンタルオフィス業者の管理番号だ。業者は電話を受けると必ず「担当者は席を空けているので折り返します」と伝えて電話を切り、受電情報を専用の電子掲示板に書き込むことになっていた。クライアントはそれを見て、相手に電話を掛け直す訳だ。警察や行政機関が電話番号からこちらを探索しようとしてもすぐには辿り着けない、時間稼ぎの仕組みだ。この業界には、こうした便利な仕組みがたくさん用意されている。リスクに見合う利潤の上がる仕事なので、関連産業も成り立つということだ。
「で、行けそうか?」
しゃがんで見上げるブッさんのささやきに、コマは思案顔で小さく答える。
「行けますね。ただ、結構ボケが入ってる感じです。5日前の電話を覚えてなかったし、送った封筒も最初は思い出せなくて、ひやひやしました」
「そうか。今の会話を忘れられたら、また一からになってしまうな。早目に刈り込み掛けるか。午後に行こうぜ、役割調整しとけ」
「っす」
今の電話はあくまで釣り糸の魚信(アタリ)を巧妙に誘導したところまでだ。糸をがんがん巻き上げて金を騙し取るのは、次の段階ということになる。ここで逃さないように、丁寧に丁寧に収穫しなければ。
支社員の電話ノルマは、アタリがない時で一人あたり一日50件。9時から17時の7時間の稼働時間で、1時間あたりおおむね7件の電話をこなさなければならない。アタリの有無は運による。50件以上電話してもまったくアタリの来ない日の方が多い。
しかしひとつアタリが来ると、手の空いている者最低2人、普通なら3人がチームを組んで、巻き上げにかかる。社員の基本給は30万、あとは歩合制だから、力も入ろうというものだ。
ブッさんは立ち上がり、時計を見た。10時25分。午後には来客予定があるから、午前中のうちに帳簿整理を済ませておきたい。来客の様子を見定めて、モノになりそうなら哲さんに引き合わせることにする。モノにならなければ、カモとして使い捨てるだけだ。
[11]文化人類学について
*
9時前に始まったインターンシッププログラム第1日目午前の部は、二階堂主任の講義と質疑応答で概ね2時間、あとは40分ほど消費者啓発のパンフレットや映像素材などを観る自習時間に充てた。
「ここまではインプット、午後からアウトプット準備に移ります。ちょっと早いけど、1時まで昼休みということで自由にしてていいよ。あ、2人はお弁当?」
二階堂の問いかけに、みなもと小室はほぼ同時に「いえ」と首を振った。
「そっか。この近くはコンビニ不毛地帯なんだよね。本庁舎まで戻れば地下に売店と食堂があるけど、このビル周辺にも飲食店がたくさんあるから、外食で良ければ選択肢はよりどりみどりかな。どこかに連れて行ってあげられるといいんだけど、やらないといけない仕事があって、申し訳ない。一番近いのは」
二階堂は胸の前に手を上げ、真下を指さす。
「ここの一階にあるGON(ゴン)てお店。700円前後で定食やカレーが食べられる」
学生にとっては学食より高いが、官公庁や大手企業の集まるこの地区のサラメシ相場としては抑え気味の価格帯だ。
「美味しいんですか?」
さらっと尋ねた小室の質問に、二階堂は「価格相応のお味ね」と笑った。
ガラス張りのエレベーターを一階まで降りると、GONは南側すぐに見つかった。入り口前のメニューを確認する。いくつかの定食類とカレー、うどん類。
「どうする?」とみなも。
「ぼくはここでいいよ」と小室。
この流れで単独行動するほどの食のこだわりは二人ともなく、そのまま入店する。12時より十数分早い時間帯が幸いしてかそれほど混んではおらず、ガラス張りに面した席を陣取ることができた。
半日一緒にいたけれど、だからといって途端に気心が知れる筈もない。こういう時の話題は「敢えて作る」ものだ。必然、午前中のプログラムの所感が入り口になる。
「知らない話ばかりで面白かったなあ。小室君はもしかすると、割と知ってる知識だった?」
「そんなことないよ。専攻は民事法だから、行政法や行政学の話になると一年の法学総合で聴いたくらいで覚えてないし」
民事法、行政法、行政学。すま大法文学部生として、学科は違うけどなんとなく違いは分かるような分からないようなというのが、みなもの正直なところだ。民事法(私法)と行政法(公法)は法学の枝分野、行政学は政治学の枝。学問分野はその成立由来と性質によって分化する。いわば学問の都合だ。行政現場にとって必要なデータや知見の総体は、単一の学問分野に収まるものではない。必然、あるひとつの現場に関係する学問分野は多岐にわたることになる。
「私はどれもちんぷんかんぷんだからなあ」
「香守さんは、どうして澄舞県庁のインターンシップに応募したの?」
「えっ……あー、まあ、知らない世界を見たかったというか」
不意に触れられたくない核心を突かれた気がして、むにゃむにゃと言葉を濁す。エントリーシートに書いた適当な「作文」をなぞっても仕方がないし、さすがに「役所に関心はないけれど彼氏の職場を見てみたかった」なんてぶっちゃけ話は言えない。
無意識に左薬指の指輪を右手で触れていたのだろう、小室の目線がみなもの指輪に向かうのに気付いた。みなもにとって少し気まずい1.5秒。
「おまたせしましたーっ! ハンバーグカレーはどちら?」
不意に元気な男の声が響いた。細面の小柄な店員がプレートを手にしている。歳の頃は四十代半ば。胸元から膝上までのモスグリーンのエプロンには、彼にそっくりの顔のイラストとGONの文字。
「あ、私です」とみなもが小さく手を挙げると「はい、どーぞ」とプレートが前に置かれた。
「じゃあこちらはソースカツ丼ね。ごゆっくり!」
もうひとつのプレートを小室の前におくと、店員はくるりと華麗に踵を返した。そこへ別のテーブルの馴染み客らしい男性から「ゴンちゃん、次いつ釣り行くの」と声が掛かったことから、彼がここの店主と知れた。
カレーの香りが鼻腔をくすぐる。みなもは合掌して「いただきます」と小さく頭を下げた。
「……なんかいいね、それ」と小室。
「え?」
「『いただきます』って。最近見かけないから」
「そう、あんまり意識したことないや」
香守家では空気のように当たり前の習慣、おそらく信心深いおばあちゃん由来だ。でもそういえば、他の人のやっているところをあまり見ない。みんな小学校の給食で6年間やってた筈なのに。
小室もみなもの真似をして合掌し「いただきます」と呟いた。なんだ、素直な良い奴じゃん。
「小室君は、公務員志望なの?」
先ほど曖昧に中断した話題を継ぐ、ただし、ボールは手放す。そういう問いだ。
「まあね。国か地方かは迷ってる。できれば国の総合職で東京に出たいと思うけど、難関だからね」
国家公務員採用総合職試験は、いわゆるキャリア官僚への道だ。大卒枠は例年十倍を超え、東大京大早稲田慶応が合格者の半分近くを占める。とはいえ五百島大学も旧帝大に迫る数十人の合格者を出すから、いお大生にとって手の届かない門ではない。あとは本人の努力にかかっている。
「ふーん、澄舞に帰るわけじゃないんだ」
「あんまり帰る気はないなあ。ぼくの地元は木継(きつぎ)、知ってる? 人口一万人を切る小さな町だよ。そこで18年過ごして、大きな街は松映と美雲(みぐも)くらいしか馴染みがなかった。それにしたって人口二十万前後だ。進学で五百島に出て、当たり前だけど、世界は澄舞だけじゃないと実感したよ。だから、もし能力が適うなら国家公務員として東京に出たい。地方公務員を選ぶなら、五百島県庁か五百島市を考えてる」
ならどうして澄舞県庁のインターンシップを受けたのか、とは聴かなかった。人にはいろいろな事情がある。インターンシップ生の三日間だけの繋がりは、決して不躾な深追いをしていい間柄じゃない。
みなもは生まれてから21年間、澄舞以外で暮らしたことはない。暮らしたいと夢想したこともない。それでも、遠い都市部に進学した友人たちは少なくないから、小室の気持ちはわかる気がした。充もそうだ。どうしても東京の大学に行きたいといい、勉強を頑張って難関・紫峰大学に進学した。家計の事情はよく知らないけれど、父しゃん母しゃんが充の願いを叶えてやりたいと苦労する様子は間近に見ていた。
「小室くんは、偉いなあ」
みなもの口から自然と言葉が漏れた。小室は将来の道をしっかりと考えている。比べて自分には何もない気がした。卒業後の進路は、まだ何もイメージできない。それ以前に……
「あぁしまっえほえほっえほっ」
みなもが奇妙な声を上げて咽(む)せたものだから、近くにいたゴン店長が「どうしました、料理に何か?」と俊敏に歩み寄る。いやなんでもないですむせただけごめんなさい、と早口に弁解して、みなもはコップの水をひと口飲んだ。その様子を少しだけ見守って、店長は再び華麗にターン、カウンターの向こうへ早足で戻っていった。
「どしたの。大丈夫?」
「うん、ちょっとね、大事なことを思い出した瞬間に気管にカレーが入りかけた。卒論テーマの発表準備しなきゃなのに、忘れてた」
昨日のゼミの時には意識していて、夜に実家のパソコンを借りて作業を始めようと思っていたのに、家ではちらりとも思い出さなかった。今週昼間はインターンシップで丸三日つぶれ、夜は他の科目の予習もある。3回生になると履修科目数に余裕の生まれる学生が多いが、みなもは4回生で楽をするためにそれなりの密度で詰め込んでいた。だから、構想発表会まで6日あるとはいえ、時間的余裕が十分にあるとはいえない状況だ。
「へえ、3年の今の時期に、もう? 僕らは4年になってからだよ」
「すま大でも普通はそうだね、これはうちのゼミの特徴みたい。文化人類学ってフィールドワークが必須だから、就活が忙しくなる前に準備を始めた方がいいってことで」
卒業論文は文献調査5+フィールドワーク3+執筆1+推敲1と心得よ。みなもの指導教官である石川准教授の教訓だ。つまり実際に論文を書き出す前の段階が極めて重要な役割を果たす。そのため文化人類学ゼミでは3年生の秋に自分の研究テーマとモチーフを宣言し、準備を始めるのだ。もちろん、その後にテーマは変わって構わない。むしろ、考えが深まるにつれて変化して当たり前と見做されていた。
「文化人類学って人文科学だよね。法学は同じ文系でも社会科学だから、人文系のやってることは想像つかないよ。ひとことで言うと、どんな学問なの?」
「ひとことで? ふふーん、わかんない!」
みなもは胸を張って正直に答えた。正直すぎて、小室は少し引いた。
*
文化人類学をひとことで表すのは難しい。「ひとこと」とは多様な研究蓄積全体の共通項を言い当てることだからだ。敢えて言えば「人間の文化・社会を」「比較して」「理解する」学問、という漠然としたものになる。対象・手法・目的のどのフレーズも、単語自体は平易で素朴だ。しかしそれぞれ複雑な概念と多様な論点が織り込まれているため、この「ひとこと」から文化人類学を的確に把握できる部外者は、おそらくいない。
文化人類学は「民族学」と呼ばれることもある。特に昭和期までは、民族学の呼称の方が一般的だった。民俗学と同じ音で紛らわしいことから、当時の文化系学生は前者をエスノ(エスノロジー)、後者をフォーク(フォークロア)と呼び分けていた。
狭義(日本語の字面的語義)の民族学と民俗学の違いを単純にいえば、前者が「異文化」を、後者が「自文化」を対象とする点にある。わかりやすい例を挙げるならば、大阪の国立民族学博物館(みんぱく)は世界各地の文物・模型を展示し、千葉の国立歴史民俗博物館(歴博)の展示内容は国内のそれだ。どちらも単なる展示施設ではなく、それぞれの学問の研究機関でもある。展示はその研究成果を社会に還元する営みといえる。
外国の文化であれ自国の文化であれ、研究者が研究対象に密着参加して祭祀・家族・労働・貨幣・相互扶助などのテーマを観察し考察する手法は、ふたつの学問分野に共通する。ただし、民族学の場合は必然的に「比較」ということが問題になる。なぜなら研究対象が異文化──研究者自身の所属するものとは異なる文化だからだ。
異なる民族の文化習俗を理解すること。それは異文化が接する場面で必ず生じるものであり、その意味では古代から行われてきた営みだ。それが近代的学問として成立するのは19世紀半ば、植民地主義の時代に欧米の研究者がアフリカ・アジア・オセアニアの文化習俗を記録したことによる。この記録こそ民族誌(エスノグラフィ)と呼ばれるものだ。
エッセイや報道などあらゆる記録的記事がそうであるように、民族誌もまた完全な意味で「事実の客観的な記録」ではあり得ない。書き手の価値観や先入観を排除することは、ある程度までは可能だ。しかし、言葉の選択、描写の浅深、エピソードの採否など、さまざまな面で書き手の主観の下支えがある。こうした原理的問題に自覚的である時、民族誌は「書き手の文化」と「観察対象の文化」の接点に生まれる比較表現と受け止められる。言い換えればそれは他者を理解する営みであり、反射的に自己を理解する営みということだ。
白い箱は、黒い紙を背景に置いた時に、よく判る。比較することで初めて白い箱の特徴、黒い紙の特徴がそれぞれに浮かび上がる。これが、他者理解の手法としての比較のアドバンテージだ。
民族学は、百数十年の歴史の中で、他者理解の理論と技術そして倫理を磨き上げてきた。そのように洗練された学問は、既存の哲学・美学・社会学などの枠組みに収まることなく、対象を総合的に把握することを指向する。それは単に異なる民族文化の理解にとどまらず、さまざまな集団の理解に有効なものだ。
ここに、狭義の民族学を包含しながらその対象領域を超えた文化人類学(カルチュラル・アンソロポロジー)が成立する理由がある。実際に文化人類学は、研究者個人にとって「異文化」と捉えられる様々なもの──例えば暴走族、精神障害者ケア施設、アイドルコミュニティ──を幅広く研究対象としてきた。その多様性が文化人類学という学問の説明を難しくする要因でもある。
──というような小難しい話を、みなもは二回生の時に入華教授の講義で聴いていた。ただ、それを理解し消化して自分なりの「ひとこと」で表現するような芸当を求めるのは、研究者志望でない学部生には酷というものだろう。
[12]慈しみ合う者、絶望する者
*
ちょうどレジでお金を払い終えたタイミングで、みなものスマホが振動した。店の外に出てバッグを開き、画面を確認する。茂乃からの着信だ。
「電話に出るね。1時までに上に戻るから」
そう小室に告げて、ホールを見渡す。東側が広い開放ラウンジになっていて、設置されたファブリックスツールの周りに人影はない。みなもはそちらに歩きながら受信ボタンをタップした。
「はい、みなもです」
「おばあちゃんです。今、電話いいかいね?」
「いいよ」
ガラス張りの壁面に背を向けて、スツールに腰を下ろす。小室がビルの外に出て行くのが見えた。まだ昼休みは30分あるから、一人で上に戻るよりは近隣の散歩を選んだのだろう。
「お父さんに電話したあもん繋がらんでねえ」
「今日は魚居(ととおり)に出張だから。運転中かも」
「ああ、そげかあ」
出張自体は嘘じゃない。ただ、父しゃんはおばあちゃんからの電話を無視することがある。決して仲が悪いわけじゃないけれど、父しゃんがおばあちゃんから少し距離を置いているように、みなもは感じていた。もしかすると、八杉の広い家を出て比嘉今に移り住んだこととも関係するのかも知れない。だから今日のおばあちゃんの電話も、父しゃんはわざと出なかった可能性があると思った。もちろんそんなこと、おばあちゃんには言えない。
実の母親なんだから、もっと優しくすればいいのに。その分、私がおばあちゃんの話を聞いてあげよう。
「みなもちゃん、あのね、おばあちゃん今日ね、とてもいい事をしたの。老人ホームのパンフレットが届いた話は、しちょったが」
「うん、夕べ聞いたよ」
「私は元気だけん老人ホームの入居権なんていらんだあもん、震災で身寄りを無くした可哀想な人がおなって、その人に譲ってあげえ事にしただがん」
入居権、震災、かわいそうな人、譲る。話が見えない。
おばあちゃんの話は長い。行きつ戻りつループしながら、午前中にあった電話の概要が分かるまでに3分半かかった。
みなもは昼前に、消費者向けの広報啓発素材をいくつも眺めていた。その多くは、悪質商法や特殊詐欺に関するものだ。世の中には本当に悪い連中がいて、平気で嘘をついてお金を騙し取ろうとしている。たまにニュースでそういうのは見ていたけれど、平和に生きてきたみなもには遠い世界の出来事のようだった。けれども午前中のプログラムで澄舞県内でも多数の被害が発生している事実を知り、あらためて世間は油断ならないなと感じていたところだ。
「おばあちゃん、それ、詐欺だったりしない?」
「最初は疑ったわね。おばあちゃん用心深いけんね。だあもん、五百島市役所の話だけんお金を払えとかパンフレットを買い取るとかそげな話じゃないって。お金はなんもかからんて。だけん、詐欺じゃないわ」
「そう、ならいいけど」
確かにお金が絡む話でなければ、詐欺の余地はなさそうに思えた。
「困っちょおなあ人のお役に立てえなら、有り難いことだわ。善根功徳(ぜんごんくどく)は自分に返ってくうけん。みなもちゃんも優しい子だけん、きっと幸せんなあで」
「うん、ありがとう」
みなもは5歳までおばあちゃんと一緒に暮らしてきた。父しゃんは一人っ子だ。おばあちゃんは初孫のみなもを可愛がり、たくさん抱っこや添い寝をしてくれた。みなもたち三人の孫を、おばあちゃんは本当に思ってくれている。
「充(みちる)ちゃんも歩(あゆむ)ちゃんも、優しい子だ。お父さんも小さい頃から優しかった。お母さんも良くしてごしなあ。香守の家のもんは、みんないい子だけん、みんな幸せだわ。みんなが幸せだと、おばあちゃんも幸せになあわ」
おばあちゃんの真っ直ぐな愛情が、自分たち家族に向けられている。少し涙が滲んで、みなもは指先で目尻を拭いた。昨夜の電話は、認知症の始まりを窺わせる不穏なものだった。おばあちゃんは少しずつ、確実に年老いている。
「おばあちゃんも、長生きしてよ?」
「ひ孫を抱っこすうまで、元気でおるけんね」
「あはは、願いを叶えてあげるのに、私も頑張らなきゃね」
「そげだで?」
祖母と孫は、電話と心を通じ合わせて、共に笑った。幸福は今、ここにあるよ。みなもはそう思った。
*
クソだ。世の中、クソだ。
一人の青年が、胸のうちで黒い呪詛を繰り返しながら、峰原通りの坂を徒歩で登ってゆく。東京、大崎。秋の午後の青空は高く広い。爽やかな空気の中、青年の表情だけが暗く沈んでいた。
今は彼を押井と呼ぼう。本名ではない、後に深網社(じんもうしゃ)内でそう呼ばれることになる名前だ。
押井は世の中を呪っていた。生きることは、苦しい。楽しいことだってないわけじゃない、けれどもそれを上回る苦痛が、彼の人生には満ちていた。生まれて来なければ良かった、と今は本気で思っている。
幼児期は幸福だった。嫌な出来事があってもその瞬間だけ泣いて、すぐに忘れて笑うことができた。忘れることが難しくなったのは少年期からだ。陰湿ないじめは精神に傷を刻み込む。思春期には更にひどい状況になった。昼の理不尽な出来事が夜の寝床で幾度も脳裏に蘇り、その度に乾きかけた傷口が開いていく。
環境を変えれば人生を打開できるのではないか。そう期待して上京したが、彼のような人間に対する周囲の無理解と嘲笑は変わることがなかった。むしろ孤立無援の独り暮らしでは精神の回復する余裕もなく、傷口から血と膿が湧き、腐臭を放つ。この数ヶ月の間に、暗く澱んだものが急速に押井の心を蝕んでいた。
クソだ。世の中、クソだ。
彼が今この坂を不本意に登っているのも、クソみたいな状況だ。
負うつもりのなかった借金。返せるアテもなく、指示に従うしかなかった。指定の銀行で新たに口座を作る。後日キャッシュカードが届いたら、通帳と一緒に指定の場所に届けること。今はその途上だ。
坂道を登りながら、人生の坂道を転げ落ちているように感じる。
自動販売機の前で歩みを止め、周囲を見回す。坂下の山手通りのビル街とは違った、人通りの少ない住宅街だ。いくつかマンションがある。この場所から電話をするよう指示されていた。
スリーコールで相手が出た。
*
「それでは今から道筋をお知らせしますね。すぐ近くですから」
ブッさんが、受話器を耳に当てて他所行きの声で話しながら、ブラインドの隙間を指で押し開いて路上を見下ろしていた。薄青色の上着を着た青年──押井が自販機の前にいる。通話の相手が近くのマンションから見下ろしているなどとは気付く筈もない。
押井に指示を出して、通話を続けたまま路地へ歩かせた。そのままぐるりと辺りを一周させることになる。
「尾行、いますか?」
コマが席に腰を据えたまま、なんだか嬉しそうに尋ねた。彼自身、一月ほど前には同じように観察されていたのだ。
「いねえよ。それが普通だ」
ここに「候補者」を初めて呼び出す際の儀式のようなものだ。ブッさんが支社長になってから4回、同じことをしている。尾行者を確認できたことは一度もない。それでも前任者から引き継いだ「決まり事」であり、やらねばならない。
そもそも、支社に外から「候補者」を呼ぶなんて、リスク大きすぎねえか? 哲さんにとって、俺はまだ使い捨て扱いなのか? その疑問は今も燻っている。
「はい、目的地到着です。ごめんね、尾行をまく必要があって、遠回りさせました。今から5分そのまま待って、マンションの3階まで上がってきてください。部屋にグッドネス物産の看板掛けてますんで、そこです」
そう指示をして、電話を切った。
「蘭さん、7分後に客が来るから、応接に通して。薄青い上着の若い奴。茶はいらない」
蘭と呼ばれた女性社員が、はあい、と気だるく答えた。
ブッさんは応接室兼支社長室に入り、扉を閉めようとしたところで、振り返った。
「コマ、こっちは20分かからないと思うから、終わるまで刈り込みは待っててな」
「うぃす」
支社長室の備品は本室のそれより少しグレードが高い程度の事務用で、エグゼクティブな感じはない。応接セットも簡素なものだ。金はいくらでもあるが、所詮は捜査の手が伸びれば即座に放棄する部屋だ。それでも自分用の椅子だけは座り心地の良いコンテッサを調達した。
その椅子に腰を下ろし、机上の書類を手に取る。これから来る青年に関する報告書だ。彼──押井が何故、今日ここに来ることになったのか。その顛末がまとめられていた。
*
三週間ほど前に遡る。
池袋西口公園にほど近い路地の雑居ビル。一階一番奥に占い師が店を構えていた。屋号はAngolmois(アンゴルモア)。オーナーの龍神(たつがみ)ズメウは、日本人で初めてルーマニアの伝統ある魔術師養成施設ショロマンツァに入校を許され、主席で卒業したという。もちろん全て嘘だ。彼はルーマニアはもとより外国に行ったことはなく、生まれて以来39年間、埼玉県以外に住んだこともない。
アンゴルモアは深網社グループの末端店舗のひとつだ。ただ、グッドネス物産のように純然たる詐欺集団ではなく、アヤシゲながら一応は表の顔を保っている。ただし、占い目的でここを訪れる客のうち条件に当てはまる人間──心が弱っている、他人に操作されやすい、金払いに躊躇がないなど──には、さらに様々な罠が仕掛けられる場合がある。表の商売をしながら詐欺のカモを探す、いわばセンサーの役割を果たしていた。
そのセンサーに青年が探知されたのは、SNSに出稿した広告経由のメールマガジン登録からだった。広告バナーには「神秘の力で邪気を祓う!」「日本人唯一の東欧魔術正式伝承者」「初回相談(15分)無料」の言葉が躍る。メルマガ登録すると特典として初回無料相談が1時間に延長され、申込フォーマットには個人情報に加えて簡単な相談内容を記すようになっていた。
広告表示回数に対するクリック率は0.7%程度。SNS広告はユーザーの興味関心に応じて配信される仕組みだが、それでも大半の人はスルーしていることになる。逆に言えば、クリックする者、さらにメルマガ登録まで至る者は、間違いなくこうした内容に強く興味を示す人間だ。広告が効率の良いスクリーニング機能を担っているわけだ。
押井から偽名で──「押井」も本名ではないのだが──相談予約があり、すぐにアンゴルモアスタッフの仕事が始まった。提供された情報をもとにネットを検索し、当日までに相談者の情報をできる限り集める。それが「占い」に必要だから。
アンゴルモアのようなインチキ占いの生命線は情報だ。事前に調べ上げた個人情報を、あたかも神秘的な力で言い当てたかのように相手に告げる。相談者はあらかじめスクリーニングされたスピリチュアルビリーバーであり、境遇をズバズバ言い当てる奇跡を見せれば、ハマる。こうした手法をホットリーディングという。
しかし、その青年の情報は目ぼしいものが見つからなかった。住所は空欄で氏名もデタラメだから無理もない。しかし、メールアドレスを流出個人情報と照合してくれるダークウェブの有料検索サービスに掛けたところ、本当の住所氏名電話番号が判明した。それ以上の情報は更に高額料金が必要になるが、そこまでコストをかけるかどうかは面談した後に判断すればいい。個人情報をこちらが探知したと相手は知らない、これだけで、はったりをかますには十分だ。
「妙だな。あなたの名前の波動と、目の前にいるあなたの発している波動が、全然違うんですよ。これ、偽名ですよね? あなたの真の名前は……コウ……コウマ……いや違う。本当は」
ゆったりしたグレーの道服に紫のガウンを羽織った龍神ズメウは、青年の前でタロットカードに掌をかざして眉に皺を寄せ、少し勿体をつけてから青年の本名をずばり言い当てて見せた。恐怖と驚愕の入り交じった青年の表情を観て、龍神は内心(よし、ハマった)と拳を握った。
しかし、そこまでだった。
事前に個人情報を調べるホットリーディングに対して、現場で相手の反応からその人間性を推察し内心を言い当てる手法を、コールドリーディングという。最初はぼんやりとした、誰にでも当てはまるようなことを言っていればいい。もともと占いを信じて来店した客は、占い師の霊感に見透かされたと思い、喜んで自分からいろいろと喋ってくれる。その反応を見ながら、少しずつ話に具体性を盛っていく。コミュニケーションを通じてパズルを組み合わせ相手の信頼感を構築する心理誘導技術であり、カウンセラーや探偵、もちろん占い師にも必須の技能だ。龍神はこの業界に足を踏み入れて10年近い。それなりの自信とキャリアの裏付けがあった。
けれども、押井に対してはうまくいかなかった。面談を始めた最初から、どうにも会話のリズムが噛み合わず、コミュニケーションが取れる感じがしないのだ。開始十分ほどで早くも「本当の名前を言い当てる」大はったりを繰り出したのは、龍神の側に場の空気を持てあます居心地の悪さがあったからだ。それが結果的に失策だった。
押井の様子はみるみるひどいものに変化した。頬が震え、目が泳ぎ、息が上がる。
大丈夫か、こいつ。何か持病でもあるのか。倒れられたら面倒だ。
「どうかリラックスしてください。この魔術空間には、私とあなたしかいません。あなたの秘密を知る人は、他に誰もいません。あなたの苦しみは私の苦しみです。どうか、落ち着いて深呼吸を」
促されて押井は息を吸うが、胸が動いていない。体が強張って深い呼吸ができないのだ。
押井が予約の際に記した相談内容は、「子供の頃からずっと無神経な人々に傷付けられてきた、人生は地獄だ」という趣旨の、深刻な色を帯びていた。明確にそう表現していたわけではないが、これはいじめだな、と龍神は当たりをつけていた。相当に深い心の傷が、こうした異常な反応の要因なのだろう。
少し気分転換させるか、と龍神が頭を巡らせ始めた時、突然押井が立ち上がった。
「ももっ、もういいです! ごめんなさい、帰ります!!」
押井はくるりと踵を返し、部屋の入口にかかったサテンの暗幕に手を掛ける。
「ちょっと待って」
龍神はそういったものの、振り返った押井の表情を見て、これは止めない方がいいなと判断した。
それでも最後に、言わなければならない台詞がある。
「ひとつだけ、伝えておきたい。いまに、あなたを助けてくれる人物が現れる。きっと女性だ。その人の願いを叶えてあげる生き方を選びなさい。それがあなたを地獄から救ってくれるから」
2秒押井は固まっていた。そのままぺこりと頭を下げて、ビルの廊下を足早に歩き出す。
龍神は入口から顔を出して、押井の背中に向けて声を掛けた。
「ごめんね、今日は星の巡りがあなたの波動と合わなかったみたいだ。無料相談は次回も有効てことにしとくから、気が向いたらまた来てよ」
占い師としての構えを解いた、龍神の素の言葉だった。押井はこちらに体を向けて、ゆっくりと深いお辞儀をした。その仕草に、育ちは良さそうだな、と龍神は思った。
押井がビルを出て行くのを確認して、龍神は頭をかいて大きく溜め息をつく。
「……悪い事したかもしれないなあ」
最後の「預言」は、詐欺への罠だ。つい勢いで言ってしまったけれど、地獄から救うどころか更なる地獄へと向かう道かもしれない。弱い者いじめのようでなんだか後味が悪い。もっとも、その罠を駆動させるかどうかは別のグループの判断になる。
占い師としての素性はインチキだが、10年近く、困っている人の悩み事相談に応じてきた。グループとしてのノルマがあるので、今回のように罠を仕掛ける場面も避けられない。しかし、自分なりに親身に考えたアドバイスが「先生のおかげで救われました」と心から感謝されることが、年に数回はあった。そんな時、龍神は素直に嬉しかった。要するに、龍神はこの仕事が嫌いではないのだ。
青年の苦しみの深さを想う。人によって、置かれた状況は異なるし、同じような状況でも感じ方は異なる。自分より20歳近く年下の青年は、自分の知らない地獄を知っているのだろう。
ああいうタイプが、哲さんの探している「候補者」かも知れないな。
報告書を書かねばならない。龍神は再び暗幕の内側へ潜った。
[13]沼に沈む
*
支社長室のドアがノックされた。どうぞ、と声を掛ける。ドアが向こう側に開いて、蘭が顔を覗かせた。
「お客さまがお見えです」
「通して」
蘭が引っ込み、代わりに押井が部屋の中に入ってきた。
「やあ、いらっしゃい。そちらへどうぞ」
ブッさんが促すと、押井ははっきりした声で「はい」と応え、合成皮革のソファに腰を下ろした。
ふうん。報告では挙動不審な小心者のイメージだったけどな。
ブッさんは書類を机上に置いてコンテッサから立ち上がり、応接セットへ向かいながら、押井から目を離さずに観察を続ける。
第一印象は、爽やかな好青年。細身で身長は170cm台半ばか。髪の毛はさらさらで服装を含め全体に清潔感がある。少し目に昏いものを湛えてはいるが、それが逆に異性には魅力的に映りそうだ。
どかりとソファに体重を預けた。半ば無意識のオーバーアクション。押井の表情に、さっ、と小さく陰が差すのを、ブッさんは見逃さなかった。やはりそうか。いじめられっ子はいじめっ子に逆らえない、それは本能のようなものだ。いざという時にマウントするのはチョロい、そう確認できれば今は十分。先ずは柔らかい当たりでいいだろう。
「で、持ってきた?」
ブッさんの明るい声音に、押井は固まったまま答えない。4秒、5秒、6秒。ブッさんは焦れて先を促す言葉を発した。
「ここに持ってくるように言われたもの、あるでしょ」
「……通帳ですか?」
「あれえ、通帳だけだっけ?」
少し声量を大きくして問うと、押井の表情に軽く怯えが浮かぶ。
「えと……通帳と、キャッシュカードですか? あ、あと、ハンコ」
「そうだよ、そう。わかってるじゃない」
押井はボディバッグから封筒を取り出し、中身を出してテーブルに置いた。異なる銀行の通帳三通、キャッシュカード三枚、印鑑が三本。ブッさんは通帳を手に取って確認した。どれも当初入金一万円の一行のみ記帳された新品だ。名義人は押井の本名。キャッシュカードには通帳と同じ口座番号と名義人がエンボス印字されている。
「確かに。で、これ、どうする? 持って帰る?」
押井は口の中で小さく「えっ」と呟き、意味を掴みかねているようにブッさんの顔を見た。
「お前が決めていいよ」
「あの、橋本さんからここに持って行けと言われたんですけど」
ブッさんはにこにこと笑顔を湛えたまま黙っている。
「えと、借金を返す代わりに……」
「借金の話は、俺は知らないよ」とかぶせ気味にいう。「それは橋本とお前の問題だ。俺は、この通帳とカードと印鑑を、お前の自由意思でどうするのかを聞いてんの」
「持って帰ってもいいんですか」
「いいよ、俺は。橋本とのことは知らないよ」
ブッさんは、決して通帳を渡せとは言わない。あくまで相手が自らの意思で通帳を渡すのを待つ。
一方で、押井は宝石商の橋本から、ネックレスの代金を払えないのであればその代わりにと今回の指示を受け、ここに出向いていた。持って帰ったら50万の借金がそのまま残る。
この人は素直に受け取ってくれなさそうな気配だ。話が違うじゃないか。どうすればいい。胸が苦しい。頭の中がグルグルする。息がうまく吸えない。呼吸ってどうするんだっけ。苦しい。
押井の顔が歪むのを、ブッさんはただ見ていた。
ダブルバインド(二重拘束)。強者から複数の矛盾する指令を受けて弱者が混乱し疲弊する状況。文化人類学者グレゴリー・ベイトソンが提唱した概念だが、勉強の嫌いなブッさんがそんなことを知る筈もない。ただ、相手をこうした状況に追い込むことで自分が圧倒的に優位に立てると、経験的に知っているだけだ。
追い込んだ先に、逃げ道を作る。そうすれば自然と相手はそちらに向かう。
「難しく考える必要はないよ。お前がこれを俺にくれるというなら、ありがとうといって受け取るよ。持って帰るというなら、それも止めない。どっち?」
初めて通帳をブッさんに渡す道筋が示された。押井はほっと表情を緩め、口を開いた。
「あげます」
言い方に幼稚なものを感じたが、ブッさんはそこはスルーした。
「わかった、お前の意思で俺にくれるというなら、受け取るよ。ありがとうな。橋本には受け取ったと言っとくから」
よし、ハマった。
ブッさんは一式を手元に引き寄せ、あらためて押井の顔をみた。気の進まないことをやり終えて、一刻も早くこの場を立ち去りたいという顔だ。けれども、今この瞬間にもう引き返せないところまで来てしまったのだと、こいつは気付いてない。
所詮は、無知で気弱なカモだ。「候補者」の器じゃあない。
*
龍神の忍ばせた罠が別班により発動したのは、押井がアンゴルモアから逃げるように帰ってきた二日後のことだ。
キャンパスに向かうため、茗荷谷のアパートから春日通りに出たところで、前から来た若い女性に呼び止められた。
「あのー、この住所を探してるんですけど、ご存知ですか」
目が大きく小柄で少女のようだが、スーツ姿を見ると二十代なのだろう。彼女の差し出したメモには、小石川の所番地とマンション名が書いてある。
「知らないですけど、たぶん、あっちですね」
と、押井は東の方角を指差した。
「こんなこと突然お願いして申し訳ないんですけど、案内してもらえませんか? 私、この辺りは初めてなので」
「スマホでナビすればいいと思います」
塩対応のようだが、押井に悪意はなく、これが彼の標準だ。しかし、女性の側もそれで引く様子はなかった。
「あの……恥ずかしいんですけど、私、地図の読めない女なんです。スマホの充電も切れそうだし。どうか助けると思って」
女性は両手で押井の右手を握り、真っ直ぐに押井を見つめる大きな瞳が少し潤んでいる。何か事情があるのだろうかという推測と、可愛らしい女性(ひと)だなという男心、他人に触れられていることの緊張と、それが異性であることの気恥ずかしさが、押井の一瞬の心の内に押し寄せた。
授業まで、あまり間がない。
「途中までなら」
「ありがとうございます!」
女性は顔を綻ばせた。誰かに喜んでもらえると、押井も嬉しくなる。彼の鋭敏な心は、他人の心の有様に簡単に左右される。
押井は自分のスマホでマンションを検索したが、ヒットしない。番地も同一のものは見当たらないが、播磨坂の下の辺りと見当をつけた。ひとまず真っ直ぐ坂上を目指そうと考えて、歩き出した。
道すがら、女性は饒舌だった。名前はサトミレイコということ。北海道の出身であること。就職のため上京して半年で心細いこと。あなたは? 素敵ですね。わあ、すごい。今度私にも教えてくださいよ。彼女いるんですか?
押井はいつもの調子で朴訥とした反応を返した。子供の頃から他人とリズムが噛み合わず、ごく一部の親友を除いて会話のキャッチボールが苦手だ。しかしサトミレイコは、まるで沈黙を恐れるかのように押井の言葉を全部拾って反応する。変な人だな、と押井は思った。
小石川5丁目交差点で押井は左方向を差し、サトミレイコに告げた。
「この坂の下辺りだと思うので、そこで誰かに尋いてみてください」
サトミレイコは、何かを言いかけて、口ごもった。押井はその様子を意に介さず「じゃあぼくはこれで」と元来た方向に5歩歩いたところで、背後に「きゃあっ」という棒読みの悲鳴を聴いた。振り向くと、サトミレイコが屈んで足首に手を当てていた。
「……大丈夫ですか?」
その場から動かず声だけ掛けた押井に、サトミレイコは捲し立てた。
「大丈夫じゃないです! 捻挫したみたい、困ったなあ、これじゃあ客先に行けない。会社で休みたいので、タクシー拾ってください。それから、心細いので、一緒に来てください!」
かけらもリアリティの感じられない、強引な台詞回し。
サトミレイコ──もちろん偽名だし路上で語っていた素性も嘘八百だったのだが──は、この時のことを後に押井にこう語っている。
「自分でも、大根だとわかっちゃいてんで? 役者志望やのに、客引きひとつうまくできひん。初めて引っかかった、ちゃうわ、ついて来てくれたんが、オッシィやってん。店まで連れてきたら歩合ゲット、うまいこと契約させたったら割り増しになるからここが踏ん張りどころや、て思た。つまり、逃すわけにいかへんカモやな。はは、ごめん、ごめんて。あの時は、まさかオッシィとこうなるなんて、思いもせなんだな」
*
デート商法は、異性を誘惑して商品を買うよう仕向ける手口だ。SNSや街頭アンケートなどをきっかけに近づき、数回デートを重ねてカモを感情移入させた後、プレゼントとして絵画やアクセサリーといった高額商品を買わせる。もちろん販売店はグルだ。これ以上は金を絞れないとみたら、その時点で誘惑者は姿を消す。販売店は表向き無関係を装っているから、文句の言いようもない。
押井は、高校卒業直前に配られた消費者トラブル防止パンフレットで、デート商法のことは知っていた。受験の終わった3年生が講堂に集められ、パンフレットを見ながら、消費生活センターの職員から1時間ほど話を聴いた。内容は若者に多い消費生活トラブルについて。その半分以上を悪質商法の話が占めていた。その時は「世の中は恐いことがあるものだな」と思ったくらいで、すぐに忘れてしまった。
自分が今まさにデート商法にはめられようとしていると気付いたのは、宝石店の応接室に軟禁状態で2時間ほど勧誘が続いた頃だった。
「これ、デート商法ですか?」
「デート商法? なんですか、それ。聴いたことないなあ」
社長を名乗る橋本はそう嘯(うそぶ)いた。優に体重100kgは越えているだろう、身長はそれほど高いようにも見えなかったが体躯は相当に太い。話の途中から上着を脱いで、薄青いカッターシャツに濃紺のサスペンダー姿。室温は快適だが顔の脂汗が天井のLED照明の白い光を反射している。
部屋の中には、ハシモトジュエルオフィスの男性社員3名がいた。橋本が押井の対面でソファに腰を下ろし、押井の背後に一人、もう一人はドアの前に仁王立ちで腕組みをしている。橋本以外はいかついタイプではないが、ただそこに居るだけで圧迫を感じさせる布陣だ。
サトミレイコは、お手洗いに行くといって15分前に席を立ったまま、戻ってこない。これは追い込みが終盤戦に入ったことを意味するが、その時の押井に知る術はなかった。
橋本は、ずい、と巨体を乗り出して、押井の目を真っ直ぐに見た。視線を受け止められずに押井の目が泳ぐ。その様子に、橋本はタメ口に切り替えるタイミングと踏んだ。
「お兄さんさあ、いちゃもんつけてもらっちゃ、困るよ。もう2時間も、こっちは説明してるんだよ? いや、まだ2時間、かな。先日のお客さん、何時間頑張ったっけ? ああ、そうそう10時間な。最後はうちの商品の素晴らしさを心から納得してくれて、契約書にサインしてくださったよ。うちもさ、品質に自信があるから、社員全員が熱心にお客様と向き合えるんだ。何時間でもね。まあ、早くにご決断いただいた方が、お互いに時間を有効に使える。で、お兄さん」
橋本はさらに顔を近づけた。呼吸が荒く、鼻息が押井の頬に吹き付ける勢いだ。その圧で、押井の呼吸は浅くなる。
「どうすんの」
押井は体を強ばらせたまま返事をしない。目の前の現実から切り離された意識に、ぐるぐると呪詛が渦を巻く。
クソだ。世の中は、クソだ──。
その時、ドアが開いて前に立っていた男に当たり、男がよろめいた。
「あ、ごめんなさい!」
入ってきたのはサトミレイコだ。彼女は部屋の空気を読むことなく、明るい笑顔で押井の隣に腰を下ろす。二人掛けソファなので自然と上腕と腿が密着し、体温を感じる。同時に橋本も押井から離れ、上体を戻してソファに体を預けた。
押井の呼吸が、少し楽になる。
緊張と緩和。
追い込んだ先に、逃げ道を作る。そうすれば自然と相手はそちらに向かう。
「私、思いついたんですけど」
サトミレイコが橋本に言った。
「こういう時に、お金の代わりに買う方法があるって、友達に聞いたことが」
「ああ……アレね」橋本は思い当たることがある素振りを見せた。サトミレイコより演技は自然だ。
「じゃあ、お兄さん、こうしましょう。50万円で購入する代わりに、3万円+αで買える方法があります。普通のお客さんには言わないんですけど、お兄さんはお金に困ってらっしゃるようなので、特別にその方法をお知らせします。それなら大丈夫でしょう?」
「あの……αが47万円なら何も変わりません」
押井が真面目な顔でそう主張した。言っていることは正しい。でも今この流れで普通はそうは考えないし、言わない。対抗するなら、そこじゃないだろ。こいつ少しネジが足りないんじゃないか、と橋本は思った。
「大丈夫ですよ。少し手間がかかるのと、あとは印鑑を三本作ってもらう分の数千円ですね。それぞれ違う銀行、違う印鑑で口座を三つ作って、一万円ずつ入れておいてください。それからキャッシュカード。それを渡していただければ、ネックレスの代金は完済ということで」
押井に向けた橋本の言葉を、サトミレイコが代わりに引き取って反応した。
「えーっ、じゃあ3万数千円で50万円の価値あるネックレスが買えるんですか!? これはお得ですねえ」
お前はテレビショッピングの司会者の相方かっ、と橋本は内心で突っ込んだ。この試用期間の一ヶ月で確信した。サトミレイコは、この仕事に向いていない。
前任者が抜ける時に同じ劇団ということで紹介され、見た目が可愛いから適任と考え採用した。しかし訓練しても演技が全然ダメなのだ。全然客を捕まえられない。デート商法は見た目よりもコミュニケーション能力が重要だ。カモに惚れさせ、高額な物でも買おうと思わせるには、それだけの手管が必要になる。こいつにそれはない。セリフが全部浮ついている。役者にも向いてねえわ。
そもそも今日の展開も強引すぎる。普通は数回デートを重ねて体の関係を期待させてから、店に連れてくるもんだろ。それを当日いきなり連れてきた。ふらりと立ち寄ってプレゼントをねだっているのか、「私がデザインしたジュエリーなんですよ、助けると思って買ってください」という流れなのか、その辺りもグダグダのまま商談に突入されたら対応に困る。普通はここでカモを逃がしてしまう。
しかし──。
そんな状況でも橋本が強引な追い込みに入ったのには理由がある。深網社のネットワークで回ってきたカモリストの押井の報告書にはKK、つまり「「候補者」候補」を示す符牒が付いていた。優先的にカタにはめ、哲さんの面談を受ける「候補者」に相応しいかどうか、支社長クラスの査定に回す必要があることを意味していた。
橋本は余裕を装いながら、押井の反応を見守った。首を縦に振るまで、何時間でも追い込み続けることになる。手間を掛けさせるなよ。
「……分かりました。じゃあ、それで」
橋本の内心が伝わったわけではないだろうが、押井は屈した。
この時、今日に至るレールが敷かれた。
*
査定役のブッさんは、通帳の受け渡しの段階で、押井を早々と見切っていた。
世の中は、支配する強者と支配される弱者に分かれる。こいつは弱者だ。強者に喰われて世の中を呪いながら骨になる運命だ。支配する側、しかも幹部「候補者」には、決してなれない。
このまま通帳を取り上げて帰らせ、俺たちとはそれきりだ。通帳は後日然るべきタイミングで、振り込め詐欺の入金先に使う。金は全額即座に引き出すが、当局に察知された時点で口座凍結され、こいつは犯罪収益移転防止法違反で逮捕される。その頃にはこの拠点はもぬけの殻だ。
目の前にいる押井の顔を見ながら、恨むなら自分の弱さを恨め、とブッさんは胸の内でつぶやいた。
その時、支社長席の机上に置いていたスマホが鳴動した。
「ちょっとごめんよ」
押井にそう言い置いて立ち上がり、スマホを手にとる。
哲さんからだ。ブッさんは通話ボタンをタップした。
「はい」といって、続く言葉を言い淀む。目の前に押井がいるのに、社内通称ではあっても自分の名を口にすることは憚られた。
「そうです、すみません来客中で。はい。えっ?」
ブッさんはちらりと天井を見上げた。つられて押井も目線を上に向ける。クリーム色の天井には染みが浮き出て、築年数の古さを思わせた。
「分かりました、客対応が終わったらすぐうかがいます。……はい……あー、そいつは」
こんどはブッさんの目線が押井に向けられた。先ほどまでの威圧の色はなく、押井は視線を受け止めることができた。押井が怖いのは、害意を乗せた視線だ。相手の意識がよそを向いていれば、怖くない。
「今、目の前にいます。まあ、俺の査定はふごうか……はあ……そうなんですか?」
ブッさんは押井に背を向け、顔を伏せて話を続ける。
「俺は、お勧めはできませんけど。ええ、そうです。──分かりました、そうおっしゃるのであれば、今から連れて行きます。はい、では」
ブッさんは画面をタップし、再び天井を仰いで、ふう、と息をついた。こんな奴に、哲さんの時間を取らせる価値があるわけがないだろう。それでも哲さんの気の済むようにするしかない。
「じゃあ、これから面接いこか」
ブッさんは押井に告げた。
「ぼくは帰っていいですか」
「なあに言ってんだよ、お前の面接だよ」
苛立ちを隠せず、自然と語調が強くなる。押井の目に怯えが走る。
「まあ黙って付き合え。終わったらすぐ解放するから」
哲さんも、直接こいつと話をすれば、見込みがないとすぐ分かるだろう──。
この時ブッさんは、そう思い込んでいた。
【続く】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
