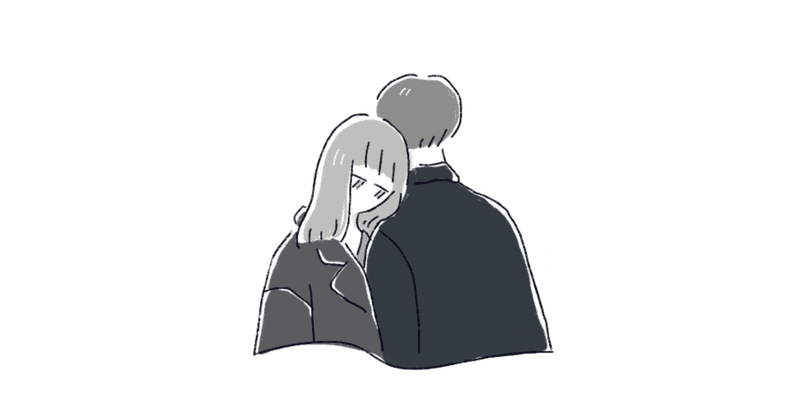
なんとなく好きで…
なんとなく好きで、その時は好きだとも言わなかった人のほうが、いつまでもなつかしいのね。
忘れないのね。
別れたあとってそうらしいわ。
その日は「しとしと」と冷んやりした雨が降っていた。私は末の娘を連れて雨宿りをしようと屋内遊技場に入った。おてんばの娘は遊具を見るなりパっと駆け出したので、「待って待って〜」と声をかけて私も急いで中に入った。
ふと、右側にある2〜3歳が遊ぶ背の低い滑り台に目を向けた時だった。
彼だ…。
白いTシャツにジーンズを着て、髪は茶に染めていたけど、毛先は色が抜けた短髪だった。力強い目元と雰囲気は中学時代のままだ。
彼は妻らしい人と彼の子どもらしい人と一緒にそこにいて、子どもが遊ぶ様子を腕を組んで優しいとは言えない表情で見つめていた。細身の妻は化粧気がなく活発な印象だった。
私が忘れられない人がそこにいる。
中学時代に出会った彼は田舎のヤンキーで、とても目立っていて、いつも可愛い女の子との恋の噂が絶えなかった。
それに引き換え私といえば、芋臭く、鈍臭く、勉強も運動も出来ないイジられるだけが取り柄の女だった。
そんな私たちの唯一の共通点は、2年間同じクラスで席が時々近くなり、テストの点数を見せ合って珍回答を笑い合う事だった。私が持っている文房具や少年漫画や音楽の趣味に共感してくれたりした。
そのやり取りがとても楽しくて、一緒に過ごす時間が好きだった。
彼を変に意識するようになったのは、3年の時に彼が私を避けるようになってからだった。
普通に話したいのに、彼は私を避け、睨みつけるようになった。
原因はわからなかった。
当時は好きだったのかも、嫌いだったのかも、何もかも曖昧だった。思春期の切なくて、苦くて、脆い…吹けば飛んで消える様な恋。
19歳の時だ。県外の専門学校に進学した私は、夏休みに地元の居酒屋に中学時代の同級生数人で集まって飲んでいた。そこに、彼と友達が乱入してきた。
私は胸の奥を刺されたような痛みを感じた。
その時も彼は私と目を合わせない。
代わりに彼の友達が私の隣に座り、こんな話をして来た。
「あいつ、お前のこと好きだったんだけどさ、俺が辞めとけって言ったの。あいつにお前みたいな芋はもったいねーもん。つーか、俺の友達がお前みたいなのと付き合うのはなんか嫌だったんだよね。」
「そうなんだ…」
そんな事しか言えなかった。胸の奥は更に痛かった。
芋には恋愛する資格無いってか…?
はっ。笑える。
何故こんな40も近くなった女が、子どもの時の恋を忘れられないんだろう…。バカみたいだ。
「あたし、あの人好きだったんだよねー。もう全然そんな気持ち無いんだけどさ」
なんて…言ってみたい。どんなに楽なのだろう…。
「好きだったよ」と言った瞬間に、きっと全て終わってくれる。嘘みたいに。消える…
そんな日を迎えられる事を…ずっと待っている。
こんな風に宙ぶらりんでいるから、いつまでも引きずっているのかもしれない。
彼と恋愛をしたいわけではない。
けれど、話したい。
「今,幸せ?」とか「今までどんな風に過ごしてきたの?」とか。
そんな事考えているうちに、遊技場から彼は姿を消していた。奥さんと子どもと出たのだろう…。
こんな風に時々偶然街で会うのは、実は初めてではない。これで5回目くらいだろうか。
全く合わない同級生だって沢山いるのに…。
彼とその家族らしき人の姿が消えて、ホッとしたような、拍子抜けしたような、悲しいような…なんともわからない感情を抱きながら、その30分後に、私も末娘と遊技場を後にした。
ある雨の日の…
まるで時空が歪んだ様な、雨雲が運んできた悪戯の様な…そんな日曜日の午後だった。
言葉にしないでいる時の何処か曖昧で混沌とした瞬間の恋の経験をきっと誰しもが持っていると思う。
それは心の中にそっと閉まってあって宝箱のように鍵をかけてあるのだけど、油断していると開いてしまったりする。
だから私は、ゆっくりと蓋を閉じて鍵をかける。
古ぼけて錆びついて行くのをひたすら待っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
