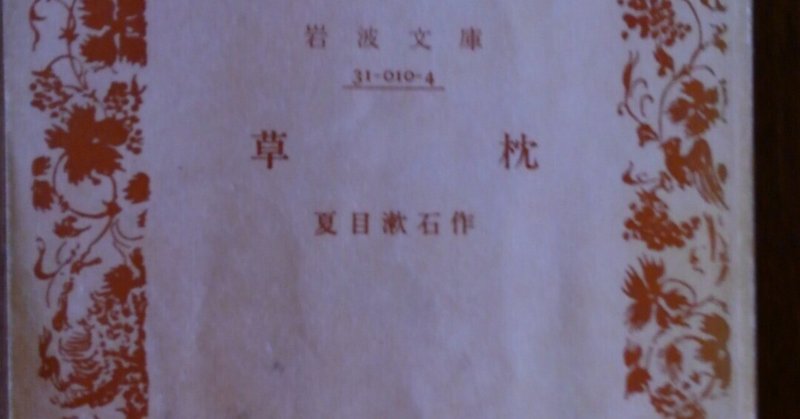
風の吹くまま、気の向くままに 4 (夏目漱石『草枕』から)
夏目漱石の『草枕』を読みました。小説の冒頭に「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画ができる。」との有名な文句があります。
作者の言わんとすることは、まさにこれに尽きると思います。けれども、これでは小説になりません。漱石は、自分を余という三十歳の画工を登場させ、この情景を実証しようとします。主な登場人物は、余の外には、出戻りの娘、那美と彼女の従兄弟の久一と離婚した夫の野武士のような男、それに父親と大徹和尚です。
余は、春のある日に非人情をしに旅に出るのです。山路をたどりながら、とめどなく俗世から隔絶の詩歌や絵画の美の境地を思考します。画工の心のうちは、古今東西の難解な語句にあふれており、それらを並べ立て、彼の心象を装飾します。それはとりもなおさず、周囲の装飾となり、美となった全体を、彼は鑑賞者の立場になって眺めるのです。
さらに言えば、膨大な知識の山に埋もれ、その隙間から俗世の点景を望見するのです。俗世の欲の中で、どろどろした人の関係から逃れ、平穏の心となるには、俗世から逃れるしかないと思いますが、その方法は、俗世から離れることであり、ひと時でもと思うなら、旅が良いのでしょう。
画工は、山の中の温泉宿「志保田」に投宿することになります。お客は彼一人で、そこには、出戻りの美しい娘、那美がおります。非人情の人となった画工に、失職した夫では贅沢ができないと逃げ帰った不人情の那美が周回します。
温泉宿の部屋で、画工が詩作を練っていると、開け放った襖の向こうを綺麗な振り袖姿の女が行ったり来たりしています。女が何度も何度も繰り返すのを、画工は凝然と見守るしかなかったのです。
画工は温泉宿の湯に入っています。彼は湯の中で思考をめぐらせます。 色々な思念の果てに、ミレーの水に沈んだオフェリアの絵に到ります。余は余の興趣で土左衛門の絵を描こう、だけど心に顔が思い浮かばないと思案します。そして今度は土左衛門の賛を作ったりします。どこからか三味線の音が聞こえてきます。
突然風呂場の戸が開いて誰かが入ってきます。三味線の音は止んでいます。女が風呂に入ってきたのです。小さき釣り洋橙の下ではよく見えません。湯煙の向こうに美しい女の裸体が揺らめきます。そんな場でも、画工は西洋画の裸体像は露骨すぎるとか、都会の芸妓の目録にある裸絵は見せんとの意が強すぎるとか知識の山の中から覗くだけで、対象の絵の中には入ろうとしません。女は「ほほほほ」と艶笑を残し風呂を出ていきます。
那美の父親にお茶のご馳走になります。相客は、大徹和尚と、甥の久一です。お茶を飲みながら、骨董好きの父親の蒐集物を見て談義します。穏やかで風雅な趣味の世界が展開します。この時、甥の久一が近々満州に出征することが分かります。
画工と那美が話をしています。那美は、振り袖姿で画工の部屋の外を行き来した訳を明かします。それは、画の先生が振り袖姿を見たいといっていたのを、峠の茶屋のお婆さんから聞いたというのです。そして、忘れっぽい人ねと責めます。それに対し、画工は風呂での出来事も親切からかと切り返します。
近くにある観海寺の鏡が池の話を持ち出し、那美は、近々その池に身を投げるかも知れないと冗談を言います。さらに続けて、往生して浮いているところを綺麗な画にかいてと懇願します。画工が返事も出来ないでいると、女は、驚いた?といい、部屋を出るとき振り返り、にこりと笑います。
鏡が池の縁におり、画工は絵の構想を練ります。池に浮く女を描くとして、その顔はと那美の顔を思い浮かべますが、それには「あわれ」がないと打ち消します。その時、池の縁の高い巌の上に女が現れ、池に飛びこまんとの勢いで向こうに飛び降ります。それを見て、画工は驚きます。
汽車の停車場で、出征する久一を見送っています。動く汽車の窓から野武士の顔が出ます。その時、眼があった那美が茫然として、「あわれ」の感情を面てに表します。それを見た画工はこの顔だと那美の肩をたたき、心の中で絵を完成させます。
不思議なことに、画工は、膨大な知識をもてあそぶだけで一枚の絵も描いておりません。山里の人たちの人情話も、夢幻の世界か、陽炎の様につかみどころがありません。それが非人情から見た美的な絵と思えば、画工の意図は達成されます。そして画工の心も平安です。それが画工の望んだ境地とすれば、旅の間のつかの間のことですが、満足となります。
画工は知識の山の中をさまようだけで行動に出ません。それが知識人の欠点と暗に比喩しているのでしょうか。画工の意識では、美の認識として、西洋のものよりは東洋にその価値を置いているように思われます。西洋文明の象徴たる汽車については、西洋に追いつけ追い越せの風潮の中でその非人間性を指摘し、こき下ろしています。憧憬と畏怖の意識が読み取れる気がしました。昭和の光景にもそんなときがあったんではなかったですか。
いずれにしても、この小説は、多様な意味を含んだ含蓄に富んだ作品と思いました。何しろ明治39年、漱石39歳での作品です。
参考文献:夏目漱石著『草枕』岩波書店1987年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
