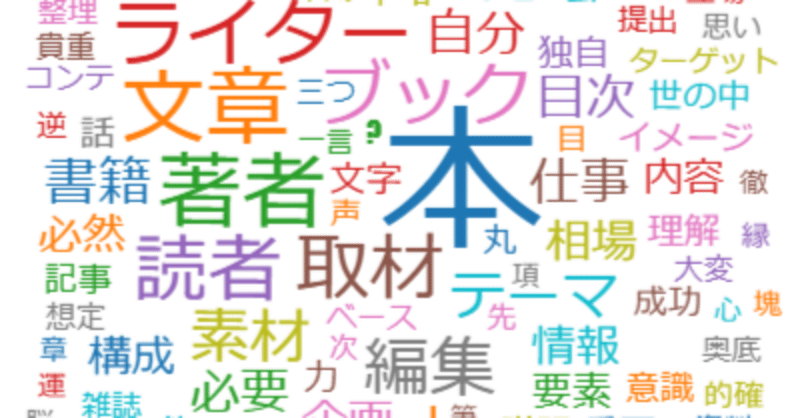
「職業、ブックライター。毎月1冊10万字書く私の方法」
「職業、ブックライター。毎月1冊10万字書く私の方法」(上阪徹 講談社)
フリーランスのライターの著者による、ブックライター(ゴーストライター)という仕事を紹介する本。有名人に取材をして、それをもとに本人の代わりに本を書き上げるという仕事にこれほど需要があるということにまず驚いた。この本の著者が「もともと書くことが得意でも好きでもありませんでした」(9ページ)と書いていて、それにも驚かされた。書き手としての立場だけでなく、出版社や編集者の立場を代弁して説明していたり、本を書く上での取材の方法や時間管理など、具体的な話がたくさん盛り込まれていて、非常に面白かった。
ブックライターには、文章力よりも、まず「聞かなければいけないことを著者からヒアリングできる力」「大量の情報の中から必要な情報を整理できる力」「読者を想定して的確な情報を的確な順番で伝える力」の三つが必要です。(8ページ)
面白い企画とは、どういうものなのか?
"相場"を知り、"読者"を想定する。これとほとんど同時進行で動いていくのが、担当する本をどんな本にするのか、という"テーマ"を深掘りしていくことです。(84-85ページ)
"相場""読者""テーマ"は、密接に関連しています。テーマを深掘りするときに、知っておかなければいけないのが、相場です。テーマとは、すなわち他の本と差別化できる要素であり、独自性のことだから、他の本がわかっていなければ、それは出てこない。逆にいえば、他の本がわかっているから、テーマを見つけられたりもするわけです。
では、独自性とは何かといえば、一言でいえば、その著者である必然性だと私は思っています。そのテーマは、その著者でなければならない、という理由があるかどうか。あるいは、そうした必然性がにじみ出る本にできるかどうか。書籍の企画が編集会議で通過するのは、そういう本なのではないかと私は思っています。その著者である必然性がある。つまりそれは、相場に対してテーマがはっきりできる、ということです。
面白い企画だったら通るだろう、という声が聞こえてくることがありますが、では、「面白い」とはどういうことか。それを理解しない限り、面白い企画は生まれないと思うのです。面白いとは、すなわち独自性があり、その著者である必然性があるということだと私は思っています。加えていえば、今世の中に求められているもの。だからこそ本を作るときには、本全体に、その必然性を貫かないといけないのです。そのためには、相場を知っておかなければいけない。現場の理解が必須になるのです。
そして独自性、必然性とは、経験や事実で語れるかどうか、ということだと思っています。だから、経験や事実をベースにした本にしなければいけない。つまり、経験や事実をどれだけ盛り込めるか、ということが重要になるということです。(86-87ページ)
本が売れるかどうかは、結果だと思っています。大事なことは、そんなことより、「いい本」を作ることだと私は考えています。まだ世の中にないと思えるような、読者の本当に役に立つ本が作れるかどうか。世の中に新しいメッセージを、新しい価値を発信していくことができるかどうか。著者が持っている貴重な情報やメッセージを、すべてうまく伝えきれるかどうか。著者やブックライター、さらには編集者の思いが詰まった本にできるか。私がいつも考えているのは、そのことです。だから、結果に一喜一憂したりはしません。いい本だったのに売れなかった、という考え方もしない。それは自分ではコントロールできないことだから。売れるかどうかは、運や縁やタイミングも大きいのです。私にできることは、「いい本」を作るということだけです。
一方で、書籍のマーケットや読者を信じている、というところはあると思っています。いい本を作れば、きっと受け入れてくれる、ということです。(89ページ)
読者にとって注目に値する素材があるのであれば、それだけで十分、本になりうる。逆にいえば、本を書くのだから文章力が必要だ、などと考える必要はないと思っています。それより大事なのは、素材であり、素材を見つけてくる力です。実際、「はじめに」で書いたように、ブックライターは、実は必ずしも文章力が問われる仕事ではない、と私は感じています。むしろ素材を集め、それを"相場"に照らし合わせ、"読者"をイメージしながら編集していく能力のほうが、はるかに重要だと思っています。(95ページ)
多くの場合、編集者が編集会議に提出した企画書があります。そこには、構成案、目次案が書かれていることが少なくありません。まずは、それにしっかり目を通しておきます。一方、多くの著者には、さまざまな資料があります。雑誌やネットのインタビュー記事だったり、講演で使ったスライドだったり、レポートや論文だったり、あるいは過去に出した書籍だったり。そうしたものは、すべていただいておいて、こちらも目を通します。そして、「これは今回の本に使えそうだな」「この話はしっかり聞いておきたいな」といった話をリストアップしておきます。その上で、企画のテーマについて、しっかり素材を引き出すためには、どんな取材が必要か。「取材のための目次」を作り上げるのです。これが先に書いた「取材コンテ」です。実際の目次とはまったく違うものでもかまいません。ひとまず聞きたいことを全部聞くには、どんなふうに聞けばいいのか、まさに「取材の構成」を考えるのです。このとき、資料から得た情報のリストアップも役に立ちます。(97-98ページ)
ブックライターとして、書籍の文章を書き進めていくときに気をつけているのは、著者の取材時の言葉を必ずしもそのまま使わない、ということです。そのまま使って読者にわかるものは構いませんが、そうでない言葉や論理展開がある。そういうときは、ブックライターが「翻訳」して読者に伝えてあげなければいけません。わかりやすく、読みやすく、というのが何より大事です。そのためには、ブックライターは著者が取材で言っていたことをちゃんと理解しておかないといけません。だからこそ、取材は重要なのです。
(中略)
そして一方で、ここはしっかり丁寧に説明をしてもらおう、というところは、きちんとカバーしておくことです。そういうとき、私は、とっておきのキラークエスチョンを用意しています。それが「もし、知識がほとんどない読者だったら、どんなふうに説明していただけますか?」です。(109-111ページ)
実はあの本は、編集者でもあり、フリーのライターでもあった、その若い担当編集者に向けて作った本でした。彼が雑誌の私の記事を見てくれて、どうすればこんな記事が書けるのか、教えてほしい、というのが、企画のスタートラインだった。ならば、彼に向けて本を書こう、と私は思い立ったのでした。そうすると、次々に「素材」が頭に浮かんできました。具体的に、こういう人に向けて、と思うと、内容は出てくるものなのだと改めて思いました。(121ページ)
また、すべての構成要素が揃う前に、見切り発車で書き始めてしまったのも、このときでした。ブックライターとして、他の著者の本を作るときには、これは絶対にやらないのですが、自分の本のときには有効だということがわかりました。書いているうちに、次のアイディアが浮かんできたりするのです。先に誰かとコミュニケーションをすることによって、脳の奥底に潜んでいる内容が表に出てくる、と書きましたが、もしかすると自分で文章を書いているうちに、何かの言葉がそうした奥底にある何かを刺激して、引き出してくれたのかもしれません。
素材がなかなか出てこないとウンウンうなるくらいなら、思い切って書き始めてしまう。書けるところからでいいので、書いてしまう。整理されていない状態で、ランダムなものでもいいので、とにかく書き始めてみるのです。自分の本なら、それもありだと思いました。(125-126ページ)
もしいつか本を書きたい、と考えているのであれば、その方向性に基づいて、少しずつ自分で素材を集めておくことです。可能であれば、素材をベースに文章にして書き留めておく。それはそのまま本には使えないかもしれませんが、間違いなく貴重な素材のひとつになります。その努力は、確実にいつか実ると思います。(127ページ)
本一冊書くのは大変だ、という思い込みを捨てれば楽になる
つまり、二五〇枚の一冊の本は、小見出しのついた五〇の塊からなっている、ということです。五枚といえば、二〇〇〇文字。二〇〇〇文字程度の構成要素が、五〇揃って、本はできているのです。いきなり二五〇枚書け、と言われたら「それは大変なことだ」と引いてしまうかもしれませんが、ひとつ二〇〇〇文字で五〇の構成要素を作りなさい、と言われたらどうでしょうか。(131ページ)
目次作りは、本の設計図である
・大きなテーマ設定を強く認識しておく
・著者を意識してみる
・読者を意識してみる
・共通項を見つける
・目次作りのキーワードを見つける
・カテゴリー分けする
・著者が伝えたいことを読者が最も受け入れやすいような流れを作る
・文章や文字ではなく、口頭で伝えるなら、と考えてみる
・自分の感情をヒントにしてみる
一番手っ取り早いのは、私が自著でターゲットを編集者に据えたように、誰か知っている人をターゲットにして、彼・彼女を頭に思い浮かべながら構成を考えることかもしれません。そうすれば、どんな順番でどんなふうに書いていけば、最も理解しやすいかが、イメージしやすくなります。
目次作りは、ブックライターの本作りにおいて、とても重要なプロセスだと思っています。この目次作りをおろそかにすると、実際に本を書き進めるときに、困ったことになってしまうのです。書く内容がはっきり定まっていないから、筆が止まってしまう。全体の内容のバランスが取れていないから、同じことを繰り返し書いてしまったりする。文章ボリュームの配分がうまくいかず、少な過ぎたり、多すぎたりしてしまう...。(155-156ページ)
要するに、しゃべっているように書けばいいのです。「文章」を書こうとせずに、自分がもし相手に、読者に話しかけて説明するとすれば、どんなふうに話すか。それをそのまま文章にしてしまえばいいのです。なぜなら、文章は伝えるためのツールなのだから。
実際、私は今もそうやって文章を作っています。「上阪さんの文章は読みやすい」と言われることがありますが、それは私が「話すように書いている」からだと思っています。無理に「文章」を作ろうとしていないのです。(164ページ)
できるだけ丸一日、書籍の原稿執筆のために空ける
私は基本的に、書籍の原稿を書くときには、丸一日か午後まるまるそれしかやらない、ということに決めています。朝、打ち合わせに行って、夕方取材がある。そんな日の、打ち合わせと取材の合間を縫って書籍の原稿を書く、ということはまずしません。なぜなら、きわめて効率が悪いからです。
書籍の原稿執筆には、かなりの集中力を必要とします。私は冗談で「著者のイタコになる」といったりしますが、「その本の世界」に入り込んで書く必要があると考えています。実際、たとえばひとつの章の内容は一気に書き上げてしまったほうが、まとまりも出ますし、勢いも出ます。情報の重なりなども意識しながら書き進めることができます。(171ページ)
編集者は、ブックライターの何に困っているのか
本書の作成にあたり、ブックライターに対して困っていることはあるか、編集者にヒアリングをかけてみました。まず、これは意外でしたが、取材がしっかりできるブックライターが少なくて困っている、ということでした。文章がそれなりに書ける、あるいは文章に自信を持っている人は少なくないけれど、取材がきちんとできない人が多い、というのです。
(中略)
編集者が困っていることの二つ目は、分量が足りない原稿が多い、ということでした。四〇〇字詰め原稿用紙換算で、二五〇枚から三〇〇枚くらいが、書籍一冊分ですが、原稿が上がってくると、このボリュームにまったく足りていない、ということがあるのだそうです。
(中略)
編集者が困っていることの三つ目は、スケジュール管理が甘い、ということでした。私は、どんな仕事でも、必ず締め切りを守ります。フリーランスになってから(会社員時代もそうでしたが)、これまで一度も締め切りに遅れたことはありません。ところが、少なくないブックライターが締め切りを守らない、という声が聞こえてきました。催促しないと送られてこない。連絡をしても返信が来ない。三日、四日程度ではなく、一週間以上、ひどいときには一ヶ月くらい平気で遅れたりする。(200-202ページ)
多くの人の印象として、文章を作ったりする仕事は「創造力」が必要な仕事だと思われているようです。しかし、私はそうは感じませんでした。「創造力」よりもむしろ「想像力」が求められる仕事だと思っていました。(225ページ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
