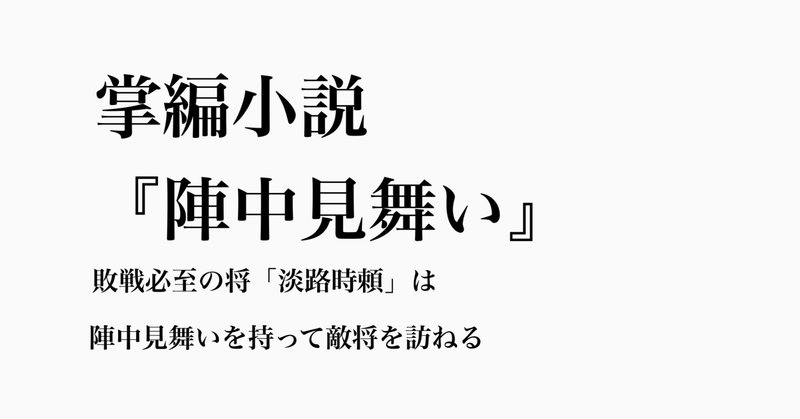
掌編小説『陣中見舞い』 1470文字
『陣中見舞い』
「斬らないで!古い知り合いよ・・・」
小将・片桐凍子(かたぎり とうこ)は腕を水平にかかげ、殺気立つ配下の動きをとめた。
白い陣幕の中で空気が揺れる中、信じられない、といった顔つきで参謀たちは侵入者に戸惑っている。
「どうやって、この本陣にまで潜入したの?」
そう問いかけられても、淡路時頼(あわじ ときより)は冷静にかまえていた。
「普通に歩いて来たさ。なんだこの陣の、警固の甘さは?」
あまりに豪胆な発言に、参謀たちはさらに言葉を失った。
時頼は、鎧も帷子(かたびら)も身につけず、護身のための刀すら帯びていない。旅の商人のような身なりだ。
壮麗なしろがねの帷子に身を包み、二本の刀を差している凍子とは対照的である。
椅子はないのか?と身振りで参謀にうったえると、出される木の箱に、よいしょっと腰をおろす。
「凍子、そう怖い顔をすんなよ、美人が台無しだぜ。ほら、陣中見舞いだ。お前の好きな『焼き握り』を持ってきたぞ」
指示台の上に彼がおいた竹皮の包みには、5~6個の『焼き握り』こと焼いた握り飯が入っていて、醤油が焦げた香ばしい匂いを放っていた。
参謀たちが、凍子に首を振っている。
「毒なんか入ってねえよ、そんなせこい真似をするわけないだろ」
時頼は、包み紙の中の焼き握りをひとつ、みずから無造作に頬張ると、片目を閉じてみせた。
凍子の口元が無意識にほころんだ。それは、子供のころから変わらぬ、彼の所作だった。
「しかし、一体どういうつもりだよ、俺の陣を2万の軍勢で囲うとは?こちらは、たかだか2百の兵だぜ?」
おどけるように両手を広げる時頼の態度には、何かを超越したものを感じる。
彼のもつ、独特の安心感すらおぼえる雰囲気。凍子は、この雰囲気につつまれて過ごした時期があった。
彼の傍らに、凍子は厳しい顔つきを崩さず、ゆっくりと歩み寄る。
「時頼、降伏してっ!私が、主上様に取り次ぐ。命までは取られないから」
凍子は、指示台を拳で叩くと、時頼をつよく睨みつけた。しかし、彼はのんきに陣幕の布や柱を眺めている。
「だから、そう怖い顔をするなと言っているだろう。早く食え、冷めるぞ」
時頼は焼き握りの包みを、凍子のほうへ押した。
「食べない・・・」
凍子は押し黙るようにうつむいた。
参謀たちがいるなかでも、お構いなしに時頼は話をつづけた。
「なつかしいだろ?焼き握り、あの庭でのことを思い出すぜ」
「・・・」
「明日にもお前は、王立軍では女性初の左中将軍・・か」
俺を見事に打ち取れよ、そう言いかけて彼の言葉は止まった。
下を向いたままの凍子は目をつぶり、首を左右に振る。
「もういいっ、もういいから!頼む時頼、降伏してくれ。降伏して・・・」
懇願するような彼女の声が絞り出された時、一匹のテントウムシが静かに焼き握りの包みに止まった。
時頼も凍子も、一瞬だけ、昔に戻ったような気がした。
強い日差し、緑の木の葉のなかを、ともにあの庭を駆けまわって遊んだ遠い昔に。
凍子は胸がおかしな感じになり、上手く息を吸えなくなった。
どうにか、息を吸い、そして吐き出した時、堰を切るように凍子の目から涙が溢れ出た。
流れ続けるものを拭かずに、指示台の包みに、乱暴に手を伸ばす。
焼き握りを手に取り、一気に口の中に入れた。
「かっ、辛いっ、ああああっ、うわああ!時頼、あんたって人はっ!」
凍子がうずくまると、参謀たちが慌てて駆け寄る。
「あははは!引っかかったな。これでまずは俺の一勝だな、明日は全軍を上げてかかって来い。凍子・・・先にあの世で待ってるぜ!」
笑い声だけを残し、いつの間にか淡路時頼は姿を消していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
