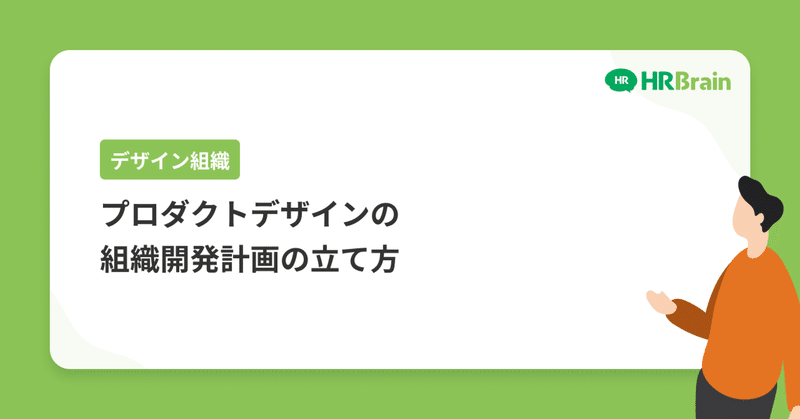
プロダクトデザインの組織開発計画の立て方
こんにちは。
HRBrainでプロダクトデザイナーをしています、あんどうです。
以前、チームの紹介の記事を書きましたが、この記事では事業と結びつけてプロダクトデザインの組織開発の計画をどのように立てているか?というのを自分の学びの振り返りも含めてお話ししようと思っています。
以下のような順序で組織開発の計画を立てていきましたので、それぞれごとに具体的にどのような思考プロセスをたどり、アウトプットとしてどのようなものを出したかをご紹介できたらと思います。
事業としての戦略と未来の想定
現状の情報収集・可視化
現状のデータに基づいて未来のデータを可視化し、差分検討
組織と役割の選択肢の検討
課題と打ち手の検討および実行
1.事業としての戦略と未来の想定
HRBrainが挑戦を続ける市場はHRの領域ではありますが、HRの領域でも業務ドメインは様々なものがあり、その中でプロダクト群が市場的にも沢山登場している状況にあります。
弊社も競合他社に漏れず、評価から始まってから新しい業務ドメインに染み出していっており、これからより多くの業務ドメインに対して新たなプロダクト群を提供していくマルチプロダクトの戦略をとっています。
その戦略に基づき、毎年複数個のプロダクトを立ち上げていくということが未来を検討する上での前提条件になります。
複数個プロダクトを立ち上げるということはその分の業務が発生するので、「時間」「人」「知識」「業務プロセス」が必要になります。これらの情報に関して未来をなんとなくの想定で作ることはできないので、現状の実態を把握する必要があります。
2.現状の情報収集・可視化
ここでは上記で挙げた「時間」「人」「知識」「業務プロセス」のうち「時間」と「人」「技術」に関して、現プロダクトデザイナーにインタビューを行います。
🔹プロダクトのボリューム感(時間と人の把握)🔹
平均開発規模で1ヶ月リソースをまるまる必要とする場合を1.0と置いた時に、自身が担当しているプロダクトがそれぞれどのくらいのボリュームか?
🔹プロダクトドメインとして重要なスキル群🔹
当該プロダクトドメインを担当する上で特に重要になるスキルをデザインプロセスから紐解いて3つ挙げてもらい、プロダクトドメインごとの必要ケイパビリティを定義
それぞれのメンバーにインタビューを30~45分程度行いながら、notionのデータテーブルを作成し、以下のような項目で収集したデータを可視化します。
リリース予定時期
プロダクトドメイン
プロダクト名
重要スキル
プロダクトボリューム
人数感
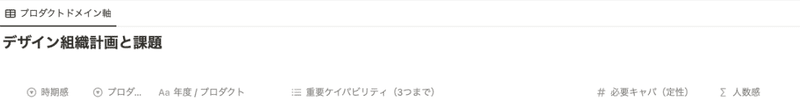
これらのデータを可視化すると、様々な切り口で現状を把握することができるので、それらも別々のテーブルで表現をしておきます。
重要スキル x プロダクトドメイン別でグルーピング
時期感 x 重要スキル別でグルーピング
3.現状のデータに基づいて未来のデータを可視化し、差分検討
ここまでデータを可視化すると、全プロダクトを跨いでの「平均ボリューム」「重要ケイパビリティ群」等が見えてくるので、戦略に沿って各プロダクトドメインにタイミングごとに、想定プロダクトを3年分配置していきます。
そうすると、現在の人数感との差分、未来の状態になった時の重要ケイパビリティの差分、プロダクトドメインごとで伸ばしていくべきスキル等が見えてきます。
見えてきたところで、より定性的なストーリーベースでの差分の未来を仮説として検討します。
未来と現在の差分がそのままで未来を迎えたストーリーを仮説として起こす
そこで起こる問題をリストアップ
問題に対して優先順位をつける
ここまで来ると、未来の状況の輪郭が見えてくるので、この未来の状態に対して「組織・役割・人」に関して、どのような選択肢を取ると、どうなるのか?を想定していきます。
4.組織と役割の選択肢の検討
自分が思うデザイナーが活躍する最も理想的な組織と役割の設計、事業として筋肉質な組織と役割の設計、事業と人がサステナブルに働き続けられる組織と役割の設計など、「組織・役割・人」の組み合わせのあり方は、組織の方針、フェーズによっても様々な選択肢があると思います。
自分は事業会社で働く一員ですので、プロダクト開発に従事する人として正しさの追求も大切にはしたいと思いつつ、以下のような観点を大切にして未来の計画の選択肢を考えます。
事業を効率よく伸ばすことができる
組織・事業の伸びに寄与してる実感を持てる
中長期的にサステナブルにみんなが働き続け、自分がどこに向かうか?を見据えられる
そんなに多くの選択肢はないですが、以下はいくつか検討した選択肢になります。
プロダクトデザイナーがデザインプロセスの機能を全般的に担保し、プロダクトドメインごとにデザイナーを配分する
デザインプロセスの機能ベース(UI/UX/リサーチ)で切り分けて、プロダクトドメインごとにデザイナーを配分する
リサーチのみプロダクトドメインを跨いで機能横断とし、プロダクトドメインごとに体験設計とUIデザインを行うメンバーを配分する
ここから更に、プロダクトの未来の状況になった際のコミュニケーションパスなども可視化した上で、大切にしたい観点を軸に一定の方針について決定をしていったという流れです。
5.課題と打ち手の検討および実行
ここまで来れば、「大きな組織と役割の方針」に対して「人数差分」「スキル差分」「時期要因」「ストーリーとしての問題」など、様々な材料が揃ってくるので課題を定義し、課題を解決するような打ち手を検討し、一定期間実行をしていきます。
弊社で立てた課題と打ち手を一例としてご紹介します。
🔹課題🔹
ひとりひとりのケイパビリティの拡大
🔹施策🔹
1. スキルのセットに基づく人材モデルの言語化
2. キャリア意向のヒアリング
3. パフォーマンス&キャリアセッションの定期開催
🚩 結果
頭の中にこうした流れをイメージしながら、半期の初めに様々な情報を収集しては計画を立て、適宜プロダクトデザインメンバーに情報共有をしていきました。
特に現状と未来の差分をリアルな数値として、みんなに展開していくことで、全員の目線が危機的な未来をどう避ける?という視点で目線が合うのは効果的だったと思います。
🎀 結び
自分の経験の棚卸しをしつつ、プロダクトデザインチームとして、こうした考えに則って事業・組織・人の成長に向き合って実行に落とし込むような行動を取っていますというご紹介でした。
こうしたことをお話しするのに興味がある方がいらしたら、ぜひ一度お話しできたらと思います👋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

