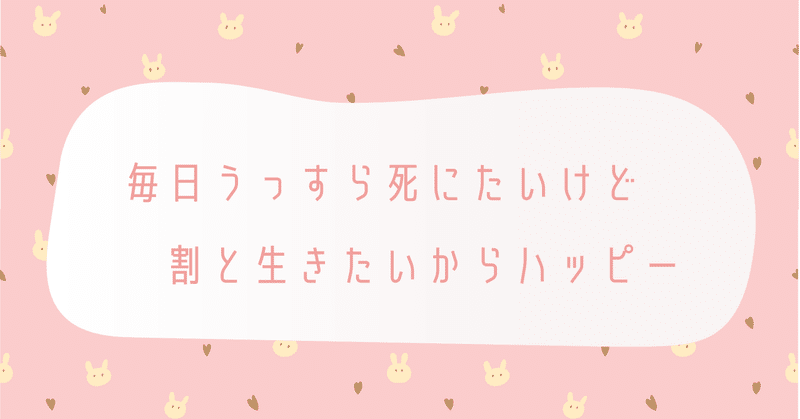
15.まともな人間でいるために、私はダンスを忘れた。
「今日から新しい女の子が入ったんだけどね」
土曜の昼下がり。マグカップを傾けながら花梨が言う。バレエスクールで講師補佐のアルバイトをしている花梨は、ときどきバイト終わりに私の家でお茶をする。
「ピルエット回るのもいきなりはできないじゃん? だからゆっくりゆっくり回ってもらったんだけど、それだけで目え回しちゃってさ」
「はは」
私はかりかりとマグカップのふちを爪でひっかきながら笑った。ずいぶん三半規管の弱い子だ。私も人のことは言えないけど。
「なんかみけこもそうだったなーって思い出して。初めてピルエットの練習したとき尻もちついたでしょ」
「いつの話だよ」
「浅田先生も覚えてたよ。みけちゃんみたいだねって」
「えー」
私は半笑いでマグカップをひっかきながら視線を反らす。リビングでは、母が柚の面倒を見ていた。最近柚は立ち上がって2、3歩歩くようになったから目が離せないのだ。みぃの姿は見えない。花梨が続ける。
「それで浅田先生がね、みけちゃん元気かなって」
元気か、と問われれば、何と返すのが正解かわからない。
視線を伏せた。浅田先生。私と花梨のバレエの先生で、今は花梨のバイト先。私たちがバレエを始めたのは幼稚園のときだ。花梨はそのままずっと続けてきたけれど、私は高校のときにやめたからもう6年以上会っていない。
もう、6年以上も踊っていない。
「ねえみけこ。もうバレエやんないの」
花梨が言った。懐かしむような声だった。私は愛想笑いで「もう踊れないよ」と言う。
「そんなことないでしょ。踊れるよいつんなっても」
「でももう体もばきばきでさ。絶対無理」
踊れるはずがない。就職もできず、収入もない身でどこから月謝をひねり出すというの。幼稚園のころから育ててくれた第二の母みたいな浅田先生に、今更どの面下げて会いに行くの。一度踊ることを忘れた足で、どうやってステップを踏むというの。
花梨は不満そうな顔で私を見ていた。それからにっと笑う。
「先生、みけこが来てくれたら喜ぶと思うからさ。またいつでもおいでよ。私も先生も待ってるよ」
そう言って立ち上がって、花梨は「帰ろうか柚」とリビングのほうに声をかけた。私も立ち上がってリビングを見る。やっぱりみぃの姿は見えなかった。
花梨と柚を見送ってから自室へ行くと、みぃはだらりとベッドに大の字になっていた。
「ここにいたの」
私は冷房をつけながら言った。少しずつ秋の気候に近づいてきた気がしなくもないが、いまだ冷房なしではすごせない。みぃは横たわったまま言う。
「花梨がさ、バレエ教室の話始めたでしょ。だからみけこの機嫌が悪くなるかなと思って逃げてきた」
「なんでよ」
バレエ教室の話が楽しくないのは事実だ。だけどその程度でみぃに当たったりするほど不機嫌にはならないし、第一、人前でみぃに当たることなどありえない。
「だって機嫌悪いみけこ見てたらこっちまでテンション下がるもん」
そう言われると返す言葉はなくて、私はすこし口ごもった。すると効き始めた冷房の音がやけに響いて、私の心臓のあたりをとみに冷たくした。
痛かった。
「みぃは、もう踊らないの」
するりとそんな言葉が滑り出た。驚いたのは私だ。みぃは驚きもせず、ひ、と唇をゆがめた。
「おまえがそれを言うの」
ベッドに横たわったまま、みぃは言った。唇だけで笑って、瞳は無感情に私を見ていた。寝返りをうちながら、続ける。
「あたしの手足をばきばきに折ったのはおまえなのに」
瞬きのあと。ベッドの上に横たわっていたのは、糸の切れたマリオネットのようにあっちこっちに手足の曲がった子どもだった。
「あ」
「あたしは踊りたかった。ずっと踊ってたかった。おまえが折ったの」
私は膝をついた。ずりずりとベッドまで這いよって、みぃの腕を掴んだ。持ち上げれば、だらりと垂れる。
そうだ。たしかに、私が折った。
かつての私は、踊ることが大好きな子どもだった。教室でも、家の中でも、人目を気にせず踊っていた。だけどそれが「まともじゃない」ことに気づいて、私は人前で踊るのをやめた。そのうち勉強のためにバレエそのものをやめてしまった。
踊ることは自由でいることだったのだ。だけど私はそれを捨ててしまった。いい大学に入って、いい企業に就職して、「まともな大人」になるために、ダンスは邪魔だった。だから捨てた。
大学生のころだ。みぃが私の前に現れてからそんなに日が経っていなかったと思う。ダンスを捨てた私の前でみぃがあんまり自由に踊るから、それが目障りで、許せなくて、私はみぃの手足をばきばきに折った。
それ以来、みぃは踊らなくなった。今に至るまで、ただの一度も。
感情のない瞳で私を見つめるみぃの前で、私はベッドに顔を伏せた。目が熱くて、何かがこぼれようとして、それを我慢しようとするとぎゅっと目頭が痛かった。喉の奥も。でも一番は、心臓のあたりが。
『ねえみけこ。もうバレエやんないの』
できるはずがない。だって私はみぃの手足を折った。そうすることで、私は私の人生からダンスというものを葬り去ってしまった。
ダンスは自由だった。ありのままのあたしでいる、ということだった。だけどまともな人間でいるために、私はダンスを忘れた。忘れた、くせに、結局まともな大人にも成り損なって、こわれたマリオネットみたいにただ地面に横たわっている。だから浅田先生に、合わせる顔なんてなかった。
衣擦れの音がした。みぃが体を起こした音だろうか。この子どもはユーレイみたいなものだから、手足が折れていようと本当は関係ないのだ。
「みけこは馬鹿だね」
みぃが言った。私はなにも言わずベッドを濡らし続けた。
「あたしは踊りたいよ」
私だって、という言葉を飲み込む。私には、どうしてもその一言が言えなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
