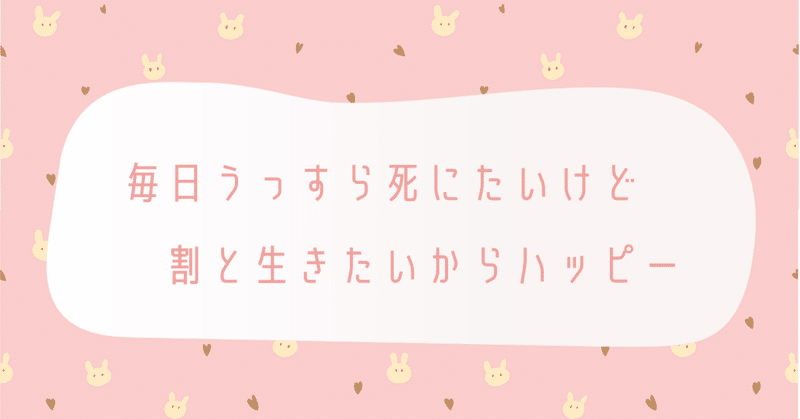
12.このおさなごは駆けるように人間になっていく。【掌編小説】
おさなごがじっと、大きな瞳で私の爪を見つめていた。
「ゆずちゃん、気になるの」
たずねてもうんともすんとも言わない。まだ言葉がわかる歳ではないから当然だ。もうすぐ一歳になるおさなごは、何も言わず私のエメラルドグリーンの爪を見つめた。
このおさなごも「爪に色がついているのが不思議」とわかるようになったのだなあと思うと、不思議な気持ちがした。
おさなごが私の前に現れたのはちょうど一年ほど前、秋の始まりだった。ふたつ年上のいとこの子ども。柚と名付けられたその子は、私にとって初めての「あかちゃん」だった。首も座らないふにゃふにゃの小さな塊を抱っこしたとき、あんまり怖くて腰が抜けそうになったのをよく覚えている。だって赤子というやつはどこもかしこも柔らかくて、小さくて、ちょっと間違えたらぺしゃんこになってしまいそうだった。
赤子が怖かった。もろい花のようで、言葉の通じない怪獣のようで。宇宙人みたいな大きな瞳に見つめられたり、抱っこした途端にぎゃんぎゃん泣かれたりすると私はびっくりして、大きな音を聞いたイヴみたいに跳びあがってしまうのだった。
違う生物のようだった赤子は少しずつ、人間に近づいていった。首が座って、寝返りをうてるようになって、はいはいできるようになって、歯が生えてきて。そのたびに私はびっくりしてへにゃへにゃの悲鳴を上げたり部屋の中をぐるぐると徘徊したりした。
あまりにも違う生物だったから赤子が怖かった。だけれど今度は、おさなごがどんどん人間に近づいていくことが怖くなった。だって私はまだ人間のなりそこないのままモラトリアムを続けているのに、このおさなごは駆けるように人間になっていく。いつか、そのまま私を追い抜いていってしまうのではないかと思った。
助けてくれ、と言ったっておさなごはどんどん大きくなっていく。先月までは私の爪を見ても何もリアクションをしなかったのに、今は私のエメラルドグリーンを瞳がこぼれそうになるまで見つめている。
「ゆずちゃん、ネイルに興味あんのかな。おませさんだね」
私の恐怖などどこ吹く風でみぃが言った。「見て見て、私の爪も緑だよ」と柚の前に自分の両手をひらひらさせるけれど、当然柚はそちらは見ない。それでちょっとみぃはふてくされて、柚のそばを離れてイヴと遊び始めた。私も気まずくなって自分の手を引っ込める。それで柚も興味を失ったようにおもちゃに視線を移した。
そのとき玄関の開く音がして、「ただいまあ」という声が聞こえた。すぐにリビングのドアが開かれ、声の主が姿を現す。
「ありがとみけこ。柚いいこにしてた?」
「おつかれ、花梨。いいこだったよ」
柚の母親の花梨は専業主婦だけれど、アルバイトでバレエスクールの講師アシスタントをしている。それで月に何度か、私のうちで柚を預かるのだ。花梨の両親は共働きだし、花梨は義母とはあまり折り合いが良くない。その点うちは私が必ずいるし、仲もいい。
「お茶でもしていく?」
「んーん、今日は宅配便の受け取りしなきゃだからすぐ帰る」
言葉通り、花梨はさっと柚を抱き上げた。それから思い出したように言う。
「もうすぐ柚の誕生日でしょ。うちで誕生日会するの。うちの両親呼ぶだけの小さいやつだけど。みけこも来る?」
「あ、いや、私は」
花梨とは幼いころからの付き合いだけれど、花梨の両親とは最近会う機会もなくてあまり親しい間柄とは言えない。花梨の夫とはほとんどしゃべったこともない。人が怖いというのに、そんな人たちが集まる場所に行けるわけがなかった。
それに、誕生日会ということはこのおさなごが着々と成長している証だ。私はやっぱり、それが少し怖い。
「来ないの。なんでえ」
「ごめん」
こわばる顔を見られたくなくて眼鏡の位置をなおす振りをした。すると花梨はあっと目を丸くする。
「みけこ、爪きれいな色だね」
「あ、ありがとう」
反射的に両手を差し出してしまう。すると花梨に抱かれた柚が小さく声を発しながら、私の爪のほうに手を伸ばした。花梨が笑う。
「柚もネイルしたいの? 大きくなったらみけこちゃんにネイルしてもらおうね」
その言葉に、不思議な感情が胸に広がるのを感じた。
大きくなったら。その言葉を聞くのはどこか怖い。この子が私を追い抜いていってしまうのではないかと思うから。だけど、この子が大きくなって、それでももし私が何かこの子にしてあげられることがあるとするなら。私がこの子にあげられるものがあるなら。それはそんなに、悪い響きじゃない気がした。
思わず私も笑う。ぷくぷくの小さな指が私の爪に触れた。あたたかい指だった。
そしてその指が勢いよく、私のエメラルドグリーンの爪を剥ごうとした。
たしかに。色がついていないはずの場所に色がついていたらおかしいと思うだろう。はがれるのではないかと思っても無理はない。幼さゆえの無垢さ純粋さでその疑問を実行に移すのもさもありなん。首尾よくはがれたら自分のコレクションに加えてやろうとか思っているのかもしれない。それはむしろ光栄なことだ、純真なおさなごにとってもこのきらきらした爪は「きれい」ということなのだから。
ここは大人として広い心で受け入れてやるべきだ。受け入れてやるべき、なのかもしれないが。
爪をはがされそうになったら防衛本能で大声が出るのも、またさもありなん。
「ゆずちゃん! それ! はがれないから!」
「あっはっは」
昼下がりのリビングに、私の絶叫と花梨の笑い声が響いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
