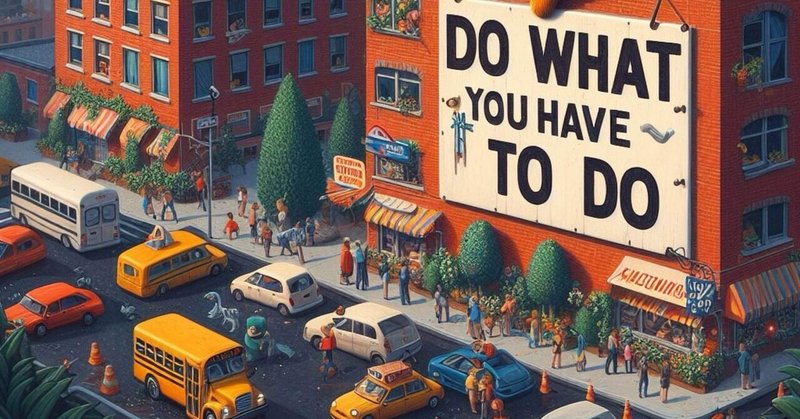
己が為すべきことを為せ
先程読み終わった本は清宮克幸氏の「最強のコーチング」である。
筆者がラグビーの監督ということで、例えがほとんどラグビーのプレイなので、ラグビー経験者以外は正確に例が理解できないという致命的な欠陥がある。
私はたまたま高校大学とラグビー部だったので(たいしたプレイヤーでは無かったが…)理解できたものの、それ以外の人からしたらよく分からない本だと捉えられても仕方がないかもしれない。
言ってることはいいことだと思うんだが、例が理解できなければ薄っぺらい主張だと思われても仕方がない気がする…
さて、今回は読んだ本と関係する様なしない様な話題である。
「己が為すべきことを為せ」
これは、私が仕事やプライベートも含めて、一種のスローガンとしている言葉である。
自分が置かれた環境、与えられた役割、それに加えて自分の能力と意志を鑑みて、自分のするべきことを分析して、実際に行動に移そう、というものである。
私自身がそれをやり切れているかは、まだ自信を持っては言えないものの、それを目指して日々過ごしていかなければならないと考えている。
初任研修終わって早々に部下を持ったものの、それ以降は中々部下を持つ機会には恵まれない職場を渡り歩いて来た。
しかしながら、そのうちまた部下を持つこともあるだろうから、この言葉を部下にも要望したいと思っている。
さて、実際にはこれはどうやって実現するものなのだろうか?
既に書いた部分が本質であるものの、少し細かく見ていこう。
まず、自身が置かれた環境の分析である。
例えば職場の環境であったり、上司が求めている事項、職場の同僚や部下の能力や適正、考え方、場合によっては顧客の特徴や関連会社のニーズなど、仕事の面では仕事に関わる全ての要因を分析の対象にする。
加えて、自分の家庭環境やプライベートなども考慮に入れると、自分の人生全体のプランニングに役立つだろう。
昔はお仕事第一主義が一般的であったが、今の時代はワークライフバランスの世の中なのである。
自分が何かをする上で、関係する物事をしっかりと把握するのがこの段階である。
次に考えるのは、自分に与えられた役割である。
本当に自分がやらねばならないことを考える前提として、他律的に求められる役割を確認しておく必要がある。
自分が属している組織の社会的役割やビジョン、自分の部署の組織における役割や機能、自分自身の現在のポジションに与えられている役割や上司から与えられた業務などを網羅的に把握する。
次に考えるのは、自分の能力と意志である。
自分の能力は、生来的な能力と、その後の経験や学習によって得た能力とがある。
もちろん、資格なんかも能力と考えて良い。(もっとも、資格だけ持っていて関連実務ができなければしょうがないが…)
それらの能力を合わせて、能力は更に2つに区分できる。
顕在能力と潜在能力である。
顕在能力とは、その能力を保有していることを本人が自覚している能力のことである。
一方、潜在能力は自覚なき、まだ発現していない能力のことである。
基本的には自己の能力を自覚する上では、潜在能力への淡い期待は捨てて、顕在能力で分析するのが適切である。
「俺には秘められた力がー!まだ認められてないし、自覚もできてないだけなんだー!」とか言っても、現実問題としてその能力を使えなければ仕方がないのである。
一方で、顕在能力だけでやっていける業務だけをやっていては成長がない。
あまり期待するものではないが、自己成長のために顕在能力以上の課題にチャレンジすることで、潜在能力が発現するかもしれない。
また、必要に応じて能力開発をすることも求められるかもしれない。
意志については、将来的にこうなりたい、こうありたいという目標に向かって、今目の前の業務に向き合うことと、今の業務をこう進めたい、こういう形に持っていきたい、といった目先の意志に大別される。
仕事にポリシーを持て!とよく言われる部分である。
さて、それらを踏まえて、自分のするべきことを分析していこう。
周囲の状況や向かうべき方向、自分自身の現状と将来のありたい姿までハッキリしたので、改めて目の前の課題に向き合ってみよう。
その課題は組織としてどの様な価値を持った課題なのか?
その課題は自分の能力で対応ができるのか?
その課題を効果的に進めるために、頼ることのできる人は組織の内外にいるのか?
また、どうすれば協力を得られるのか?
その課題の解決を通じて、自身の目指す姿に近づける成長ができるのか?
その課題を解決するための資源は確保できているのか?
できていないとすれば、どうやって確保するのか?
又は代替策を講じるのか?
その課題の優先順位は?
優先順位が低いならば、誰かにやってもらえたり、着手を後回しにできるのか?
同じ、ないしは少しの追加の労力で、もっと大きな成果が出せるのではないか?
出せるとすれば、その方法は?
より良い成果を得るために、もっと巻き込める人や組織がいるのではないか?
その課題を解決しつつ、プライベートと両立することはできるのか?
検討事項は沢山あると思うが、それらをしっかりと踏まえて分析していこう。
当然のことながら、この分析は当初のみならず、実際の行動に移した後でも引き続き実施することになる。
何故なら、状況は行動している間にも変化し続けるし、検討の段階では認識できていなかった問題にブチ当ることも珍しくないからである。
自分のすべきことが定まったならば、それを実行に移そう。
優先順位をつけ、関係者と常に連携を取りながら、必要に応じて上司などにも報告をしつつ、的確に業務を遂行していこう。
崇高な計画だけ立てて満足するのは、ただの意識高い系である。
実施して、成果を出して初めて価値が生まれるのである。
やってみたはいいものの、なかなか成果が出ない時もあるだろう。
そんな時には、試行錯誤しつつ、場合によっては他の人の力や知恵を借りて、しっかりと課題を解決していってもらいたい。
また、この考え方を持った組織を作り出せれば、悪しきセクショナリズムからの脱却ができると考えられる。
組織とは、ただの寄せ集めの集団とは違うのである。
組織に属する個人は、何らかの役割を果たすことを期待されて、その場にいるのである。
人に決められたことだけをやっていれば、それはまさに歯車だと言えよう。
最近では、言われたことだけを最低限こなしていればいいや、と言う人の少なくないという。
それはそれでひとつの考え方ではあるが、それだけでは面白くないのではないか?
当然与えられた役割を果たすことは大切である。
ただ、しっかりとその与えられた役割の中で、自分自身で的確に分析して得られた、本当の意味での自分の果たすべき役割を果たせた時、自身をより高みに持っていくことができるのではないだろうか?
また、全体を見渡した上で、自分でやるべきことを定めて行うことで、組織として有機的な連携を確立することができると言えるだろう。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
