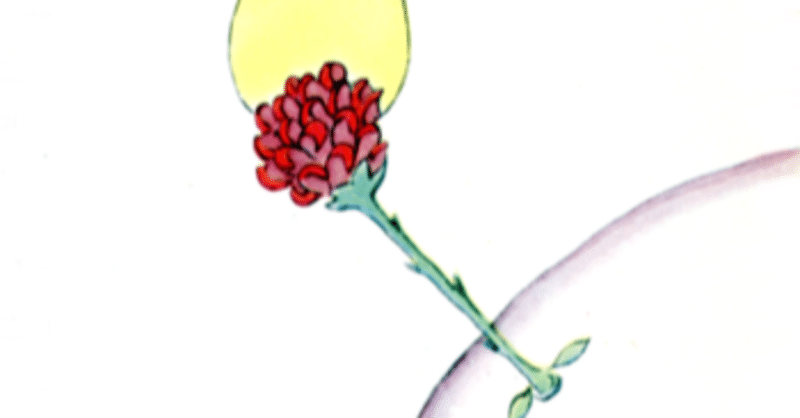
ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.4
Ⅶ
五日目。やっぱりヒツジのおかげで、ちっちゃな王子さまの人生の秘密がもうひとつ明らかになった。
王子さまが何の前ぶれもなく唐突に、それまでじっとだまって考え込んでいたことについてぼくに質問してきたんだ。
「ヒツジがさ、小さな木を食べるんだとしたら、もしかして花も食べる?」
「そりゃそうだよ。ヒツジはぶつかったものをなんだって食べちまうよ」
「トゲがある花でも?」
「ああ。トゲがある花だって同じさ」
「だったらトゲは、いったい何のためにあるの?」
そんなことは知ったこっちゃなかった。ぼくはそのとき、かたく締まりすぎたエンジンのボルトを外すのにいっぱいいっぱいだった。もしかしてこの故障がひどく深刻なものなんじゃないかと感じはじめて焦っていたし、今にも底をつきそうな飲み水は、ぼくに最悪の事態を想像させてもいた。
「ねえ、トゲは、何のためにあるの?」
ちっちゃな王子さまは、一度たずねた質問を絶対にあきらめない。ぼくはボルトのせいでいらいらしていたから、でたらめに答えた。
「トゲなんて何のためでもないよ。あんなのはただの、花の嫌がらせさ!」
「ええっ!」
王子さまは少しだまり込んだ後、ぼくにうらみがましい視線を向けてきた。
「信じらんない! 花ってのはか弱いんだ。すごくデリケートなんだよ!きっとあの子たちはできるかぎり安心したいにちがいないんだ。自分のトゲのことでさえおそろしく思っているんだ……」
ぼくは何も答えなかった。ちょうどその瞬間は、(もしこのボルトがまだ外れないようなら、かなづちで一発ぶん殴ってやるぞ)なんてことを考えていたところだったからだ。すると王子さまは、またしてもぼくの考えをさえぎった。
「なのに君は、君はそんなふうに考えるっての? 花たちが……」
「ちがうちがう! ぼくは何にも考えちゃいないよ! あのね、ぼくは、今忙しいんだよ。そんなことよりずっと重要なことで、頭がいっぱいなんだよ!」
王子さまは、あきれた顔でぼくを見つめた。
「ずっと重要なことだって?!」
王子さまの目には、かなづちを手にして、指を油で汚し、彼にとってひどくみにくく見える物体の上にかがみこんでいるぼくが映っていた。
「君の話し方は、まるで大人みたいなんだね!」
その言葉にぼくはハッとして、少し恥ずかしくなった。だけど王子さまは、手厳しくこう続けたんだ。
「君は何もかもまちがえてる……ぜんぶごっちゃにしてるんだ!」
王子さまは本当に本当に怒っていた。黄金色のその髪が、ゴウッと逆立つくらいだった。
「ボクの知っている星にね、『赤おやじ』ってよばれてる人がいたんだ。その人ときたら、花の香りをかいだことも、星をながめたことも、だれかを愛したこともなかった。足し算以外、何ひとつしたことがなかったんだ。毎日毎日、君みたいに顔を真っ赤にして『ああ、私はマジメな人間だ! 私はマジメな人間だ!』ってくり返してはいつもいばり散らしていたんだよ。
あんなのはね、人間じゃない。あんなのは、キノコだよ!」
「えっ、なんだって……?」
「キ ノ コ !」
ちっちゃな王子さまは今や、怒りのあまり真っ青になっていた。
「何百万年も前から、花たちはトゲを生やしてる。そしてやっぱり何百万年も前から、ヒツジは花を食べてるんだ。なのに、どうして花たちがこわい思いをしてまで何の役にも立たないトゲを生やし続けているのか、ってことを知ろうとすることが重要なことじゃない、って? ヒツジと花の戦いなんて大切なことじゃないって言うの? 太っちょ赤おやじの足し算なんかよりも重要で、大事なことではないって、君はホントにそう思うの?
もしボクが……ボクがね、世界中でたった一つだけの花を知ってたとするよ。それはボクの星以外のどこにもないものなんだ。それが、もしかしたら、ある朝ボクが気づかないうちに、ちっちゃなヒツジ一匹にあっという間に絶滅させられちゃうかもしれないってのに、それが、そのことが……大切なことじゃないって?!」
王子さまは今度は真っ赤になって続けた。
「だれかが、何百万の星の何百万の花たちの中のたった一つだけの花を愛していたとすると、その人はその何百万もの星を見つめるだけでしあわせを感じられるんだ。『ああ、このどこかに、私の花があるんだ……』って。 だけど、もしヒツジがその花を食べちゃったら、その人にとっては、ぜんぶの星がいっぺんに消えちゃったみたいなものなんだよ! それでもそれが、大切じゃないの?!」
もうそれ以上は何にも言えなかった。破裂するみたいに、ワーッと泣き出しちゃったからだ。
いつの間にか、夜があたりを包んでいた。
ぼくは手に持っていた工具を放り捨ててしまった。かなづちもボルトも、のどのかわきも、死さえもどうでもよかった。
いまここに、この星に、ぼくの故郷である地球の上には、ただ、ちっちゃな王子さまをなぐさめるということ、それだけがあった。
ぼくは両腕で王子さまを包みこんだ。そしてゆっくりとゆらしてやった。
「君が愛している花は、大丈夫だよ……そうだ、ぼくが君のヒツジに、口輪を描いてあげるから……君の花を守る覆いも描いてあげる……それから、ぼくがね……ぼくが……」
もう、何を言えばいいのかわからなかった。自分がひどくもどかしかった。どうしたらあの子の気持ちにたどりつけるのか、共有できるのかがわからなかったんだ……あの子の涙がつくり出す世界は、本当に神秘的なものなんだよ。
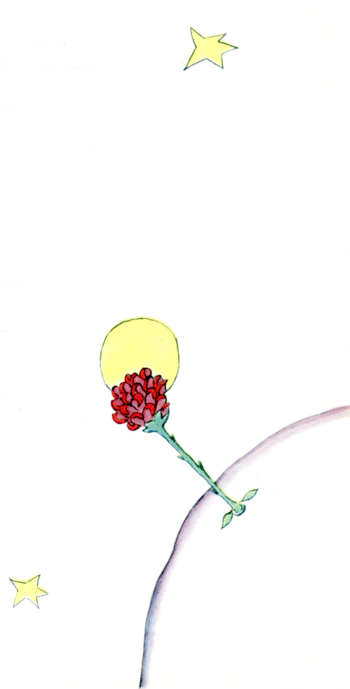
文章を読んでなにかを感じていただけたら、100円くらい「投げ銭」感覚でサポートしていただけると、すごくうれしいです。
