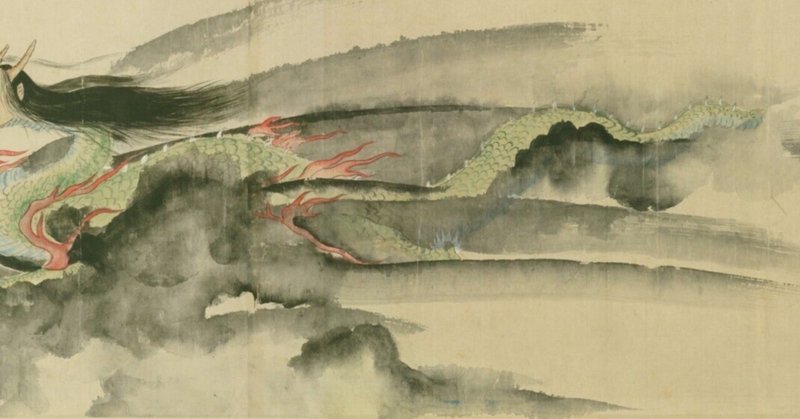
秘められた暗い恋 『摂州合邦辻』と「野崎村」 [近藤史恵『二人道成寺』文藝春秋/2004]
『摂州合邦辻』をモチーフとしているということで、近藤史恵のミステリ小説『二人道成寺』を読んだ。
歌舞伎界で起こる事件を調査する私立探偵“梨園の探偵”今泉文吾が登場するシリーズのひとつで、本作では、人気若手女方役者の妻が、夫の不在中に自宅の不審火に巻き込まれて意識不明になり、そのまま昏睡状態が続いているという事件をめぐるストーリーになっている。
題名のイメージからは「道成寺」の話なのかと思われるが、実際には『摂州合邦辻』、『新版歌祭文』野崎村が重要なモチーフになっている。
物語の発端では、対極的な若手の女方役者2人−−亡き大御所の華やかな御曹司と、養成所出身の実力で人気を得た役者−−が、偶然にも同時に『摂州合邦辻』の玉手御前役を演じることになったことが描かれる。
ただ、芸道小説ではないので、『摂州合邦辻』とは何か的なことを期待しすぎると外れる。それぞれの役者がどういう考えで玉手御前に取り組み、どう演じるか、それを通してどう成長するかというような芸道物的な精神面は描かれない。
また、本作では、登場人物が、『摂州合邦辻』、あるいは「野崎村」の登場人物になぞらえて配置されている。それが1対1で対応するのではなく、何重にも写し取られ、転換されていくのというのは、アイデアとしては面白い。ただ、あくまで著者が捉えている『摂州合邦辻』と「野崎村」なので、それがうまくいっていると取るかとうかは、著者の考え方(演目の捉え方)自体を読者がどう感じるかによるだろう。
個人的には、本作は、伝統芸能ものを一般エンタメに供するにあたって、どういう工夫がありえるのかということの勉強になった。
歌舞伎物の一般向け小説は、時々見かける。しかし、モチーフとしては、リアリティラインの設定が難しそうだなと思う。歌舞伎に関心がない、あるいはまったく観たことがない人が抱いているイメージと、歌舞伎が好きで、頻繁に観にいく習慣がある人の実感とでは、ズレが大きいのではと思うからだ。現実の役者をモデルにする・しないの問題もあるし。
本作では、歌舞伎役者については、「歌舞伎にまったく関心がない、あるいは観たことがない人が抱いているイメージ」の方向にかなり寄せているように感じた。「なんか格調高そう」「なんか敷居が高い」というイメージをうまく使っており、ふわっとした“お高い”感じをふわっとしたままにしておくことで、あくまで読んだ人のイメージの範囲で受け取れるようになっている。役者の人物像から生身感は排除され、類型的な人物像に造形してある。そのため、若手設定のわりに、振る舞いが結構な大御所風になっている。実際の歌舞伎業界のものいい(?)によくあるような、「実はこんなに普通なんです、みなさんと同じなんです」的なものは、ない。
(物語の視点となる、下っ端の大部屋役者は、普通の子として描かれていますが)
ただ、それによって単なる一般論に帰さないよう、役者の後援会の内幕を描くことで、業界の特殊性を出している。前述の通りかなりふわっとさせているので、「本物」の内幕は実はこうなんです的な、押し付けめいたあつかましさはない。
とはいえ、なんともいえないリアリティのある部分もあり、たとえば役者の奥さんは小綺麗な格好をしているんだけど、それは一般社会とは異なる独特の小綺麗さで、「メロンソーダ色のスーツ」とか、街中ではまず見かけないが伝統芸能業界だとロビーにこういう人絶対いるわ、てかそれ一体どこで買ったんだ的な描写は、「なんか、わかるわ……」感がある。
描写に違和感を覚えるとしたら、幕内の当事者たちが、やたら「梨園では」「梨園では」と言うことかな。説明台詞の導入として仕方ないんだろうけど、そんな出羽守、ある!?!??!??と思った。いや、実際、そういう喋り方をしている人たちがいるのかもしれないですけど……。
歌舞伎ファンの人がこの本を読んでどう思ったか知りたいと思って検索したが、出版が2004年と古いせいか、そういった「内々」の人の感想は見つからなかった。ただ、ミステリ好きの方が「業界の内幕もの」として楽しんでおられる感想は多くあり、やっぱりこの描写は上手いんだなと思った。
ストーリー全体的としは、登場人物それぞれの、他人には計り知れない「秘められた恋」をめぐって、物語が動いてゆく。
どんな恋なのか。相手は誰なのか。
個人的に引っかかったのが、番頭の描写。主人公のひとりとして、御曹司である人気女方役者についている、30代の女性番頭が登場する。
結構びっくりするのが、この人、出てきた瞬間、自分とこの役者の妻に内心でグチグチ文句言ってるんですよね。どういうことなのか、このキャラクター、全体的にグチが多い。つねにあらゆることに文句か揶揄を言っていて、幼稚というか、社会性がないというか……。自分だけが正しくて仕事が抜群にでき、役者からも好かれて大切にされているかのような自己評価で、役者の妻やよその役者の番頭を小馬鹿にして、見下している。いや、見下しているとははっきり書いてないけど、あまりにも他人への揶揄が多くて、異様に感じる。そして、地方公演で1ヶ月名古屋(御園座)滞在しなきゃいけないのが嫌だ、会期中でも東京と名古屋を往復できる奥さんは羨ましいとか、さすがにそれはそういう仕事でしょうということにまでグチを言っているのは、不気味に感じる。
いくら若手だとしも、人気役者の番頭がこれで務まるのか? 太い贔屓やら他の役者との挨拶やらは奥さんが対応するにしても、こんな人、客前や、よその役者の前に出せないのでは……?
自分は歌舞伎は気まぐれでしか見に行かないし、好きな役者もいないので知らないけど、実はこれがリアルなのか? それとも、若手役者だと、御曹司とはいえ、「まともな人」は雇えないのか? 番頭業界の闇?
ミステリ小説だから、これになんらかの理由があるのかと思って読んでいた。しかし、特に理由はなかった。著者は歌舞伎好きとのことで、取材をしてないゆえではないだろうから、なぜこんなキャラクターに設定したのか。
登場人物のうち、この女性番頭だけがポジションとして一般人寄りなので、感情移入用のキャラクターなのかもしれない。もしくは、自分が普段エンタメ小説を読まないからわからないだけで、これくらいの極端キャラでも普通なのか(かなり若い子向けの本?)。個人的には、「めっちゃ性格が悪いキャラが我が物顔で出てくるよっ!」って、人に勧めたくなった。
嫌な奴だからこそ、この番頭の描写をもっと掘り下げて欲しかった。
「ファン」の暗い愛憎というテーマで。
この番頭は、現在は業界関係者ではあるが、元々は後援会の一員で、前の番頭が辞めたので、声をかけられて番頭になったという設定。だからか、チケットを毎回買って差し入れをしてくれる後援会会員の若い女性ファンへの視線は好意的なものとして描かれている。
(役者からその女性ファンへの視線も好意的なものとして描かれている。ただ、実際問題として、毎回チケットを買っている程度、ちょっとした差し入れをする程度で歓心を買えるものなのか。事実なら、手紙なり差し入れなりのチャレンジ?のしがいがあるとは思うが)
重要なこととして、この女性番頭は、自分がついている役者のことが好きなんだよね。
本作は一人称視点のモノローグ式なので、その本人の独白として描かれるんだけど、そこでは、あくまでそれは恋愛感情ではないと語られている。そのうえでの、役者への疑似的な恋愛感情、役者の妻への嫉妬心。自分ではそれをかけがえのない唯一崇高なものだと思っていて、それによって自分は無条件に承認されると思っており、またそれによって他人を見下している。そのことに、もっと突っ込んで欲しかった。
「自分の応援する気持ちは他の人とは違う、崇高で唯一のものだ。対象を本当に理解しているのは自分で、恋愛感情と混同している奴らとは違う」という、自分の好意を過剰なまでに承認されたいという暗い欲望は、ファン視点の芸能業界ものでは時々見るテーマだ。
『一の糸』の前半も一種そういうものだと思うし、若手俳優業界を舞台にしたエンタメ小説でも読んだことがある。というか、現実においても、ファンに若い人が多い若手俳優や宝塚界隈だと、ファンの中でそういう「応援への対価や承認」への希求を感じること、あるいはそれにまつわる揉め事を目にすることも多い。
当事者からすると本気、誠心誠意なことには間違いないんだけど、他人からすると異様、異形としか思えないこの感情。多かれ少なかれ、多くの人が持っているものでもあると思う。私にもそういう部分があるので、関心がある。
本作の場合、あくまでミステリ小説なので、物語の本筋に関係のないどす黒い感情の深掘りを意図的に避けているのだと思うが、惜しい感じがした。純文学作品なら、そっち行くだろうな。
最後に、ネタバレ。(この本を読もうと思っている方は、この先は読まないで)
<ネタバレ>
人気若手役者が本当に想っていた相手が誰なのかは、暗にでも書いてあったほうがよかった気がする。ラストシーンの舞台が『二人道成寺』なだけに、道成寺をどうとるかで、その相手が誰なのかがぶれてしまうように思った。すでに2演目盛り込んでいるうえに、事実として発生した火災事件とをからめるにあたって、二つの意味にとれてしまう道成寺のモチーフの当て込みに無理があるのかもしれない。
女性番頭をお光(野崎村)になぞらえるのは、さすがにお光はそこまで性格悪くないだろと思った。お光もただの純朴娘ではないという解釈については、若手役者の妻(お染にたとえられる)が「お光は、出家は自分で決めたことのくせに泣き出したりして、ウザい、嫌い」ということを言い出す場面はある。いや、現実に文楽なりで「野崎村」が出るとき、感想を検索すると、お光を痛い芋娘と捉えている人、一定数いるのだが、それとは違うモニョりを感じた。著者は本気でこの女性番頭のようなタイプの人を、素朴だけどピュアな子として(その性格がウザいと取られることもあるとしても)肯定的に描いている感じがする。なんというか、不気味に感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
