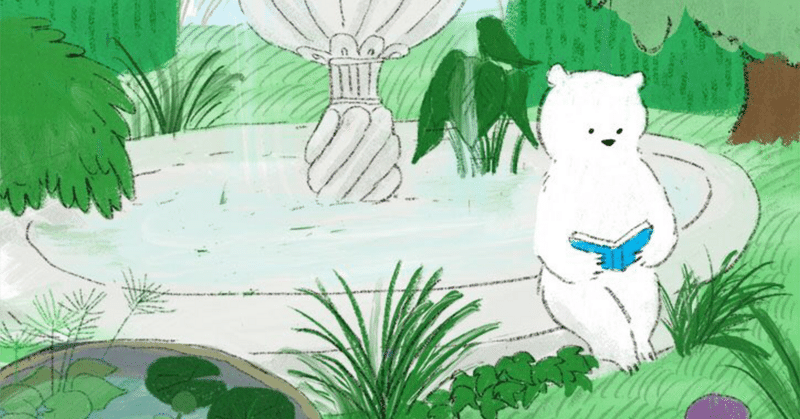
近所の文庫が居場所だった あまるいメガネの先生のおくりもの
子どもの居場所をつくろうといった話を聞くたび、私の居場所はどこだったかなと考える。
居場所というと、くつろぎ、安心、というニュアンスが入るので、何を感じていたかも条件に入る。
となると、家はそこ以外選択肢がないわけだし、習いごとの教室は課題をやらないと気まずいから苦痛な日も多かった。運動は好きじゃないから公園で遊んでいた記憶はうすい。
唯一、これかなと思うのは、近所の文庫である。
家から歩いて15分くらいの場所にあった文庫は、自宅の1階を改装してつくった場所で、ショートヘアでまあるいメガネをかけた「文庫の先生」が運営していた。
小さくてころっとした体にいつもえんじ色の割烹着をきていたが、親しみやすいおばちゃんというよりも、どこかピピリとした緊張感を感じさせる人だった。やっぱり「先生」と呼ばれるだけのものを子どもながらに感じた。
靴を脱いで玄関からはいると、左側の低い棚に赤ちゃんや幼児向けの絵本が並んでいて、右側には小学校低学年向けの本。突き当たりには高学年むけの児童書が並んでいた。
だから、『月のぼうや』『ネッシーのおむこさん』『14匹のシリーズ』は左側にあって、『晴れときどきブタ』は入口付近の右側の棚にあって、『ハリスおばさんパリにいく』シリーズや『チョコレート工場の秘密』や『魔女ジェニファーと私』は奥に並んでいるといった具合だった。
幼稚園のころから約10年通い続けたので、これまで読んできた本に囲まれ、どこに好きな本があるのか、よく知っていた。
この文庫に通い続けた理由はいくつかあって、何より先生が勧めてくれる本がめちゃくちゃ面白い、というのが一番大きかった。
読むと夢中になってしまう作品ばかりだった。
そして、興味が移り変わったきたときや年齢があがっていったときに、それを察知して寄り添ってくれたおかげで飽きることがなかった。
先生には無数の引き出しがあった。海外の作品が好きな時期はドイツ・イギリス・アメリカの色々な名作を勧めてくれたし、フィクションに飽きてきたときは伝記や動物ものを勧めてくれた。
そして、余計なことを聞かないものも良かった。
元気?とか学校どう?とか聞かれることもなく、だから親戚の挨拶のような会話をする必要はなかった。そこにいる他の子たちとしゃべる必要もなかった。本を返してまた借りて先生とちょっと話すだけ。だからこそ長く通えたのかもしれない。
時々、お汁粉を食べさせてもらったり、夏祭りをお手伝いをしたりした記憶がある。
もう一つは、母が先生をとても信頼していたこと。母は文庫の先生と文通までしていて心を許しているようだった。
だからこそ、ある程度になったら一人で行けたし、文庫にいくと母が喜ぶのをよく知っていた。
「あの人はただの絵本好きのおばちゃんではなくてね、児童書にすごく知識も造詣もある人だったのよ。」とは後日母から聞いた話。
それから、弟が途中から外遊びとゲームに夢中になって文庫に通わなくなったので、差別化するために、本好きなお姉ちゃんという評判を崩したくなかったのもなんだかんだ行き続けた理由。
最近ふと気になって、母に、文庫に会費を払っていたのかと聞いてみたら、「なにも払っていないよ、当時はお金がなかったし会費なんて考えたこともなかった」。でも「先生のまわりにもいつも手伝っている人がいたよ」。
想像するに、補助金などを使ったとしてもかなり自分の財産を投じて開いていた場所。先生の意思を感じた近所の人たちが手伝っていた、というところだろうか。
結果として、私は今でも本が好きだ。物語の世界や、言葉を集めて何かを綴ることを身近に感じる。文庫が近所にあったことは、結構その後の人生を左右していると思う。
100段以上ある広い階段を登って降りて、毛虫が出まくる薄暗い公園の前を通って、手さげかばんに絵本を入れて歩いていった日々は、やっぱり今の自分の大事なところに繋がっている。
先生はきっともう亡くなっていて直接は伝えられないけれど感謝の念をおくりたい。
子どもだけで行くことができて、行っても行かなくてもいい自由があって、文庫の日にはいつ行っても開放されていて「先生」がいて。本の喜びを無料で伝えてくれた近所の文庫は、やっぱり「居場所」だったんだろうなと思う。
今、思うとほんとうに贅沢だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
