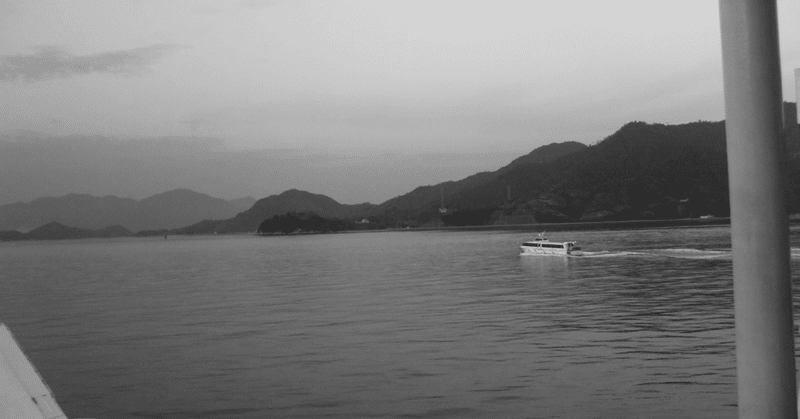
「定信お見通し 寛政視覚改革の治世学」 タイモン・スクリーチ
高山宏 訳 青土社
著者の父親はラブレーなどの研究家のマイケル・スクリーチ。
序
18世紀後半、松平定信の時代を、今に至る日本全体のイメージが形成され始めた時期として、それに(諸外国の船の到来や、アイヌ関係などにおいて)意識的だった定信を描く。彼一人で全てを行ったわけではないが、マージナルな白河から来たこと、それから吉宗の孫である意識、その頃京都(まだ京都という呼び名はこの当時無い)にあった大火事によって被災した内裏の復旧、などなど。これらの政策に批判的眼差しを杉田玄白が、美術面での共同者として円山応挙が、それぞれ挙げられている。この人のもうちょっと一般的な考えは講談社学術文庫の方になるのかな。
(2020 01/13)
序について二つ補足
松平定信が首席老中になった頃(18世紀後半から末)、スクリーチ氏の言うところでは、徳川体制は50年経たずして崩壊するとほとんどの人が考えていた…という。そういうこと聞いたことも考えたこともなかったけれど、とにかくスクリーチ氏によれば、19世紀前半には当分続くと思われたそう。そしてその立て直しを行った中心人物が定信だという。
(それは定信やその他日本国内の動きだけでなく、それ以上に世界の動き、フランス革命やそれに続くナポレオン戦争のために英露とも動けなかった…ということからの外患の一時棚上げが関与している)
上で述べた通り当時「京都」という呼び名は無く、「京師」と言われていた。それを「京都」とし、「主上」ではなく「天皇」と呼ぶようにした人物こそ兼仁(光格天皇)だという(この人、「世界文学全集を立ち上げる」で出てきた人? 確か傍系出身でその為に自分の身分確立に尽くしたという)。
第1章「松平定信と内憂ディレンマ」
今日は「守る定信」まで。
本書では定信は十八世紀末の不安感と、それがうみだした創造力を表す一種の代喩(シネクドキ)として働くはずである。
(p36)
その背後では社会的集合意識の現れが熟成されて、定信の政策を実現させたのだろう。定信の復古の呼び声に同調した人々もいる一方で、揶揄した人々もまたいる(恋川春町や大田南畝など)。これら全ての力の均衡点に定信がいる図。
今(でもないか)の築地市場辺りは、隠居(黒幕として政治を行なっていたという)した定信が、千秋館という館と庭園を作った場所でもある。
定信の外患に対する対応は、先代の田沼時代のように海軍や船を作ることには消極的で(一応取りかかってはいるのだが)、砲台を周縁の海岸線に備えつける政策をとったが、その海岸線を見て回った中に谷文晁がいて、その絵が本の図録にあるのだが、場所の特定や地形の情報を明らかにするというより、絵としての収まりを重要視している。
(2022 02/22)
定信本、第1章読み終え。
定信の千秋館にガラス窓を取り入れたという。自分の著書にもガラスを使った比喩を書いている。ガラスを通して世界を客観的に見ることができると。一方江戸城には、それに先立つ家斉の初期にガラス窓が取り入れられた、その際に盗まれたりもしたという。
古きを好んだ「復古」の定信はもちろん蒐集家でもあったが、それまでの多くの例のようにその物自体を集める(田沼意次などは自邸に至るまでの場所でそういうものを並べていたという)のではなく、学者や絵師に筆写をさせ、その紙製美術館的なものを作成し、またそれを印刷させ普及させようとした。またそのままにしておくと崩れてしまうようなものは好んで自身の別邸である六園(六義園ではないよね)の懐古園に収納した。
筆写といえば、定信は「源氏物語」の筆写をなんと7回もしたという。最初はきっちり1年、最短では3か月。法然絵巻の複製が出回った時、定信はこれを見て当麻寺の絵が入っていないことに気づき自分で!描いて挿入したという。
また自身の自画像も、白河藩から去る時の置き土産としてのもの(1787)と、54歳の時のもので顔だけ自身が描き身体は狩野養信が担当したもの(1812)がある。これはガラスの鏡を見て描いたのだろうか、とスクリーチ氏は想像している。生きている時に肖像画を描かせるのは、日本ではあまりなかったのが、この時代18世紀始め頃から頻出される。本に載っている杉田玄白の肖像画は、楕円の枠があり西洋ガラスを模したものとされる(日本の鏡は円形)。
定信が描いた猿の絵。水に映った月を本物だと思って手を出している、という禅の寓意図を元にした絵なのだが、定信は2点変えている。水に映っているのは月ではなく猿自身、それから手は出しているのではなく引っ込めている。
物質が本質的たりうべからざることなど先刻承知。しかし物質あればこそ我々はむざむざと滅却せず耐えられること、またたしかだ。口さがなく大騒ぎするのは止めよう、と定信は言う。そして絵に、束の間の中間の時の、しかしまたそれ故に大いに迫るもののある仕事をしてもらおうではないか、と。
(p88)
(2022 02/23)
第2章「「解体」のメタフォリックス」
この章の中心人物は杉田玄白。「解体新書」の邦訳は、原著にある宗教的、哲学的部分は意識的に除いたという。新たなメディアが様々登場し一見華やかにも見える世相が、玄白には世の崩壊と見える。この頃、田沼意次が幕府天文台に資金を出してずれてきた天文現象を観測しようとしたが、ずれは酷くなり、例えば正月一日にいきなり日食ということもあったそう。
とそんな中で起こった浅間山噴火。この時期、白河藩主だった松平定信は一人の餓死者も出さなかった(という伝説にはスクリーチ氏も少し懐疑的)。
(2022 02/24)
昨晩と今朝で第2章読み終わり。
前にこの時代の人々は、幕府(朝廷も?)の終わりがすぐそこに来ていると認識している、という指摘をみたが、この章は丸ごとその証明のようなもの。浅間山噴火に続いては(年代順ではない)家治の息子家基の落馬による死、久能山と日光両東照宮の火事、目黒行人坂からの大火、そして京師(京都)炎上。特に京師炎上の際には、文筆も絵画も様々な記録が登場した。
その話題に絡めて、日本の主要輸出品目であった銅の鉱脈減少による、オランダ始め外国貿易の衰退、及びナポレオンによるネーデルラント占領の影響でオランダ船が長く来なく、朝鮮通信使も長く中断した上、再開しても対馬までということ。ここで前任蘭館長でもあるヘンメイが掛川宿で殺される(自害とも)という事件が起こる…
あと、幕府・朝廷の終わり、この世の終わりを意識し始めた、というのに絡めて、この時代は家にも外でも時計が流通し始めた頃に当たる。当然、定信の千秋館にも幾つかあった。鐘の音で外から突然知らされるのに変わり、継続する時の流れを把握する場としての時計。
とぎれることがなく、しかも目で見ることのできる時間との出会いがいかに象徴的な力を発揮したかはいくら強調してもあまりある。
(p140)
(2022 02/26)
第3章「図像管理する王権」
日本では「非在の図像学」西欧は「ヨーロッパ各王家は可視性の海に漂っているという赴きさえある」
(p177 編集有り)
将軍にしても主上(天皇)にしても、「高貴な人の姿を見てはならない」ということで、「下に下に」から、道の両側の家から出させる(「レザーノフ滞在記」の長崎奉行への道のりを思い出す)、主上が火事から逃げてきた時は周りの群衆を斬って捨てる…
ただ日本(というか東アジア全般)第は、権力者は自らの「徳」で治めるのであって、自分の居城などは粗末でいい、よって防備も最低限、という思想が仁徳天皇の例など挙げて一般的であった。その一例として、江戸でも京師でも大火で天守閣がなくなったのを再建しないのはその思想のためでもある(資金不足ということもあるだろうけど)。
図像管理といえば絵画。狩野派と土佐派という潮流があって、前者は将軍家に仕え徳を絵画化する「唐風」、土佐派は主上らに仕え日本的な美学を絵画化する。という図式は大雑把というかかなり雑で別の意図を持ったような区分け方。狩野派も町狩野といって町衆に取り入る人もいたし、土佐派も江戸に出て住吉派になったりしている。
でも、本居宣長などは唐風をかなり非難している。
(2022 02/28)
狩野派の中興というか政治化したというか…という動き。それを半分批判しつつ「いま画」を描けという定信の思想。そして、しかし究極の「いま画」は「浮世絵」だったということ。あまりに(定信的に)堕落した浮世絵の場合は捕まることもあったそう。
(2022 03/01)
今日で第3章終わり。
京師炎上と内裏再建。
内裏再建についていつも唱えられる言葉が「復古」だった。定信もいつもそう言ったし、兼仁も同じであった。蘇生、復元の意あり、と辞書は教えてくれる。ここでは、虚構、でっちあげというニュアンスもある。
(p222)
「復古」を掲げ壮大な計画を言う兼仁に対し、最初定信は渋ったが、後に以前より大きな内裏にすることに同意する。豪勢な建築物(木材を集めるまで庶民の木は切れない)に対し京の庶民はどう思ったか。それは定信自身の思想とも反することであり、こうして定信は文化のことだけを主上に回した。
内裏内の絵は、伝統的な狩野派の絵は主上の遠くに配し、近くには大和絵、土佐派、京狩野(要するに京師近くの絵師)に任せた。こうした絵師の中から幕末時の尊王討幕の思想を持つものが現れる。
兼仁が亡くなった時、諡として光格が選ばれた。これまでは居住している京師の地名からつけられていたが、そうした慣行を脱した。そして主上ではなく天皇という呼び名もこの頃から。京師ではなく京都と呼ばれ始めるのも。
折角、兼仁好みの内裏にしたのに、1854年また炎上する…
(2022 03/02)
第4章「応挙、「新意」に走る」
というわけで、円山応挙の章。本居宣長の絵画論では「まこと」と「とりしまり」が重要だとされた。「まこと」は写生、「とりしまり」は形態同士の連繫相関(まあまとまり)。これら両方、特に後者に秀でたのが円山応挙。
この時代、西洋絵画も知られるようになり、遠近法とか消失点とかいう技法もとられるようになる。秋田藩主佐竹義敦の蘭画風の絵画(署名までオランダ風)とか、応挙の「阿蘭陀目鑑」で見る風景画などもある。
またまた、p254の鯉の滝登りの絵。これは伝統的な主題(応挙は主題自体には新しさを求めなかった)なのだが、次のページの狩野派と比べると、本居宣長の船の描き方論(p252-253)の狙いがよくわかる。
p267には、定信が重要と思った人の肖像画集を企画したが、その最初かつ最大のものである応挙の肖像があるけど…普通のおじさんだな…自らを強くアピールすることのない(若冲とかはアピールの典型例)人だったらしい。
以下、引用。
応挙の扱う絵画的要素はひとつ残らず規格の中のものだった。ただそれらが互いに均質化されていたところがみそなのである。
(p259)
「均質化」は宣長が「とりしまり」と言ったのとほぼ同じだろう。
応挙の傑作はほとんどが大火後のものである。なにしろ大都市がひとつ丸々まっさらの白紙なのだ。様式を引き取り、横略するにも、やりたい放題の入れ食い状況なのである。
(p263)
京師が京都になる、その只中に応挙がいた。
(2022 03/03)
鑑賞を画家の仕事と見るところが応挙の新しさであった。画家は制作者であり、かつ最初の鑑賞者である。もしこのことを画家がよく弁えているなら、絵を見る人間の役割を先取りするわけで、人々が絵の世界に入るのをずっと楽にさせることも、彼らをいち早く自分と同じ意味理解に拉致することもできるはずだ。
(p277)
応挙は特に弟子には、制作のことより、どう絵を見るかについて教えていたという。
この時代の絵のパトロンである上流階級の注文に多い、襖絵や屏風絵について、応挙はどの位置から見てもまとまりのあるものにすることを心掛けていたという。この実例は「応挙寺」と言われる、兵庫県城崎周辺にある大乗寺にあるという。
あとは、顔料、色の話。この時代には前にも見たように西洋画の技法が入ってきていた(実際の西洋画はただ2枚あるのみで皆筆写していたという)。筆法(筆の動き)を重視する従来の美学は、定信、宣長始め多くの人が否定的で、西洋から入ってきた顔料をもっと流通させようとしていたが、何の間違いか長崎ではそれを海中に投げていた。定信はそれを回収する命令を出す。
なんとか第4章読み終わり。
(2022 03/06)
第5章「中心と周縁」
そもそも山野「をめぐる」ことで、山野についての絵や文章が生じてくる歩行の新感覚と描写行為自体への耽溺が絶妙にからまり合いながら生じてきた構造は、日本でもやっと知られ始めだしたようだが、同じ構造がどういう次第か、ほぼ同時代の江戸の各大名庭園にもそっくり確認できる。回遊趣味から園路ガイドブック発行まで、十八世紀後半のいわゆる英国式風景庭園の突発的な大流行を傍注に、ぜひこの『浴恩園仮名の記』は読まれる必要がある。
(p308-309)
…と、書いておいて、「それはこの本の目的ではない」としている(そして、それなのに次の次のページで、またそういう論点を出しているところみると、これは故意的記述を越えて何かの宣伝なのではないか、と思ってしまう。
それはともかく…
前も挙げて現在の築地にある定信の庭園、そこには4つの関所がそこにまつわる和歌などの文学的モティーフ植物などとともに建てられている。
深川にあった定信の庭園とこの築地の庭園との間を、船を使って行き来していた。また建物の窓から洋上の船を掛軸のように見渡せて、新しい異界を来る者に感じさせるようにした。
(定信ではない)尾張藩の戸山庭園では、飛び石で川を渡った直後、仕掛けで急に水位が上がり、飛び石は水没し渡った人を驚かした、という。
この時代に大名庭園作りがまた流行したのだが、この動きに対する批判もまた出てきている。それに反応して作る側も気を使って名前をつけたり(「後楽園」など)。そして白河の南湖庭園では、垣根とかなく誰でも入って散策することができるようになっていた。
(2022 03/07)
天下(日本領域)のばらんばらんの風景に悪を感じると敢えて言わないのが定信の政治学であった。
(p369)
谷文晁が代表格だけど、「写真」のように写生して(「写真」という言葉は既に存在していた)、海防やそして国内の物見遊山の旅のための案内としての絵も増えてきた。
前に読んだレザーノフの名前がここで出てくる。松前には形だけの大砲があって、それをロシア船が持っていってしまう、という事件も起きた。ここでアイヌの人々の絵を描いたものが主上(天皇)も見ていたり、定信は松前藩を一回は廃して幕府直轄にするなど(その後また松前氏が戻る)。
源氏物語絵巻、石山寺にあるものを修復しようとして、そのうち2巻が無くなっていることがわかる。実はその2巻は白河藩にあったのだ。という話。
p395にある、弘法大師が描いたという絵を模写したいという谷文晁一行と、それは御法度でありそうなったら祟りで死ぬという寺の僧、結局模写することに成功する。そこから、次の一文。
本気で過去を引き継ごうというのであれば、つながりが断たれてしまわないうちに思い切った手を打たねばならない。これが十八世紀末、一つの強迫観念となった。
(p397)
(2022 03/08)
「定信お見通し」を読み通し
というわけで、なんとか読み終わった。
最後の話は音楽について。ハーモニカは将軍に献上されたが、ストリートオルガンは定信が拒否したという。どこが違うのか…
それから、この時代から流行し出した三味線とかの新しい民衆音楽も拒否し、笙などの雅楽を「復古」させようとしていたという。中国、朝鮮で滅びてしまった古音楽が日本には残存しているからという。民衆音楽の方は前に見た「浮世絵」と同じ理論なのだろう。
スクリーチ氏のインタビュー「江戸を見る、江戸を斬る」
だけど三つめは、その当時の言葉を理解しながら、自分の方法、あるいは自分の分析は現代のポスト・マルクス主義、あるいはポスト記号論、フーコーみたいな方法論を使って、特に裏の力、イデオロギーの、その社会に染み込んで見えない程のコントロールをしているものを意識して明らかにすることです。
(p422)
だから、定信は京都を「歴史化」したんです。反対が多くて、特に京都の町人など、なぜ「復古」された街に住まなければいけないのか、新しい方がいいのに(笑)。
(p423)
見えるもの、見えないものの相互作用を見極めて、違った見方を差し出す…ということか。「監獄の誕生」とか比較しても面白そう(そちらは読んでないけど)。
(2022 03/09)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
