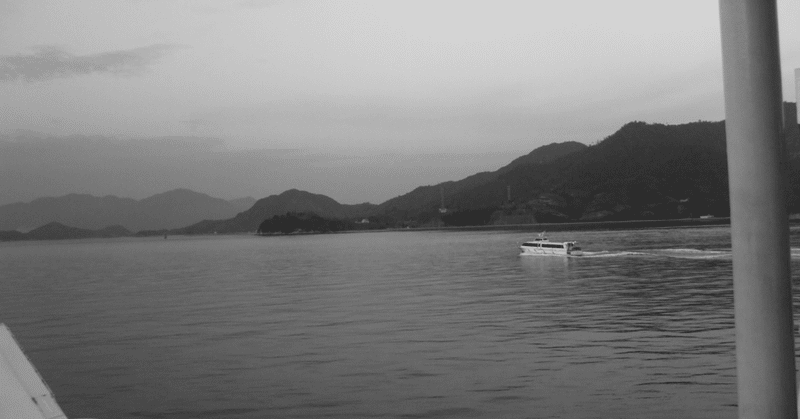
「ファシズム、そして」 和田忠彦
水声社
ファシズムの物語
「ファシズム、そして」より始めの3章
第1部から冒頭3章「ボンテンペッリ」「サヴィーニオ」「ファシズムの物語」(章の名前は省略、読み順は実は逆順)を読んだ。
幾種類のファシズムがある以上、そのひとつひとつが多様で、しかも時には矛盾する傾向をいくつも内にかかえこんでいることになる。そうした傾向が発展してそのファシズムの基本的特徴を少なからず変えてしまうことすら起こりうるのだ。
(p60)
(1938年、イタリア共産党を追われたアンジェロ・タスカの言葉)
ボンテンペッリはマリネッティらの未来派との決別を中心に、サヴィーニオは画家キリコの実弟で前に「現代イタリア幻想短篇集」(国書刊行会)の中の「「人生」という名の家」を読んだことがある。最初はフランス語から創作を始め、ツァラやピランデッロとのそれぞれに短い交流期間を経て、怪物のような絵画を多く描くようになる。こういうファシズムとは相容れない「無国籍者」は前に感じた「閉じていない」感に通じるのかも。
「ファシズムの物語」(p60の文章含む)では、ボルジェーゼの「ルベー」というファシスト・コミュニスト双方になれない知識人の姿を描いて逆にファシズム下で売れてしまった作品(後にボルジェーゼは大戦後の回想録でこのことを苦く回想している)のことが興味深かった。
(2016 07/10)
「ファシズム、そして」の最後のエーコの章は、エーコの「小説の森散策」(岩波文庫)でも取り上げられたシューの小説論。
(2016 07/17)
アキッレ・カンパニーレ
「ファシズムと笑いーアキッレ・カンパニーレの軌跡」と「引き裂かれた詩ーアメーリア・ロッセッリ」を読んだ。これで第1部は終わったかな。
若者たちには、全体主義の言語表現を逃れ、批難するための〈どこか別の場所〉が垣間見えていた。どのような体制や時代にあっても、〈どこか別の場所〉をみつける可能性があるのは大切なことだ。
(p76-77)
少年時代にカンパニーレのユーモア小説を読んだ思い出を語るカルヴィーノの言葉から。カンパニーレは戯曲や小説(その合間みたいな作品が多い)を体制に反抗することなく、しかし完全に御用作家とはならずにユーモアの灯火を守った、と言える(のか)
アメーリア・ロッセッリ
続いてのアメーリア・ロッセッリは今日借りてきたイタリア現代詩集(「詩の住む街 イタリア現代詩逍遙」工藤知子訳 未知谷)にも出てきている。フランスに生まれ、イギリスついでアメリカに渡ったスペイン市民戦争の英雄の娘は、3か国語を宙吊りに使用しながら、それぞれの言語で詩を書く。
ロッセッリのいう「貧者の文法」とは、こうした転倒によって詩的言語を私的言語に還元してしまうような話し言葉のエクリチュールを生むための規則のことだが、それは、ロッセッリのかかえる言語宇宙の渾沌をかすかにせよ鎮めることができるのは、私的言語そのものが詩的言語と完全に重なり合う一瞬の白昼夢以外にはないということなのかもしれない。
(p96)
イギリスやアメリカ滞在期にも、同じ名前の祖母アメーリアがダンテなどをイタリア語で孫に語り継いでいたからこそ、後の詩人はイタリア語で詩を書くことができた。がそれは十三世紀の詩的言語そのものであり、現実のイタリア語との接点は薄かった、という。
著者和田氏がこのアメーリア・ロッセッリという詩人の存在を知るのは、これもイタリア現代詩集に出てくるアンドレーア・ザンゾットとペソアの話をしていた時だったそうだ。
(2016 11/27)
イタリアの「鉛の時代」
断章の章はあらゆる媒体に書いたものの寄せ集め。だから、マヤコフスキーからイタリア映画まで昨日読んだ2、3でもいろいろ。イタリア映画も文学(カルヴィーノやエーコなど)も、「鉛の時代」(1970年代後半?辺りのイタリアに蔓延したテロの時期)を意識しないで読むと大事な論点を見逃すとのこと。
(2016 12/06)
モラヴィアと映画
モラヴィアについて少し。著者和田氏によると、カルヴィーノやエーコの作品に比べ、モラヴィアの作品は映画化で「原作を越える」ことが多いという。自身も映画好きであるモラヴィアにとって、これは名誉なのかも。という話題。
(2016 12/07)
「ファシズム、そして」はファシズムとネオリアリズムを連続した視点で捉えた時に、どのような新しい見方が見えるのか、というところ。
(2016 12/08)
1930年代イタリア再考
二回に分けて読んできたこの本、昨夜読み終わった。
第3部の残り2つは主に1930年代のヨーロッパ志向とアメリカ志向について。知識人のこうした志向性に対して和田氏は批判的に論じている。またこの時期は「翻訳の10年」と呼ばれ当時の外国現代作家の翻訳が進んだ時期でもあるという。
(2016 12/09)
たとえばマリネッティやマヤコフスキーが、みずからのヒロイズムに恐怖することを知っていたら、疾走することの孤独は軽やかな愉悦に転じ、かれらの夢も詩のなかで読み継がれていたかもしれない。
(p117)
(2016 12/10)
関連書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
