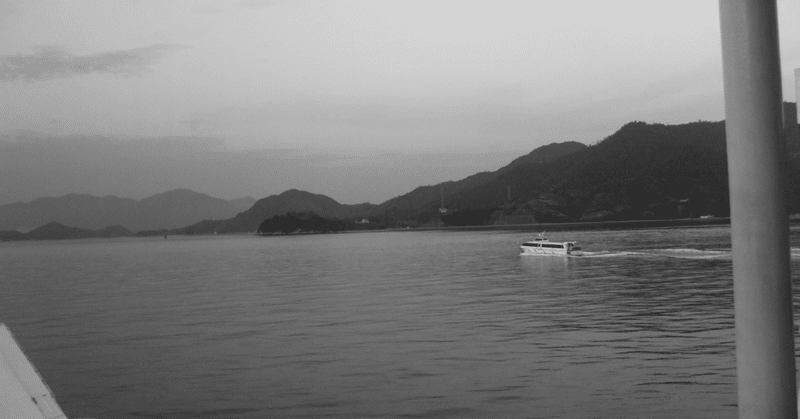
「神経症者のいる文学 ーバルザックからプルーストまでー」 吉田城
名古屋大学出版会
新御茶ノ水風光書店で購入。
(2011 02/15)
神経症からみたフランス文学
序章を読んだ。神経症については、17世紀から19世紀中頃まではあまり医学的見地からの進展はみられなかったけれど、どちらかというと文学作品の中に事例が多く見られること。細かいところではモリエールの喜劇の中に医者フェチ?依存症?の主人公が出てくる喜劇があって、その男の娘の結婚問題という劇の本筋ではハッピーエンドになっているが、主人公自身の依存症は最後(のオチ?)になっても治らない、というのがなんか興味を惹いた。催眠治療とか聞くとちょっと引くけど、これが直接ナンシー学派とかになってフロイトに直結するのだと思うと、催眠とか暗示とかいうのも今日と近いところにあるのだな、と改めて思う。
(2013 04/01)
神経症の理解の歴史を眺めた序論と、バルザックからプルーストまでの本論。今はバルザック「谷間の百合」まで終わったところ。ルフェーベルがこの小説に(実在あるいはモデル化された当時の医師が5人も出てくることから)「医学小説」と名付けたらどうか?と言っているらしいのですが、それに対しこの本の著者吉田氏は患者もいろいろいるから考慮にいれてね、という。
具体的にはここで出てくる夫人はこれから19世紀末かけてにたくさん出てくる女性の神経症者のハシリみたいな存在ではなかろうか。自分の生きている範囲しか知らなかったこれまでに比べ、イギリスの女優?の恋愛遍歴など知ってしまう世の中になってしまった?から…
そういう意味の女性神経症は、現在では克服されているのか、あるいはいないのか?
(2013 04/04)
フロベールの父親と音楽の効用
今日は帰りにフロベール自身の神経症についてのところを読んだ。
まず父親について。作家フロベールの父親は、獣医一家の三人兄弟の末子なのに関わらず人間の医者となり、かなりの尊敬を集める。その父親に対し、複雑な思いを持っている次男坊作家フロベール。その作品「ボヴァリー夫人」の最後の方で出てくる医師というのがフロベールの父親の面影で構成されているという…そこでは割りと世間一般的な医師の評価…だけど、「紋切り型辞典」にもあったように皮肉めいた評価も存在する…自身は病弱な作家は父親の自然科学的道でもなく、母親の宗教的道でもない、別の道…文学の道を進む。
続いてフロベール自身のてんかんについて。てんかんと言えばドストエフスキーのイメージだったが、フロベールもそうだったという。一つ気になったのは、彼自身の書き残す症状のイメージと、それから治療の指示で酒などとともに音楽が禁止事項になっているということから、ひょっとしたら音楽を聴くということの一つの効用はてんかん的なイメージの追体験ではないか、という考え。
サルトルがフロベール論「家の馬鹿息子」というのを出していて、精神分析的な緻密な分析をしている。
(2013 04/05)
ボヴァリー夫人とサランボーは同一か否か
「神経症者のいる文学」のフロベールの章を読み終え。フロベールが残した作業メモなどから、ボヴァリー夫人とサランボー、この両者(あとはアントワーヌも)が最初から神経症者という設定であったことを解明。ボヴァリー夫人がきっかけのはっきりした衝動的なものなのに対し、サランボーは複合的な偏執狂的になっている。でも、同じような症状も出てくる。根本の根本は同じところなのかも。
ボヴァリー夫人の症状の中の「計画を練り、全てに関心を示し」とあるところはなんか自分自身とも共通しているところもあるなあ、と感じたり。
p105~106のフロベールの手紙はなかなか読み応えがある(女性の神経症の根本には「永遠の夫」がある…先の根本の根本はここか…とか、物質主義と精神主義を研究し始めたことが19世紀の唯一の名誉だ…後者はこの本で述べられているようなことだろうけど、前者は?マルクス的な社会学的なものを指す?あるいはボヴァリー夫人に現れていたようなボードリヤール的な消費社会?)。
サランボーは随分前に読んだけどよくわからなかったから、もう一度見直してみようかな。
フロベールがこの時代(シャルコーの少し前)に、神経症は脳とかのどこかの部位が悪い(器質説)のではなく、心の病気だと(心因説)考えていたという結論。作家の鋭い視線が医学に先立った好例。
(2013 04/07)
今日はゾラからユイスマンス、モーパッサンへ。
ゾラの隔世遺伝含めた全体的呪いみたいな神経症から、ユイスマンスの神経症を入口とする頽廃?芸術アラカルト、そして個人的なモーパッサンの神経症まで、エトセトラ、エトセトラ。
この中では一番モーパッサンが自身も神経症度が高い。ユイスマンスの「さかしま」登場の主人公(生い立ちが、ゾラのルーゴン=マカール叢書の第五世代とか、「ブッテンブローク家の人々」の最終世代みたいな何もかも衰弱した生き残りみたいな感じ)の神経症から逃れたくてやることが全て神経症を呼び起こすみたいな構図はとてもよくある一般的な図式なのかもしれない。
またモーパッサンとフロイトはだいたい同じ時期にパリでシャルコーのもとに学んだ。ということで、この二人がそこで交流してたら的な本(小説ではなくて何らかの批評みたいだけど)もあるという(実際はそういう事実関係は出ていない、が)。ところで、モーパッサンのここで挙げられている短篇のうち何かをどこかで読んだ気がするのだが・・・
(2013 04/08)
ジェリコーの狂人の絵
今朝もうとうとしてちょっとだけしか読めなかったけど、「神経症者のいる文学」は文学ではなく絵画の章。こういうインタールード的な章を置くというのもこの本の特徴の一つ。
「メデューサ号の筏」のジェリコーが精神病患者の挿絵を書いていたという話題に…とだけしか進んでいない。(2013 04/09)
補足:ジェリコーは「メデューサ号の筏」を描く為に、死体のスケッチをたくさんしたという。
(2021 04/08)
ジェリコーからムンク、シャルコーへ
標題に書いた通り絵画の章続き。精神科医であったシャルコーはもとより、ジェリコーのも医学書の挿絵等に使われた(あるいはその前提で描かれた)ものなので、そういう意味では真ん中のムンクだけが系統違う。そのムンクのところに書いてあった「印象」と「表現」(美術史でいうところの印象派と表現主義、英語などではそれぞれ「外から内へ」「内から外へ」と反対の意味になる)の違いのところが参考になった。シャルコーの時代になると写真も取り入れられてくる…
シャルコーの「芸術における悪魔憑き」
シャルコーの章(第8章)の後半から。シャルコーと言えば催眠療法…そのパフォーマンスはどこまで真実だったのか謎ですが…それを前にも書いた通りフロイトやモーパッサンなどが見にきていた、というのがすぐ頭に浮かびますが、その他にもこういうタイトルの本も出していたらしい。
主に芸術作品(収集の為にいろいろな場所を回ったらしい)を素材にして、中世などに魔女とか悪魔憑きとか言われて処刑されていた人々は実は神経症者だったのではないかという論点を、審美的にではなくあくまで医学的に捉えようとした本。
ポイント1、シャルコーらが、こうした図像が古代にはほとんどなく中世からよく出てくると言っていたのだが…この辺、古代末期の問題と絡みそうだ。
(「古代末期の形成」ピーター・ブラウン 足立広明訳 慶應義塾大学出版会 など)
ポイント2、そうした中で古めのものがガリラヤ湖の奇跡というもの。とある男にとりついていた悪霊をイエスが追い出し、悪霊(たち)は豚の中に入りこんで豚は湖に次々と飛び込んでいくというシナリオ。これってドストエフスキー「悪霊」扉のところに書いてあるヤツだよね。ドストエフスキーもてんかん持ちだから自身の体験からも書いたかも。いろいろ想像できる。
ポイント3、シャルコーたちによれば、一番神経症者を「正しく」描いたのはルーベンスだという。
(2013 04/10)
意志の病い
第4部のプルーストに突入。今朝のところは「失われた時を求めて」以前の短編から。後の時代より、神経症のまた喘息の苦しみを直につたえているのが多いという。そんな中で自分的にちょっと気になったのが「意志の病」というもの。親の過保護と子の神経症が重なるとこれになって意欲がなくなる、という。自分を含めて今の世代全体がこういう状態と説明もついてしまうのでは…
後は、2つの短編で見られる対象がいない時に恋慕がつのる、というウシトキでもよく出てきたテーマ、とか。
(2013 04/11)
ここからは「失われた時を求めて」に現れる神経症を見ていく「神経症者のいる文学」最終章。後の話者ほか様々な恋愛の母型となっている自らの偏執から抜け出せないスワン、実際の医師のモデルが何人かいて作られた「神経症は芸術的であるから放任してもよい」的な(半分はプルースト自身の考え)医師、そしてその医師に半ば誤診されたレオニー叔母。話者はこの叔母から神経症を多く伝えられたと考えているみたい。話者自身と行動傾向は正反対ながら元は同じところから出ている、と感じているらしい。
「誤りの堆積の中から真理が生まれる」という表現は拾いモノ。
「神経症者のいる文学」読了報告
レオニー叔母が暇にまかせて夢想した作り噺も、プルーストになって「失われた時を求めて」の一挿話になった、という視点は面白いかも。
同じくレオニー叔母が外出恐怖症で、それを補う為にいろいろな外出の計画を夢想するというのは、なんか軽度に考えればそういう人が近くにいるかも。旅番組見て行った気になるとか(笑)。
まとめの後書きでは、ユイスマンスの頃から神経症に対して積極的な評価や意義が出てきた…それを展開したのがプルースト、ということらしい。
神経症者どころか、気の合わない者をすぐ排除してしまう傾向が強まっているような気がする現在ではどうだろうか。
…でも、もう一歩独自な説も読んでみたかったような気もする…この本…
(2013 04/12)
作者・著者ページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
