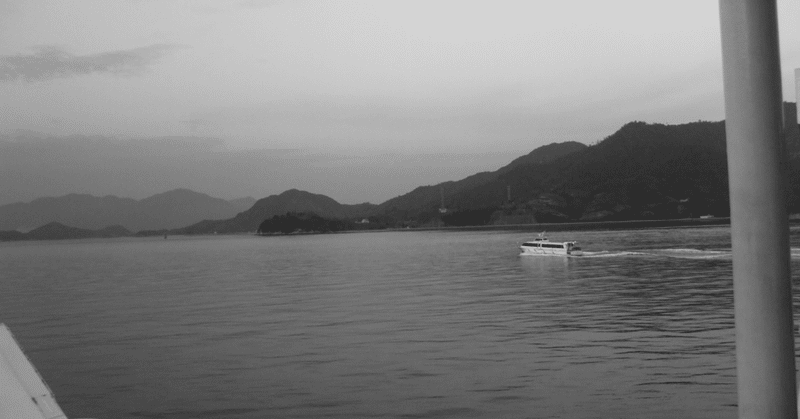
「乱視読者のSF講義」 若島正
国書刊行会
三鷹、水中書店で購入。
3篇目まで
今日はSF講義少し読んだ。 ウェルズの「スター」は地球に別の星が衝突する(それで終わり、救い無し)という、ある意味お決まりパターンをあえて越えた短篇。この短篇の語り手は実は火星から事の顛末をみていた火星人、後の「宇宙戦争」と語り手と現場が逆転している、と指摘。2、3篇目は地球外生命体とのコンタクトというレムに繋がっていく問題系。3篇目はある意味レム的だけど「語りえないもの」の連鎖で逃れているフシもあるのかな。
(2015 11/24)
ディストピアから去る人々
今晩は若島氏のSF講義を持ってきた。それぞれに気になるけど、9回目のル・グィン「オメラスから歩み去る人々」、ディストピアの短編はやはり?特に気になる。
街の記述と記述の記述というメタレベルの2つの構造。それからディストピア(ユートビア)はどのように(読者の想像の視点を入れたとしても)地下の犠牲となる子供達がいる限り実現はしない。そしてこの記述された街にも、また作家自身もこの街を去り次の街へ、実験へ向かう為に去る人間がいる…など。
あなたの好きなように、信じられるユートピアを想像してみてほしい。そのユートピアがどのようなものであれ、そこにはそのユートピアを成立させるためのスケープゴートが必ず存在する。従って、そこは本当のユートピアではない
(p104)
この第一部「講義録」のラストはレムなのだけど、だんだんそこへ繋がってきた?
(2016 01/18)
開かれた系としての自分
今読んでいる若島正氏の「SF講義」の第一部後半から
言い換えれば、ハリスの変身には、恐怖と同時に魅惑がある。
(第10回 ディッシュ「アジアの岸辺」) (p115)
全く別の人間になることはぞくぞくする体験なのだろうか。そこには死と再生がある。自分という存在が決定項でないことに救いを求める道が開けてくる。 さて第一部の最後がディックとレム。レムのディック論とディック自身の作品に共通する「にせもの」をキーワードにしている。
一方レムはこの「講義」の冒頭でもありレムの文学エッセイでも高く評価していたウェルズの後継者としての位置。それは個人の人間ではなく人類という種全体を問題系に入れているところから。ウェルズとレムの間に入る作家としてステープルドンという名前が挙げられている。この人もあまり「SF作家」としての言及がないというが。
(2016 01/19)
タグとしてのSF
若島氏の「SF講義」。ウェルズのSF作品と社会小説の割合はおおざっぱに半々くらい…だけど、論じられる時はどっちかの側面でだけのことが多く、全体としてはあまり論じられない。そもそもウェルズ自身はSFかどうか意識していたのかな。
今、作品読む側からしても、ジャンル区分けとしてのSFというのは本質的な意味を持たない。なんでボルヘスやビオイ=カサーレスやコルタサルはSFではないのに、レムやウェルズはSFなのか… こういった作品にはSFの要素がある、というタグ付けの感覚が必要なのでは。そこには当然他のタグ付けも加わる。ミステリーとか教養小説とか、えにもあ…
さて、ウェルズの人物描写にある不完全さを、人物を作り上げたのが「オメラス」「所有…」のル・グィン。逆に完全に人物排除の方向に進んだのがレム。という図式…
(2016 01/23)
スタニスワフ・レムとジーン・ウルフ
「SF講義」いろいろあるのだが、ここではレムとジーン・ウルフに絞る。
そのような破調には、この『完全な真空』を統一のとれていない、いわば「不完全な真空」にしようとする倒錯した意図が感じられる。冗語法の「完全な真空」は、撞着語法の「不完全な真空」を自然に想起するように仕組まれた言葉ではないのか
(p231)
「完全な真空」読んだの相当前だな、少なくとも、ボルヘスより前…えと、レム語るとウルフに行けなくなるので、これはこのままで…
そういう小説の構造以上に、手触りが似ている部分がある。つまり細部が非常に凝っていて、しかもそれぞれが乱反射のように対応している。それを糸を引っ張っていくように読むことができるところ。
(p263)
ジーン・ウルフの「ケルベロス第五の首」と比較されているのはナボコフの「青白い炎」。どちらも複数の語り手がテクストを語っているのだけど、実は全て一人の語り手が語っているのではないか?という説も、両作品にある。
ウルフは「読み終わった後にもう一度書棚から出して再読する人の為に書く」ともあるインタビューで答えている。この「ケルベロス第五の首」には他にも書き出しが「失われた時を求めて」を下敷きにしているという指摘がある。第一部にはジーン・ウルフの名前が浮かび上がってくる仕掛けもある。SF作家が自伝を書くとこうなるのかなあ? (「ケルベロス第五の首」の訳者柳下氏との対談もあり)
最後に「SF講義」から引用3つ
最終的な正解を手に入れることは、けっして読書の本質ではない。そうではなく、書物に魅了され、その迷宮の中でさまようことこそが、読書の本質ではないか。…(中略)…わたしたちはひたすらこの書物のみを手がかりにして、自分の直感をたよりにしながら、読みのアンテナに引っかかってくる細部を丹念に拾い上げ、少しずつ少しずつ、この迷宮を進んでいけばいい。
(p270)
本のオビにもあったこの言葉。筋を追っているつもりが、いろんな細部につられて道を見失ったり迷うことは多々ある。それでもいいのだ、と教えてくれる。ひょっとしたら、というか多分、書き手もそこで迷ったりしているのだろうから。
だとすれば、老いゆく世界で到来が待望されている〈新しい太陽〉とは、実は一人の新しい「読者」ではないのか
(p272)
ウルフの「新しい太陽のウールス」解説から。こういう作品内と作品外が開かれているのが、ウルフのもう一つの特徴なのかも。それはウルフの「出張講義」で取り上げられている「ガブリエル卿」という掌編でも、「それはこの本だった」という実にゾクゾクする一文で簡潔に現れている。
最後はあとがきから。
とうに夜半を過ぎてからが、小説を読む時間だ。小説という鏡のむこうに、真夜中になっても眠れずに小説を書いているもう一人の姿を、わたしはそこに発見する。
(p307)
鏡を媒介として書き手と読み手がやりとりしている、そんな読書の構図。 なんか最後はSF講義というより読書論みたいになっていった…ウルフも若島氏にとってもそこが主題の一つなのだろう。
というわけで、「SF講義」読み終わり。どれかこの中から一つ作品読んでみたいところなんだけど…
(2016 01/24)
補足:ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」と、トマス・ディッシュ「アジアの岸辺」はこの後読んでいる…
関連書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
