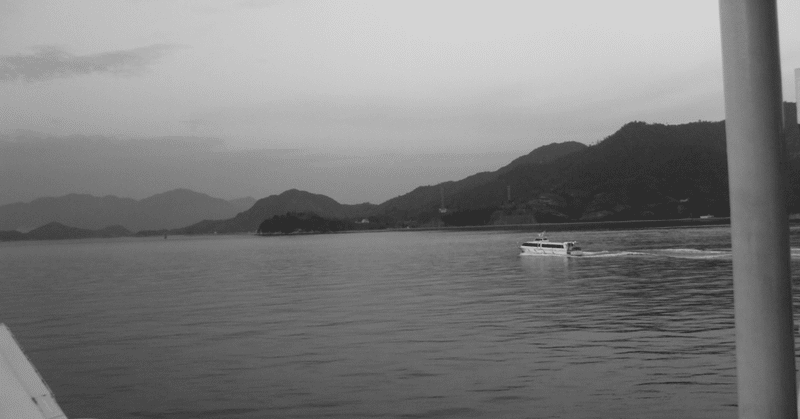
「異端者たちの中世ヨーロッパ」 小田内隆
NHKブックス NHK出版
異端とは
「異端」とは、もともとギリシャ語で「選択すること」を意味したという。
選択・・・近代以降、自分で自分の生き方を選択するのは(もちろん徐々にではあるけど)当たり前のこととなった。しかし、この本が主題とするヨーロッパ中世では、カトリック教会の教えに「服従」することが正しく、「選択」は則「異端」だった。
前近代人にとって異端はひとつの可能性ー普通はむしろ程遠い可能性にすぎないが、現代人にとっては、異端がひとつの必然性となる。
(p16)
この言葉はアメリカの社会学者バーガーの「異端の時代」という本からとられたものだが、まずこの「異端の時代」というタイトルが示す「時代」は、中世(前近代)なのだろうか、それとも「現代」なのだろうか。社会学者の言葉ということで「現代」のことかな、とも思うけど。面白そうな本だなあ。
また、「可能性」ということは、中世の生活では常に「選択」できる余地があった、ということを示す。でなければ、これほどいろいろな異端が出てくるはずがない。で、その「選択」した一部に(社会逸脱論やラベリング論がよく合致するように)カトリック教会が「異端」と(後づけで)名付けた。ということのようだ。
ということで、先のp16の文の「(現代が)ひとつの必然性となる」というところの「ひとつ」は「ただひとつ」なのか、どうか、気になるところだ。
(2012 01/13)
古代から古代末期
イエスの死後、いろんな教説が飛び交う中で、今現在カトリックと言われている教義が議論され形作られていった。パウロの時代には「分裂」であったものが、ユスティノスが「異端」というカテゴリー?(異教のイメージも絡めながら)を生み出した。グノーシス主義との対決の中で様々な司教が論戦したが、やがてカトリックが成立するとともに文書化(新約聖書決集)、組織化(教皇→司教のヒエラルヒーはまだ)の動きが起こる。
古代末期の最後はやはりアウグスティヌスで、彼は異端を正統のカトリックに連れ戻す為には世俗権力の力も借りるべし(暴力介入)と、中世異端尋問の先駆けとなる思想展開をした(書き上げられなかった「異端について」)。古代末期の全体的な宗教動勢はブラウンの研究(「古代末期の形成」など)を参照のこと。
(2012 02/11)
グレゴリウス改革…ビフォーアフター
第1章を読む。この本の主要な話題である12~15世紀の異端(カタリ派とかワルド派とかあともう一つ)の第2~4章に至る前段階。つまり11~12世紀前半頃の話。
この頃までにヨーロッパでは封建社会が定着し、経済が安定化してきた。11世紀には久しく起きてなかった異端問題?(それまでは異教との戦い)が出てくる。それはこのキリスト教社会を権威づけるものへの批判であった。
でもあんまり長くは続かず、次の時代は異端問題は消え失せ、グレゴリウス改革の時代へ。改革派が攻撃したのは、聖職を売買したり聖職者が妻帯したり…というもの。これは清浄化という意味もあるが、それより聖俗を区分して、教会側から世俗権力を追い払って逆に世俗側を支配しよう、とするもの。いわゆるカノッサの屈辱の叙任権闘争。
これがある一定の成功を治め、教会側が権力を持ち富を持ち始める。そしてこの頃、「不服従は異端なり」という考えまで出てくる。そうした中、12世紀前半には新たな異端問題が登場する。これは教会のものを破壊していく、というラディカルなもの。これも長続きはせず、こうした中からカタリ派が生まれてくる…というところまで。
かなりはしょっているけど、まとめ。
カタリ派
この後、カタリ派の章の第1節まで。
カトリック側が想定していたカタリ派の「対抗教会」とはカトリック側での想像の産物でしかなく、カタリ派の「真実」は「完徳者」がカリスマとなって一般のカタリ派信者と取り結ぶ(古くからある)形なのではないか、と小田内氏は言う。
あと、カタリ派がパウロ派やボゴミール派由来ではないかという通説?も、小田内氏はどちらかというと否定的。両派の影響を受けずとも説明できるという。とにかく、カトリック側の(たぶん自らの教会の諸制度の発達に合わせてしまった)「誇大妄想」という現象は、なんだか他の社会的現象を捕えるのにも役立ちそう。そんな気がする。
(2012 02/19)
カタリ派とテクスト共同体
彼らの「沈黙」を前にすると、改めて異端審問官やカトリック神学者が強調してやまないカタリ派の大教会は、創られた虚構ではないかと思われてくる。
(p106)
カタリ派側の著作がほとんど残っていない現在、カタリ派の実情を知るには、カトリック側の著作を見るしかないのであるが、そこに出てくるカタリ派の大きな教会組織というものに対しての引用文。自分達の組織環境からしか不明瞭なものを把握できない、とも言えるし、もっと広く言えば、噂とパニックの社会学にも発展しそうな気もする。
で、現実のカタリ派組織については、著者は完徳者のカリスマと信者との人的・象徴的つながり、そしてカタリ派神学や聖書などのテクスト共同体ではなかったかと。
この12世紀後半から13世紀にかけては、身体というテーマが頻出してくる。ベルギーのベギン会などもその一反応。キリスト教の教説内に身体観の振れがある、その振れに敏感になったのがこの時期。p120にあったいろいろな水準でこの身体という振れが論じられ、語られた、というのが、今のまとめかな。
テクスト共同体とかに関しては、前にたぶん「ウェブ社会をどう生きるか」(あるいは多神教と一神教)で書いた「モバイル宗教」という動きの続きになるのかな? 近代になり宗教改革をへて「プロ倫」へ。現在は自動車そしていわゆるモバイル。孤立化と拡散化とグローバリゼーション、てっとりばやく言えばエントロピー最大化(笑)。
(2012 04/04)
変化への恐れと女性身体観
カタリ派の章を読み終えた。今日読んだところの自分なりのまとめをすると標題のような感じ。
中世人の世界観ではあらゆる変化は衰退であり腐敗であった。
(p127)
社会が動き始めたこの時代、余計に不動の世界に憧れがましたのかな? そんな変化…生殖と死を代表するのが身体、それも女性の身体。そういったものへの恐れはカトリック側もカタリ派側も根は同じ…という。
そこに新たな動きとして「聖体拝領」とそれによる身体観の肯定が現れる。前に挙げたベギン会などの聖女はその一例。女性側から聖体としてのパンを肉体的に味わい、生殖を肯定化していく。そういったことで、カタリ派の提出した身体問題を克服?していく…そんなプロセス。
ワルド派
ヴァルデス(リヨンの商人…ではなく?教会組織に関わる高利貸し?)が回心して清貧の仲間を結成し、説教の許可を得ようと宗教会議中のローマ教皇に会いに行くところまで…序盤と行ったところか。
(2012 04/05)
著者はワルド派らの、一般信者が俗語で聖書読んで仲間内で説教しようという動き、それに対するカトリック聖職者側の対応は拒否反応だけでなく、肯定的な反応もあったのでは、としています。ワルド派も単独としてあったわけではなく、いろいろな運動の一バリエーションだったのではないか、と。こうした運動に成功したのがフランチェスコ会などの托鉢修道会。失敗したのがワルド派…という二元論では割り切れない…と。
(2012 04/07)
ペトルス・カントールとヴァルデス
ワルド派後半。一昨日書いたヴァルデスたち等の一般信者の説教に対する反応の二通り。の一方を代表するのが、パリの(標題に挙げた)ペトルス・カントール。彼は、ヴァルデスを念頭に一般信者の説教の場を理論化した。それは当時の普通?の聖職者が説教に無関心なのに対する危機感の現れでもあった。このペトルス・カントールに学んだのが、後の教皇インノケンティウス3世。
そうした流れの中で、ワルド派も一部はカトリック側に吸収され、また一部はディアスポラ化し、地下活動化する。前者はやがて記述から消えるが、後者は…
(続きは次の日記にて…)
ワルド派(ここは複数形で…)
ワルド派の続き。
ディアスポラ化したワルド派は、出発地点のラングドックやロンバルディアより、当時としては周縁のピエモンテとかアルプス地方、またボヘミア・ポメラニアなど東方にも向かった。こうした流れは小さい共同体で、自分たちの起源をヴァルデスよりもっと古いコンスタンティン大帝や使徒時代まで遡って考え、聖書を中心にした「テクスト共同体」をなしていた。
で、こういう小グループはお互いの交流も少なく、ワルド派とひとくくりで考えるより、複数形で考えた方がよいとのこと。もう一つ。ワルド派はカトリック教会の最低限の関わりは持っていて、その点は普通?のカトリック教徒と違いはなかった。そんな中でオリジナリティーを持つ生活。それを伝えるのが、この本にある女性信者の告白であるし、「ワルド派の谷へ」で出ていた話でもある。
で(2回目)、こうした二重生活は、宗教改革、そして新教側に合流という形で終わる…って書いてあるけど、細かくみるといろいろありそう。さっき書いたカトリック側に吸収されたワルド派のことも合わせ。
小さな共同体、その中での組織化、とかいうとやっぱなんか新教側の一派みたいな感じだよね。そういう小さな組織がカンパニーとか会社組織とかになり…なんて勝手に想像すると、なんか「歴史は折り返す」のかしらん…
(2012 04/09)
フランチェスコ会
フランチェスコ会がキリスト教世界のヒエラルヒーに組み込まれる中で分裂していく。一方の穏健派は祖フランチェスコの清貧思想を緩和し「所有」と「使用」の法体系を作り上げていく。もう一方の精霊派と言われる人々は、フランチェスコに忠実に従い、教皇側の「世俗的」体制から離れていく。こうした人々のうちもっとも急進的な人々が「不服従の異端」として火刑に処されることになる…
(2012 04/11)
ベガンネットワーク→読書会?
第4章。フランチェスコ会の中の急進清貧派は、その一部が火刑に処されたことによって異端視されていく(著者によるとカタリ派やワルド派と違い、今回対象としている精霊派とベガンの場合は、最初から異端弾圧のメカニズムの対象となった人達である、と言う)。そうして逃げてきた精霊派の人達をかくまったのが、同じフランチェスコ会の一派ベガンの人達。ベガンの思想の元は既にこの時期亡くなっていて聖人化していたオリーヴィーという人物。真のキリスト教刷新は自分たちが行い、教皇を代表するカトリック教会は世俗的な「肉体的教会」である、アンチクリストである、というもの。
そのかくまわれた精霊派の聖職者と一般信徒の集まりであるベガンとの間で、聖書やさっき挙げたオリーヴィーなどの著書をより集まって読んでいく会合みたいなのも開かれる。この時代のリテラシー向上も注目ですが、なんだか近代の読書グラブや読書会の中世版…先駆け…のような気がしません? こういう伝統はこの時期から脈々と…最初はヴァルデスの聖書の言葉を教えてもらったところのように個別に細々と…こういう通史も見てみたい。
(2012 04/12)
ベガンその後…
第4章精霊派とベガンの章読み終わり。
ベガンなのだが、1318年の前にも書いた急進的清貧主義の精霊派聖職者4人が火刑になってから、ベガンへの弾圧も始まる。一方、ベガンの方では、地下の抵抗活動になり、精神的主柱のオリーヴィーだけでなく、火刑にあったベガンの仲間たちも聖人化し、火刑の翌朝にはそうした聖遺物を拾うベガンの人々が見受けられた、という。
でも1320年代には弾圧も過酷になり、1330年代にはイタリアに残党を残すのみでほぼ壊滅したという。教皇主権を否定する方向に走り、別の教会を建てようとした点では、カタリ派とベガンは共通点あるのかな?そして結末も…逆にカトリックとのミニマムな繋がりだけは残したワルド派はなんとか?残った…カタリ派もベガンも舞台はラングドック…
一方、教皇側では、ヨハネス22世が「所有」と「使用」は分離しない。よって、フランチェスコ会の清貧とはそもそも虚偽である、と判断(教勅)を下す。この辺、民法的にも面白いところかも?
これであと第5章のみ(だっけ?)。5章のうち、最初と最後の章がカトリック側の、異端を(ラベリングして)生み出す側の物語。中に挟まれた3章が、異端側の、「選択」した側の、テクスト共同体の(カタリ派はどうでしたっけ?)物語。そういう構成。
(2012 04/13)
身体とダグラスとミメーシスと
というわけで?「異端者たちの中世ヨーロッパ」最後の第5章読み出したのですが、いろいろ混乱してうまくまとめられるかどうか、とにかく引用集(笑)。
p255から256にかけての「迫害社会」に関するムアとジラールの違いに関する考察。ムアはこの異端弾圧が始まった時代に、異端だけでなくあらゆる周縁者が同じ時期に迫害され始めた…という。ユダヤ人、疫病患者、同性愛者…でも、ジラールは暴力はあらゆる社会や文化の根源にあるものという。もちろん、これは正誤の問題ではなく、どちらの側面に光を当てるかによるのだろうけど…
…ここからは、カトリック側の対異端対策・言論が形成される過程が描かれる。キリスト教世界は、自然は身体になぞらえ、それに対する異端は穢れ、疫病、悪魔(及び例えられる動物、その動物や異端者内部での性行動の集会)とされる。人類学者ダグラスは穢れとは身体と環境との境にあるもの(汗とか垢とか体液とかいろいろ)と定義する。身体とは体系であり、体系を乱すものが穢れであると。そう考えると、西垣氏の情報概念は穢れになるのかな?
さっき挙げたジラールはこんなことも言っているらしい。
どんな馬鹿げた噂にも飛びつく興奮した集団心理が読み取れる。…(中略)…そうした状況を生み出すのは、相互に模倣し競合する過程で生じる秩序解体の危機であった。この「ミメーシス的競合」の理論は、中世異端の迫害を理解する上でも示唆に富んでいる。
(p286)
やがて、この激しい模倣の応酬の結果、相互の間に差違の消失の危機が立ち現われ、キリスト教の秩序は脅かされる。
(p287)
なんだかジンメルも参照してみたいところだが…模倣と差異化の応酬か…
喚喩と隠喩の違いは…
罪の説明と魔女狩り
第5章後半からピックアップ…
異端審問官って、中央集権的に管理されてたわけでなく、各個人に任されていたらしい。特に最初のうちは。
この時期は、異端審問の他に、最低限でも年1回の罪の告白がキリスト教徒に求められ始めた頃。でも、これまであんまり民衆そのものに興味のなかった教会側は、罪とは何かから説明しなければならなかった。それで、初めて告白の儀式をする農夫(だったかな?)にまず様々な罪を教えたところ、その農夫がその全ての罪を答えた。びっくりしたけど、よくよく聞けばただ繰り返していただけとのこと、という笑い話みたいな話もあったという。
一方、笑い話ではすまされないのが、魔女狩り。もともと魔術とかいうのは、それがキリスト教の教義に触れる時だけが異端で、ただ魔術をする行為だけでは罰せられなかった。けれど、ヨハネス22世の後くらいから、魔術そのものが異端とされ、それに付随するあるいはそれと関わりの深い(あるいは全然関係なくとも?)民衆文化が消されていった。という。
付け足し。魔女狩りのところは、どっちかというと、教会より、教会から独立してきた世俗権力…国家…が担当した、という。こうして、フーコーのいう個人に内在化する監視機能の初歩が(告白制度とともに)出来上がっていく…
(2012 04/15)
関連書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
