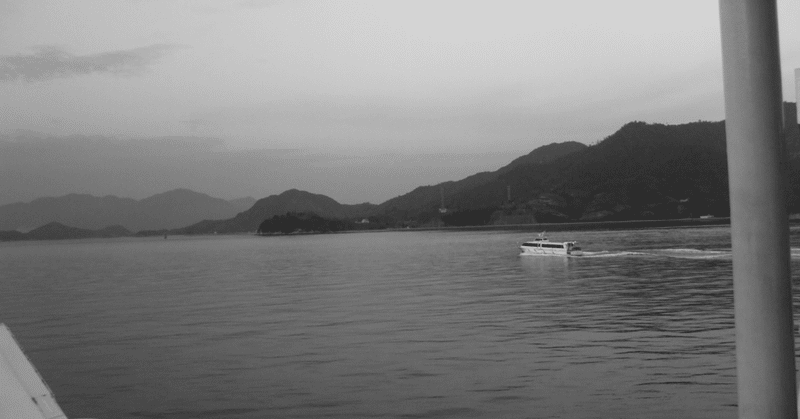
「クワイン」 丹治信春
現代思想の冒険者たち 講談社
現在は平凡社ライブラリーで出ている。
ホーリズムの船
われわれの信念体系という「人工の構築物」の内部構造は、ただ一つに決まるとは限らないのである。
(p107)
この構築物をクロスワードパズルのようなものだと考えるとわかりやすいのでは、という。確かにクロスワードパズルも本当に正解は一つなのかはわからない。そして新たなデータ、出来事の度に内部構造の補修をしていく。大改造が必要な時もたまには?ある。それがクーンのパラダイム変換だったりラカトシュのリサーチ・プログラムだったりするわけだ。この構築物全体を「ホーリズム」と捉える。大改造はそれが大変だという以上に、言葉の相互理解のために保守的に維持される。
われわれの船が浮かんだままでいられるのは、それに改造を加える各々の場合に、その大部分を継続事業としてそれには手をつけないようにするからである。ことばが理解可能であり続けるのは、理論の変化が連続的だからである。われわれは、破砕を避けられるだけゆっくりと、ことばの用法に変形を加えるのだ。
(p142 「ことばと対象」より)
「船」とは当然先の構築物のこと。次は翻訳不確定性について。
(2015 01/18)
カルナップとクワイン
哲学の主題は、世界のあり様そのものではなく、世界の記述の仕方取り決め方法、要するに言語の問題ではないか、として20世紀始めに「言語論的転回」が起こる。その中心の一つがヴィトゲンシュタインであり、もう一方がウィーン学団。後者は論理実証主義を掲げ、形而上学的なものからの離脱を図る。その中心人物の一人カルナップにクワインは会いに渡欧。心酔するけれど、後に対決する。命題記述に還元できるとするカルナップに対し、昨日書いた内部の構築物全体が重要で変化はその周縁で起こるとするクワイン。
まあ、思想は後に対立したけれど、カルナップが亡くなるまでよく交流はしていたみたい。あとは、クワインはかなりの旅行好きで日本にも来ている。最初の講義は真夏で、冷房ない為部屋の真ん中に大きな氷柱立てて、それが溶けてしまうまで講義と討論していたという。日本旅館で畳の上に原稿をばらまいて悦に入っていたともいう。
(2015 01/19)
翻訳不確定性
クワインは翻訳不確定性の取っ掛かり。翻訳の結果には無数のバリエーションがあり、どれも有用(話が通じる)がそれらは全く意味内容が違う、ということ。ホーリズムの構築物の内容が各世界で異なることからの帰着なんだろうけど、それだったら別にここでのデモクリトスのような例まで出さなくても、個人間でも社会間でもありふれていることでは…でも、クワインの考えているレベルはそれとは違う気がする。
(2015 01/22)
翻訳は不確定ではあるけど、バリエーションが複数できるだけで不可能ではない。不確定であって不可能ではない。著者の言う「心理主義的言語観」では「本当の言いたい内容」があるという立場に立っているので「不可能になる」けど、クワインの言語観はそこまで求めていなくて(本当の言いたい内容などない)、お互いの言語行為の繰り返しそのものだという立場なので、通用すればよい。
ところがクワインは自然科学に関しては「不完全性」とあたかもどこかに完全なものがあるかのように考えていた。でも晩年には自然科学においても「不確定性」の方になっていった。これも言語行為を通して…
(2015 01/23)
存在すること、非存在のものを思うこと
面白いけど、かなりややこしいのでそのつもりで…
「ペガサスは存在しない」という文でペガサスがいないとすぐに片付けることはできない。その文は存在しないものについて語っている。それは不可能だからペガサスは存在するのだ、という意見がある。また、「ペガサスは存在しないけれども、しかしあるのだ」という意見もある。
そこで?ラッセルが登場する。ラッセルは次のような書き換えをする(なんでペガサス文でないかはその辺ややこしくてまだピンと来てないから…)
「国会議事堂の四角い丸屋根は美しい」→「何かは、四角く、かつ、国会議事堂の丸屋根であり、かつ、それは美しく、また、それ以外の何ものも、四角く、かつ、国会議事堂の丸屋根であることはない」となる。それはそういう条件を満たすものが存在する、という趣旨なのだが、この文では偽となる。こうして存在しないことを主語にしたことによる存在・非存在の混乱?を避けることができた。主語は「何か」という宇宙全体なのだから。
こうした条件を満たすか満たさないかの表現をクワインは「量化の変項」と呼ぶ。「存在するとは、変項の値となることである」というテーゼの誕生である。
で、実際に何が存在し何が存在しないのかは、ホーリズムのいう信念体系の構築物中の文の変項を正しく導けば判明される、それが科学の仕事である、とクワインは言う。科学と存在論は表裏一体なのである。
最後にまだなんとなく捉えきれていない自分のクワイン観のヒントになる文が現代思想の冒険者たちシリーズの帯コピー?にあったので、それを。
「真理はその全体の連関にあって確かさを保ちながら、不確定の中を漂流する」
(「変形しつつ漂流する」の方がいいような気も…「真理」をどう捉えるかによっても異なるかも)
(2015 01/25)
一冊の本は、ただ一つの自然数で表される
第4章読み終え。指示(単語)や構文(文字の並び)も、ある一つの体系からもう一つの体系に翻訳するのにさまざまな可能性が出てくる、という話。
そんな中に出てきた標題の件。アルファベット文化圏での本の文字の並びをゲーデル数で表す。ゲーデル数とは各アルファベットや記号に各々素数(だっけ)を当てはめ、それを出てきた順番の数累乗するとかなんとか、いろいろする(笑)と出てくる数。例として出てきた3種5文字の列でも6桁くらいの数になったから、一冊の本になると、それこそ天文学的な数になるだろうけど、全く同じ文字配列の本でない限り同一の数にはならず、またゲーデル数からの復元も素因数分解すれば簡単?にできる、という。
進化の果ての人間
(あ、別に人間が特別とか終着とかいう意味ではない…)
というわけで、今日は「クワイン」を読み終えることができた。第5章「認識論の自然化」、いわゆる自然主義について。カルナップの合理的再構成(還元主義)が上手くいかなかったことを踏まえ、クワインは(行動主義的)心理学を取る。ヒュームの恒常的連接から因果関係を形成していくやり方もその一つとされる。学習とか進化心理学に近くなってきた。
本当の自分、自然から超越した自己というものを否定(クワインの無神論は相当に深い)し、哲学と科学の違いは相対的なものとする。でも、哲学には他の諸科学とは違った側面もある。
それではいったい、全体としての世界はどのようなものなのか、そして特に、われわれ人間はその中で、どのような位置をもつのか
(p252)
さて、こうしたクワインの自然主義に対し、一ノ瀬氏は「制度的事実」はどうそこから導けるのか、と疑問を呈していたのだが、どうだろう。本当に道はないのかな。人間の言語・社会活動において自然主義はどう翻訳されていくのだろうか。前に聞いた「言語環境に暮らす人類」の問題として捉えなくてはならないのだろうけど。
あと、著者丹治氏は自身の直観として、これから自然主義的な考え方が引用されることが多くなってくるのでは、と考えているようだ。
(2015 01/27)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
