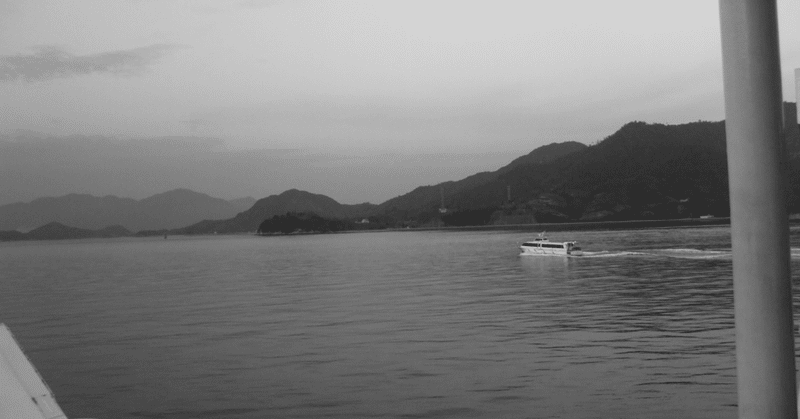
「アルチュセールの思想 歴史と認識」 今村仁司
講談社学術文庫
中野古本案内処で購入。495円(税込)
(2020 08/06)
序章から
(これは中の論文(1970年代前半)より後、補足で書かれたもの)
歴史的(伝記的)マルクスと理論的マルクスを切断しなければならない。
マルクスの弁証法を上部構造と下部構造の矢印の向きを反対にしたものとして見る見方は、ヘーゲルの弁証法を逆向きにしただけで、マルクスの独自性が見えてこない。
ヘーゲルのはめ込み可能な等質な空間は、マルクスによる様々な要素が絡み合っていて、それらは独自性を持つ。時間も等質、目的論的なものではなく、異質な要素が組み合わさっている。
(2020 08/08)
今日、序章読み終わり
個人はイデオロギーの世界に「投げだされる」ことによって「主体」に「成る」。ところで、このような「主体になること」のプロセスを起動させるのが、「呼びかけ」である。社会とは象徴体系をもつものであり、それはさまざまの象徴的手段をもってたえずシャワーのように個人に「よびかけている」。「呼びかけ」によって、無規定個人は「某国の、何某として、何かの地位ないし身分をもち、何らかの役割を果たすもの」として複合的に形成されていく。社会とは象徴的関係の固まりであり、それは複数の「呼びかけ」の束である。
(p36-37)
イデオロギーと呼びかけはどう違うのかな。イデオロギー(普通使われる意味での党政治テーゼとかいう意味ではない)が何らかの他者へのベクトルを持ったものが呼びかけ?
一方、もう一つのマルクスの用語「生産様式」は今の言葉でいうと「構造」だという。
この呼びかけ理論はフロイト-ラカン特に後者の鏡像界と似ているし(ソ連系伝統的マルクス主義ではフロイトとマルクスを結びつけるのは御法度)、フーコーとブルデューの仕事にも(権力装置とかハビトゥスロンとか)継承されているし、テクストの読み方(書物を諸処のテクストとディスクールに分解した)には後のデリダに継承されている(デリダはマルクスの脱構築読みを実践しなかったが、それは既にアルチュセールが行なっていたから?)
(2020 08/16)
思弁的観念論(ヘーゲル)は、マルクスが言うように、実在を思考(論理、精神)の結果だと考えて、思考と実在とを混同する。経験主義的観念論は、実在に関する思考を実在そのものに還元して、実在と思考とを混同する。両者いずれも、一方を他方に投げ入れる。
(p72)
そこでマルクスが登場するわけか…
(2020 08/28)
経済学の対象と経済現象の追及
「経済学」が自己を定義づける「対象としての経済」とは、「経済学」にとって問うべからざる絶対的所与であるが、これをこそマルクスは批判しなければならなかった。
(p88)
どうして(いかなる理由で)古典派経済学は経済学の対象を問う自己言及を禁じ手としたのか(軽く定義くらいはしてたとは思うけど)。それは、世界の同質性に依拠していたから、とここでは言う。この同質性という性質はヘーゲルもまた同じ。
(2020 08/29)
経済現象は、経済学にとって所与であったが、さらにその背後にそれを所与として定立させるいまひとつの、より深い、所与、いわば絶対的所与としての人間学がある。「経済的なるもの」の定義は、この人間学の作用であり、人間の欲望が一定の事象をそのように規定するのである。
(p91)
マルクスの批判は、この「かくれたる神」であるこうした人間学(欲望によって個人も社会も動く)を拒否するところから始まる。
マルクスから科学認識論へ
マルクスの仕事は単に経済学だけでなく、諸科学の認識論の革命・断絶を視野に入れている。ということで、アルチュセールへと続くフランス認識論から、アレクサンドル・コイレ、ジョルジュ・カンギレーム、ガストン・バシュラールを。
コイレは「ガリレー研究」「天文学革命」といった近代物理学の「革命」期の研究で知られる、バシュラールと同時期の研究者。彼は科学史の「連続主義」、「萌芽、先駆者」探しを徹底的に批判する。
コイレの研究を近代物理学以外、特に医学史、生物学史に広げたのがカンギレーム。
「科学史とは何についての歴史なのか」。この問いは根本的原理的な問いである。
この同義反復的テーゼを根本的にうちくだくことがなければ、他の歴史研究と同様、科学史も科学的になりえない。
(p102)
最後はバシュラール。今村氏は、ここではドミニク・ルクール「ガストン・バシュラールの歴史的認識論」を引いている、とのこと。
バシュラールが発見したことは、科学はそれに固有の実践の外側では対象をもたぬこと、したがって科学はそれ自身の実践の中で独自の「規範」ないし「規準」を生みだす、ということである。
(p110)
このp110と次ページ辺り、前の所有者の書き込みが凄まじいが(笑)、それはともかく、ここで言っていることは、科学それ自体の営みを営みながら、自らの「対象」とか「規準」と言われているものを作り出している、ということだろうか。この文についてはもう一度じっくり考えておきたいところ。
(このルクールは前に読んだカンギレーム(カンギレム)のクセジュ版の著者)
(2020 08/29)
ヴィジブルとインヴィジブル
理論的問題設定によって定義された領域内にある何ごとかを「見る」ということは、主体の眼の働きではなくなる。対象や諸問題のなかで見られるのは理論的問題設定の領域そのものである。ヴィジブルなものがこのように定義づけられるとすれば、インヴィジブルなものは、ヴィジブルなものの裏、つまり、理論的問題設定の構造によって可視性の世界から排除されたものである。一定の理論領域の中に新しい問題や対象が現存していても、理論的問題設定によって理論の対象であることを禁止され、抑圧されるかぎり、それらはインヴィジブルなものとしてとどまる。
(p142)
非本質的部分は、対象の外部、対象の目に見える表面を占める。本質的部分は、対象の内的な部分、目に見えない中核を占める。ヴィジブルとインヴィジブルの関係は、内部と外部との関係、つつみ-つつまれる関係である。
(p146)
p146の文章は第1、2文と第3文の内部と外部の配置が裏返しになってるからちょっと間違えやすいのだけれど、このp146で言われるヴィジブルとインヴィジブルが、p142で言われているヴィジブルとインヴィジブルと同じなのかどうかがまた曖昧。だいたいは同じなのだろうけれど。
まあ、マルクス-アルチュセール-今村の側から言えば、インヴィジブルなものを見えるようにし、本質的部分を分析することこそ重要ってことだろうけれど。それには「理論的問題設定」自身を解体せねばならない。となる。
円と円の概念、ヘーゲル批判にヘーゲル使うマルクス
円の実際と、円の概念の区別。スピノザがデカルトに対しこの二つを混同していると批判。マルクスはヘーゲルに対し二つの混同を批判するが、その際認識は実在的対象とは全く別の過程で生産されるとマルクスはいう。ここかなり気になるというか批判に晒されそうなところだけど、そこでは思惟の対象、理論的生産諸手段(まあ平たく言えば認識能力とか判断の認知構造とか?)、歴史的生産諸関係(理論的、イデオロギー的、社会的)の結合で認識されるという。まあ、それはいいとして…
論理的序列と歴史的序列の関係。経験主義は歴史的序列に論理的序列が従うべき、ヘーゲルは論理的序列に歴史的序列が従うべき、とする。に対し「マルクス主義的」認識論では「両序列間の一対一対応関係」を神話として消滅させなければならないとする。この新たな全体性認識は「資本論」で展開されているというが…
マルクスの「論証」について。マルクスは、ヘーゲルの枠組みを批判するときに、あえて意図的にヘーゲルのモデルを使うという。マルクス主義的認識論は起源・生成といったイデオローグを批判し、現在の社会から認識作用から、過去の社会・認識作用を把握できると考える。「人間の解剖は猿の解剖のカギである」。
(2020 09/04)
認識論的切断と古典派経済学との対峙
第三章「理論的実践の構造」の最後の部分。「理論的実践」とはマルクスの言う「実践」(個々の行為そのものではなくそれらが束になった構造的なもの)の一種。経済的実践と同じように原料があり、生産者と生産手段があって、生産物が生じる。そこで原料と生産物は素材(要素)は同一だが、構造は異なるものとなる。というところにバシュラール由来の認識論的切断がある、という…のだけど、どうかなあ。少なくともクーンの理論とは全く別物のような、そしてこの考えと、ヘーゲルの即自-対自-即自対自という弁証法を比較対象と果たしてできるのかな、とも思う。
続いて第四章「理論的実践の一例」の始めの方。ここでも、古典派経済学との対峙が重要ポイント。
経済現象が量化可能なものとして同質的な現象であり、そのようなものとして経済が定義されるうるのも、人間が欲望の主体として、生産し、交換し、消費するところの人間学的構造の方向づけを前提としてはじめて可能である。
(p186)
これは当然、古典派経済学の方。
リカードゥの「分配」の概念は、マルクスが指摘するように、本来的に「生産」に属するものと、本来的に「分配」に属するものを同時に含む概念である。
(p189)
リカードゥの理論を殆ど知らないのだが、スミスの古典派経済学の完成者で一般的には「生産の経済学者」と言われているという。ここでの分配の二重性が、リカードゥが生産ではなく、欲望=消費の人間像を基本においていたことの証左だという。この辺り、今村氏の経済学、人間学とも交わる箇所であるだろう。
(2020 10/13)
理論的原料(リカードゥ)を変革する理論的労働手段(ヘーゲル)それ自体が、その変形の労働によって変革されるのである。その結果が、『資本論』の中で作用している弁証法である。それは、もはやヘーゲル弁証法ではなくて、全く別の弁証法である。
(p221)
リカードゥ追加…
(2020 10/28)
第6章「歴史と認識-アルチュセールとアルフレート・シュミット」
ここと次の第7章はドイツとイギリスにおけるアルチュセール理論への批判の検討。6章では前者。
前提…フランスのアルチュセール(構造主義)批判は、サルトルやルフェーブル、ゴルドマンらによって行われた。彼らは、「構造主義者」達の認識論的成果を認めつつ、それはイデオロギー的には高度資本主義の肯定的イデオロギーに成り代わる可能性を含んでいた、というもの。
だが、ドイツ代表?アルフレート・シュミットは認識論的評価もまるごと「構造主義からの歴史への排除・攻撃である」と批判する。
シュミットの引用は2箇所とも最後の「理論と歴史、歴史と構造」から。
アルチュセールが主張したことは、科学的認識過程(思考過程=理論)と実在的社会史的過程とを直接的に連関させることは、認識論的には不可能である、というのであった。
(p287)
実在社会に理論を当てはめようとする時、その実在社会は頭の中で既に「理論」化している。
生きられた-生きられる歴史は、認識論的には(つまり科学的認識のなかでは)認知不可能である。それは、認識論的な《無=ゼロ》であり、イデオロギー的には内容豊かな《無限》である。
(p288)
特に後者《無限》が気になる。これは前のページではアルチュセールが「想像的な問題」と呼んでいるもの。そこに何が該当するのだろうか。考えてみたい。
科学的認識論と近代西洋哲学の基礎の「認識の理論」を区別する姿勢は、バシュラール一派はもちろんのこと、フランスでは一般的なもの。心理学ではピアジェが、その両者の関係についてはロベール・ブランシェが(アルチュセール学派のバリバールやマシュレー、そしてドミニク・ルクールの定義は科学的認識論に行きすぎていると論じている)論じている。
(2020 11/03)
イギリスにおけるアルチュセール
第7章からちょっとだけ。
イギリスのアルチュセール受容と批判は、フランスでのそれがひと段落したあとの1972年に盛んになった。
マルクス主義において、《歴史とは運動する自然-人間のシステムである。そして歴史の原動力は階級闘争である。歴史はひとつのプロセスであり、主体なきプロセスである》。
(p308)
マルクス主義は置いとくとして、ここにアルチュセールの社会の見方がよく現れていると思う。そしてそれは、イギリスのジョン・ルイスの人間主義的、ヘーゲル弁証法的なマルクス主義とは大きく対立するものである。
(2020 11/04)
まず第7章続き。ルイス批判論文の頃、アルチュセールはこれまでの自分の認識論を自己批判するようになる。要点をまとめると、哲学には「対象」などはなく、あるのは理論と理論の間の階級闘争である、また哲学と科学の関係はこれまでは哲学→科学(タレス→プラトン)であったが、マルクスから科学→哲学(科学者マルクス→哲学者マルクス)になったというもの。今村氏によれば、この自己批判は以前の全面否定ではなく、補充であると考えた方がいいとのこと。
アルチュセールと人類学
第8章は人類学を含み、今村氏の研究テーマの一つと重なり合う…のだけど、ここでは素描という感じか。アルチュセール派ではないものも含め気になるもの。
1、現代の科学精神はバシュラール的段階を「既に」超えている?
例えばレヴィ=ストロースの人類学、ジャック・ラカンの精神分析、社会科学におけるサイバネティックスの応用、等々で-展開されているように、人間、社会の諸事象は、《コミュニケーションと交換の一般理論》によってトータルにつかみうる
(p334 ミシェル・セール)
2、(この時代(1970年代)の現存する)社会主義国家の共産革命論との関係(シャルル・ベトレーム)
第三世界からの研究とこれまでの概念見直し(ガンダー=フランク、サミール・アミン等)
3、ゴドリエの理論、神話分析と物神論
レヴィ=ストロースの神話学の対象と『資本論』の物神性(フェティシズム論)は、ゴドリエによれば、たがいに重なりあう。ゴドリエは、レヴィ=ストロースの神話分析の手法(言語学モデル)をマルクスの理論に結合させて、未開社会と近代資本制社会とを貫徹する《社会関係のフェティシザシオン》過程と構造の理論を構築しようとしている。
(p346)
最後に「文献解題」からも二つ。
「資本論を読む」で共著者の一人のピエール・マシュレー。この人はまた「文学生産の理論」という本を書いている…確かこれ、「文学理論」の解題で冨山氏が「次の10冊」とかで紹介して図書館になかったヤツでは…
アルチュセール「哲学と科学者の自然発生的哲学」…一見よくわからないタイトルだけど、これは1960年代の自身の見解を批判していく第二期の作品。哲学と科学には唯物論的志向と観念論的志向の方向性があり、どちらかといえば観念論的になりがちな哲学と科学に介入して、唯物論的志向に変えていくことが自身の哲学の使命だ、ということらしい。
(2020 11/06)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
