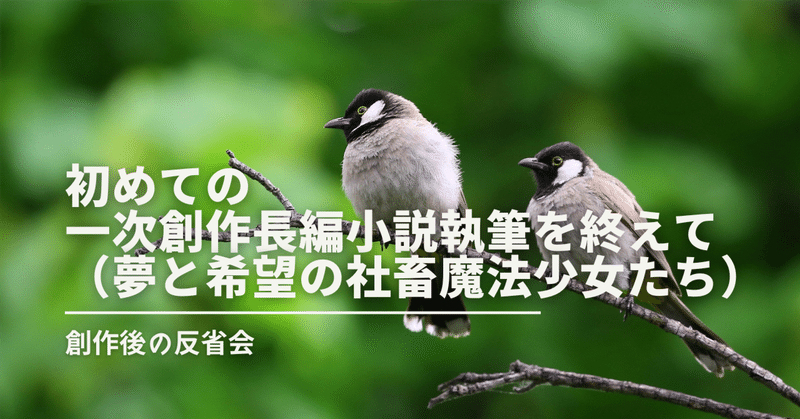
【反省会】初めての一次創作長編小説執筆を終えて(夢と希望の社畜魔法少女たち)
今回、私は初めて一次創作の長編小説を執筆しました。
それが「夢と希望の社畜魔法少女たち」です。
第十話までで区切りが一旦区切りはついているので、この執筆を通じての反省会をしようと思います。
特に大きな反省すべき点は4つありますので、今回はそれをここに記しておき、私が後で振り返ることが出来るようにしておこうと思います。
(なお、本編は下記にありますので興味がございましたらご覧ください)
1.長編小説を書く時は体調を万全に整えよう
今回の最大の反省点は、小説を書くための技術的なことではありません。
長編小説を書く場合は「自分の体調を万全に整える」ことが大事だと痛感しました。
長編だと10万文字前後は書くのがおそらく一般的かと思いますが、当然、これだけの文章を1日で書くのは物理的に不可能です。
(1秒で1文字書いて一切修正しなかったとしても約28時間かかる)
1ヶ月あるいはそれ以上の長期間かけて少しずつ書いていかないといけないのですが、それはつまり「1ヶ月間以上体調をキープし続けなければならない」ということでもあります。
〆切がなければ気にしなくてもいいのかもしれませんが、仕事だったり公募に出すなどの目的があるならそうもいきません。
私の場合は昔から頭痛持ちだったので、案の定、寝込む日が多くなったことで完成させるまでかなり難航しました。
5月末に処方してもらった薬で頭痛が飛躍的に改善されたことで6月末の完成までもっていけましたが、薬が効いていなかったら今でも完成しなかっただろうと思います。
小説執筆に限らないことですが、体が資本というのは間違いありません。
2.キャラクターをしっかり立てよう
最初に話を考え始めた時、まずは自分が好きなものを書こうと決めたので「大きい剣を振り回す女の子」を書こうというのは早い段階で決まりました。
ストーリーのテーマも「憧れからの脱却」にすると早めに決まったのでここまでは良かったのですが、肝心のキャラクターがだいぶブレました。
これは一次創作ゆえの難しさですが、自分の頭の中でしか存在しないものを描写するというのは本当に難しいです。私は現在進行系でイラストの勉強もしているため、小説もイラストも一次創作のキャラクターを描くのは困難極まりないと痛感しています。
キャラクターの生い立ちや設定などは事前に作ってメモしてあったのですが、そのメモ程度では人間を1人作り出すところまでは至れなかったということでしょう。
恥ずかしながら実際に作った主人公の設定は下記になっています。
白樺ココ
15歳の魔法少女。
7年前、朔夜に助けられて魔法少女になることを目指す。
感情を表に出してしまいがちで、嘘がつけない性格。
しかし、本人は実はあまり感情を表に出すべきではないのではないかと悩んでいる。
芯が強く、不当な扱いには断固抗議する。また、他人の嘘や裏切りを許さない。
当人は気がついていないが、そういった人間らしい一面が周囲の人間を次第に惹きつけていっている。
おしゃれが好き。
魔法少女事務所に念願かなって所属するが、かつて自分を救ってくれた朔夜がそこでスタッフとして死んだ目で働いているのを見つけてしまう。
魔法の杖は両手剣の形状をしており、力を開放すると圧倒的な威力を見せる。欠点は両手じゃないと力を開放できないこと。
魔法少女名は「スノードロップ」
衣装は白を基調とした形となっており、ウェディングドレスに間違われてもおかしくないデザイン。
チビと言われることが何よりも嫌いだが、実際チビなのだからしょうがない。
改めて見たときに問題点は2つあります。
1つ目の問題点は、設定と実際の本文中での描写で食い違っている部分が生まれている点です。
そうなってしまう理由は単純で、作者である私の頭の中で明確なキャラクターのイメージが生まれていないからだと思っています。
ではなぜ頭の中で明確なイメージが生まれていないかというとそれが2つ目の問題点に繋がります。
2つ目の問題点は、キャラクターの設定がストーリー上で必要になりそうな要素だけで構成されてしまっていることです。
キャラクターを実在するかのようにリアルに描くためには、一見すると必要なさそうな日常生活に関する設定も考えておかなくてはいけないというのが今回の執筆を通じて気がついたことです。
「なぜこのキャラクターはこの場面でこのように行動したのか」ということに説得力や厚みを持たせるには、そのキャラが普段どんな生活を送っているのかという情報が必要不可欠なのです。
これをちゃんと考えておかないと、作者である自分の日常というのがキャラクターに映り込んでノイズになってしまいます。実際、今回のお話ではそれがかなり多くなっていると私自身も実感しています。
どこまでしっかり考える必要があるかは今後の私の執筆を通じて学んでいかないといけませんが、何時に起きるか、好きな食べ物は何か、嫌いなものは何か、どういうことをされると怒るのか、など様々な情報を固めておく必要があるでしょう。
結局のところ、どんな非日常を描くのだとしてもそれは日常の描写があるからこそ説得力やリアリティを持たせられるということです。
3.伏線は回収できるものだけにする
回収されてない伏線がかなり大量に発生してしまいました。
「協会」周辺の話が特にそうですね。あとは石動の過去の話もそうなっている気がします。
テーマの部分を描くことを重視しつつも周辺のことも書きたいとなった結果、伏線未回収になってしまうという悲惨な結果になっています。おそらく、群像劇を書くのが難しいというのもこれに近いことなのかもしれません(私は経験がないのでただの憶測です)。
しかも今回は一人称視点で書いてしまったので、伏線回収の難しさにさらなる拍車をかけてしまいました。三人称視点の幕間を2つ入れたのはそれを少しでも解消するための苦肉の策です。
回収できない伏線は張るべきではない、というか張ってはいけないと思うので、具体的にそれをどうやって実現するかは今後の課題です。
4.視点や時系列はできるだけ動かさないようにしよう
前段の話にも書いていますが、今回は幕間として主人公以外の視点を書いています。
ただ、出来ればこれは避けたいことです。
読んでいる側からすると視点が動くのは混乱するからですね。
幕間という形で独立させた話にしたのでギリギリセーフな気もしますが、幕間二では時系列の移動までしているのでこれも読者を混乱させるという意味で良くないです。そう考えるとやっぱりアウトですね。
視点や時系列を動かさないというのは原則かなと思います。
最後に
今回は自分自身の未熟さを痛感してしまいましたが、1つずつ反省すべき点を修正していくことでちょっとずつでも成長していけるはずだと思っています。
そのためにも、健康に気をつけて1つでも多くの作品を少しでも早く執筆することが大事かと思いますので、今後も精進していこうと思います。
時間が許す限りこのような反省点をまとめた記事も書いていこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
