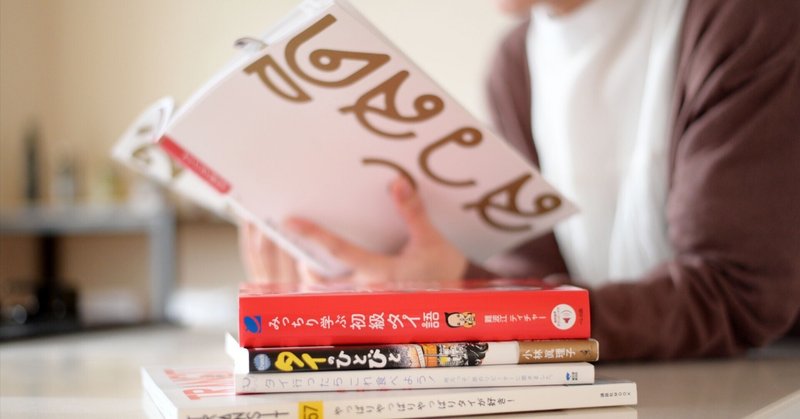
心理士、タイで駐在妻になるらしい。
ことの始まり。
2021年春。
長女が幼稚園に入園することになるそのタイミングで、
私は数年ぶりに社会復帰し、
スクールカウンセラ―、
児童相談所での勤務に加えて、
開業カウンセラーとしての仕事を始めていた。
そんなとき、不意に夫が話しかけてきた。
「えみちゃん、タイ料理好き?」
その質問に対して
「え?食べに連れて行ってくれるの?」と答えた私は間違っていなかったはず。
このときはまだ、
何がタイ料理なのかもわかっていなかった。
のちに、
タイ料理の声調(発音の仕方、声の高さ)にまで詳しくなるとは思っていなかった頃のこと。
それから2年近くが経った2023年3月。
3ヶ月半の夫の単身赴任期間を経て、
私はかくもタイ王国の首都バンコクで駐在妻生活を開始することとなったのである。
タイについていくのか、日本に残るのか。
夫のタイ赴任が決まってから、
いや、
正しくは会社から打診されから、
私と娘二人も帯同(タイについていくのか否か)を決めなくてはいけなくなった。
とは言っても、私は赴任の話を聞いてからずっと、ついていくつもりでいた。
なぜかというと、「面白そうだから」。
こういうと、ふざけたノリで決めたと思われそうだが、
もちろんそういうわけではない。
他の職業もそうかもしれないけれど、
私はつねづね臨床心理士は自分の体験や経験など、
その全てが身になり、捨てるところのない職業だと思っている。
大学院の入学式の日の、
「くだらないことをしないと、くだらない人間になってしまいます」という
某教授の言葉が、
10年以上忘れられないでいることも影響しているかもしれない。
でも、
私は特別頭が良いわけではないし、
さほど経験が多いわけでもない。
これは、私にとって結構なコンプレックスで、
活躍している心理士の友人たちを見ては、
私が、自分自身の〝強み〟として誇れることは何だろうか。
何もないんじゃないだろうかと、ずっと悩んでいる。
開業カウンセラーとして起業するときにも、
自分の強み探しは手こずったし、
いまだに「これ!」と胸を張れるものはない。
だからこそ、
今いる環境とは異なる環境に身を置いてみることに興味があったのかもしれない。
日本の「こうあるべき」に知らず知らずのうちに侵されている思考が、
どういうふうに崩されるのか。
噂に聞く「マイペンライ(問題ないさ)」なお国柄に、
どんな影響を受けるのか。
それが楽しみだったのだ。
想像と現実の違い。
夫が単身赴任していた3ヶ月半の娘たちの寂しそうな様子と、
夫に再会したときの嬉しそうな様子を振り返っても、
このとき、帯同することを決めたことに後悔はない。
ただ、タイの予想以上の物価の高さと、
欲しいものがすぐに手に入らない環境。
加えて渡タイしてすぐ1ヶ月間まるまる娘たちの春休みで
自分時間がもてないことなど、
色々なことが重なり、
最初の数週間は結構、いや、かなりうつうつとしてしんどかった。
加えて、
普段は低容量ピルを服用することで軽減していたPMSが非常に重く出てしまい、
イライラしたり落ち込んだり、
大声をあげて泣いたりと、
家族にもとても迷惑をかけてしまった。
適応障害になるんじゃないかと本気で不安になったし、
夜寝る前にどうしようもない不安感に襲われて、
自分が知っている方法で対処しようとするもののうまくいかず、
夫に泣きついたこともあった。
正直、
国内ではあるが引っ越しは何度も経験しているし、
自分のことを柔軟性のある人間だと思っていたので、
こんなにしんどくなるとは想像していなかった。
しんどくなっている自分が情けなくて、
それもまたうつうつする要因になってしまった。
無駄な自己肯定感の高さが、
しんどさを加速させてしまったのかもしれない。
それを隠してキラキラした情報だけを流すのもしんどくて(別に流さなくても良いのだが)、
当時の仕事用のInstagramには、
結構しんどい状況も隠さず投稿しては、
人から優しい言葉をかけてもらったり、
「無理に楽しまなくても良いってわかって安心しました」という、
駐在妻予定の方からのメッセージをもいただいたりしていた。
私にとって、この仕事用のInstagramアカウントの存在は大きかった。
個人で仕事を始めたことで多職種にわたり知り合いが多くでき、
心理士さんたちとのつながりも、それまでとは桁違いに増えた。
そして、お互いの発信を見ているので、
年に一度の学会で会うだけの関係よりも、
もっと密につながることもできるのである。
そんな人と関わることで私が助けられたことも多くあったので、
このタイミングで関わってくれた方々には感謝してもしきれない。
〝頼ること〟と〝甘えること〟。それが私には難しい。
さて、何度か書いたように、
我が家は帯同するまでの3ヶ月半、
夫は先にタイに渡って単身赴任をしていた。
というのも、
夫の会社の規定で、
夫自身が生活と仕事に慣れるまでの間、
家族が引っ越してくる準備を整える間、
3ヶ月間は家族は赴任先についていくことができないのである。
これについて「なんで?」と人に聞かれることが多かったが、
いざ私たちがタイに到着してみると、
私が右も左もわからない状態でなにもできないなか、
先に駐在員の先輩にタイでの生活のいろはを教えてもらっていた夫がいたことが何より心強かった。
もしここで夫も右も左もわからない状態だったとしたら、
と考えると恐ろしい。
そんなこんなで、
我が家の場合は幼稚園の修了式が終わってから渡タイすることにしたので、
3ヶ月半の間、夫不在の状況となったのである。
この未就学児2人のワンオペ育児、
最初のうちは人から「大丈夫?」と聞かれても、
「案外気持ち的には大丈夫やけど、体力がもたなくて」と答えていたし、
そう考えようとしていた。
だが、夫が渡タイした途端に体調と睡眠に異常が出た時点で、
全然大丈夫じゃなかった。
ある日、
長女の幼稚園から、長女が嘔吐したので迎えにきて欲しいと電話がきた。
そのあとすぐ、
幼稚園に長女を迎えに行き、
次女の通う別の保育園に「姉が嘔吐して病院に連れていくので、予定よりお迎えが遅くなるかもしれない」と電話をし、
病院を受診し、
帰りの車で再び嘔吐した長女の対応をし、
次女を迎えに行き、
家に帰って夕飯を作り、
ぐったりする長女を看ながら次女に夕飯を食べさせようとしたら
「このごはん食べたくない」と言われ。
とうとう「お母さんだってしんどいんだよー!!!!」と、
爆発して泣いた。
全然大丈夫じゃなかった。
しんどいという思いを、
「誰にも頼れないし、甘えられないから」と蓋をしていただけだった。
それに気づいたのはワンオペになって約2ヶ月後のことだった。
そしてこの後、
無事に長女の症状が私にうつり、
繰り返す嘔吐で身動きが取れない状態になってしまった。
それでも、
私は「子供たちのご飯さえなんとかできれば大丈夫」と思っていて、
「誰かに何かをお願いする。頼る。」ということは考えていなかった。
しかし、
少し前にたまたま目にしていた、
「自立とは依存先を増やすこと」という言葉を思い出した。
あれ?
もしかして、
今の私は自立できていないということなのか?
もしかして、
私は人に甘えても良いんだろうか?
そう思うことができ、
私の実家よりも近くに住んでいる義母にヘルプを出した。
義母にヘルプを出すのは結婚してから初めてであり、
「迷惑じゃないだろうか」とめちゃくちゃ心配だった。
でも、義母は嫌な顔はまったくせずに娘たちに食事を準備してくれ、
私が動けない分、
たくさん娘たちと遊んでくれ、
最後には「たくさん一緒に過ごせて、遊べて幸せだった」
とLINEで連絡をしてくれた。
「頼ってよかったんだ」と思えたし
「頼ることで喜んでもらえることもあるんだ」と学んだ出来事であった。
そして、
「今までももっと頼っておけばよかった」と、少し反省した。
私の意地のせいで、
義母が娘たちと一緒に過ごす時間をあまりつくってこれなかったかもしれない。
この反省の結果。
というわけではないが、
私たちが渡タイする2週間前に、
義母と、義妹夫婦、甥、そして私たち3人でディズニーに一泊旅行をした。
(夫は不在)
そのときには娘たちも義母(ばーば)に存分に甘え、
一緒に遊ぶことができたようである。
そして私も義母とお揃いのマスコットキーホルダーを買ってもらい、
ニヤニヤしながら帰宅した。
そのマスコットキーホルダーはタイに来てからもしっかり棚に飾ってある。
この3ヶ月半のワンオペ期間中、
子どもたちが体調を崩さないか、
常に気を張っていたように思うが、
それでも、家族3人で支え合って乗り越えてきた3ヶ月半でもあったと思う。
特に、いろんなことを理解して、
妹の面倒をみながら私のことも気遣ってくれた長女には、
感謝以外の何も伝えられない。
本当にありがとう。
不治の病「人と関わっていたい病」に気づく。
タイに引っ越してから1ヶ月間は、
ちょうど幼稚園も春休みの期間だったので、
私と娘2人はまるまる1ヶ月間べったり一緒に過ごすことになった。
お出かけする先も、
遊びに行くところもどこに行けば良いのかわからず、
もちろん私自身も娘たちも友だちがいないので、
家の中で過ごしたり、
マンションのプールで遊ぶ程度で、
娘たちはかなりつまらなかっただろうと思う。
それでも、
その間に長女のホームシックが落ち着き、
同じマンションで仲良く遊べる友だちができたので、
彼女たちにとって必要な時間だったのかなとも思いたい。
そして春休みが終わり、
娘たちが幼稚園に通い始めたのだが、
バスが7時過ぎに迎えに来る我が家。
お迎えの14時30分までまるまる自分の時間なのである。
日本にいた頃は個人で仕事をしていたこともあり、
実務時間以外にも雑務が多く、
毎日なんだかんだ忙しくしていたので、
ぽっかり空いた時間をどう過ごせばよいのかわからなくなってしまった。
そして、知り合いが全然いない状況で、人恋しくてたまらなかった。
とにかく誰かと喋って、笑い合いたかった。
日本にいた頃から、
Instagramを見ていて、
バンコクにもボランティア団体がいくつかあることは知っていた。
そしてそこでボランティアを募集していることも。
本当は、数ヶ月タイで過ごしてから応募しようと思っていたが、
暇すぎて、
寂しすぎて、
2人の幼稚園が始まってからすぐに申し込んだ。
どれぐらいすぐかというと、
幼稚園が始まって2日目である。
家の片付けや整理など、
やることはいくらでも大量にあるが、
それらのやる気はまったく出ないので、
とりあえず外に出て人と関わることを選んだ。
これまでの1ヶ月間で、
人と喋らないと鬱々して病みそうになることはもうすでに実感していたので、
私にとってはゆっくり休むよりも、
人と関わることの方が最優先で重要だったのである。
不治の病「人と関わっていたい病」。
おそらく根本的な治療法はないが、対処療法は「人と関わること」。
まずは対処療法を取り入れたい。
これから続く、タイでの生活。
なんだかんだ書き連ねてはみたが、
夫のタイでの任期はおそらく5年。
私のタイ生活はまだ2ヶ月も経っていない。
タイでの生活はこれからが本番なのである。
きっと、
楽しく感じることもあれば、
この最初の数週間以上にしんどくなることもあるかもしれない。
それでも、
せっかくやってきたタイで、
私がしたいこと、
私にできること、
色々探して行動していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
