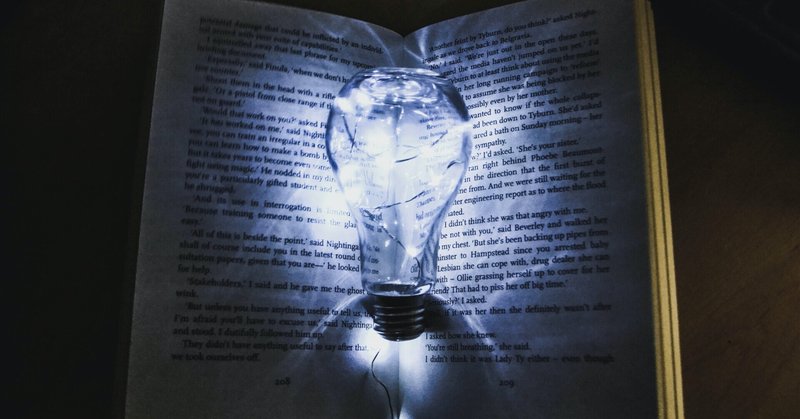
「理系的発想」と二つの〈想像力〉
世田谷学園は、「星新一賞」に何かと縁がある。
この「学友ANNEX」にも掲載している「脳内眼鏡」は、2019年に募集された第7回「星新一賞」のジュニア部門最終候補作だ。惜しくも受賞とはならなかったが、冴えたアイディアと卓越した文章力は、ぜひ多くの人に味わってもらいたい。
それ以前にも、第6回はジュニア部門グランプリと優秀賞を、第2回でもジュニア部門優秀賞を学園の生徒が受賞している。(まもなく募集が開始される第9回にも、多くの生徒が挑戦してくれることを期待している。)
ちなみに、「星新一賞」は、「理系的発想からはじまる文学賞」をうたっている。この言い方がなんとも絶妙で、単に「理系文学」としていないところに大きな特色がある。
* * *
ところで、伊藤亜紗さんをご存知だろうか。視覚障害者をはじめ、様々な障害を持った方々と直接やりとりしながら、多様性や身体性に関する研究をされている、気鋭の研究者だ。昨年も、「さわる/ふれる」の違いから、触覚がもたらす倫理の可能性を論じた『手の倫理』(講談社選書メチエ)や、スポーツを視覚以外の感覚に翻訳するというコンセプトから、スポーツ観戦の新たな可能性を拓いた『見えないスポーツ図鑑』(晶文社、渡邊淳司・林阿希子との共著、その成果は特設のウェブサイトでも公開されている)を刊行するなど、執筆活動も精力的に行っている。
2015年の刊行以来ロングセラーとなり、絵本作家のヨシタケシンスケさんによるカバーも目を惹く『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)には、伊藤さんの一風変わった経歴が紹介されている。
子供の頃から生き物が好きだった伊藤さんは、本川達雄さんの『ゾウの時間 ネズミの時間』(中公新書)に感化され、生物学者を志したという。この中から「いま読んでも胸がときめく一節」が紹介されている。
足りない部分を「想像力」で補って、さまざまな生き物の時間軸を頭に描きながら、ほかの生き物と付き合っていくのが、地球を支配しはじめたヒトの責任ではないか。この想像力を啓発するのが動物学者の大切な仕事だろうと私は思っている。(『ゾウの時間 ネズミの時間』p.138)
そんな伊藤さんだが、大学3年の時に文学部の美学専攻へと進路を変更している。生物学から美学へ。一見すると大きな転換に見えるが、伊藤さん自身はそのようには捉えていない。
その後、大学院に進学して博士号まで取得しましたが、結局自分は「自分と異なる体を持った存在への想像力を啓発する」という本川流生物学を美学の手法を使って実践しようとしてきたんだなあ、とつくづく感じます。(『目の見えない人は世界をどう見ているのか』p.24)
「自分と異なる体」というのが重要だ。我々は、視覚を中心とした感覚によって外界を認識している。だから例えば、全盲の人が認識する世界について、視覚が使えない代わりに、ほかの感覚で認識していると考えてしまう。実際には、視覚の欠損は、感覚の欠損ではない。だから世界の欠損でも、もちろんない。異なる感覚で認識される世界は、全く別の姿をしている。例えば、「ある全盲の男性は、柵の横を通ると『音的なしましま感』を感じると言います。」(『手の倫理』p.71)――言われてみれば「なるほど」だが、こんな相違が認識のすべてにわたって起きているのだ。
あるいは、先に挙げた『見えないスポーツ図鑑』でも、スポーツ選手の状況認識において、視覚以外の感覚がどのように機能しているかが、競技者・指導者とのやり取りの中で明らかにされていく。障害という特別な状態でなくても、身体はいとも容易く視覚を置き去りにする。
そして、このような他者理解に向かおうとする想像力の在り方が「理系的発想」なのではないかと思うのだ。
* * *
ところで、想像には二つの様態がある。「そこにないものを思い描く〈想像A〉」と、「そこにないものを、あるものと前提して考えを広げる〈想像B〉」である。
例えば、一瞬でどこへでも移動することができるドアを思い描き、「どこへでもドア」と名付ける。これは、〈想像A〉である。
もしも、そのようなドアが実現したら、この社会はどのように変わるのだろう。通勤通学の時間は消失し、公共交通機関も不要になるのだろうか。むしろ、移動が純粋に娯楽の対象となり、「どこへでもドア」は便利な道具ではなく、合理主義の象徴と捉えられてしまうかもしれない。このような想像は、〈想像B〉である。
当然、理系分野の研究においては、〈想像A〉の寄与するところが大きい。不可能を可能にする。今は誰も想像すらしていないことを実現していく。それは紛れもなく人間の想像力の産物であり、これは〈想像A〉の力だ。
しかし、それらの技術がどのように社会に実装されていくのか、それがどのように生活を変えていくのか、そういう視点は〈想像B〉の範疇だ。ひと昔前なら、科学者の倫理と社会的責任として議論された領域だが、今や、我々一人ひとりが想像力を発揮すべき領域に変わった。テクノロジーを利用することの倫理を、開発者や販売者に預けてしまえる時代ではない。
加えて、「そこにないもの」に、三つの様態が存在することにも注意が必要だ。すなわち、「本当にないもの」と「今ここにないだけのもの」と「あるのに認識できていないもの」である。伊藤亜紗さんも取り組む障害者の問題は、後ろの二つに含まれることが多い。これらは、ただ「ない」のではなく「ないことになっている」「ないことにされている」場合もある。この範疇を捉えるには〈想像A〉だけでは不十分である。そこにある溝を埋めるべく〈想像B〉を発揮することが求められる。
「理系的発想」からはじめて〈想像B〉を駆動した先には、新しい社会の可能性が広がっている。そこに、専門の別はない。誰もが幅広い情報の結び目(ノード)となって、巨大な岸壁を登攀する足掛かりになることができる。そうすれば、岸壁の向こうに肥沃な大地の広がりを発見することができるだろう。
鵜川 龍史(うかわ りゅうじ・国語科/小説家)
Photo by Clever Visuals on Unsplash
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
