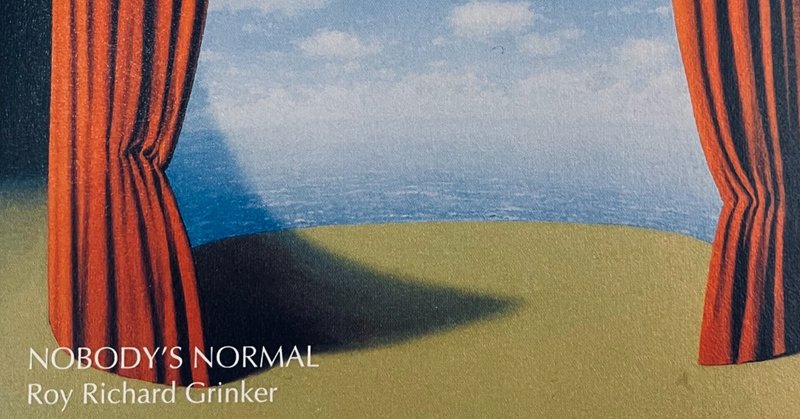
大好きな言葉からふと突きつけられた障害や差別への課題感。『ここがロドスだ、ここで跳べ』
『ここがロドスだ、ここで跳べ』は、マルクスの「資本論」やヘーゲルの「法の哲学」で引用された有名な言葉で、とても好きな言葉です。改めて調べると、AKB48の曲にもなっていたので流石秋元さん、と思いつつ。(昔々、秋元さんについて記したのも思い出しました。noteは過渡期の記録が主題なので今と違う思考かもしれません↓)
本題の言葉の出自は下記のようなイソップ寓話の物語です。
「ここがロドスだ、ここで跳べ!」(ラテン語: Hic Rhodus, hic salta!)とは、イソップ寓話の「ほら吹き男」の話をもとにした成句。あるほら吹きの競技選手が遠征先のロドス島から帰り、「ロドスでは大跳躍をした、みながロドスに行ったらロドスの人が証言してくれるだろう」と吹聴するが、これを聞いた男が「それが本当なら証人はいらない、ここがロドスだと思って跳んでみろ」と言い返したというものである。
(参照:Wikipediaより)
出自となった寓話の文脈で言うと、『嘘つきの戒め』としても捉えられる気がしますが、『理想論や妄想を語るのではなく、今ここで行動しろ(結果を出せ)』といった意味で使われていることが殆どだと思います。私もその意味合いでとても好きな言葉です。自分に対しての戒めとして唱えることが多いこの言葉ですが、ふと「ロードス島(ロドス)が誰にでもある社会だろうか」という疑問が浮かびました。
「障害という言葉の無い社会」を目指して生きてきたのはいつも綴っている通りで、その中で障害があることにより様々な機会損失があることにも沢山直面してきました。障害に限らず、所謂スティグマ(疾患や障害による差別や根拠のない烙印)に代表される様々な差別が当たり前のように存在する社会です。そんな社会で「ここで跳べ」と言えないことも沢山あって、その理由は跳んだ先に落とし穴が待ち構えているような環境もあるから、そしてそもそも「ロドスで跳んだ」という経験すら存在し得ない環境もあるからだと感じています。
もう少し具体的に考えると、「挑戦して失敗した時のセーフティネットを無視して挑戦させる」ことや「失敗した時のセーフティネットが無い(もしくは痛すぎる)から挑戦できない」ということが沢山あって、『ここがロドスだ、ここで跳べ!』という前に『ロドス(での経験)を作れているだろうか?』という疑問に直面しました。
この課題感はいつも感じていることなのですが、改めて自分がいつも反芻している言葉から突き付けられたような気がしてハッとしています。
少し抽象的な話に引き上げてしまいますが、アウシュビッツ収容所に収容されたユダヤの人々が『働けるか、働けないか』の基準でガス室に行くかどうかを決められたのは有名な話です。唯、現代でもこの基準は強く存在していて、『働けない』とされる障害や疾患(所謂スティグマ)があると社会はその存在を『働けない』人生へと強引に引っ張っていきます。
そして、現代の『ロドスで跳んだか、跳んでないか』は『働けるか、働けないか』つまり『何らかの実績や挑戦の跡があるかどうか(学歴や職歴など)』で判断されているとも言えないでしょうか。
拡大解釈ではありますが、「働けるか、働けないか」の軸で人を判断してしまうのは資本主義(成長主義)の非常に良くない側面だと思います。資本主義の枠の中では確かに必要な判断軸になることもあるのかもしれませんが、その軸が人への敬意を著しく損なうケースも多々散見されます。
私の父はその意味でいうと「働けない人」の期間が長かったので、父を自然と見下したり(本人は同情的で無意識なケースも多いです)、敬意を持たずに接してくる人を、幼少期からよく見てきました。私の父は私が最も敬愛する人ですし、父の中の多様な側面を見てもらえれば、誰もが敬意を持つ部分があると思っています。これは私の父に限らず、どんな人にでも言えることでは無いでしょうか。
話を本題に戻しますが、『ここがロドスだ、ここで跳べ』と思える社会、言える社会はとても魅力的だと思います。唯、そのロドスをどれだけ作れているのか。資本主義の枠で人を判断するような偏ったロドスや、何かしらのスティグマを作りそれを排除するようなロドスばかりが増えてきた人類の歴史にはなかった『新しいロドス』を作り出す必要があるのでは無いでしょうか。人の中にある多様性を尊重し、その「多様なロドス」が前提とされた中で『ここで跳べ』と思える社会をつくりたい思いです。
そんな文脈から、自分が目指す「障害という言葉の無い社会」は、『誰もが「ここがロドスだ、ここで跳べ」と思える社会』でもあるなと再認識しています。
『ここが資本主義だ、ここで跳べ』と言うなら大跳躍をする覚悟もあります。『ここが差別社会だ、ここで跳べ』と言うならそこで跳びながら闘う意志もあります。唯それは、私が跳ぶ先に希望があって、跳んだ先で落とし穴に落ちても誰かが引っ張り上げてくれるようなロドスでなければならないと思うし、そうであったから今自分はここにいるのだと思います。
抽象的な話になりましたが、あらゆる人の多様な側面に着目して敬意を持ち、その人のロドスがなければ共につくる意志をもち、それでいながら『ここが資本主義だ、ここで跳べ』と言われる日常と闘いながら、これからも『ここがロドスだ、ここで跳べ』と自分に言い聞かせる日々を送るだろうと思います。
命や人の価値を資本軸で合理化する社会から成長できるように。
『ここがロドスだ、ここで跳べ』と言い続けながら、多様なロドス島が存在する未来をつくりたい。
追記:写真は今年5月に刊行された「誰も正常ではない」という本です。今回の主題とは関係ありませんが、直近読んだ本の中で良書だったのでその記録も。本書は資本主義、戦争、医学と科学によって変遷してきたスティグマの歴史について多角的に捉えられていておすすめです。(滅多に本は紹介しませんがこれは良書だったので是非)
「誰も正常ではない」の448ページの中から一節だけ本書から引用して、考えたことを記録しておきます。
「ミクロネシアには、精神障害を逸脱としてではなく、親族の絆を強化する関係形成的な経験として解釈する社会が存在する」
障害や病気を、ネガティブではなくポジティブへの契機として真剣に受け入れる文化やコミュニティは確かに存在するようです。唯、今の日本では当事者にそんなことが易々と言える社会でもなく、他者が求めるものでもないと思いますし、それが主たる解決策とも思えません。
多様なロドスをつくること、全体最適な思考停止ではなく、個別の複雑な課題と向き合いながら「ここで跳べ」と言える社会実装をしていくことが今の自分の目指す姿です。
それが実現できた時、このミクロネシアの一例のような解釈が新しい倫理となり、一人ひとりの人間が絶望や希望と常に向き合いながらも、「ここがロドスだ、ここで跳ぼう」と思える未来をつくっていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
