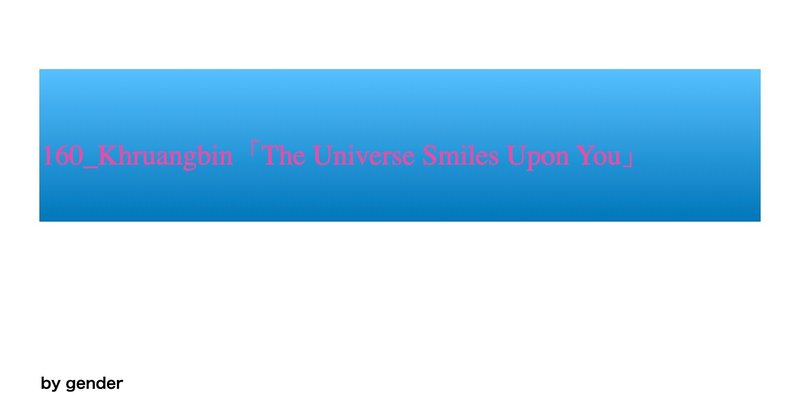
160_Khruangbin「The Universe Smiles Upon You」
どこからか子供の遊ぶ声が聞こえた気がした。ああ、またどこかの街のどこかの路地に迷い込んだらしい。午後のこの時間、どこからか海からの心地よい風が流れていて、私が着ている半袖のシャツの隙間にこの涼やかな空気が滞留している。
今日の朝見た自分の夢の中で見た光景を、外に出てずっと探していて、なんとなく自分が面白いと思った看板とか、目についた人を追っていたら、なぜかこんなところまで来てしまった。
幼い頃から、蝶々とか、知らないおじさんを追っかけてどこかに消えてしまう、なんともフラフラした危うい子供だった。両親もほとほと心配して困り果てて、私の体に紐でもくくりつけておこうかと真剣に考えていたくらいらしい。犬じゃないのだから、と母は祖母に叱られた。なんともおかしみのある話ではあるが、親にしてみたらそれだけ切実な問題ということだったのだろう。
私はそうやっていろんなところに消えていったが、不思議と危ない目にあったことはなかった。いつも親切な人のご好意に預かったり、周りが動いてくれて親に連絡してくれたりして、大体ことなきを得ている。
なんでそんなことをするのかと言われてもわからない。何かを追っている最中というものは私の意思が介在していないというか、特に何も考えていない。ある意味、それは瞑想のようなものに近い気がする。
その習性はある程度、歳がいっても変わらなかった。逆に電車やバスも利用するようになって、移動範囲が広がってしまった結果、悪化してしまった感がある。やっぱり私はどこかしらネジが一つ足りない人間らしい。友達に迎えに来てとお願いばかりするので、私は「迷子の宇宙人」と呼ばれた。(別に嫌われていたというわけではない)
私はそんなこんなで大学中退後も毎日やることもないので、日々こんなことばかりしている。家にいて、たまにギターを弾いて詞を書いて、それにも飽きて外の景色を眺めていると、ふと気付いた時には外に出ている。たまに靴も履いていない時もある。しかし、こういう生活をするのを私自身が望んだことだった。
さて、来たのはいいが、どうやって家に帰ったらいいのだろう。いつも、その場所に来てから気づいて、だいたい私は途方に暮れる。ここまで来れたのだからちゃんと帰れるでしょ、と人に言われるのだが、私にとってそう簡単な話ではない。誰かに電話をかけようかと思った矢先、この間も付き合って恋人に愛想を尽かされて、家を出ていかれてしまったを思い出した。
彼は財閥系企業に務めるエリートサラリーマンで、私とは全くもって正反対のまともな人間だったが、体の相性だけはなぜか非常に良かった。そこは彼も私も満足だった。私のことをちゃんとしっかりと人間にしたいとか言っていた。私は彼が言ってる意味がよくわからなかった。彼は私と結婚するつもりだったらしい。
彼はアウトドアとか旅行とかで、私のこのよくわからない習性のようなものを解消しようと試みたらしい。要は渡り鳥や鮭の遡上などと一緒なのだと。この前も相模原のキャンプ場のグランピングとやらに、二人で出かけた。焚き火をしながら、2人で夜空を眺め、ワインをくゆらす。そういうものがあれば大丈夫だろうと、彼は思っていたらしい。何が大丈夫なのだろう。私は別にそういうものは何にもいらないのに。
「やっぱり、こういう場所で日常のストレスを解消する必要があるよね」
「私は特にストレスないけど」
「…そうだね、僕は君と違って毎日大変だよ、上司の無理難題にも対応している」
「そう、大変ね」
「あのね、君さ。ホント変わっていると思うんだけど、普通の女の子だったら、こういう場所に来て素敵だねとか、そういう言葉が出てくるんだと思うんだけど」
「私が来たいって言ったわけじゃないし」
「でも、いろんなところに君はフラフラ出かけてしまうじゃないか。この間も、広島まで行ってしまって、迎えに来てとか電話してきて。無茶苦茶だよ」
「仕方ないの。気づいたら広島にいたんだから」
「君は、もう本当に…」
彼はそこでもう私と議論しても無駄だろうと気づいたのか、会話をやめてしばらくずっと焚き火を見ていた。
「君といると、たまに自分がとんでもなく、くだらない人間に思えるんだ」
「くだらない?」
「わからないかい?僕も君のようにフラフラとどこかに行きたいっていうわけじゃないんだ。君のやっていることは僕には理解できない。果たして君の存在が僕と噛み合わな過ぎて、こうやって二人でいること自体、不思議で仕方ない」
「でも私、あなたがいないと家に帰れないわ」
「そうだね、そのために僕がいるかもね」
彼は再び焚き火の火を見つめた。いつも理性的なのに、たまにこんな風に吐露するように感覚的なセリフを吐く。彼は私の中に何かを見つめている。それは私自身にもわからないものだが。
その夜は、バンガローの中で彼は激しく私の体を求めた。別に私は拒みはしない(いつも渋々、私のことを迎えに来てくれるし)彼は私が想像できないくらいとんでもないストレスのある日常の中で、抗し難い欲求のようなものを抱えて生きていて、それを私にぶつけてくるのだろうと思った。私はいつもそれを受け入れる。それくらいは私でもできる。でもやっぱり彼の言った通り、彼と私は違う水平線に立っているのだろうと、彼と体を重ねながら私は思っていた。結局、その晩は二人とも文字通り精も根も尽き果ててしまった。
子どもの声を追って、いつの間にか海の見える公園に私はたどり着いて、ベンチで彼とのあの夜を思い出したら、自然と体が反応してしまった。ダメだ、これじゃあ私がはしたない女みたいじゃない。やっぱり私みたいな人間は、彼のような保護者の庇護の下で一生大人しくしておくのがいいのかしら。私は私の人生というものをこれまできちんと鑑みたことはないのだが、確かにいつまでもこんなことばかりしていられない。
彼に連絡を取ろうかとスマホをタップして、やはり止めた。「今、どこにいるのかわからないんだけど、迎えに来て」だなんて、どの口で言えるのだろう。私は私の欲求を持って、彼を散々に振り回してきた。代わりに、彼の求めに応じて私の体を差し出すのも一つの契約の形なのかもしれなかったが、おそらく彼はそんなことを望んではいまい。彼の言う「人生の伴侶」とやら、私に対してきちんとしたパートナーになって欲しいに違いない。
結局、私は海風の吹く公園で、砂場や遊具で遊ぶ子供たちを見ながら、どうやって家に帰ろうか考えていた。子供たちの遊ぶ声が自然と私の眠気を誘う。このままここで眠ってしまおうか、そんな気分だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
