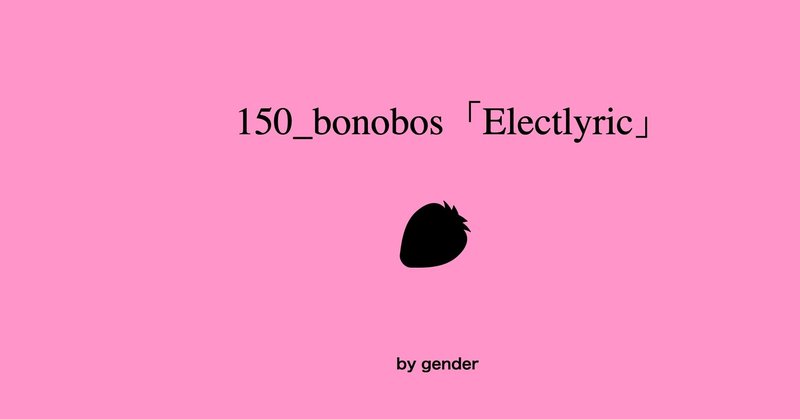
150_bonobos「Electlyric」
「あのさ、隠すなよ、俺のこと」
「え、隠してなんかないよ、ただ」
「ただ、何?隠してんじゃん、俺のこと、彼氏だよね。なんで、俺がアミの彼氏だってこと、みんなに隠ししてるの」
「隠してるわけじゃないよ、ただ、なんか自信がないだけ」
「自信がない、って誰が。アミが?俺はアミの彼氏だから、自信はあるよ」
「そういうんじゃない、なんか違うの、潤くんは彼氏だよ、間違いなく。そうだって。だから、それでいいじゃん」
「よくない」
俺はバタンとアイスカフェオレをテーブルに置いた。その音が、カフェの店内に周囲の目を引いたようだが、構わず派手な格好をした隣の女子の4人組は無駄話を再び始めた。学校のクラスの誰々がyoutuberになるとかなったとかで、機材持って学内を間抜けな格好でウロウロしているらしい。冗談まじりで話が盛り上がっているようだ。俺とアミとの間の沈黙を埋めるように、彼女たちの会話がマンガのふきだしのように現れては消えた。
「あいつじゃ絶対、動画盛り上がらないよね」
「再生数100とかだよ、絶対」
「えー、ちょっと興味あるから、見て見ようかあ。チャンネル登録するのは別として。顔だけはちょっといいじゃん、あいつ?」
「でも、話が致命的に面白くないんだよね、自分の話ばっか」
「自分大好きマンだから」
「言えてる。でもそういうのがyoutuber向いてんじゃないの」
ピーチクパーチク、隣の女子どもの話は終わる気配はない。うるさすぎて、俺はだんだんとイライラが募ってきた。アミも着ている白いワンピースの紐をいじっている。明らかにこの話はしたくない、という気配を暗に自分に伝えているようだった。何か俺が間違ったことをしているのっていうのか。
アミは友達の誰にも、俺が彼氏であることを伝えていない。そういうスタンスというか、それがやり方なんだよ、と言う。なぜ、そうなのか、具体的な理由を聞こうとしても、曖昧なことを言われてはぐらかされる。アミとはクラブで知り合った。俺は大学生で、彼女は飲食店に勤めるフリーター。
付き合った当初はこの娘はまあそういうものなのかな、とも思っていたけど、段々とその疑問が積もっていく。なんとなく小さく引っかかったように思っていたものが、ずっとまとわりついてきて、段々はっきりと目に映るようなものとして気になってきた。
アミと付き合ってきたこれまでの彼氏もそうだったのか、俺だけがそうなのか。なぜずっと隠しているのか。アミから友達を紹介されたこともないし、俺も俺の友達を紹介しなくていいと言われる。なんなんだろう、突き詰めたいことはいくらでもある。俺の追求を交わして、いつもそこはグレーにしたがる彼女に、俺はもやもやとした不信感を拭えないのだった。
「うーんと」
アミはレモンスカッシュをストローで飲み干した。液体はコップになく、ストローから空気を吸う音だけが響いた。やけに虚しく響く。
「さっきから、何こだわってんの」
「いや、だからさ。俺が彼氏だって認められていないっていうか」
「そんなことないよ」
「でもさ、例えばだよ、アミが友達とクラブに行ったとするじゃん。んで、誰か男が声かけてきたときにさ、話盛り上がって、誰か付き合ってるやついんの?みたいな時、どう答えるの?」
「そんな奴と話さないよ、潤くんっていう彼氏がいるんだし、そもそもクラブにも今はもうそんな遊びにも行かないし」
「でも、見たいのあったら、クラブ行くんでしょ」
「だから、その時は音楽目当てだから。男と遊ぶためにクラブ行ってんじゃないんだし」
彼女は深いため息をつきだした。器の小さいめんどくさい男だと思われてるんだろうなと想像すると、俺も段々と彼女を追求することがむなしくなっていった。しゅんと自分の体が小さくなっていくように感じる。
「つか、もうこの話やめない?」
「なんで?理由聞かせてもらってないのに」
「だ・か・ら、自信がないから、って言ってんじゃん」
アミは立ち上がって腕時計を見た。カバンを机の上に出して、片付け出している。「4時からバイトの早番だるい」とさっき話していたから、それを気にしているんのだろう。バイト前のだるい時にせっかく二人で会ってるのにこんな話しないでよ、と言いたげな顔だった。
アミの自信っていうのは何のことを言っているのだろう。僕はアミが特段、自信のない女の子という風には見えなかった。アミは背は小さいが、明るく染めた髪と周りとは違う独特のセンスのある格好で、クラブでまるで木の葉が風に舞うように一人で踊っていた。
「この人の曲、前本人から聞かせてもらった」
「この人がオーガナイズしたパーティに昔誘われて行ってみたけど、結構おもしろかった」
そういうふうに、アミの話を聞くところによると、どうやらDJやクリエイターの知り合いも多いようだった(だが、俺はもちろん彼氏として紹介されたことはない)どうやら、アミは自分だけのリズムのようなものを持っていて、一人だけでフラッといろんなことをする子なんだろうと思う。
自尊心の低い女の子といえば、アミとは別に自分の中で一人思い浮かぶ子がいる。同じクラスで目立つ女子グループの中に一人だけ少し毛色の違う子が混ざっている。別に特に外見が違うわけじゃない。(というか、大学も女子はみんな同じ格好をしていて俺は見分けがつかない)その子は一見いつも楽しそうに周りの女子と笑っている。
だが、彼女はいつもその女子と誰かと一緒にいて、一人でいるところを見たことがない。女子っていう生き物はまあ大体がそんなものなんだろうけど、俺はいつも、彼女の笑顔に違和感を感じざるを得なかった。自分の存在を認めていない、というものをかすかに感じるのだ。
アミが店を出ようとしてレシートを持っていくのを、俺は座ったままで眺めていた。別に会計は俺が払うつもりだったのに。アミはこういう時、彼氏の俺に対しても貸しを作るようなことをしない。俺の言うことを寄せ付けないような、頑としたものがあった。会計を終えたアミがツカツカと座っている俺の方に戻ってきた。彼女は背が低いから、立っていても、座っている俺と大体目線が一緒だ。
「自信ないのは、私、潤くんが最初だから」
「最初?」
「はじめてだってこと」
「俺が?はじめての彼氏ってこと」
「言わすな、バカ。ムカつく」
アミはそう言って、カバンを僕に投げつけてきた。周りから見たら、俺は滑稽なほどキョトンとした表情をしていただろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
