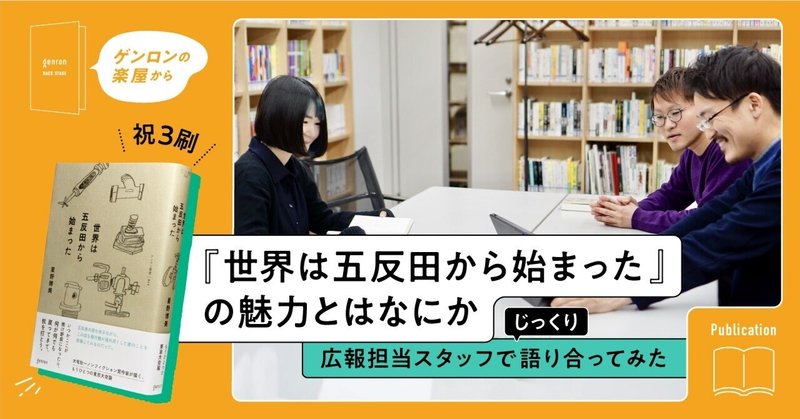
祝!第49回大佛次郎賞受賞!!『世界は五反田から始まった』の魅力とはなにか――広報担当スタッフでじっくり語り合ってみた
「五反田本はどうしてこうも読み手の心を揺さぶるんでしょうね」
『世界は五反田から始まった』。通称、「五反田本」。今年7月に発売、10月、11月と重版を重ねています。全国新聞や地方新聞に掲載される五反田本の書評、Twitterでの読書感想から弊社ゲンロンに寄せられるお手紙の数々。質・量ともに熱のこもった言葉は、著者・星野博美さんによって込められた軽やかかつ重みのある語り口に反応されたものでしょう。
かくいうぼく、ゲンロンスタッフの青山俊之もそのひとり。入社したての当初、「世界は◯◯から始まった」の◯◯に自分の出身地を入れ、自己紹介記事が書けるのではと考えたんです。五反田本の大きなメッセージは、戦禍を生き延び、その後にも知恵やノウハウを継承すること。星野さんが五反田本で描くまちと家族を掘り下げ、自らと世界をつなげることは、読み手をはじめ、いつかどこかの誰かにも開かれた営み、のはず。
「よし、ではその一歩を! だがしかし、いかにして……?」
思うように弾まないキータッチ。とはいえ、五反田本に垣間見える星野博美さんの気骨さや思わず読み手の記憶を呼び起こす地域や家族の描写といった魅力はぜひ読み手のみなさん、あるいはこれから書き手になるみなさんにもお伝えしたい。
読み手へと熱量を伝播する五反田本はどのような文章なのでしょうか?
書き手の星野博美さんによって描かれた五反田本はどのような社会や出版の文脈にあるものだったのでしょうか?
五反田本は、日本社会の影にある戦争の影響や現在のコロナ禍など、日本の近現代史が軽妙に織り込まれた傑作です。五反田本をささやかながら広報してきたゲンロンスタッフの青山俊之、栁田詩織、野口弘一朗は、そんな五反田本の魅力はTwitterのつぶやき字数では伝えきれない!とぼやいてきました。今回はこの3名が五反田本を振り返りつつ、その魅力を掘り下げます。

東京の地理感覚と大五反田圏
青山俊之 はじめに、五反田本の軽妙な文章をぜひ読んでみてください。
戸越銀座のわが家の車庫から路地を抜けて中原街道に出、ゲンロンカフェのある五反田駅界隈を通り過ぎ、JR山手線の高架下をくぐり抜けると、道路の名称はいつの間にか桜田通りに変わっている。そのまま桜田通りを直進し、建築家ヴォーリズの建てた明治学院大学のチャペル(一九一六年竣工)を左手に見ながら走り続けると、じきに高級ホテルと高級マンションに囲まれた、そこだけ二世紀ほど時代がずれているような、すすで真っ黒に染まった古い寺が左手に出現する。それが清正公だ。うちの車庫からは右折二回で到達する。
東京に居住したことがないぼくにはこの文章に登場する地理感覚や固有名は正直さっぱりでした。ですが、星野さんの自宅から目的となる「清正公」に至るまでの道のりの情景がくっきりと浮かびます。土地勘がなくても違和感なくすいすい読み進められてしまう。これはあくまで一例ですが、みなさんは五反田本の魅力をどのように感じましたか?
栁田詩織 わたしが惹きつけられたのは、五反田本に数多く出てくる家族あるある話です。サイコロ遊びの丁半や花札といった家族と過ごした昔の記憶を引き出しながら、五反田本のキーパーソンである祖父の量太郎さんのことばが出てくる場面があるじゃないですか。
時には少しまともな話もした。酒が抜けていたのだろう。
「ここが焼け野っ原になったらな、すぐに戻ってくるんだぞ。家族全員死んでりゃ仕方がねえが、一人でも生き残ったら、何が何でも帰ってくるんだ。わかったな」
博美にはさっぱり意味がわからなかった。
「そいでもって、すぐ敷地の周りに杭を打って、『ほしの』って書くんだ。いいな」
「うん、わかった」
「そうしねえと、どさくさにまぎれて、人さまの土地をぶんどる野郎がいるからな」
よく意味はわからないが、おじいちゃんがそう言うなら、そうしよう。
いつかここが焼け野原になったら、何が何でも戻ってきて、杭を打とう。
星野さんのお父さんは焼け野原に杭を打つ、という話は覚えていない。けど、読み進めていくうちにそのお父さんも突然思い出すことがあって、徐々に星野さん家族の来歴が明らかになっていく。家族には記憶忘却系の人と記憶保存系の両者がいる話題があがっていくところなど、ちょっとしたあるあるが面白いんですよ。具体的な家族の描写だけど、多くの人が共感できるような目線が入っているんですよね。
野口弘一朗 前半の子どもの遊びの話からさりげなく出てくるこの文章もすーっと読まされてしまう。この場面は、五反田本の後半で城南大空襲から逃げて生き延びる知恵につながる大事な箇所だよね。冒頭の軽妙な五反田話や家族の思い出話から終盤にて戦禍を生き延びるメッセージへとつながる展開はさすがの一言でした。

青山 五反田本は家族と土地の記憶が豊かに描写されるだけではなくて、そこに星野さんが抱いた好き嫌いといった感情もはさまれるのもまたいいんですよね。しかも、その描写がまた変に嫌味ったらしくもない。たとえば次の家族描写。
この「熱海での避暑」は、わが家では比較的よく知られた昔話だった。特に、母が父の軟弱さをやんわりと批判したい時などに、この話を持ち出す機会が多かった。そして最後は
「あんたは乳母日傘のボンボンだから、頭を使わないのよ!」
などと言って、トドメを刺す。家庭内の小さな階級闘争である。
母の神経を逆撫でするのは、「避暑」という行為そのものだったに違いない。
「家庭内の小さな階級闘争」という家族あるある表現を読んだとき、自分の場合はどうだったかなと、ついつい思い返しちゃいました。読む人の記憶を引っ張ってくる魔力が五反田本には宿ってるんですよ……
野口 ぼくは五反田本を読んでて、星野さんは歩く人なんだな、とも思いましたね。五反田駅を中心に半径約1.5kmを「大五反田」として、その自分の生活圏やちょっとした道端の記憶を捉えるのも繰り返し歩くからこそだなと。

栁田 東京の人の地元意識って区とか関係なく自分が移動する範囲じゃないですか。この星野さんの生活圏である大五反田の具体的なエピソードの細部に人は共感する気がします。
青山 あっ、なるほど、東京に住まわれているかたは大五反田というエリアの設定をそう読むんですね。
野口 ぼくは滋賀出身で大学時代から関東に引っ越してきたのだけど、地方から来る人は特に沿線のイメージで東京を捉えている、とも言われてるんですよ。それもあって、円で大五反田を捉えているのが五反田本の面白いポイントですね。
郷土史としての五反田本
栁田 野口さんは営業に行かれることも多いですが、五反田本の営業に行かれてどう反響を感じられましたか?
野口 駅前のブックファースト五反田店さんで売れていることはとてもありがたく感じます。五反田店さんに来店してしばらく後ろからこっそり観察したことがありました。昼休みのサラリーマンが同僚に向かって「おい、こんなのあったぞ!」と声をかけていたり、地元の人かなーと思えるおじいちゃん・おばあちゃんが手に取っていたりしました。幅広い世代の方に読んでいただいている気がしてうれしいです。
青山 五反田本の着目点を東さん(※東浩紀)に伺った際、2つのポイントを挙げていただきました。まず、大田区や品川区のエリアを対象とした文化的な出版物が抜けている中で五反田本はその穴を埋めた書籍である、とおっしゃっていましたよね。
野口 確かに近現代をテーマにした本だと、新宿、山谷、渋谷、上野と浅草といったエリアや、第二次世界大戦に関しては東京大空襲の話が多い気がします。大田区と品川区のエリアはすっぽり抜けているイメージがありますが、住宅街とか小さい町工場が多かったからかもしれません。
青山 五反田本はコロナ禍の産物と著者本人である星野さんがおっしゃっています。コロナ禍で取材に出歩けなかったからこそ、祖父・量太郎さんが残した手記や郷土史といった地元での資料調査があって五反田本ができあがった。東京の近現代史や出版文化に呼応しつつ、星野さんだからこそ書き上げられたのが五反田本だと感じます。
栁田 東さんがあげた五反田本のもうひとつの特色が、地域アーティストがその土地や記録の意味を掘り起こすように書かれた郷土史のようなものだ、でしたね。
野口 地域に赴いた芸術作品を描き上げられているのが、五反田本の表紙や挿絵を描いている弓指寛治さんです。弓指さんの絶妙なタッチが五反田本の世界観をイメージに落とし込んでくれているのもまたいいんですよね……

青山 地域アーティストが描いたような郷土史としての五反田本というのは非常にしっくりくる捉え方で目から鱗でした。ところで、郷土史っていまどういう位置づけなのかがわからなかったので調べてみたところ、自費出版が多く、内容に対しても客観的ではないとか言われてるみたいです。
栁田 研究としては郷土史はダメ、みたいなやつですね。星野さんの五反田本はあくまでノンフィクション作品ではありますが。
青山 郷土史的なものに家族や知人、土地柄に対する星野さんのコメントがさりげなく入り込んでいるのが面白いのですけどね。事実描写の中に星野さんのぼやきが入り込んでいる文章には、次のようなものがあります。
二〇〇六年に目蒲線が蒲田を切り捨てて「目黒線」「多摩川線」となり、東京メトロ南北線と都営地下鉄三田線が乗り入れた頃から、武蔵小山はどこへ向かおうとしているのか、漠然とした不安を私は抱いていた。その予感が当たったように、二〇一四年、「武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開開発事業」が決定され、駅前歓楽街を区画整理して超高層マンションが建設されることになった。
[…]
私は時々、怖いもの見たさでパークシティ武蔵小山を見に行く。いくつかはこの風景にも慣れるのかもしれないが、いまのところ、庶民的な町に突如出現したバベルの塔、といった趣で、異物感が半端なく漂っている。
[…]
町本来のキャパシティに見合わないタワーマンションが建って地価が上がった結果、かえって場末の雰囲気が色濃くなり始めている商店街。あまりに皮肉である。
[…]
駅前のタワーマンションをひやかしたあとは、その裏手にひっそり建つお寺に寄る。そのお寺と墓地は、かつての歓楽街のちょうど真横にあり、二つのタワーマンションから見下ろされる形となっている。
ここには武蔵小山の歴史を語る、大切な慰霊碑があるのだ。
野口 この慰霊碑に向けた語りは、大五反田圏の武蔵小山商店街の住人が戦時中に満州に赴いて多くが帰らぬ人となった満蒙開拓団について語る大切な導入の部分でもあるよね。
青山 星野さんは自分自身の身近な生活領域からこうした歴史的な意味を掘り起こすのが非常に上手ですよね。日常的によく観察しているのだなと思わされます。

栁田 東京は変化が激しく、この建物がなくなってしまったらどうしよう、みたいな映画館とか建物に対する愛着が宿るんですよ……そうしたこだわりが具体的な描写となってわたしたち自身の生活や地域の記憶を引っ張りだす気がします。
野口 歩く速さで見ているから覚えているんですかねぇ。好きな道ってあるじゃないですか。五反田本を読むとそういう感覚を思い出させられます。
青山 五反田本は、まるで星野さんがガイドを務めるドキュメンタリー映像を見るように読み進められます。映像的に描写が思い浮かび、それが読みやすさの秘訣なのかもしれない。
栁田 個人的には、星野さんの地元エピソードも大好きです。目黒線沿線民だったので、シンゴジラのエピソードが面白くて。
『シンゴジラ』で、鎌倉沖から再上陸を果たした第四形態のゴジラは、武蔵小杉で自衛隊から集中攻撃を受けた。武蔵小杉の代名詞である二棟のタワーマンションをゴジラが倒すのではないかと、いまかいまかと待っていたが、倒さなかった。スクリーンに向かって、私はそっと舌打ちした。
青山 五反田本には、読み手に「驚き」をもたらすような技法が随所に盛り込まれていますよね。タイトルに込められたわたしの物語から世界への逆転、大五反田に対するある種の過剰なこだわり、シンゴジラの話題にあるように軽めの導入から引き入れられる戦争などです。
野口 しかも、こうした対照的なメッセージが具体的なエピソードとして読めるのが五反田本なんです。ぜひ読んでほしい!
栁田 多くの読者のみなさんにとって、地域に対する愛着や家族との思い出など、わたしたちの来歴を省りみたくなる本だと思います。
青山 それこそ、「家族的類似性」を引き立てる本なのかもしれませんね。しかも、引き寄せられたわたしが、いつのまにかわたしたちや世界の物語へとつながって、生き延びの話になる。この物語(フィクション)から生き延び(リアル)のメッセージへと至る逆転も五反田本の大きな魅力です。
家族的類似性とは、父・母とわたしや兄弟・姉妹には目もとや身振りがどことなく似ているけれども、共通した特徴がないことを指す哲学用語。言語・論理哲学者ウィトゲンシュタインが用いたキーワードの一つ。
おわりに
以上、五反田本の広報担当である3人の雑談でした。ここまで読んでくださったみなさん、ぜひ一度、星野さんの文章をお読みになってください。ちょうどいいところに現在、五反田本はwebゲンロンで「第一章 大五反田」と「第二章 軍需工場」が全文無料公開中!

第一章と第二章は、わたしから世界の物語へとつながる五反田本のホップ・ステップ・ジャンプのうちのホップの部分です。著者・星野博美さんと五反田本の魅力がこの先のジャンプに現れます。青山の私見ですが、ジャンプの瞬間にその人の作家性や批評性が色濃く出ます。ぜひ、五反田本が導くジャンプを体験するために、書籍をお買い求めいただけると幸いです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
