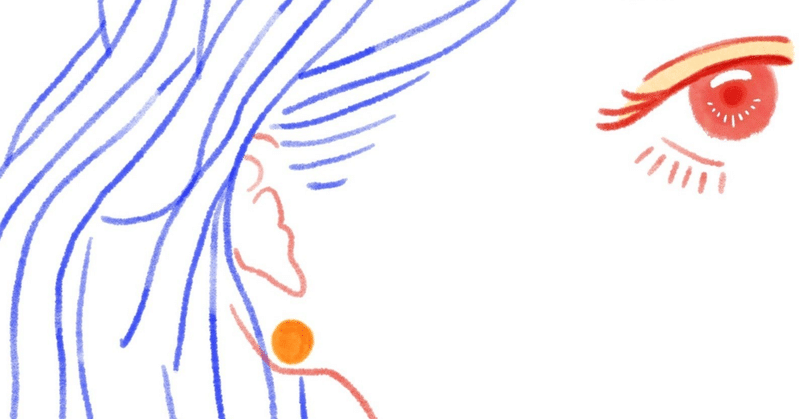
【極超短編小説】あなたの中に
玄関のドアを開けると夕飯の匂いした。僕のお腹は条件反射のようにグーッと鳴った。
「ただいまー」
僕は靴を脱ぎながら言った。
タッタッタッと足音が聞こえて、彼女が廊下を駆けてきた。
「おかえりなさい」
小柄な彼女はそう言いながら、飛びつくようにして大柄な僕に抱きついた。知らない人が見たら、小さな娘が父親に抱きついているように見えるかもしれない。
「ただいま」
と僕は返して彼女を抱きしめた。
「ごめんなさい。本当にごめんなさい」
彼女は僕の胸に顔を埋めたまま、暗い口調で言った。
「ん?どうしたんだい?」
「あなたに貰ったピアス……片方失くしてしまったの。朝、起きたらはずれてしまっていたみたいで……。ベッドも部屋も探したんだけど、見つからなくって……」
「なんだ、そんなことか。気にしなくていいよ」
彼女が失くしたというのは、彼女の誕生日に贈ったゴールドの小さなピアスだった。彼女はとても気に入ってくれて、ずっとつけていた。
「本当にごめんなさい」
彼女はそう言って、僕に抱きついた腕にギュッと力を込めたとき、僕のお腹がグーッと鳴った。
「お腹が空いたよ。早く夕飯食べたいな」
その日の夕飯は、もつ煮、中華スープ、餃子、肉団子などなど。学生の頃、ラグビーをやっていた大食いの僕のために彼女は、毎日、たくさんの品数と大量の料理を作ってくれた。
仕事柄、彼女は料理に関わっていたこともあって、料理好きで、料理上手だった。何でも作れて、その全部が美味かった。特に、肉料理が好物の僕に合わせて作ってくれるものは絶品だった。彼女と暮らし始めてから外食することはなくなり、彼女が仕事で出張のときでさえ、彼女は僕のために料理を作り置いてくれた。
彼女は僕の友人の親友で、その友人から紹介されるかたちで、偶然出会った。出会った瞬間からお互いに惹かれ合って、その日から一緒に暮らし始めた。一緒に暮らし始めたのを知った友人からは「私の昔からの親友だし、あの娘は本当にあなたのこと、すごく愛してるんだからね。絶対大切にしてね」と何度も念押しされた。
僕は彼女のすべてを愛していた。何から何まで。僕は特段、稼ぎが良かったわけでも、イケメンでもなかったが、彼女は僕を愛してくれた。彼女に「僕のどこがいいの?」と聞いたことがあった。そのとき彼女は「ギュッとしてくれるところ」と微笑んだ。
「また、同じものを買いに行こう」
ベッドの中で、僕の腕に頭を乗せた彼女にそう言った。
「ありがとう」
彼女は僕の胸に腕を回して、体を寄せて言った。僕も彼女の体に腕を回して抱きしめた。
「もっと、もっとギュッとして。もっとくっついて」
彼女は腕に力を入れて、そう言った。
「おい、おい苦しくないかい?」
僕は腕の力を少し抜いて、言った。
「だめ!ギュッとして。くっついて」
彼女はさらに腕に力を込めて言った。
「これ以上は無理だよ」
と言って僕は少し腕に力を込めた。
「もっと、もっとくっついて……このまま、あなたの中に入れたらいいのに……」
と言って彼女は僕の胸に顔を埋めた。
僕は彼女の体を抱きかかえるようにして、さらに引き寄せた。しばらくすると、静かな彼女の寝息が聞こえてきた。
翌朝目覚めると、彼女はすでに出かけていた。
枕元に彼女からの手紙が置いてあった。手紙には仕事で少し長い出張をすること、食事は出張先から毎日僕へ冷蔵で送るから、それを食べて欲しいこと、忙しくて電話はできないけれど、毎日メールすると書いてあった。
僕は手紙を読んだ後、ベッドから起き上がり窓のカーテンを開けた。灰色の空から雨が降っていた。遠くに見える鉄塔が霞んで見えた。
「寂しいなぁ」
と僕は思わず独り言を言った。
翌日から、彼女からの食事が届き始めた。僕が仕事から帰ってくる時間に毎日届く冷蔵パックには、その日の夕飯、翌日の朝食と弁当までが入っていた。
彼女の作った料理は、僕の好きな肉料理が中心で相変わらず美味しかったし、食べていると彼女を思い出して不思議と寂しさが薄れるのを感じた。
彼女が出張に行ってから1週間ほど経った。その日も彼女が送ってきた夕飯を食べているとき、スマホにメールの着信の知らせがあった。
料理を頬張りながらスマホを操作していると、ガリッと何か硬いものを噛んだ。口の中からその硬いものをつまみ出し、彼女からのメールを見た。
「あなたの中に入りたい」
とメールに書いてあった。そう言えば、彼女はそんなこと言ってたな、と思い出しながら口から取り出したものを見た。それは彼女が失くしたと言っていたゴールドの小さなピアスだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
